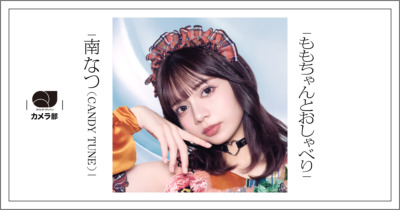まだコロナ禍の影を少しも感じさせない2019年末。この国のテレビ歌番組の象徴といえる『NHK紅白歌合戦』で、異例の3曲が取り上げられた作曲者がいた。
それは本人が不在でありながら、その存在感を大きく感じさせる出来事となった。
その作曲者の名は米津玄師。 そして2020年8月、自身もアーティストとして数々のヒット曲を歌ってきた米津が、満を持してリリースした新作が『STRAY SHEEP』である。
発表するや否や傑作の呼び声の高いこの作品を、J-POP批評の俊英imdkmが読み解く。本作で辿り着いた米津の現在地についてじっくりと考察してもらった。
キャリアを重ねる中で着実に変化してきた、米津玄師の“ある要素”とは
米津玄師のニューアルバム『STRAY SHEEP』。発売前にして出荷枚数100万枚を突破。初週の売り上げは88万枚を記録し、現時点での米津のキャリアにおける最大の数字となった。ちなみにロングセラーを記録した前作『BOOTLEG』(2017年)の初週売り上げは16.1万枚で、そこから比べれば5倍以上の伸び幅だ。今や米津の代表曲となった「Lemon」の大ヒットを経て、キャリアが次の段階へ達したことを示す記録である。
インターネット発のVOCALOID(ボカロ)カルチャーの流れを汲むアーティストがヒットチャートやマスメディアを賑わせるようになって久しい。その代表的な例が米津玄師の活躍だろう。もともとは2009年にハチ名義でボカロP(プロデューサー)として活動を開始し、やがて頭角を現す。当時発表した「マトリョシカ」はニコニコ動画上で1000万再生を達成。数少ない「VOCALOID神話入り」のボカロ楽曲に名を連ねる1曲となった。
2012年には、作詞・作曲・編曲、さらにはアートワークまでを自ら手がけたメジャー・デビュー作『diorama』を皮切りにソロ活動をスタート。ハチ時代の過密なメロディやアレンジはやや後景に退く一方で、ギターロックを出発点としながらエレクトロニックなサウンドも貪欲に取り込んで作風も変化し、自身の声との向き合い方も変わってきた。そして、今回の新作『STRAY SHEEP』は、そのような、“声との向き合い方”という観点から見ても、極めて興味深いアルバムといえる。
まずは米津の楽曲における、“声との向き合い方”を過去作から振り返ってみよう。歪(いびつ)な箱庭のように構築された『diorama』では、ギターサウンドに溶け込むように佇んでいたヴォーカルが、次作『YANKEE』では自立した存在感を放つようになる。何しろ、アルバム冒頭を飾るのは「リビングデッド・ユース」の多重録音された自身のコーラスだ。いかにもポップス的な構成が取られている「アイネクライネ」では、いきなりヴォーカルから始まる。何より印象的なのは歌に入る直前のブレス。同曲のほか「WOODEN DOLL」や「メランコリーキッチン」「眼福」でも歌に入る直前のブレスがはっきりと聴き取れる。これは『diorama』ではほとんどなかったことだ。また「KARMA CITY」でのふたつのメロディラインを併置する平歌のアレンジもユニークだ。
つづく『Bremen』では、米津のヴォーカル自体がよりダイナミックにうねり、開放感のあるものに変化している。張り上げるような力強さから、少し脱力しつつ震わせる繊細さまで、声自体が持つ表現のレンジが広くなっているのだ。さらに、ハーモニーを加えるコーラスワークも洗練され、効果的に歌(とそれが語る物語)への没入を誘う。それは「ウィルオウィスプ」でのややクドいほどのビブラートであったり、あるいはところどころに聴かれるファルセット(個人的には「Neon Sign」のそれが印象深い)など、時系列を追って聴き返すといっそう鮮やかに感じられる。
“声の拡張”の先にある『STRAY SHEEP』はいまだ通過点なのか?