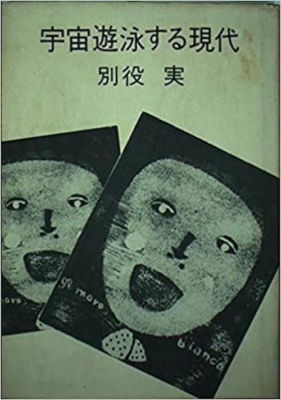意表を突かれる、著作の数々
別役作品で演劇以上に私が親しんできたのは評論やエッセイである。そこでも、まともに受け止めていいものか戸惑わうことが多かった。たとえば『日々の暮し方』という、一見、生活の知恵を説くようなタイトルのエッセイ集の目次を開くと、「正しいあいさつの仕方」「正しい日記の書き方」などに交じって「正しい誘拐の仕方」「正しい電信柱の登り方」、さらには「正しい死刑の仕方」などと穏やかならぬ項目が並んでいて面食らう。私がこの本で最も興味深く読んだのは「正しい地下鉄の乗り方」という一章だったが、これとても、笑いながら読みつつ、やはりどこか戸惑わずにはいられない。
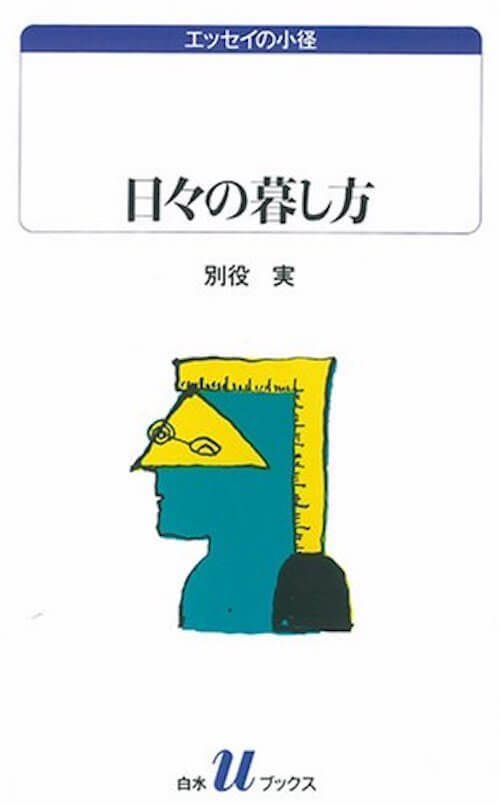
この文章でまず意表を突かれるのは、地下鉄に乗ることは空間体験ではなく時間体験だという捉え方だ。地下鉄はおおむね地下の暗渠(あんきょ)を走っているがゆえ、《乗客は、自分がどこにいてどの方向に向いつつあるのかを、知ることが出来ない。ただ、出発駅と到着駅を知っているだけなのであり、その意味で、地下鉄は、これからそれに至る時間経過に過ぎない》というのが、その理屈である。別役によれば、このことが《現在、言われているところの「地下鉄問題」》のすべての基因になっているという。なぜなら《人間は、空間体験抜きの時間体験を強制されると、生きていることを否定されつつあるような、或る抑圧を感じとらざるを得ない》からである。
地下鉄サリン事件を想起させる「地下鉄問題」懇親会
ここからさらに読み進んでいくと、唐突に“「地下鉄問題」懇談会”なる組織が登場する。この組織が考え出した解決策というのが、またかなり乱暴なものであった。何しろ、《地下鉄の中で乗客たちが、生きていることを否定されつつあるような抑圧を感じるのは、そこで乗客たちが生きているからである。もし、出発駅で乗客が地下鉄の車内に足を踏み入れたとたんに失神し、到着駅まで覚醒しなければ、問題は簡単に解決される》というのだから。「地下鉄問題」懇談会は、乗客を失神させるための術策として、やむを得なければ殴るとか、あるいはタイムスイッチつきの失神用チューイングガムを配布するといった提案を行うのだが、もちろんいずれも実現には至ってはいない。
ちなみにこのエッセイが書かれたのは80年代後半(単行本にまとめられたのは1990年)だが、私は読んでいてどうも1995年に起こった地下鉄サリン事件を思い出さずにはいられなかった。ある宗教学者は、東京の地下鉄でサリンを撒いたオウム信者たちが、その実行に踏み切ったのは必ずしも教祖・麻原彰晃の「洗脳」のみに起因するのではないとして、次のように指摘している。おそらく信者たちは心の根深い部分で、東京の地下鉄網に象徴されるような「精巧な自動機械としての群集社会」を強く嫌悪し、ラッシュアワーの人混みに紛れる群集の生き方を「救われない」と感じていた。彼らはそんな「救われない」群集の魂を救済(ポア)するために、あのような凶行に及んだというのだ(大田俊寛『オウム真理教の精神史―ロマン主義・全体主義・原理主義』)。ここに指摘されるオウム信者の動機は、地下鉄で「生きていることを否定されつつあるような抑圧を感じる」乗客たちを救うには、いっそ客全員を失神させ、仮死状態にしてしまえばいいという「地下鉄問題」懇親会の発想と、ほとんど変わりがないのではないか。
「自分と世界の対応感がない」
このエッセイに限らず、別役はさまざまなところで地下鉄に言及している。実は彼は地下鉄のファンだった。きっかけは、中学の修学旅行で初めて銀座線に乗ったことだという。その後、1957年に大学に入るため上京してからも、特に用のないまま地下鉄に乗っては、こんな楽しみ方をしていたらしい。
《車内で目をつむって、車両がいま地上のどのあたりを走っているのか、想定された地図を追うだけで充分楽しかったのである。思いついたところで降り、地上へ駆けあがって、地図と見合う風景に出会うのもひとしおと言えた。このとき、ホームから地上へ出る階段の折れ曲がり具合で、地上に出たとたん、一瞬方向を失うことがある。「えっ? 私はどっちから来て、いまどっちを向いて立っているのだ」というわけである。/ここから、頭の中で思い描いていた地図と、いま立っている現実の場所が、ゆっくりと折合いをつけてゆく過程も、何とも言えない》(『東京放浪記』)

地下鉄の出口で一瞬、方向を見失いながらも、次第に頭の中の地図と今現実に立っている場所を重ね合わせることで、自分の位置を定めていく、その過程に快感を覚えるというわけである。しかし時代が下るにつれ、まったく違う方法をとる人たちが現れたと、別役は別のところで語っている。
《渋谷で地下鉄銀座線に乗って、銀座で降りて服部時計店へ行くとしますね。地下道から地上に出るとき、渋谷がこっちで浅草があっちだ、それで服部時計店は線路のこっち側にあるから、そうするとここにあるなと、こんなふうにまず方角を見定めて、つまり世界と自分とを対応させて、確かめてから動きはじめる。これは古い人間なんですって。新しい人間は、とにかくタッタッタッと上がって、案内板を見て、「A4」とかいうところを上がって行く。そのときに、自分と世界の対応感がないんです。記号に従って行く》(『若者たちの大神 筑紫哲也対論集』)
これは1987年の対談での発言である。「自分と世界の対応感がない」とは言い方を変えると、自分と世界にリアルな関係性を見出せないということだ。日本は高度成長期を経て、あらゆる面においてそんな状況に入っていった。別役が活躍した演劇の世界も例外ではない。