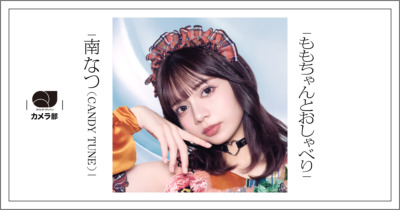「飛影はそんなこと言わない」に立ちのぼるミソジニー
「飛影はそんなこと言わない」というネットミームがある。
90年代に生まれ今なお使われることがある、非常にポップなフレーズと化したものだが、その出どころ、背景はゾッとするような代物だ。
このミームの由来となった出来事はとにかくショッキングなのでここで詳細を書くことはしないし、調べるとしてもその点にじゅうぶん注意してほしい。
何せこの言葉が生まれる経緯に関与した男性たちの態度は壮絶だ。ジェンダーイシューや社会の不均衡について惨たらしいまでに稚拙で、特に「女性のオタク」に対する暴力的な無理解とミソジニーが端的に現れたものといえる。
それだけ当時の世の中において女性のオタクというものが埒外の存在だったということ。いかに世間(の主導権を握る男性たち)にとって“存在を想定せずに社会を運営していって問題ない”類のアウトサイダーとして扱われていたかを物語る、ひとつの象徴的なトピックといえるのかもしれない。
そういった状況は社会全体はおろか、オタクコミュニティの中でも同様、あるいはそれ以上に苛烈だった。BLをはじめとする女性のオタクたちが育んできたカルチャーや、そもそも“女性であること自体”が掲示板などの場でミソジニーの的となり、一部の男性のオタクたちから幼稚な暴力を際限なく浴びせられてきた。
そんな流れの只中にあった00年代初頭、今より格段に世間の「女性のオタク」へのリテラシーが低かったあのころ、中川翔子は現れた。
翔子・ライジング
最初期の中川翔子を目撃したときのひやりとした感覚を覚えている。
眞鍋かをりに次ぐ“ブログの女王”という肩書を引っさげ、自身のオタク趣味について「ギザ」「ギガント」といった独特の言葉遣いでまくしたてる。『幽☆遊☆白書』の名場面を再現し、ブルース・リーへの敬意を表明し、『ドラゴンボール』のトランクスが傷つく姿で性の目覚めを迎えたと語った。それを受けてのスタジオの出演者の反応はまさに呆然という感じだった。トークの、ショーのプロ集団がそろいもそろって明らかに処理し切れていなかった。

ただ“ひやりとした”理由はそれだけじゃなく、実体験を想起したからだ。
自分のクラスに“こういう子”がいて、“こういうこと”が起こったからだ。
学校で生きていく上では、クラスの中心人物と呼べるような生徒たちが作り上げた、クラス内での“定形のコミュニケーション”のようなものへの忠誠心を問われる。選り分ける特権を得た支配者たちは面倒な“定形外郵便”を嫌う。同調圧力を各々が察知し、適応できる者がいればできない/しない者もいる。
中川翔子と重ねて見たのは、そういった定形とは違ったコミュニケーションをする子がアクシデント的にクラスメイトの前に立って何かをしゃべることになったときの沈痛な空気だった。もちろんオタク的な趣味嗜好の生徒にもクラスの中心人物たちが規定するようなコミュニケーションを取る子はいたのだけれど、各々思い浮かぶ記憶に近いものがあるのではないだろうか。
ただ、中川翔子は駆け出しのころこそ大いに共演者たちを困惑させたものの、テレビ出演を重ねるごとにどんどん定着していった。それは単に彼女自身が芸能界に定着していっただけではなく、彼女と近い属性の人々を世間に定着させることでもあったのではないかと思う。
もちろん彼女のレプリゼンテーションを好ましく思わない当事者もいただろう。中途半端に日の目を見て、晒し者にされる心地がした人もいたかもしれない。外野から干渉されず好きにやりたいと思った人もいたかもしれない。
そして、彼女が目立つ存在であるがゆえに、彼女を女性のオタクの代表として見て、全員が彼女のようなパーソナリティであるといった扱いを受けて不本意な思いをした人もいただろう。
ただ、“テレビで一度見た”から、どうやらああいう趣味嗜好の人がいるらしいことはわかる、というところまで存在を顕在化し慣れさせ、まずは最低限のリテラシーを担保する役割を果たしたことは、多大な功績といえるんじゃないだろうか。
時代の流れとしてタイミングがちょうどよかったのかもしれないとか、事務所のプロモーションの巧みさとか、外的要因はいろいろとあれど、結局は彼女自身の実力、つまり類まれなプレゼン能力、表現力、そして熱量によって、彼女は無理解を突破してきた。あれだけ心から楽しそうな姿を見せられたら、忌避感も次第に溶かされていく。