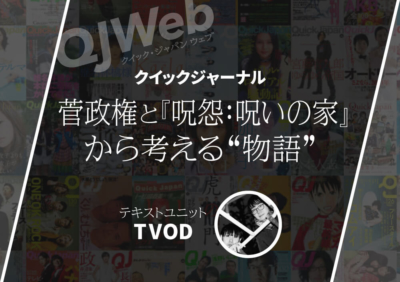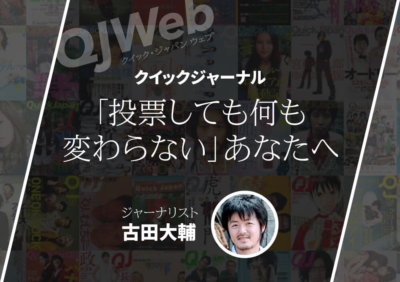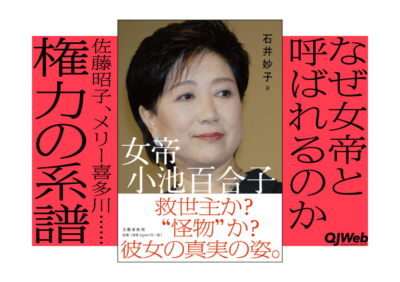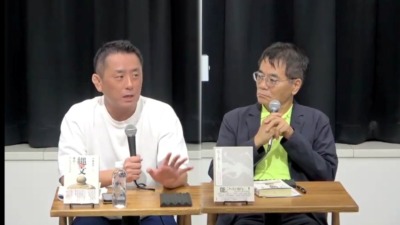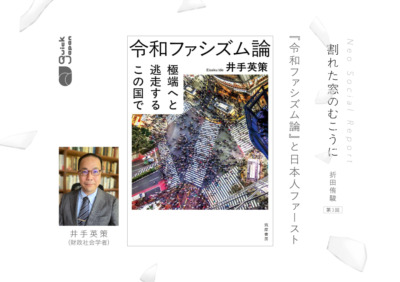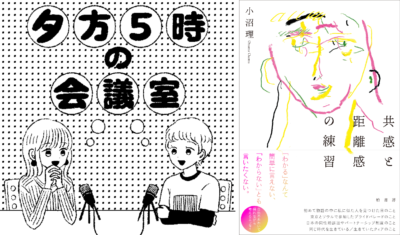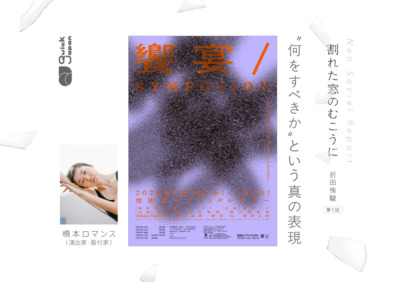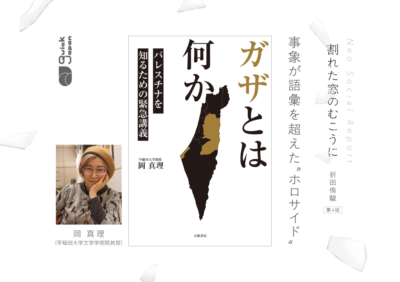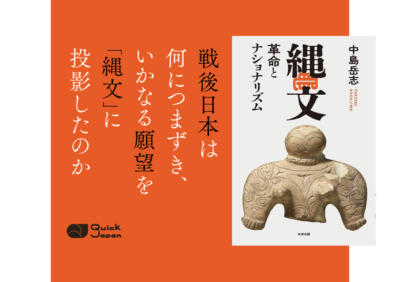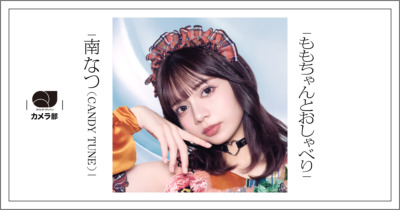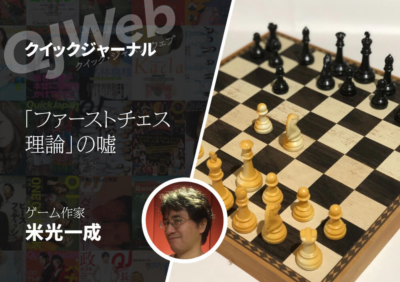可視化への欲望を高めつづけるツイッターの影響
パンス 説明責任を果たさない、という問題は安倍政権のころから指摘されてたけど、もう完全に説明しないとこうなるんだな、というのを見せつけられてるような感じがあるね。よく「分断が起こっている」と言われるけど、みんなが完全に「分断するぞ!」と判断してやっているわけではなくて、ある程度こうした政権の振る舞いとか、議論をする環境に左右されちゃうなと僕は捉えていて。
その環境こそが、いまはSNSになるわけです。敵とされる人や組織の内心を「暴く」こと自体が意見表明になっちゃうような雰囲気があるんだけど、それって一歩踏み外すと陰謀論にもつながっちゃう。

コメカ そもそも個々の「内心」は他人からは不可視のものであって、だからこそ論理的な言葉を用いた説明やコミュニケーションを通して諸々の問題に取り組んでいきましょう、というのがまあ近代的な合意であったはずなんだけど、SNSが普及すればするほど、その合意が壊れていってる感じがするね。
ツイッターにしてもさ、あれは個々の「内心」というか自意識が無防備に丸出しになりがちな場所じゃない? あそこではどんどんとこう、「内心」の可視化への欲望が人々の間に高まりつづけている感じがするんだよね。デマや陰謀論というのも、「あれは表からはこう見えるけど、裏側は本当はこうなっているんだ」みたいな、可視化への欲望だよね。イデオロギーの傾向とは別の水準で、「世界の裏側は本当はこうなっているんだ」みたいな感じで、「隠された真実」へのアクセスをしたがる人が異様に増えている。
でもさっきも言ったけど、近代的な価値観としてはさ、可視化し得る論理や言葉に社会的コミュニケーションの論拠を置くべきっていう話だったはずなんだよね(笑)。そこのプライオリティが下がってきているからこそ、政府も説明責任を果たさなくてもやっていけちゃう状況になっちゃってる。国民側も、権力に対して理屈で批判や糾弾をすることよりもむしろ、ネットで問題を「ネタ」化してみんなであーだこーだ言ってこねくり回すことばかりに時間を取られがちになっていくという……。
パンス これねーけっこう難しくて、たとえば自分たちがやってるような批評的なるものにも通じてきちゃうんだよね。「内心はこうなっているのでは」といって分析していくという営為。これをやり過ぎるとトンデモになってしまう傾向があると思ってて、わりと気をつけてる。
トンデモや陰謀論というのは、披露したらまわりの人も共感してくれたりする。最近では「社会を語る」とか「批評する」行為も割と近くなっちゃってて、ツイッターとかでみんなにサクッと共感されるほうに自分を合わせ過ぎてると、原理原則からズレてきたりして。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR