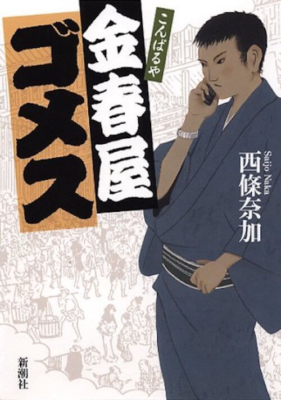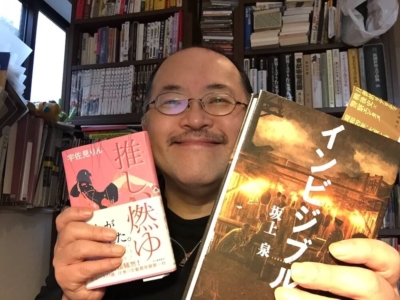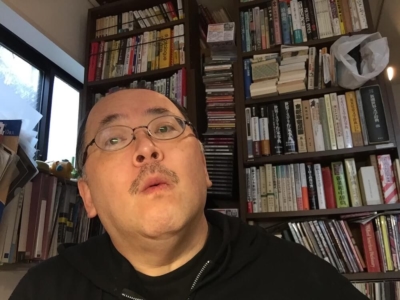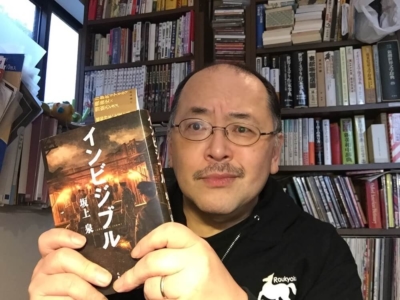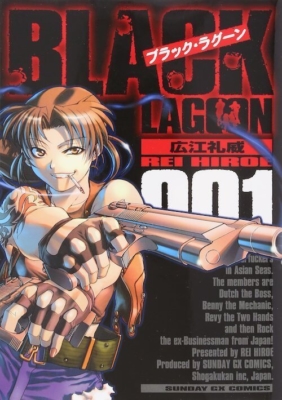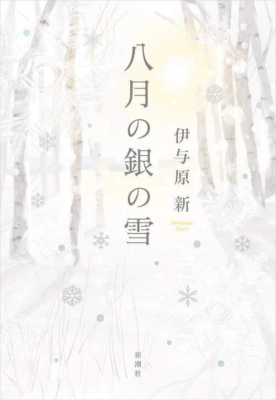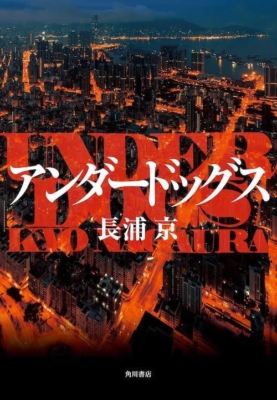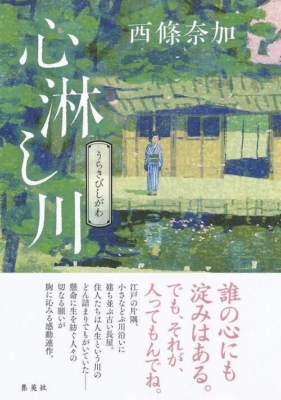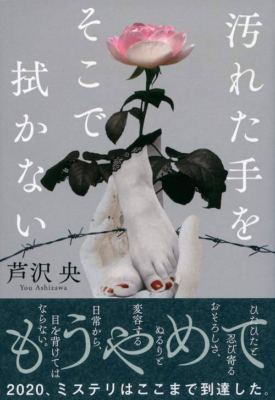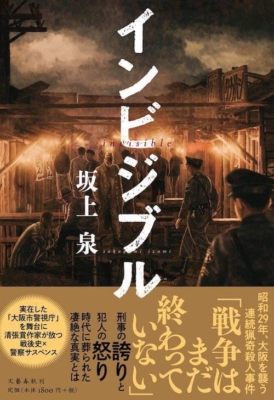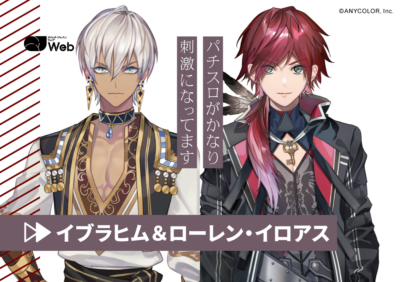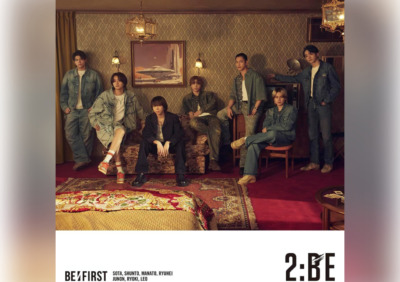批判しにくい『八月の銀の雪』
杉江 伊与原さんは横溝正史ミステリ大賞出身者です。ミステリーの著作ももちろん多いんですが、理系の博士課程を修了した方でもあるので、その素養を活かした作品で独自の地歩を築いてこられました。
マライ 各篇の語り手は、日常生活の中で「偶然に遭遇した」スゴい人々によって、世界観をアップデートされていく。これは素朴な感想なんですが、この「偶然に遭遇」する場面の多くがなんというか、『ぶらり途中下車の旅』(日テレ)でなぎら健壱さんが「あれぇ? おじさん何やってるんですか?」と街角で声をかけた相手が、実は自宅屋上から空と雲の観察と描画をひたすらつづけて40年!のスゴい人で、的な情景に見えてしまうんですけど。これはあの、狙ってやっているんでしょうか。
杉江 理系版『ぶらり途中下車の旅』! いいなあ、出版社はすぐに帯をそれに差し替えたほうがいい(笑)。
マライ ありがとうございます(笑)。中身について率直に言うと「いい話」というより「内容について批判しにくい話」という印象が強いです。
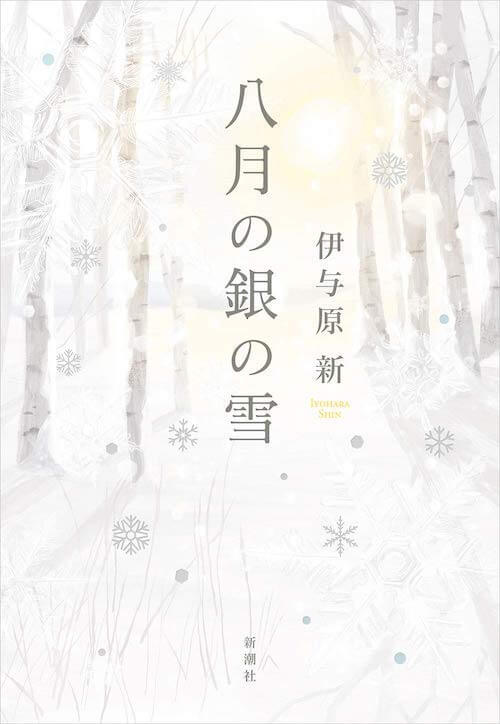
『八月の銀の雪』あらすじ
人見知りをする性格の〈僕〉こと堀川は、就職活動で挫折を味わいつづけている。そんな彼は、侮蔑の眼差しを向けていた外国人のコンビニエンスストア店員と、ふとしたことで会話を交わすようになる。実は彼女には大きな秘密があったのだ。表題作を含む科学小説集。
杉江 作者の気持ちを代弁すると、我々が見過ごしにしている日常にも、実は科学について深く考える種は眠っていて、それに気づくことによって世界はもっと美しいものになるのに、ってことだと思うんです。だから社会についてのさまざまな不満を抱えている人が出てきて、科学的な解釈を知って心を新たにするという展開なのではないかと。井之頭五郎風に言うと「科学、そういうのもあるのか」という感じですかね。水伝説とか、そういう非科学的な言説の流布についての危機感みたいなものが作者の中にあるのだろうと勝手に推測しています。
マライ ちょっとこの短篇集、浮世離れ感が微妙に的を外している印象があるのです。あと、水伝説みたいなオカルトに踊らされている人をそこから「引き剥がす」ほどの力は感じられない。

杉江 そこは『心淋し川』と共通する部分かもしれません。人生の賦活という物語の図式は、はまる人向けでそれが心に刺さらないとたぶん浸透が難しいんですよ。でも、科学という観点で世界を再発見するという物語はいいんじゃないのかな。もしかすると、もう少し世間の言説に対する防御力がない、若い世代向けの物語なのかもしれませんね。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR