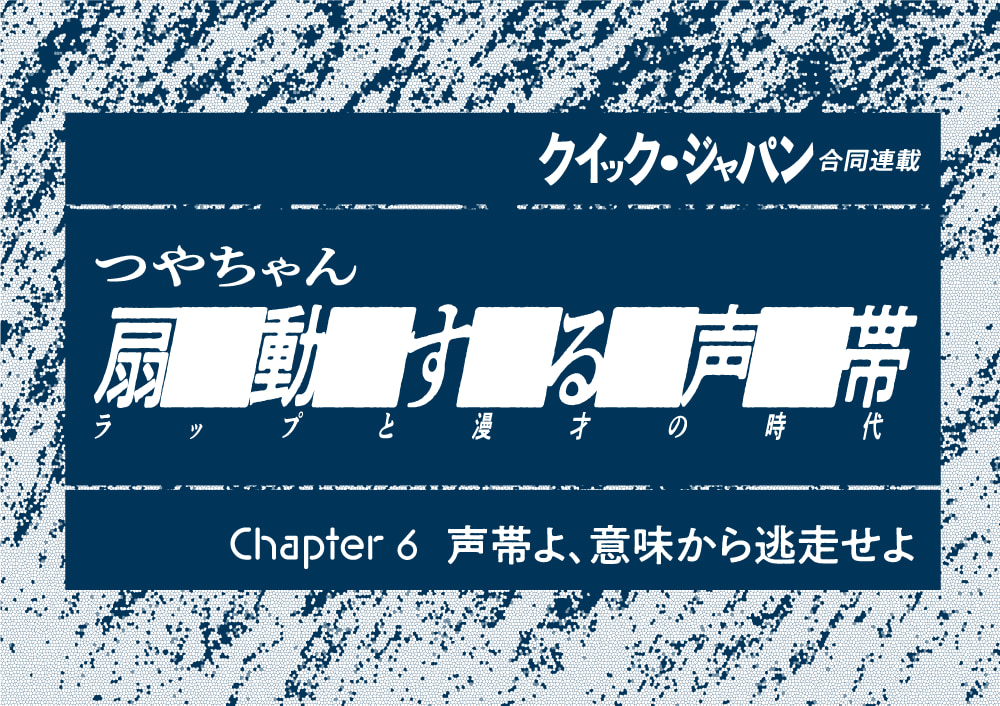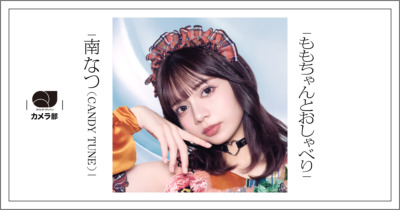新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」Chapter6。
※この記事は『クイック・ジャパン』vol.163に掲載の連載記事を再構成し転載したものです。
Chapter6「声帯よ、意味から逃走せよ」
ラップはいかにしてリスナーの心を揺さぶるのだろう? 鋭いリリックをリズムに乗せ発することによって? では、漫才はいかにして観客を笑わせるのだろう? おかしなストーリーをリズムに乗せ発することによって?
鋭いリリック、おかしなストーリー。その鋭さとおかしさとは、<意味>である。ラッパーは、自らのバックボーンをもとにした生々しいリアルをリリックに落としこむ。漫才師は、空想や体験によって得た滑稽なエピソードをストーリーとして磨き上げる。意味を練り上げ規則的な響きとして鍛え上げることによって、世界を構築する。言い換えるならば、意味を伴った世界が音とともにリズムと化すことで、ラップや漫才に命が吹き込まれる。
─本当に? ラップや漫才は、常に<意味>から逃れられないのだろうか? あなたが心動かされているラップや漫才から<意味>を奪った瞬間、それらはつまらないものになってしまうのだろうか?
実は、その問いに対し果敢に挑んだ者たちがいる。<意味>が生成される一瞬よりも先だって、<意味>という有限の揺りかごに回収されないまま、生まれたてのリズムを鳴らしながら。
ジャルジャルと『M-1』─漫才からのエクソダス
2010年の『M-1グランプリ』決勝で、大胆な手法を採用したジャルジャルの試みを挙げよう。
「コンビニ店員」というテーマでふたりが演じていく漫才は、作品冒頭からいささか様子がおかしい。来店した客に「ありがとうございました」とボケるのは店員役・福徳秀介だが、その瞬間の後藤淳平のワンテンポ速いツッコミ。その後もボケ‐ツッコミというやりとりを流れ作業的に速くこなしていくことで違和感が生まれ、とうとう福徳が「ツッコミ速いわ」と苦言を呈する。
しかし、後藤はこう述べるのだ─「知ってるからな」「なに言うか知ってるからな」「あれだけ練習したから」─。『M-1グランプリ』の舞台に、明確なメタ視点が放り込まれた瞬間である。福徳はついつい「初めて聞いた感じでやるのが漫才やろ」と応答するしかない。
メタ‐漫才師の世界を観客に提示した直後から、彼らのやりとりはさらにエスカレートしていく。後藤は「勢いよくのびのびとツッコんでくれ」という福徳のアドバイスを従順に実行し、「ダッ!」「ケッ!」「ナッ!」という掛け声でツッコむのだ。これは、2000年代後半の漫才が次第にテンポを上げ、台本を完璧に頭に叩き込み演じ切ることによってインプロビゼーションとしてのダイナミズムを後退させていった状況へのアンチテーゼにも映る。
それら“効果音”でのリアクションは福徳にも伝播し、最終的に彼らは「ダッ!」「ナッ!」としか言わないままボケとツッコミを繰り返すという、メタ‐漫才師から脱‐漫才師へトランスフォームする摩訶不思議な展開を『M-1グランプリ』決勝の大舞台で果たしていく。
ここには、<意味>の喪失がある。漫才に伴う練習や台本といったあらゆる仕組み、いわば『M-1グランプリ』というシステム自体に背を向けたジャルジャルは、漫才から抜け出して漫才自体を外部からまなざすことで、作品をエレメントの次元へと分解し、それでもこびりつく内容を漂白し、結果的に<音>のみを残してしまったのである。
漫才から意味性を引き剝がし音のみで表現する行為、それはつまり「骨組み」のみを残すということだ。過剰な進化を遂げた2000年代の漫才というアートフォームを一度振り出しに戻すという点で、音に集中する=骨組みだけを取り出すという彼らの試みは非常にクリティカルであった。
その大胆さは、以後の活動においてもメタ的に<漫才=即興風のしゃべくり>を捉える視点を、<コント=演技による寸劇>の中に取り込み、コント内漫才とも言うべき入れ子構造を試みる、あるいはコントと漫才を重ね合わせる、という形で結実していったのだ。
<意味>は水しぶきに消える
世界中股にかけたい/世界中股にかけたい/大事なことは2回言うタイプ/大事なことは2回言うタイプ
Tohji, banvox「Super Ocean Man」
ジャルジャルと通底するような痛快な表現を、ラップというフォームで試みたのはTohjiである。banvoxとの連名で発表し2022年の夏のヒップホップ・アンセムとなった「Super Ocean Man」の冒頭で、彼は「世界中股にかけたい」と宣言する。
けれども、実はここで重要なリリックは「大事なことは2回言うタイプ」のほうだ。なぜなら、「大事なことは2回言うタイプ」というラインそれ自体をTohjiは2回繰り返しており、つまりここでは「世界中を股にかけたい」という極めてラッパー的成り上がり精神と並列する形で「自分は大事なことは2回繰り返すタイプである」というラッパー・Tohjiに向けてのメタ視点が立ち上がっているからである。
言うまでもなく、ヒップホップとは一人称の音楽である。徹底して「自分語り」をするというヒップホップの定義を確立したのはRHYMESTERだが、ライター/批評家の韻踏み夫は先日刊行された書籍『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス)で、彼らの作品『リスペクト』(1999年)をして「実際にこれ以降の日本語ラップはすべて、ここで発見された「一人称」の中身を発見する過程なのだとさえいえるだろう」と述べている。
RHYMESTERの「B-BOYイズム」ではBの定義をブレイキング、バトル、バッドであるとも記しているが、私はここに日本語での<ベタ(≒cliche)>をそっとつけ加えたい。一人称での自分語りとはそれ自体がまさしくベタなものであり、ゆえにヒップホップカルチャーは基本的にベタさを許容する。紋切り型のワンループ・ビートに、車、ジュエリー、女性、それらの中心に鎮座する「俺」。ベタは、ラッパーが重要視してきた美学だ。
ところが、Tohjiは一人称にメタを導入する。「Super Ocean Man」のMVでの印象的なシーン。海で遊ぶ女性たちの間から、覗くようなショットでTohjiはその姿を捉えられる。監督の木村太一の鋭い視点によって映像化されたTohjiのメタ性は、漫才におけるジャルジャルがそうであったように、作品そのものをエレメントの次元へと分解し、それでもこびりつく内容を漂白し、結果的に<音>のみを残していくのである。
MVに映る、細かい水しぶきのように分解され崩れたフロウで高揚感を煽っていく「Super Ocean Man」でも十分に<音>に対するアプローチは試みられているが、Tohjiの急進的な実験が最も極まったのはやはりLoota、Brodinskiとともに作り上げた『KUUGA』(2021年)だろう。ラップがラップになる以前の、一つひとつの音が解体されることで<意味>を喪失し<音>になったそれらは、ビートのマテリアルとフラットになることで砂嵐のような繊細さを伴いリスナーを襲う。『KUUGA』はジャルジャルの漫才でいうところの「ダッ!」「ナッ!」と同じような個体の響きによって駆動されているのだ。
それら鋭いメタ視点は、結果的に、一人称に足をすくわれ陳腐と化してしまうラッパーたち、コントロールされた演技派芸人と化す漫才師たち、彼ら彼女らが溺れるナルシシズムをも打破するパワーにあふれている。ラッパーや漫才師が常につき合っていかなければならない諸刃の剣を、ジャルジャルとTohjiは退けるのだ─<意味>という有限のゆりかごを突き破って。