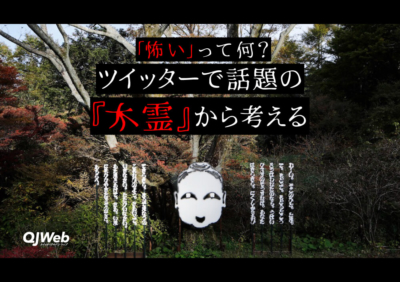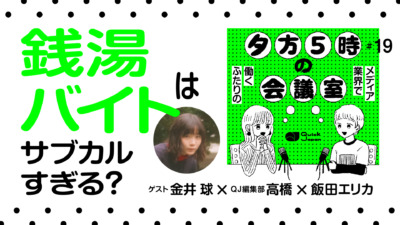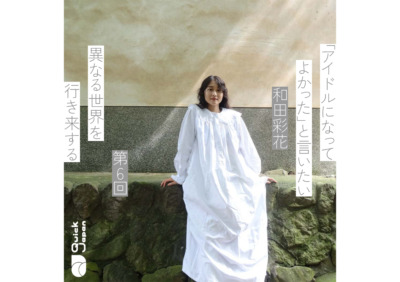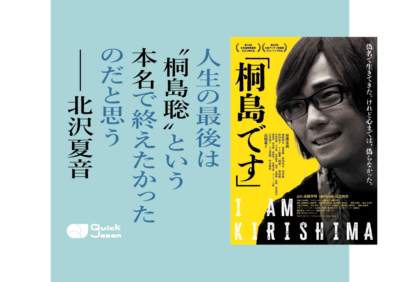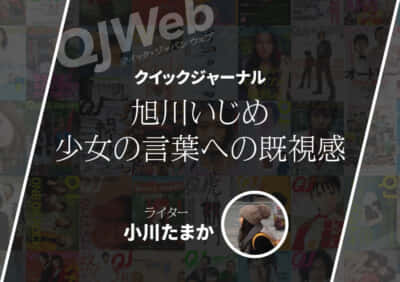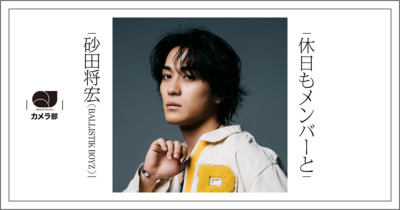ブラジルでの生活──貧しくて、帰国すらできない日系人も
実際の移民の生活はどんなものだったのだろうか。戦前に移住した人の多くは亡くなっているため、戦後に6歳でブラジルに移住し、30年ほど滞在して1991年に帰国した長谷川眞子さんに、神戸の「海外移住と文化の交流センター」でお話を伺った。

長谷川さんのご両親は満州から引き揚げてきて、1957年に一家7人で移民した。長谷川さんの子供のころの生活は、船に乗って学校に通ったり、ヤシの実やアサイーなど珍しい果物を採って食べたりした、と楽しそうに話してくれた。
その一方で、水道や電気もない不便な暮らしで、湿地帯にあった町はよく洪水になったそうだ。「学校はブラジル人の先生が3人しかいなくて、一度に60人くらいの子供を見るような状態でした。私は全然ポルトガル語はわからなかったので、学校に行っても教室に座っているだけでした」。
最初、長谷川さん一家はアマゾン川下流のグァマという地で米作りを目指したがうまくいかず、高台のアカラという町へ移って胡椒(ピメンタ)の栽培に切り替えた。胡椒は「黒いダイヤ」と呼ばれ、朝鮮戦争の特需で一時期は現地の人を何人も雇うほど儲かっていたが、根腐りによって全滅。その後、養鶏を始めたものの、それもうまくいかなくなった。1973年、長谷川さんが16歳のときに父親に日本語学校の先生の職が決まり、サンパウロに引っ越した。
ブラジル移民の中には長谷川さん一家のように成功した例もあるものの、地元の農園にコロノ(契約農夫)として雇われたり、いくつもの農園を転々として、日本にいたときよりも貧しい状態で、帰ることもできず悲惨な状況に置かれた人もいたという。