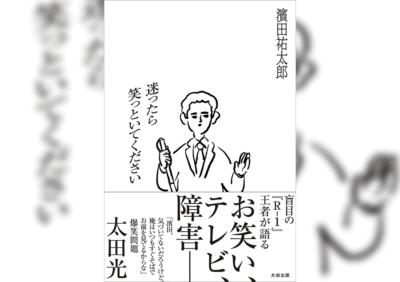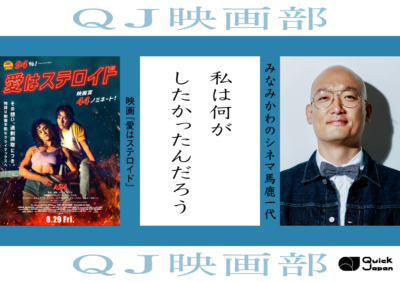坪内さんなら、この出来事を、この風景をなんと語っただろう
今、手元には『文学を探せ』の他にもう一冊、坪内さんの『東京』という本がある(この2冊を鞄に入れてアパートを出た時点で、この原稿を書くことが決められていたような気がする)。『東京』は森山さんが編集長だった時代の『クイック・ジャパン』で連載されたもので、坪内さんが東京のある街についての記憶を書き記し、その街を北島敬三さんが撮る――という企画だ。
巻末にはふたりによるエピローグ対談が掲載されている。そのラストで、今の街の変化のヒドさ――「今」というのはこの連載がおこなわれていたゼロ年代半ばだ――についてふたりは語る。
北島 人が人を見なくなる、これ最悪でしょ。「見る」ってすごく危険な行為だけど、だからこそ学べるわけじゃない。
坪内 俺も新宿で事故に遭ったのだって、チンピラとぶつかった時、そいつを睨んで、それでボコボコにされたわけだからね。バブルの時は地上げでも、人間がやってる感じがした。そういう意味で人格を感じられたけど、今は街の変え方を見てると、人格がないんだよ。コンピューターっていうかさ。今はたしかにヒドいよ。でもさ、この三年ぐらいを凌げば、なんとかなるんじゃないかなあって気がするんだよね。だから若い人には、悲観しないで欲しいっていうかさ。俺も五十歳だからさ。
坪内祐三『東京』写真・北島敬三、2008年、太田出版
『東京』が『クイック・ジャパン』で連載されていたのは、2004年1月号から2007年6月号までだ。
僕が初めて坪内さんと仕事をしたのは2007年6月のことだから、坪内さんが「若い人には、悲観しないで欲しいっていうかさ」と語っていた時期だ。
それからしばらく経って、東京オリンピックの開催が決まってから、東京の街は大きく様変わりした。そのことに、「悲観しないで欲しいっていうかさ」と語っていた坪内さんは、悲観的になっているように見えた。ある時期から僕は坪内さんと福田和也さんによる対談連載「これでいいのだ!」(雑誌『SPA!』)の構成を担当させてもらっていたが、たとえば2013年4月12日号で、坪内さんはこう語っている。
坪内 (略)それにしても、東京オリンピックを前に東京はめちゃくちゃになってるね。浅草六区は今すごいよ。つい最近まで、浅草六区は戦前の写真とほとんど変わらなかったのに、それが急激に変わっちゃって「オレは今どこにいるんだろう」と。すごいね、オリンピックって。前のオリンピックのときは東京大改造で、それを呪詛した人もいるわけだけど、あのときはグランドデザインがあったわけ。今は適当にぼこぼこやってるから、浅草が芸能の街じゃなくなってるんだよ。
『SPA!』2013年4月12日号
ただ、悲観しながらも、坪内さんは常に街を歩き、視線を注ぎつづけていた。
だから、今年の東京オリンピックのことも、僕は心のどこかで楽しみにしていた。坪内さんはどんなふうに東京を歩き、どんなふうにまなざして、どんなふうに書くだろうと。
その視線は永遠に失われてしまった。
坪内さんなら、この出来事を、この風景をなんと語っただろう。
それはもう、想像するほかない。
想像はわたしたちに委ねられている。
2020年の初めに亡くなったことを、坪内さんならどう語っていただろう。そんなことを想像する。「2020年は2020年でも、東京オリンピックの前に死ぬってシブいよね」。そう笑いそうな気もする。「いや、どんなにヒドいことになったとしても、その東京を見届けたかったね」。そう残念がりそうな気もする。いずれにしても、これから先のことは、わたしたちがわたしたちの目で見るほかない。
締め切りとして指定された20時が迫ってきた。
坪内さんに教えてもらって通うようになった酒場――どちらも階段を降りた地下にある店だ――も、営業が始まっているころだ。
今日はこれから、どちらの店に行こう。朝からずっと迷っているけれど、まだ決めかねている。
そのうちの一軒を訪れるとき、僕はいつも、最後の一段を降りたところで一度立ち止まり、店内から流れる音に耳を澄ませていた。そこに坪内さんの声があれば、あるいは坪内さんが好きな曲が流れていれば、緊張しながら扉を開けていた。
もうその声を聴くことはない。頭ではそうわかっていても、足を止める癖は抜けそうにない。その声は、耳の奥にまだ聴こえている。