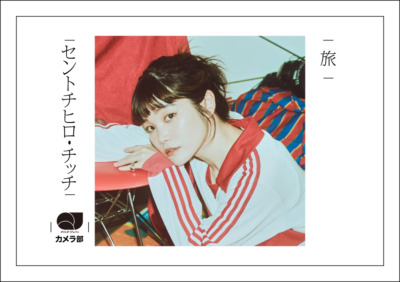僕にとって「恐ろしい視線」は坪内さんだった
坪内さんが亡くなったのは1月13日だ。
その前日、僕は坪内さんの『文学を探せ』を読み返していた。
今年から読売新聞の読書委員を務めることになり、何か自分の背骨となるようなものを求めて、『文学を探せ』を読み返したのだ。
そこには、たとえば、「批評としての書評とポトラッチ的書評」という文が収められている。そこには新聞書評に対する厳しい言葉がある。
本屋で本を探し求めることから書評の仕事ははじまる、と私は考える。私が新聞書評のいわゆる書評委員会制に批判的なのはその点である。彼(彼女)らは、書評委員会会議の机の上に並べられた膨大な数の新刊を眺め、ただチェックして行くだけだ。本屋好きの人ならまだ良い。しかし彼(彼女)らの多くは、書評委員会の席でチェック出来ることを口実に、新刊本屋に足を向けなくなる。つまり、棚のリアリティがうすれて行く。もちろん、これは、あくまで私の推測である。だが、たいていの新聞書評のツマラなさ、および時代との微妙なズレかたを見ていると、この私の推測は、当らずといえども遠からずだろう。
坪内祐三『文学を探せ』2001年、文藝春秋
こうした言葉に、背筋が伸びる思いがする。あるいはまた、こういう言葉にも。
既に何度か口にしていることだが、私は、書評の仕事とは、本屋で本を選ぶ所からはじまると考えている。書評も一つの批評であり、批評とは究極的に、何かを選び取ることである。そのあとの理屈(言葉)はいくらでもデッチあげることが出来る。そして世の多くの人びとは、その「言葉」の部分にこそ批評があると思い込んでいる。
同書
書評を書こうとするとき、それらしい言葉を書くことは簡単だ。それこそ、「いくらでもデッチあげることが出来る」。だが、それらしい言葉を書いてしまいそうになるとき――それこそ「ニューながい」を「ごく普通のカレーだった」と書いて話を先に進めてしまいそうになるとき――いつも浮かんでくるのは坪内さんの目だった。

「文学を探せ」は『文學界』で連載されたものだ。その第1回は、「中上健次の不在から、話は高橋源一郎・室井佑月の部屋へ」である。
文学の世界に、中上以前中上以降という言い方ができるかもしれない。小林以前小林以降、あるいは三島以前三島以降という言い方ができるように。
同書
中上健次が亡くなってしばらくした頃、中上健次がよく通っていた新宿の文壇バーの、あるママは、私に、中上さんが亡くなってなんだか皆さんのびのびしたみたいと口にした。
恐ろしい視線が消えて人は弛緩する。
この人物に読まれていると思うと、人は、その人物が自分と相反する文学観の持ち主であっても、いや、相反する文学観の持ち主であればなおさら、いい加減なことを言葉に書きあらわすことができない。自分のインチキぶりが見抜かれてしまうから。小林秀雄の凄みのある視線は中村光夫や大岡昇平といった年下の文学者はもとより、横光利一や井伏鱒二といった年上の文学者たちも泣かした。三島由紀夫の死と共に、彼の同世代の文学者たちの間から、ある緊張感が消えた。
文学は、しょせん、言葉でしかない。けれどその言葉を、多くの凄玉たちが、じっと深く読み込み、少しでも浮ついたところがあれば、激しく反応する。時には暴力をともなって。そうやって磨かれていった文学世界は、今やほとんど消滅しかけている。
久しぶりでこの言葉を読み返して、僕にとって「恐ろしい視線」は坪内さんだと思い返していたばかりだった。そのときは、その視線がまもなく消えてしまうことを、想像もしていなかった。
(次頁「坪内さんなら、この出来事を、この風景をなんと語っただろう」につづく)