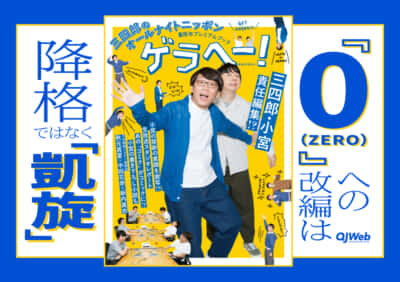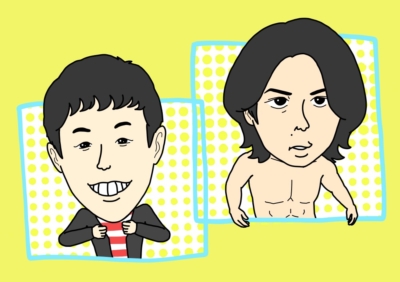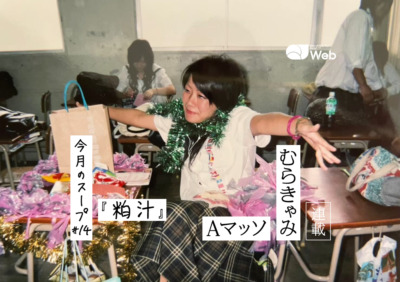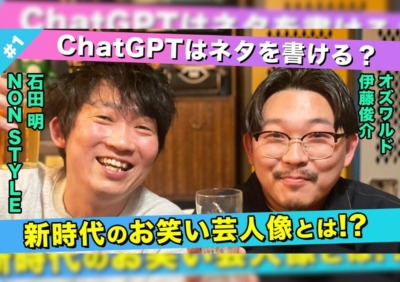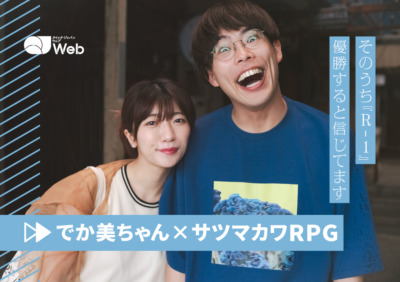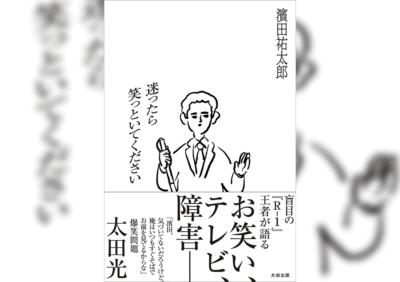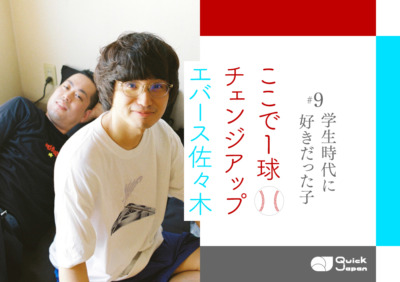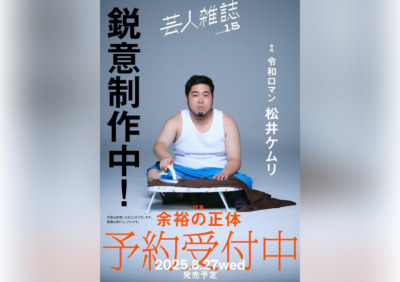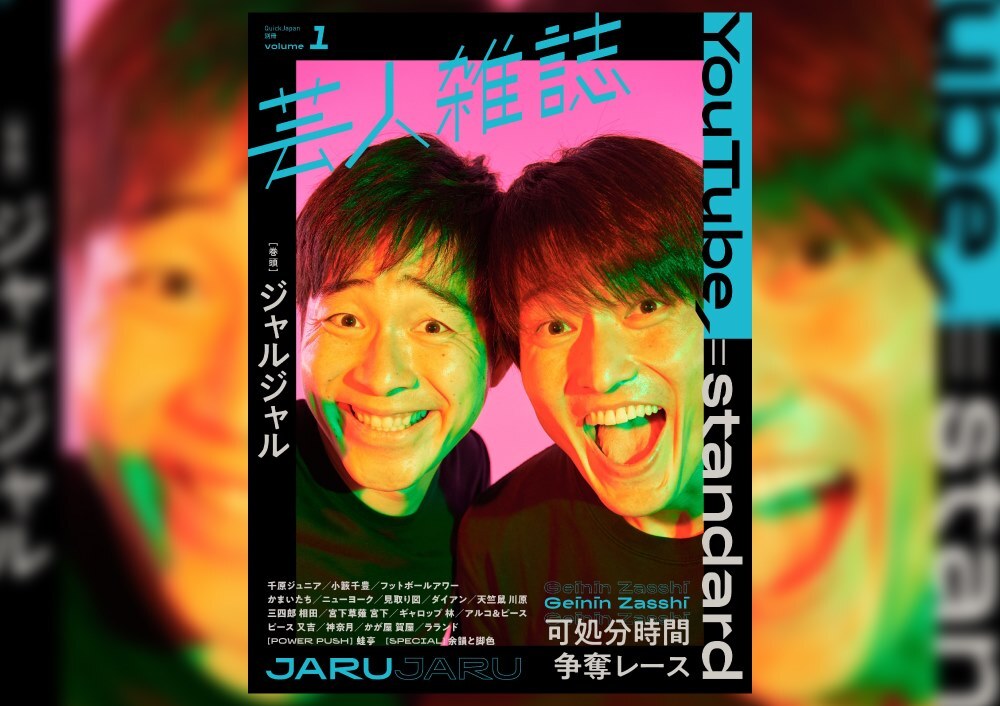『三四郎のオールナイトニッポン』は、前身となる「オールナイトニッポン0」の枠では最長の4年、昇格して1年、そして今年4月以降も継続が決定したばかりの人気番組だ。彼らのネタもラジオも、偶発的なおもしろさが感じられる。しかし本当に“偶発的”なのだろうか。
あらゆるエンタメやカルチャー、事象についての“感想”を綴るブログ『kansou』を運営するかんそうが、今回は三四郎の漫才の本質に迫る。
三四郎の漫才の本質
三四郎の漫才のおもしろさはずっと「粗さ」だと思っていた。
「バチボコ」「鼻爆発して死ね」を筆頭とした小宮浩信の独特なワードセンスと滑舌の悪さから繰り出されるキレツッコミと、相田周二の予想外の角度から来るサイコボケのコンビで、その特徴はアドリブにも見える「フリースタイル漫才」。基本は相田がボケ、小宮がツッコミを担当しつつも、そこに縛られないのが三四郎。小宮がキレ散らかすネタもあれば、ひたすら相田が暴走するネタもある。ボケ・ツッコミが絶えず入れ替わり立ち替わり、徐々にその境目がなくなっていく。そして最後には「オチなんてありませんよ」と言わんばかりに唐突に終わる。雲散霧消、その様はまるで「煙」。
役割だけでなくネタの内容も予測不可能。たとえば「美容師をやりたい」とコント漫才を始めるかと思いきや、その手前で足踏みしボケ倒す。一歩も話が進まないまま、終わる。また別のネタでは「リア充に劇薬ぶっかけたい」「ガンジーに扮して道行く人を蹴り飛ばしたい」とそのフリ自体がオチているパワーワードをぶち込みその場をカオスと化していく。
この圧倒的な「作り込んでいない感」は漫才中なのにふたりのラジオを聴いているような感覚に陥る。他のコンビでは絶対に真似できない唯一無二のスタイル、それが三四郎。ゆえにM-1グランプリなどではセミファイナル常連コンビでもありながら、どこまでがネタでどこまでがアドリブかわからない芸風は「作品性」が求められる賞レースにおいては評価が得られにくいという側面もあったように思う。
しかし、三四郎の本質とは「アドリブ風に装うことのできる演技力の高さ」だと気づいた出来事があった。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR