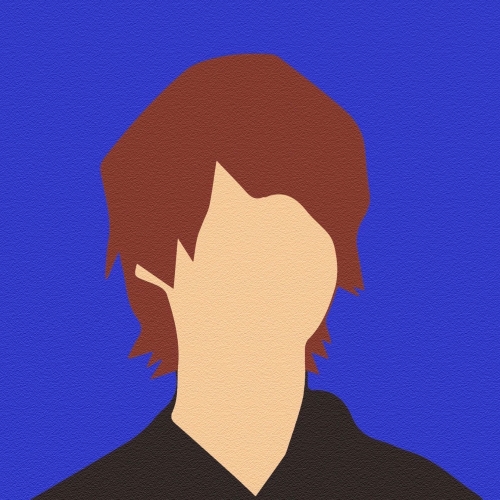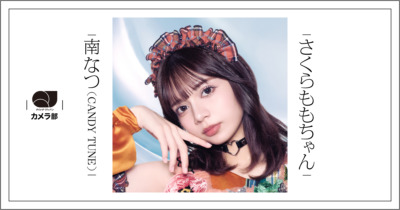構成作家・河谷忍による連載「おわらい稼業」。ダイヤモンド、ケビンス、真空ジェシカら若手芸人とともにライブシーンで奮闘する、令和のお笑い青春譚。
お笑い番組を作るために制作会社に就職した河谷。しかし、待っていたのは理想と違う現実だった。退職願を出すまでの半年間を振り返る。
面接からの約束
「基本的には全員のやりたい番組に就かせてあげたいと思ってるから」
面接のときから聞き続けてきた言葉だ。目の前の男がしゃべるたびに周囲には珈琲の匂いが立ち込めた。カップになみなみに注がれた珈琲が湯気を立てているのではない。この男は珈琲を飲みすぎて鼻から吸った空気を口内や歯にまとわりついた珈琲臭のフィルターに通して排出する人間“逆”空気清浄機なのだ。普段は芳醇で至高なあの香りも、人の中から出た時点でただの異臭である。少しばかりうっとなるが、うっとなってませんよみたいな顔で話を聞く。
だいたいのADといえば自分が望んでいない番組に配属されて文句を垂れながら仕事をするイメージがあるが、私が就職したこの会社の社長は各々が望む番組に配属させられるだけの力があるようで、久しぶりに会う同級生数人と飲みに行ったときに「あの子呼んだら来てくれるんちゃうかな、電話してみる?」と、名前を聞いても何してるかわからんような知らんインフルエンサーの連絡先を持っていることだけがポリシーのしょうもないスタートアップ勤務の男のような口ぶりだった。今思えば「口ぶり」という言葉は口で屁をこいたみたいな音だから不快である。
「ぼく、面接でも言ったかと思うんですけど、お笑いがやりたいんです、お笑いの番組を作りたいです、というかお笑い以外はやりたくないです」
私はテレビの現場で仕事をするということに対して、関西弁の女子小学生がいじめられたときに言う「うち、負けへんで」ぐらい鮮明なビジョンを持っていたのだ。何があってもお笑い以外のことはやりたくないし、やっても仕方がないと思っていた。なんなら東京に出てきたのもお笑いの仕事をやるためである。それ以外のことをするぐらいならすぐに実家に戻ってバイト生活をするほうが幸せだと思っていた。
「OK、さっきも言ったけど基本的には全員をやりたい番組に就かせてあげたいと思ってるから」
社長はそう言うと少し笑って見せた。黄色い歯の隙間からおそらく珈琲の匂いがする風がやってきたので、私は鼻の息を止めて「お願いします」と返事をした。実際の勤務が始まるまでの期間に、上司たちが新入社員たちをどの局のどの番組に配属するかを決定していく。今となってあの会社は社員と社長との距離が近くて風通しのいい職場だったなと感じる。距離が近くて風通しがいいぶん、こっちは社長の口から吹く珈琲の偏西風を浴びることにはなるのだが。数日後、社長から呼び出された私はそんなんじゃ済まないような衝撃のひと言を浴びせられることになる。
理解できない現実
「いろいろと役員で話し合いを重ねた結果、あなたには局への派遣というかたちではなく、うちの会社の制作部門として、まずは通販番組を担当してもらいます」
タクシーで「どちらまで?」と聞かれたので「渋谷駅まで」と言ったらドライバーの実家まで連れていかれて、見知らぬ家族とこたつで味噌鍋をつつかされているような感覚になった。もっとわかりやすくたとえるならば、仕事帰りにコンビニで弁当を選んで、今日はいつもと違う麺類を買ってみようかしらとお弁当の棚からそばやうどんの棚に横移動するも、並んだうどんやそばがさっきお弁当の棚で見た生姜焼き弁当の魅力には勝てずにまた横移動で棚を変え、変なステップを踏んだようになりながら結局いつもどおりの生姜焼き弁当を選んで家に帰り、レンジに入れて500Wで3分と書かれた表示どおりにあたためをスタートしてその間に手洗いとうがいを済ませながら靴下を脱いで風呂場で足だけを洗って部屋に戻ると、あとちょうど10秒ぐらいになっていてわくわくしながら減っていく秒数の画面表示に合わせて首を縦に振り一秒一秒が減っていくのを楽しみながら待ってあたため終了の音が鳴ってレンジの扉を開けるとうんこが入っていたみたいなことである。
自分で言っていても意味がわからないが、当時の自分は理解が追いつかないあまり白目で天井を見つめていた。500wで3分温めた生姜焼き弁当は知らないうちにうんこに変わってしまったのだ。通販番組がうんこだとかを言いたいわけではけっしてない。自分が思い描いていたものとはあまりにもかけ離れすぎているということである。テニスとペニスぐらい違う。きっと親も読んでいるだろうからあんまりペニスとかは言いたくないのだが、そんなことも平気で言えてしまうぐらいには違うのだ。しかしテニスもペニスもラブゲームという点に関しては一緒かもしれない。ゲームでいえばMr.Childrenの「シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜」の歌詞に「ねえ 変声期みたいな吐息でイカせて 野獣と化して Ah Ah」とあるが、あれはさすがにエロすぎると思う。
「あいや、すいません、僕はその、バラエティがやりたくて」
当たり前である。私は面接のときから言い続けてきたのだ。「お笑い番組がやりたいです。お笑い以外はやりたくありません」。そのたびに社長からは「希望には沿う」と言われ続けてきたのだ。なにやら眩暈(めまい)がしてきたような気がした。
「うん、まあ、その気持ちはわかるけども、ゆくゆく、ね」
嘘だったのだ。愛想なしの社長が笑った。珈琲の匂いがした。
通販番組のADとしての仕事
ADとしての初めての仕事は、次の通販特番で紹介する商品の魅力を番組内でどうやって引き出すかの会議だった。たとえば商品が枕であれば、その枕の上で寝ているときと寝ていないときで足ツボマッサージを受けたときの痛さが変わるだとか、美顔器具であれば顔の半分だけその機械で1分間マッサージを行い、顔の左右で引きしまり加減を見るだとかを打ち合わせる。タレントが開発に関わったハンドバッグについて話をしているときに「夏場の放送なのでこのタレントさんが外を歩いてるときにバッグから大きな麦わら帽子を取り出して、こんな大きい帽子も入りますみたいなアピールはどうですかね」と言ったら総合演出にはっきりと「黙れカス」と言われた。
私は面接のときから言われ続けてきた約束と違う現場に行かされて、やりたくない会議に参加させられて、それでも「仕事は仕事!」とがんばって発言をしたら「カス」と呼ばれる仕事に就いてしまったのである。小動物なら泡を吹いて死んでるぐらいのストレスを初日で抱え、これが社会かとお先真っ暗になってしまった。どれくらい真っ暗かというと、芸大生がやってる夜にはバーになるタイプのカフェの照明ぐらい真っ暗だった。たぶんこんなたとえをさっきの会議中に私がみんなの前で言ったとしたら、馬乗りになって首を絞められていたに違いない。先に言ってしまうが、本当に退職してよかったと思う。
その制作会社は半年も経たないうちに辞めた。決め手になったのは通販特番の放送が終わってやっと次の番組に就けると思ったら、社長から言われた次の仕事がさっきの通販番組の続編だったからだ。そんなわけあるかいなと思った。そんなわけあるかいなって言った。実際に。しかしびっくりすることに、そんなわけあったのだ。
退職願を出した日
とある猛暑日だった。都内のレンタルハウススタジオを手配し、撮影に使用するアイテムを先輩とハウスの中に運ぶ。大型のハイエースが停められる駐車場から少し離れた場所にそのハウスはある。台車の上に機材や商品を載せてハウスまでの坂道を登っていくが、もちろん後輩の私がすべてを運ぶ。下着の中まで汗をかき、すべてのやる気がなくなる。
やっとの思いでハウスに到着し、備えつけのエアコンをできる限り最大風速で運転させる。ズボンのポケットに入れていたハンカチは足のももにかいた汗を吸い込んですでにびしょ濡れになっていた。額の汗を拭ってぬるくなったポカリを飲み干しながらハウスに置かれたソファに少しだけ腰かけた。
「おい」
先輩に声をかけられ、私は慌ててソファから立ち上がった。
「すいません、ちょっと暑くて疲れちゃってて」
「いや、そうじゃなくて」
「はい?」
「汚いよ、そのソファ」
「え、全然汚れてないですけど?」
「ほんとに何も知らないな、AVだよ、AV」
「AV?」
「ここ、普段AVとかでも使われてるような場所だから、そのソファの上でも何やってるかわかんないよ、たぶん変な汁とかいっぱい染み込んでるし、ウゲ、きもちわり」
先輩は足早にその場を離れるとサイズにしてA3よりもひと回り大きいぐらいの黒い板を段ボールから取り出した。
「そろそろエキストラさん駅に着くから迎えに行ってきて」
やっとの思いで到着したこの場所、まだ冷房も完全に効いていないなか、涼みもできていないこの状況で外に飛び出して駅まで行かなければならない。そのとき私はこの先輩のことを鬼だと思ったので、それ以降、この先輩のことを陰で勝手に「鬼」と呼んでいた。たまに同期のADとご飯に行ったりすると「こっちの番組はあの有名女優がきれいだった」とか「あの芸人が優しかった」とか「あの人は愛想が悪かった」とかを聞かされるのだが、こっちから出るのは決まって「鬼がさ」から始める話ばかりだった。
エキストラは一瞬でわかった。駅前で日傘をさして首からタオルをかけた大きな女性だった。私以上に汗をかいていて、一歩一歩足を出すたびにひゅうひゅうと喉から音が鳴っていた。歩かせるのがかわいそうだとも思ったが、こればっかりは仕方がない。
「水着は準備してくださってるのかしら? ひゅう、ひゅう、私今日持ってきてないけども、ひゅう、ひゅう」
「はい、こちらで用意しておりますので大丈夫です」
「よかったです、ひゅう、ひゅう、遠いわねえ、ひゅう」
再びハウスに到着すると、鬼がカメラや商品のセッティングを済ませていた。やることはやってくれる鬼なのだ。本当の鬼でいうところのおそらく緑鬼である。赤鬼や青鬼は自分がメジャー鬼であることをきっと理解しているはずなので、面倒なことはほかのやつに押しつけて自分たちは楽をする。鬼なのに天狗である。その点、緑鬼は色としてメジャーだけど鬼の種類の中ではマイナーな自負があるので自分でできることは自分でやるに違いない。
「ああ、ひゅう、ひゅう、暑いわね」
エキストラは靴を脱いでハウスに入るや否や、部屋にある座れるものを探し始めた。あっと思ったその瞬間、彼女はソファに深く腰かけてしまった。
「ひゅう、ひゅう、ひゅう」
私と緑鬼は、明らかに目が合ったにもかかわらず、ふたりとも見ていないふりをした。私にもし教会に行く機会があるとするならば、まず真っ先にこのことを懺悔したいと思っている。
「それではこちらに着替えていただきまして」
私はひと息ついたエキストラに水着を手渡した。これから行う撮影は、さっき緑鬼が段ボールから取り出していたA3より少し大きな黒い板を使う。この板は上に乗ると振動で体が小刻みに揺れてよけいな脂肪を燃焼させるというダイエット器具だった。
水着に着替えたエキストラが板の上に乗る。明らかにミシミシという音がして全員冷や汗をかいたが無事に電源が入った。カメラマンが「回った」と合図を出し、私は板のスイッチを押した。「ドドドドドドドドド」と細かい音を立てながら上に乗るエキストラを揺らす。カメラマンに力が入る。
カメラマンは突然「寄りでもいっちゃおう」と言うと、ドアップで揺れる腹の撮影を始める。
「あ、はは、けっこう近いんですね、恥ずかしい」
「いいですよ、奥さんこれすごくいいですよ」
「本当ですか? やだもう」
「もうちょっと寄りで撮っちゃおうかな」
「やだもう! そんな近くで!」
「いいですよ奥さん、すごくいい」
「んもうっ」
カメラマンは大きな声で叫んだ。
「はああい、オッケぇぇ!!!!」
その日に私は退職願を出した。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR