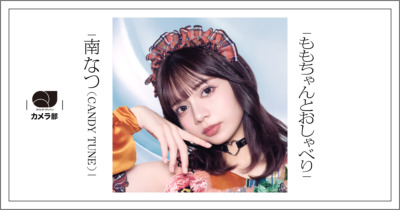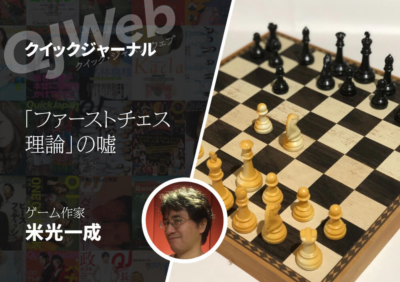インターネットで本人が顔を出すことが一般的ではなかった2010年代のインターネット。その世界で歌い手たちが活動するためにイラストMVは生まれた。「歌ってみた」動画にとってどのような役割を果たしてきたのか、イラストMVの歴史とその効果についてライターのヒガキユウカが解説する。
目次
「歌い手」とイラストMVの始まり
2020年6月27日、香取慎吾がYOASOBI「夜に駆ける」の歌ってみた動画をYouTubeに公開し、注目を集めた。もともと「歌ってみた」は個人が楽しむ同人音楽の文化として発展してきたが、今や多くの著名人が挑戦している。
「歌ってみた」自体はネット黎明期から存在していたが、ニコニコ動画というプラットフォームによって急速に拡大した。個人が匿名で気軽に動画を投稿できること、コメントやマイリスト数によって視聴者の反応をダイレクトに見られること、タグやランキングといった視聴者が新しい動画と出会いやすい仕組みがあったことも影響し、音楽好きの“遊び場”として発達した。
その中で「歌ってみた」活動をする人が「歌い手」と自称したり、周囲からそう呼ばれたりする文化が生まれ、歌い手たちの音楽は同人活動の範囲で楽しまれていた。活動の場はニコニコ動画以外にも広まり、メジャーシーンとの境界も日に日に曖昧になった。今や「歌い手」からプロのミュージシャンとしてデビューすることも珍しくない。
そんな「歌ってみた」は、歌自体だけでなくそれに付随する映像も含めた総合芸術として発達してきた側面がある。というのもニコニコ動画には音源だけの投稿はできず、なんらかの映像をつけて動画の形にしなければならなかったからだ。歌い手たちは、著作権フリーのイラストを活用したりイラストレーターに依頼をしたりして、映像に使用するイラストを用意した。
メジャーシーンと決定的に異なるのは、ほとんどのMVがイラストを使った映像(イラストMV)であったことだ。今でこそ顔出しをする歌い手も増えてきたが、ニコニコ動画が主戦場だった当時、顔出しをする人はほとんどいなかった(そもそも2010年前後はインターネットで顔を出すこと自体が珍しいことだった)。顔を出さず活動をする場合、自分の分身となるアイコンが必要となる。そこで歌い手たちは自分を二次元キャラクター化し、活動の際に使用していた。そんな経緯もあり、歌い手のMVには彼らの分身に当たるイラストや、曲をイメージしたイラストが用いられることが多い。
イラストだからこそできる表現や適度に残された余白の存在は、ファンの考察欲をくすぐる。今回は「歌ってみた」「歌い手」文化の発展を支えたイラストMVとその特長、効果について解説する。