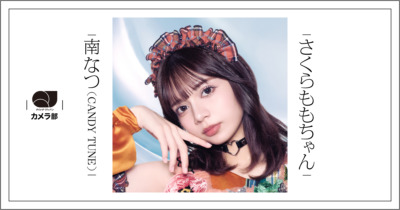今年4月、編集者/文筆家・北出栞の初単著となる『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ デジタルテクノロジーと「切なさ」の編集術』(太田出版)が刊行された。その刊行記念として、QJの連載「扇動する声帯」をもとにした著書『スピード・バイブス・パンチライン ラップと漫才、勝つためのしゃべり論』(アルテスパブリッシング)の発売を控えるつやちゃんとの対談をお届けする。
かたやアニメカルチャーを中心に展開されてきた〈セカイ系〉という概念、かたやヒップホップやお笑いといったパフォーマーの身体性が前面に出るジャンルにおける「声」と、一見まったく交わらないようにも思えるトピックをめぐって文筆活動を展開するふたりが、2020年代の表現をめぐる重要キーワードとして「テクスチャー」という論点で交差する。両者のスタンスの違いも含めて、2020年代文化の行方を占うヒントに満ちた対話となった。
身体性の希薄化と「天使性」の顕現
北出 献本に際して、SNSで「批評でも評論でもなくあえて「創作」と呼びたくなる」というコメントをくださいましたよね。
つや ひとつの結論に向かって進むような本じゃないと思ったんですよ。批評なり評論というのは最終的になんらかの結論を出すものだと思うんですけど、この本は〈セカイ系〉というレンズを通して見えてくるさまざまな事柄を、発散するかのように書き連ねているところがある。だからこそ、終わり方が好きで。「これ以上に言葉はいらない。あとは、祈りと旋律の仕事だ。だから、この本の執筆もここで終えることができる。」そうか、こんな批評があっていいんだと。北出さんが関心を持っているものが断片的につなげられていて、そこに起承転結もあまりないし、この本自体にすごく〈セカイ系〉的な浮遊感がある。
北出 そこは無意識の部分ではあったんですけど、この本の中で主題にしているのが、「固有性よりも匿名性」みたいなことで。話題を点描していって、その中から読んだ人がそれぞれの絵を描いてくれたらいいな、と思いながら執筆を進めていたのはその通りです。
つや 北出さんという人物の人となりを知っていればいるほど、そういったアプローチ自体も含めてやっぱりこの本は北出さんでしかないという、不思議な納得感がある一冊だなと。
北出 あとがきのところに少し書いたんですけど、自分自身が「〇〇ではない」という、否定系の形でしかアイデンティファイされないという感覚をすごく持っていて。「私」というものを否定し続けていくんだけど、その否定し続けること自体が「私」なんだというところに回帰してくる。つやちゃんさんのもう一個のコメント、「どうしても身体論として読んでしまう」というのは、そういうところにあるのかなと自分は解釈してて。
つや そうですね、まさに。そういったアイデンティティに対する違和って、つまりは自身の身体についての違和感と密接につながっていると思うんですけど、この本を読んで、浜崎あゆみにしろポスト・ボカロミュージックにしろ、改めて流動的で不定形な身体というものが前提になっていることを感じたし、北出さんの関心もそこにあるんだろうなと再認識しました。やっぱりこれだけ人類の文化資産についてのデータベース化が進んで、生成AIによる可能性も広がってきている中で、音楽にしろなんにしろ、芸術表現って、もうその人固有の身体をいかに問題提起するかでしかほとんど差がつかないということを感じるんですよね。
北出 それには同感な一方、TikTokのダンス動画とか、YouTuberとか、今は自分の身体を前面に出して、アクションして、その面白さで引っ張っていく表現が目立つじゃないですか。でもなるべく身体を隠したまま表現したい人もいるはずで、そういう人のための理論を作りたいという気持ちがあるんですよ。
本の中でつやちゃんさんの記事も参照させていただいた、「天使界隈」「くらげメイク」みたいな、身体性を希薄化させていくようなあり方が、身体性とセットで語られがちなヒップホップやファッションの領域でも出てきていて。かつては『エヴァ』みたいに大きい作品があって、それに応ずる形でネットコミュニティから〈セカイ系〉というワードが出てきたのに対して、現代は作品を作り、とりあえずネット上にアップするということが誰にも容易になっていて、それについて語るコミュニティも、さまざまなSNSやプラットフォームに分散している。かつての〈セカイ系〉と同じ感性、なるべく匿名的でいたいみたいなことと、その孤独感を、本当は誰かと共有したいみたいな感覚のアンビバレンスが、今だとnyamuraやTohjiなどの、SNSや投稿プラットフォームに表現者自らが天使性をまとって顕現する事例として現れているんじゃないかって話なんですね。
だから、つやちゃんさんが天使界隈とかの記事を書かれていたのは、自分からすると意外だったんですよ。つやちゃんさんは個人的な好みとしては、ヒップホップやR&Bにしろ、表現における「色気」をなにより大事にしている人だと思ってたから。「色気」とはなにより身体性をいかに受け手に意識させるかということで、天使に近づきたいというのは、それを積極的に隠そうとしている人という理解を自分はしているので……隠そうとしても隠しきれないものがあるから、そこに惹かれるってことなのかな。
「きめ」=テクスチャーの重要性
つや 自分からするとnyamuraやTohjiは、身体を希薄化していくというかたちで、その人固有の身体的問いが重要なテーマとして作品に反映されている……という見え方になりますね。そもそも、hyperpop周辺が生んだ退廃的なムードにしろ、PinkPantheress以降支配的になった「Ethereal」なムードにしろ、身体を希薄化させることで問題提起する傾向が近年は強まっていると思います。
それは規範的とされてきた性のあり方に対する抵抗など、個別の状況があるのでなにが理由とは一概には言えないですけど、その対極として身体性をはっきりと打ち出している人たちももちろんいて、両者が引っ張り合うように文化を形成しているような状況がある。K-POPが最も象徴的で、サウンドだけで捉えると、前者はNewJeans的なもの、後者はaespa的なものとしてひとまず言えるでしょう。
自分がいわゆる作品論や芸術論に興味を持ったきっかけは、学生の頃にロラン・バルトの「声のきめ」(『第三の意味』所収)というエッセイに出会ったことなんです。バルトはそこで歌について、歌唱の技術的なうまさみたいなものとは別に、声の「きめ」という評価軸があるんだということを言っている。非常に抽象的な概念なんですが、今もその謎を解き明かすために音楽を聴いたり文章を書いたりしているところがあります。自分にとって「色気」という言葉でイメージされるのは、身体性そのものというよりはこの「きめ」のほうに近い。
だから、身体がいかに作品に現出しているかという点で北出さんとあまり好みが合わない部分も多いけど(笑)、この本の問題意識の持ち方は、いま言ったような意味ですごく共感できるんです。
北出 なるほど。確かに「きめ」、つまりテクスチャーという話でいえば、この本にも共通したテクスチャーを介して、異なる表現ジャンルをつないでいくみたいなところがあって。象徴的なものとして「青空」とか、「半透明性」というのを押し出しているんですけど、これらのテクスチャーは身体からは離れたところにあることが直感的にもわかると思います。そして、そういうものを大事にしつつ、自身の身体性は積極的に消していこうとする人に自分は惹かれる。
つや ですよね、そこは違いますよね。

トラックメイカーの身体性って?
北出 自分は音楽リスナーとしては、バンドが好きで、そのインタビューが載った『ロッキング・オン・ジャパン』(ロッキング・オン)も逐一読んで……といった、典型的な「邦ロック」好きみたいなところから入ってるんです。ヒップホップも含めたエレクトロニック・ミュージック、DTMで作られる音楽に関しては、仕事上の必要に迫られたのもあって、コロナ禍で集中的に勉強したんですよね。
そこで衝撃を受けたのが、横川理彦さんという音楽家の方が書いた『サウンドプロダクション入門 DAWの基礎と実践』(ビー・エヌ・エヌ)という本で。そこには、「音楽を構成する三大要素はリズム・メロディ・ハーモニーと言われているけど、DTMで波形を直接取り扱えるようになってからはサウンドのきめ、つまりはテクスチャーによってアイデンティファイされるようになったんだ」ということが書かれていて。
つや SNSの音楽好きの間でも話題になっていましたよね。
北出 ですね。それまでは音楽のことを、まさにリズム・メロディ・ハーモニーが織りなす起承転結というか、ストーリーに沿って聴くものだと思っていたんですよ。「ロキノン系」にしても、セルフヒストリーを深掘って、こういう家庭環境だったからこういう曲なんでしょみたいな、渋谷陽一イズムがあるわけじゃないですか。そういう枠組みの中にいながら、「(作曲者である)自分自身よりも曲の方が偉くて、自分はその声を受信してるだけなんだ」みたいなことを言っている、BUMP OF CHICKENが好きだったんです。
でも、そんなロックバンドとしては異色だったはずのBUMPが、「ロキノン系」の代表格になり、後発の、自分自身の身体を隠して活動するボカロPたちに大きな影響を与えていたりする。これってユースカルチャーのひとつの巨大な幹を作っているはずなのに、語る言葉が全然ないなというのはずっと思っていて。
で、さっきのサウンドの話を知って、音楽をテクスチャーの組み合わせの妙や、それを実現するDTMソフトの機能にフォーカスして語ることができるんだと思ったときに、いろんなピースがハマって。そこから「新海誠」という作家のバイオグラフィよりも、彼が使っているAdobeのソフトとかのほうが「新海誠らしさ」というものを形作っているんだ、という今回の本の論旨につながっていくんですね。
つや なるほど。それは非常に現代的なアングルですね。
北出 今回の本では、現代の「作者」というのは、ソフトウェアを対等な相棒と見なして、「協働」する人なんだという定義を打ち出していて。人間が半ばソフトウェアに主体性を明け渡すことによって「出力」されたものが、「作品」なんだという。そこでつやちゃんさんに聞いてみたいのが、たとえばトラックメイカーの身体性ってどう考えますか、ということで。
つや 身体性というと普通は歌やラップのことを考えそうだけど、北出さんはトラックメイカーのほうに意識がいくということですね。
北出 というより、純粋にソフトウェアのことを考えたいのだけど、それを操作する人間の身体があるよなと、「仕方なしに」身体の存在が浮上してくるって感じですね、思考の流れとしては(笑)。
トラックメイカーだけじゃなく、映像制作とかでもそうですけど、パソコンの前に座って、マウスなどのインターフェースを介してソフトウェアを操作して、コラージュ的に作品を作っていくという身体性があると思っていて。芸術における身体性って、たとえば絵画だったら筆をストロークする腕の動きであったり、逆にそこから離脱しようとしてジャクソン・ポロックみたいな人が出てきたりするという流れがあるわけですけど、特にイラストレーションにおいては、ほとんどの人がマウスやペンタブを使っている。作品と身体の関係というものを考えるときに、ソフトウェアやインターフェースと一体化した、サイボーグ化した身体みたいなものを想定する必要があると思うんですね。そういう身体について語る言葉って、まだない気がしていて。
仮にパソコンに意識があったとしたら、自分の前に座った個々の人間の区別なんてつかなくて、「ああ、「人間」がなんかやってるぞ」としか思わないわけじゃないですか、おそらく。でも、実際にはそこから多種多様な作品が生まれてくるわけで、そんな「無名の身体性」とでも言えそうなものに関心がある。
つや 今はシンガーソングライターとしてトラックメイクも歌も全部ひとりで完結させるという制作方法がかなり広がってきているのが面白いですよね。トラックを作って、それに合うラップとか歌を入れた上で、思っていたイメージと違う声質で歌が入ったから、ちょっとトラックのほうを変えようかな、といったことが常にデスクトップ上で起きている。その声も、オートチューンによって加工するのが前提になっていたり……だけど、それでも作品に記名性が生まれるからすごい。身体はサイボーグ化しても、そこにまだ固有の身体に対する問いがある限り違いが現れるということなんだと、北出さんの話を聞いていて思いました。

Y2Kリバイバルの背景にあるもの
北出 この本は、Y2Kリバイバル論としても読めるようになっているはずなんです。そもそも〈セカイ系〉という概念が2000年代初頭に生まれたものですし、当時の、インターネットとパソコンが普及したばかりで、回線もスペックも貧弱な中、「どこか遠く」みたいなものに接続できそうでできないもどかしさというのが、時代の感覚としてあったはずで。それを『ほしのこえ』みたいなアニメ作品にした新海誠もいれば、浜崎あゆみや、その歌詞に影響を受けたケータイ小説もある。NewJeansのMVに影響を与えていると言われる、岩井俊二の『リリィ・シュシュのすべて』とかもそうですね。
Y2Kがなんで流行っているかというと、仮説としては、現代の、誰とつながっているかすべて監視化され、「あなたはこういう人間です」というのがアルゴリズムにすべて先回りされ……というのを窮屈に感じているティーンエイジャーの人たちが、とはいえ、インターネットとは一蓮托生となっていて、そこから脱することも難しい中で、インターネットやパソコンというものが出てきたばかりの時代の表象に、「ありえたかもしれない未来」を託しているということなのかなと思っていて。デジタルテクノロジーによって「どこか遠く」につながるということへの期待と、それと表裏一体の「自分が誰でもない」ことの不安や孤独が、ないまぜになっていた時代の感覚というか。
つや まさにそう思いますね。あと、社会背景も大きいのかなと思って。2000年代初頭までは、やっぱり不況だなんだと言いながらどこかバブルの残り香があって、「あの時代」が戻ってくるかもしれないという希望がまだあった。今は確実に戻ってこないだろうという諦めが蔓延しているし、実際戻ることはないですよね。Y2Kと言われる作品を見ると、ユートピア的に当時を描くものが多い。「そんなに素敵な時代だったっけ?」みたいな(笑)。むしろデフォルメの強度というか、その塩梅を競っているような印象すらある。次はどうなるんでしょうね。2010年代リバイバルとかあるのかな?
北出 なさそうな気がする……。今回の本でY2Kの対岸に置いているのは、やっぱりソーシャルメディア、スマートフォン以降なんですよね。つまり2010年代以降、正確には2007年以降で。この年の近辺でiPhoneが出た、Twitterも出た、ニコニコ動画も出た、YouTubeも出た。初音ミクもだし、『エヴァンゲリオン』の新劇場版も。カルチャーとしての「2010年代」って、そこから規定されていったと言えると思うんですよ。それに伴って、孤独をじっくり味わうみたいなことができなくなってきた。それこそダイヤルアップ接続とかで、つながるのを待つような感覚としての孤独ですよね。
あと、バブルの残り香があったという話がありましたけど、逆にいうと現実にはバブルはとっくに終わってたわけで。世紀末とかもあったりしたから、なにかしらのポイントオブノーリターンが来てるぞっていう感覚自体はあったと思うんですよ。そのうえでの、精一杯の空元気みたいなものが、今からすると明るく見えるっていうことなんじゃないかなと。
つや それはそうですね。
北出 2000年代初頭は絶望と希望の間で揺れていたのに対して、現代はもっとのっぺりと絶望が続いている感じ。本の中で出している「半透明」というキーワードも、白か黒かではない、曖昧な領域でフワフワと漂っているという意味で使っているところがあって。それは実際にY2Kのビジュアルにも現れているし、「あのヴェールの向こう側はもしかしたら闇かもしれないよ」っていうところも含めての美学って感じがするんですよね。
つや みんながSNSを使うようになったとき、有象無象の混沌とした情報社会が加速すると思っていたんです。でも意外に、すごくきれいに区画整理された。もちろんミクロで見ると情報は有象無象なんだけど、驚くくらい規定どおりにしか流れない。
2010年代って、基本的に「みんなで生きやすくなっていこう」という時代だったと思うんです。人権的にもジェンダー的にも、いわゆる「弱者の声」が可視化されて、そこにSNSが果たした役割も大きい。でも実際のところ、新たにそういった部分に配慮した区画が作られただけで、現実世界では区画同士の行き来はほとんどない。生きやすくなりつつあるはずなんだけど、でもなんだか生きにくいという不思議な感覚だけが残った。交通の回路が乱れないというか、情報も価値観も、区画整理されたところをスーッとただ流れていっているだけのような。
北出 自分はそういう意味でもダイアルアップ接続や、普及し始めたばかりのパソコンにはあった、動作上の遅延みたいな感覚が大事なんじゃないかと思うんです。この本の中でソフトウェアの話を多くしているのには、そういう理由もあって。たとえばDTMは、スマホだけで完結させる人もいますけど、大半のトラックメイカーはいまだにパソコンを使ってるわけじゃないですか。その際タッチパネルではなくて、マウスや鍵盤などのインターフェースをパソコンに接続してソフトを操作している。
そこには原理的に、情報を入力してからモニタに反映されるまでのコンマ何秒間かのレイテンシーがあるわけです。一方、タッチパネル以降のインターフェースというのは、その感覚をなるべく無化させる方向に進化している。この感覚の変化がたとえばSNS上で社会的な言説を組織しようとするときなど、無意識のレベルで人間に与えている影響はあるんじゃないかという気がしていて。
つや あるでしょうねえ。
北出 で、スマートフォンの表面のように、のっぺりしているというか、平たくツルツルした感じになった世界で、そこに引っかかりとしての身体性を見つけていくという方向性が一方にあるとしたら、自分は現世がツルツルなのはもう仕方がない、だったら、思いっきり意識を上とかに飛ばしたほうがいいんじゃないか、みたいなことを考えている。
つや 空とか?
北出 そう(笑)。そのひとつとして、2000年代初頭の作品に一度ギューンと遡ってみて、そこから逆照射することによって見えてくるものを探っていこう、と考えたんです。
つや それが北出さんがこの本で取った戦略であると。おもしろいですね。でも、自分はまだ上に飛ばず、身体を地に着けたまま、もう少し声のきめについて考えたいかなぁ……。