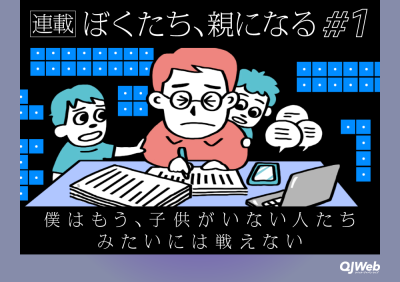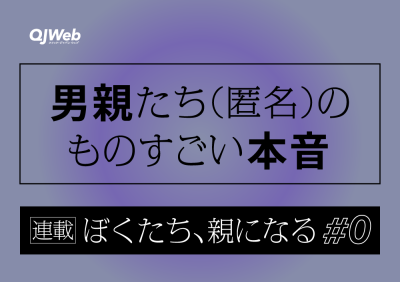子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を、匿名で赤裸々に独白してもらうルポルタージュ連載「ぼくたち、親になる」。聞き手は、離婚男性の匿名インタビュー集『ぼくたちの離婚』(角川新書)の著者であり、自身にも一昨年子供が誕生したという稲田豊史氏。
第1回は、ふたりの子供を授かり、今は妻子と別居中だという40代男性の独白。後編は、妻との出会いから結婚・出産、別居に至るまでを語る。
大手出版社に勤める書籍編集者の栗田将さん(仮名、43歳)は、30歳で販売営業から念願の編集職に異動。生活のあらゆる時間を本作りに充て、死にものぐるいで努力した結果、10万部以上のベストセラーを何冊も世に出した。
しかし第二子が誕生して妻が栄養士の仕事に復帰し、栗田さんも相応の育児を担当することになったとたん、編集者として最も大切な「没入」や「インプットの時間」が激減してしまう。栗田さんは悟った。「もう、子供がいない編集者と同じようには戦えない」と。
そんな栗田さんは、妻子と2年前から別居しているという。理由を聞くと、栗田さんは妻(栗田さんは終始「嫁」と呼んでいた)との出会いを語り始めた。
目次
「正社員じゃないと、一人前じゃない」という嫁
※以下、栗田さんの語り
嫁とは、共通の友人を介した飲み会で知り合いました。当時の彼女は埼玉県の実家住まいで、栄養士として市内の保育園に勤務していたんです。
実は彼女、高校でまったく勉強についていけず、2年生のときに中退したという過去があります。中学までは学年トップクラスの優等生だったものの、その高校が県下有数の進学校で、どんなに勉強しても下1割から抜け出せない。それで心が折れてしまったそうです。中退後は家族の勧めで大検を取り、短大の栄養学科に進んで栄養士の資格を取りました。
飲み会後、僕らは交際が始まり、都内に引っ越して同棲をスタート。嫁は埼玉の保育園に通うのが大変になってしまったので、結婚を機にすぱっと仕事を辞めました。嫁自身の意思です。
嫁は自己肯定感の低い人間でした。交際当初の口癖は「私は人生ドロップアウト組」「昔の友達には恥ずかしくて会えない」。聞けば、高校時代の同級生の大半が、名のある大学から名のある企業に就職しているとのこと。高校の進路指導は「最低でもMARCH」が合言葉だったそうです。

そんな人と、なぜ結婚したか。僕はもともと、人生にはうねりと変化があるものだと思っているんです。
ジェットコースターみたいなもので、今は谷底にいても、いずれは必ず上がってくる。僕だって30歳を前にして編集者になれました。それに、同じジェットコースターでも、一緒に乗っている人数が多いほうが楽しいじゃないですか。
結婚後、ごく自然に子供を作りました。ふたりとも昔ながらの考え方の人だったので、「結婚したら子供を作るもの」という発想になんの疑念も抱いていなかったんです。
第一子、上の息子は「幼稚園に入るまでは家で子供の面倒を見たい」という嫁の希望を汲み、そうしました。
上の息子が3歳になって幼稚園に入園すると、そのタイミングで嫁はパートに出るようになり、2年後に下の子が誕生。すると「パートではなく、栄養士として正社員で働きたい」と言い出しました。
嫁の中にはずっと、ある種のうしろめたさがあったんです。「私は中学まで優等生だったのに、いい大学にもいい会社にも入れなかった。せめて正社員じゃなきゃ一人前じゃない」って。
生真面目なんですよ。その生真面目さこそが、彼女の自己肯定感を下げていったわけですが。
別居の提案は嫁から。彼女が本当に求めていたものは
彼女の中にはずっと、「正社員として働いていない自分は不甲斐ない」という気持ちと、「でも母親として子供の面倒を見なければ」という責任感が同居していました。なんなら、「子供を作り、母親になってこそ一人前」という気分もあったと思います。
実は下の息子が生まれたとき、そんなアンビバレントな心理状態がたたって、嫁は産後うつになってしまったんです。
僕は「子供見てるから、外出てきなよ」などと提案していましたが、「行くところがない」「会う人がいない」「お金を使うことに罪悪感がある」と言うばかりで、なかなかうまくいかない。
それで、今思えば僕が悪かったのですが、僕はそのとき、本作りに没頭するあまり、彼女のつらい胸中をじゅうぶんに「聞いて」やれていませんでした。
僕がしていたのは、ただ正論を述べることと、解決法の模索です。つらいなら保育園に入れればいいじゃない、それで母親の義務を放棄したことにはならないよね、外でお金を使うことに罪悪感なんて感じる必要はないよ、カルチャースクールか地域の集まりにでも入ってみたら話し相手ができるのでは──みたいな。
でも、彼女が求めていたのは、そういう「ロジカルなソリューションの提案」ではありませんでした。もっと、気持ちに寄り添うことだったんです。

嫁との心の距離は、そのころから離れ始めていたように思いますが、とにかく下の息子は1歳で保育園に入り、嫁は栄養士の仕事に正社員として復帰しました。
嫁とのコミュニケーション不全が3年ほどつづいたところで、新型コロナのパンデミックに突入しました。お話ししたとおり、僕は仕事が思うようにできなくなって鬱屈し、「戦えない」という焦りや不機嫌が、嫁への態度にも出てきてしまいました。
別居を提案してきたのは嫁です。2年前くらいですね。僕は抵抗することなく承諾し、自宅マンションを妻子に明け渡して、家を出ました。今は隣の駅でひとり暮らしをしています。
子供のこともあるし、離婚はしていません。子供とは隔週ペースで会っています。妻子に生活費を渡すと僕の年収は300万円くらいになってしまいますが、不満はありません。再婚する気はないし、特に欲しいものもありませんので。もう43歳ですし。
40代になった今、すでに自己表現欲は満たされている
僕は30代でヒット作を何冊か出せたので、すでに自己顕示欲や自己表現欲は満たされてるんです。ぶっちゃけ、もう定年退職したい気分ですね。
生きていくのに困らないだけのお金があれば、それでじゅうぶん。「40歳は心の定年」って言ってる人がいますが、その気持ちはよくわかります。

人は何歳くらいで一番いい仕事をするのか、考えたことはありますか? 職種にもよりますが、文化系にとってインプットの量が稼げてアウトプットの質が一番高い時期って、やっぱり30代から40代の頭までという気がするんです。周囲の人たちを見ていると。
これが編集者の場合、それだけじゃない。自分がいいと思ってるものと、世の中がいいと思ってるものが、自然とぴったり合っている時期が、30代の10年だと思うんですよ。これってすごく大きい。
この時期を過ぎると、いちいち補正が必要になるんです。自分が直感的に「いいな」と思ってはいないものが、社会のメインストリームだったり、話題の中心だったり、経済を動かしていたりする。
僕の場合はSNSが顕著で、ツイッターが出始めたときは直感的に「いいな」「自分でもやってみたい、いろいろ試してみたい」と思ったけど、TikTokはそうじゃなかったんです。
30代は、蓄積した知見の量と、思考や発想力のキレと、フットワークやコネクションや組織内でのポジションのバランスが、一番取れている時期。「黄金の10年」とでもいうのかな。
で、子育てにリソースを取られる時期というのが、その「黄金の10年」に丸々かぶっちゃってる。
「黄金の10年」が子育て期と丸かぶり
そのかぶりを避けるには、子供を作る時期を思い切り早めるか、思い切り遅くするしかないじゃないですか。
だとすると、仕事をジャマしない子作り適齢期は、たとえば「23歳or47歳」といった二択になります。23歳で子供ができれば、小学校入学で29歳。僕は30歳手前で編集者になったわけですが、それだとちょうどいい。
ずっと前から、一部の女性はこういう発想でライフプランを組んでますよね。早めに結婚してすぐ子供を作り、ビジネスパーソンとして一番脂が乗ってくるであろう30代に、子育ての一番大変な時期がかぶらないようにする。
でも、男で前もってこれに気づけている人って、僕の世代にはほとんどいないんじゃないですか? まさか、子育てがここまで仕事をジャマするとは予想していませんでした。
というか文化系男子の多くが、自分がいつ「ベストパフォーマンスを出せなくなるか」を事前に予想できていない。僕もそのひとりでした。
男性でも、フィジカル(肉体)を売り物にするアスリートの方々はちゃんと意識していますし、意識せざるを得ません。自分のフィジカルのピーク時期から逆算して、人生設計をしなきゃいけないから。
本来は文化系男子も、能力のピークから逆算して人生設計をするべきですが、フィジカルの衰えに比べて「知的生産活動がいつから衰え始めるか」は、なかなか定説がないですよね。
仕事のやり方は「地引網」から「一本釣り」へ
職業によっては、ある年齢を超えたら、ことさらインプットしなくてもそれまでの蓄積でやっていける、ということはあると思います。稲田さん(注:インタビュアー)のような文筆業の場合、インプットをしつづけないと、向上どころか現状のキープすらできないので難しいでしょうが。
それができないなら、解決策は子育て自体をインプットにする、つまり子育てをアウトプットのネタにするしかありません。編集者ならさしずめ「絵本を作る」「育児書を企画する」でしょうか。でも、そんな簡単に部署異動できるわけでもありません。
近頃の書籍編集者としての僕は、30代のころとはかなり違うスタンスで仕事をしています。以前はノンフィクションであればそれこそなんでもやっていましたが、今は手がけるジャンルを絞っているんです。
といっても、育児書や絵本を作るというわけではなくて、今まで作っていたものよりは視野角を狭めているということ。アンテナを張りまくって限界まで興味の範囲を広げるというよりは、強く興味を惹かれたテーマだけをじっくり腰を据えて深掘りしていく。そんな感じです。

30代のころの僕の仕事のあり方は、「世の中の問題はこうで、これがこういうふうにいい方向に行くためには、こういう本を出したほうがいいんじゃないか」という仮説を立ててから取りかかる、というものでした。
文字どおり、全ジャンル・全分野を見渡した上で、問題の在りかをサーチする。これは地引網みたいなもので、大量の情報をいったん全部取り込んで、それを机にばーっと広げて、これと、これと、これ……みたいに選別するんです。
でも、今はもう一本釣りです。このへんかな?と当たりをつけて、ピンポイントで釣り糸を垂らす。第二子が生まれて以降、インプットの時間が減ったのもありますが、やはり30代のときほど自分の感性が「キレて」いないからですね。まさに「心の定年」状態ですよ。
「仕事」と「親であること」、すべては手に入らない
「なぜ子供が欲しかったのか」と問われたら、答えに困ってしまいます。子供と遊びたかった、のかな? (数秒の沈黙)うん、それくらいかな。当時は子供を作ることのリスクもデメリットも、まるでわかっていませんでした。
でも、「なぜ」を考え始めたら、身がもたないわけですよ。もたないからこそ、世の中が少子化になっているわけで。前もって完璧に計画してからじゃなければ子供を作れないのだとしたら、持つ人は減って当然です。そればかりは、詰めて考えないほうが踏み切れる。
その結果、黙って仕事上の達成目標を下方修正するか、家庭を破綻させるかの二択を迫られる。僕は、結果的に後者を選ぶことになってしまいました。
上の息子は今12歳ですが、僕が家を出たことについて、たぶん納得はしていないと思います。両親が別々に暮らしている状態が子供たちにとっていいことだとは、もちろん思いません。
ただ一方で……これは僕が子供たちに対して言う言葉ではなくて、僕が僕の人生を考えたときに思っていることですが、「すべては手に入らない」んですよね。
「すべて」の中には当然、「仕事」と「親であること」が含まれています。すべてが手に入らないときに、何を捨てて何を取るのか。それが人生なのだと、日々痛感しています。
「ぼくたち」にとって、親になるとは
※以下、聞き手・稲田氏の取材後所感
同じ業界にいる者として、「よくわかる」としか言いようがない。強烈極まりない告白だった。その上でふたつ、言い添えたい。
ひとつ。栗田さんの言葉にもあるように、「育児で仕事の質が落ちる」は、とっくの昔から女性がこうむっていた超アンフェア案件だ。文化系男子が子供を作って育児参加し、ようやくそれに気づいた、というべきか。
女性からの「何を今さら」という声が聞こえてくる。しかし栗田さんを含む「ぼくたち」は、そうなる覚悟も、そうなるであろうという想像力もなかった。仕方がない。今まで親からも社会からも、そんなことは一切教わらなかったからだ。
もうひとつ。栗田さんはまだ恵まれている。家族は崩壊したが、43歳にして文化系男子としての自己表現欲は満たされているからだ。彼は心の定年を決め込んではいるが、けっして惨めではない。
問題は、栗田さんのような状況に苦しみながらも、栗田さんのようにはクリエイティブ上の成果を未だに上げていない、世の大半の文化系男子である。その数は、それなりのサイレントマジョリティと呼べるほどには多そうだ。
連載第1回にして、文化系男子の「自己実現と子育て」の関係にまつわる論点がほとんど出尽くしてしまった感がある。しかし「ぼくたち」は、“ここ”から始めなければならない。
いい年して、未だに自己実現欲を放棄できない「ぼくたち」は、「子供を持つこと」をどのようにして人生に齟齬なく組み込めばよいのか。「ぼくたち」にとって、子を持ち、親になるとは、いったい何を意味するのか。
【連載「ぼくたち、親になる」】
子を持つ男親に、親になったことによる生活・自意識・人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらう、独白形式のルポルタージュ。どんな語りも遮らず、価値判断を排し、傾聴に徹し、男親たちの言葉にとことん向き合うことでそのメンタリティを掘り下げ、分断の本質を探る。ここで明かされる「ものすごい本音」の数々は、けっして特別で極端な声ではない(かもしれない)。
▼本連載を通して描きたいこと:この匿名取材の果てには、何が待っているのか?