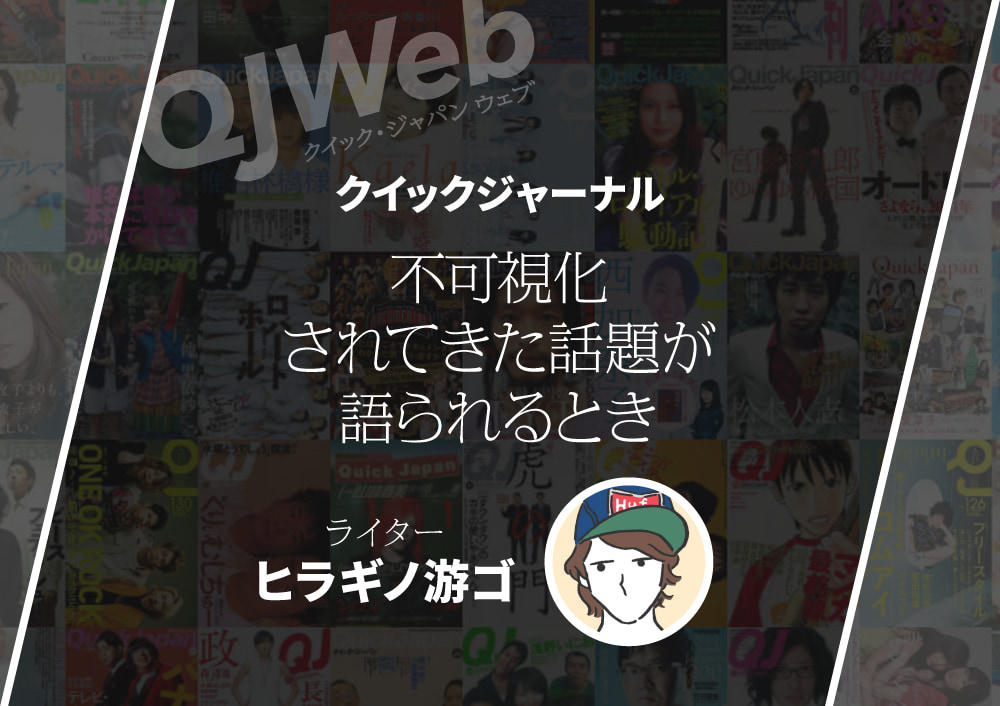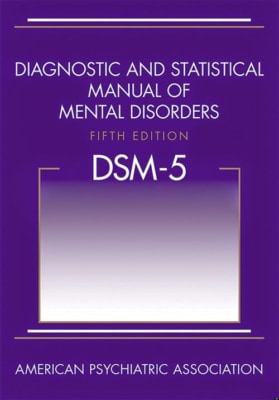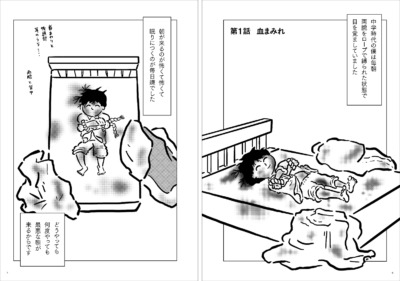『あちこちオードリー』(テレビ東京)でのオードリー若林正恭とオリエンタルラジオ中田敦彦の会話が大きな反響を呼んだ。明言こそしないものの、ふたりはそれぞれの非定型発達傾向について語らっていたのだ。
近年“大人の発達障害”といったフレーズで取り沙汰され、徐々に可視化されつつある発達障害。しかし、TVショー・バラエティ番組の世界ではいまだ当事者(あるいはその傾向を自覚する人)がフィーチャーされることがごく稀であるといえる。そんななかでの件の放送には、SNSにおいて共感や驚きの声が広がった。
しかし、ほかのマイノリティ属性同様、近年になって可視化されるようになってきただけで、けっしてこれまで存在していなかったわけではない。
“ちぐはぐな会話”の副音声
番組中、若林・中田の両名はそれぞれの特性による困難さを語り合った。
中田は近年、これまでの行いを顧みて、自分なりに家族や周囲の人を大事にしてきたつもりだったが、ある日妻から「人の気持ちがわからない」と指摘され、“ある症候群”に該当するのではないかと仄めかされたという。「そんなふうに思われていたのか」とショックを訴える中田に、若林はやおら、子供のころの忘れ物の話を始めた。授業参観や三者面談の案内など、大事なプリントを持って帰れない。持って帰らなきゃと思っているのに、何度も同じことを繰り返してしまう。自分でもなんでこんなふうになるのかわからなかったと。
これは一見、唐突に話が飛んだ、ちぐはぐなやりとりだ。中田の「人の気持ちがわからない」話をスルーしてまったく関係のない話をし始めたと感じた視聴者もいただろう。ただ、また別の層はこの若林の返しに込められた副音声を聞き取ることができる。若林からの「俺もだよ」という共感のメッセージだ。
困難さの種類こそ違うものの、若林も中田と同じように発達特性によってほかの人があまりしない苦労をしてきた。それを仄めかすのがあの「忘れ物」の件で、返事になっていないようでいて実は深く共感を示す応答だったのだ。
発達障害についてネット上で横行している好ましくない現象のひとつが、非専門家による恣意的な症状の断定だ。きちんとした診断の手順を踏まずに(本人を含む)誰かの診断名を決めつける、あるいは診断を受けるべき人を定型発達だと断じて医療から遠ざけるなど、有害さが指摘されている。だからこの記事でも、本人が公表していないことをどうとも断定することはない。
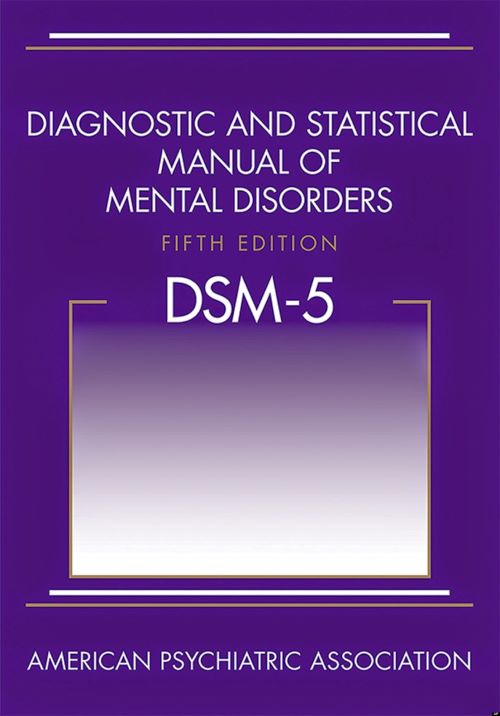
ただ、当事者や傾向を自覚する人、またケアに携わる人は、中田・若林両名が語った内容を受けて、それぞれ思い当たるものがあるだろう。当人たちもそうして伝わる人にだけ伝わるレベルに留めて、慎重に会話を進めていたように思う。
インペアメントとディスアビリティ
お笑い芸人以外にも広げると、自身の特性を公表している著名人は数多くいる。米津玄師は高機能自閉症(原文ママ)、モデル・タレントの栗原類はADD(注意欠陥障害)、ハリウッド俳優のトム・クルーズはLD(学習障害)と、枚挙にいとまがないほどに存在するが、これはあくまで公表しているものだけ。公表していない、また診断を受けていない潜在的な人も含めれば割合はさらに大きくなる。
繰り返すが、現在の社会で発達障害に分類されるような特性を持った人々は、このトピックに関心を持ってこなかった人々が想像するよりもおそらくずっと高い比率で存在してきた。にもかかわらず、社会はそうした人々に“使いやすい”ようにできていない。だから一部の特性が「障害」と見なされる。
インペアメントとディスアビリティという概念がある。
たとえば「下半身が動かず、生活が困難である」という状態を想定する。このとき、「下半身が動かない」という事実がインペアメント。対してディスアビリティは「生活が困難である」という部分を指し、これが一般に「障害」と見なされる。つまり、「下半身が動かない」こと自体が障害なのではなく、車椅子では著しく生活に困難をきたす社会があって初めてそれが「障害」となるということだ(障害の社会モデル)。
メガネの発明以前の社会では、視力の低さが生活に著しい困難をきたし、「ディスアビリティ」になり得ただろう。しかし、社会が発展したことにより、現代では市販のメガネで補える程度の近視はまず「障害」とは見なされない。では、発達障害についてはどうだろうか? 定型発達の人々にだけ過剰に適応したこの社会は問題である、だからよりバランスの取れたものに変えていこう、というのが現在高まりつつある気運だ。

「お笑いと発達障害」は今に始まった話ではない
『あちこちオードリー』の放送から少し遡ると、10月17日にお笑いコンビ・プラス・マイナスの岩橋良昌が強迫性障害を持つことを公表した。こちらは精神障害の一種だが、「お笑いと発達障害」を考える上でも非常に重要なイシューだといえる。
強迫性障害は「自分でもつまらないことだとわかっていても、そのことが頭から離れず、わかっていながら何度も同じ確認などを繰り返すなど、日常生活にも影響が出てきます」と説明される(厚生労働省の公式サイトより)。
岩橋の場合は特に「やってはいけないと言われたことをやってしまう」性質が強く、かねてバラエティ番組で取り上げられていた。岩橋以外にも近い特性を持つ芸人は脈々と存在しており、後輩では首を振りつづけるなどの特有の動きを繰り返すキャツミというピン芸人がいて、彼らのそうした特性は業界で“クセ”と呼ばれる。
「病名がついたらもう“クセ”を笑ってもらえなくなるのでは」という懸念があったと想像できるが、そんななか一歩踏み出して診断を受け、それを公表したことは、業界に素晴らしい進歩をもたらしているように思う。
というのも、お笑い芸人には、これまでに挙げた人々に限らず、特有の癖を繰り返したり、生活に著しい支障をきたすほどに不注意や遅刻や意思疎通のミスが見られたりといった人が多く見られる。それらは往々にして“エピソードトーク”として、笑い話としてアウトプットされるが、場合によっては「笑ってていいのかこれ」と感じざるを得ないこともあるだろう。
チュートリアル徳井義実の税金未納の件が報道されたとき、SNS上では「自分も同じことをやりかねない」「他人事と思えない」「明日は我が身」と、彼同様に「やらなければいけないことを先送りにする」性質を自覚する人々からの投稿が相次いだ。
お笑いの世界は、そうした特性を持つ人々が働く場としてある種またとない包括性のある業界といえる。当人たちが「普通の職業ではまずやっていけなかっただろう」と語るように、社会から阻害されるような人々がその特性を活かして仕事ができる場所としての側面を持つ。
ただ同時に、笑いに昇華されることが一種のガス抜きになり、ケアを受けることから遠ざかっている面もあるのではないかと想像する。「お笑い芸人としては長所だから」というのが正しいとしても、それ以前に一市民である以上、生活に困難を抱えているならば、公共の福祉が提供されてしかるべきだ。
お笑いの世界には、障害に限らず、セルフケアがないがしろにされる傾向を強く感じる。本来もっと深刻なはずの貧困や不健康、酒やギャンブルへの依存、借金など、おもしろがることで一時的な苦難の緩和はできるとしても、根本的な解決から目を逸らすことの正当化や、社会への不適切な価値観の膾炙(かいしゃ)につながるようなことが日々行われている。これは“おもしろい”のだろうか、と都度問い直していきたい。ちゃんとおもしろいことをおもしろがりたいから。
“おもしろい”はまだまだたくさんある
親しくない相手には当たり障りのない話題から始める。またその「当たり障りのない話題」とは天気や気温や季節、共通の知人の近況などのことを指す。葬式では神妙な顔で物静かに、結婚式では主役を立てつつ楽しそうにしているもの。そういったコミュニケーションのフォーマットを、我々の社会は長い年月をかけて構築してきた。
社会生活を送るなかで、我々はフォーマットへの忠誠を日々試される。定型から外れてはいけない。秩序を乱してはいけない。「こう発言する人はこう思われたい人だ」という思考の省略を可能にするフォーマットから逸脱すると、意味不明な存在になってしまう。爪弾き者にされる。そういう者を罰するためのKYという言葉が流行ったこともあった。
お笑いの世界もまた、強固にそういったコミュニケーションのフォーマットを構築してきた社会のひとつだ。
ただ、「お笑いのフォーマットに則っている」ものと「おもしろい」ものは違う。重なり合う部分はある、ただイコールではない。日常生活の中にはもうずっと前から、まだお笑いがフォーマットとして認識していないおもしろい会話がある。時には猛烈にハイスピードで、時にはものすごくスロー。ワープし、反転し、空中分解することもある。詩的で、構築的で、すこぶるシャイだったり、とんでもない近距離パワー型だったり。コミュニケーションのかたちは無数にあり、そのいくつかは現代社会で障害と見なされる要素を持つ人々によるものだ。
我々の社会は当事者たちに「話題があちこちに飛ぶ」「他人の話を遮る」といった特性としてよく指摘されることを気に病ませつづけてきた。しかし、そういった会話もまた、おもしろくて、思慮深くて、馬鹿馬鹿しくて、安らぎを感じ、愛おしいコミュニケーションのひとつのかたちだ。
発達障害以外にも目を向けると、すでに何人もが、世間一般で“笑えない”ものとされてきた自身の属性を笑いとして昇華し、コミュニケーションの可能性を切り拓いている。
先天性の視覚障害がある濱田祐太郎は、自身の“見えないこと”をネタに『R-1ぐらんぷり2018』の栄冠を勝ちとった。その濱田からも関心を寄せられているのは、今年の『M-1』準々決勝に進出したコンビ「ブレード・ランナー」。ボケの車太郎は車椅子ユーザーだ。
車は濱田祐太郎と一緒に“椅子取りゲーム”を軸にした番組である『千原ジュニアの座王』(関西テレビ)に出たいとリプライを飛ばしていた。
また、こちらは障害とは別軸のマイノリティ属性だが、ライブシーンで活動するコンビ「コリアンチョップスクワッド」はふたり共に在日コリアンで、「合コンに来た女の子が在特会だった」というネタで笑いを起こしていた。漫才の形式に落とし込まれた差別へのカウンターだ。笑ったのはもちろん、人間の、文化の可能性を再認識させられ、名状しがたい高揚感を覚えた。
ただ、こういった例を引き合いに「マイノリティの可能性」といった言及をするのはひどく傲慢なように思う。そもそもマジョリティが「自分は選ぶ側だ」と思い込み、勝手に自分たちでフォーマットをこしらえて、それにそぐわないさまざまな人の可能性を潰してきてしまったことが背景にある。今になって可能性に気づいたのだとしたら、今まで気づけなかったのはマジョリティ自身のせいなのだ。そのことを忘れずにいたい。
ずっと共にあった、本来もっと何気なくしゃべれる話題がたくさんある。我々はもっといろんなことで笑えるはずだ。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR