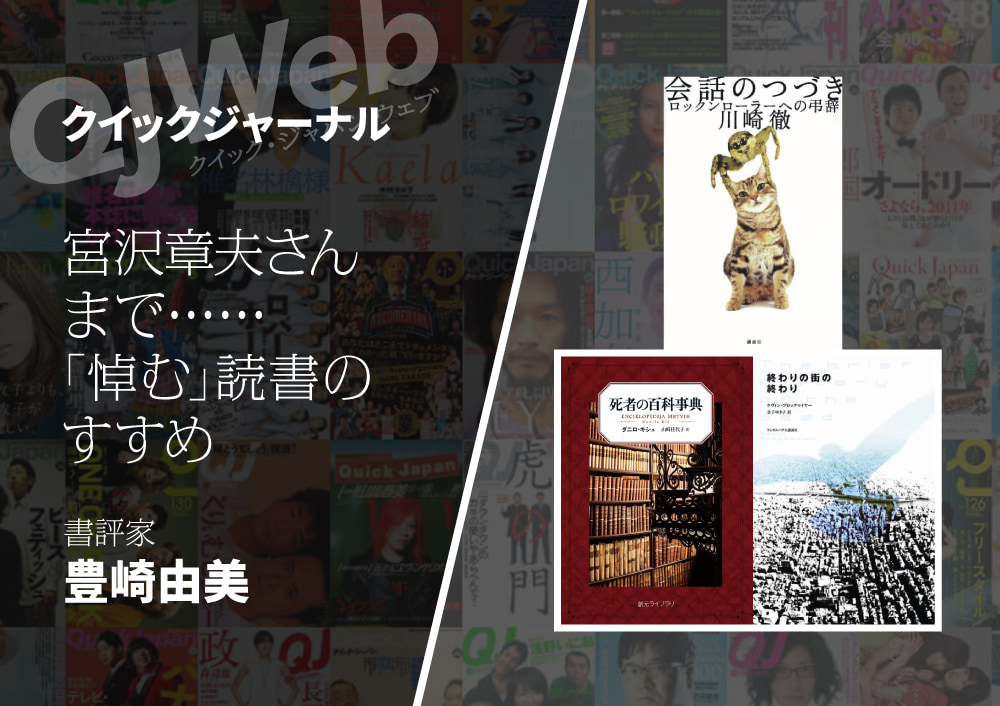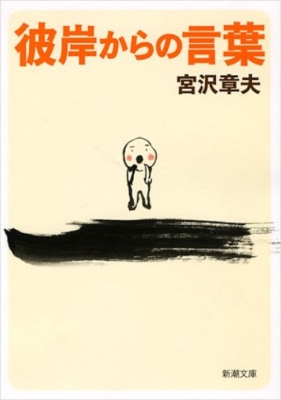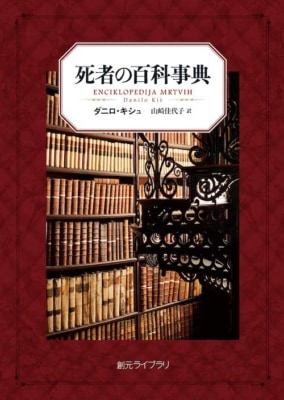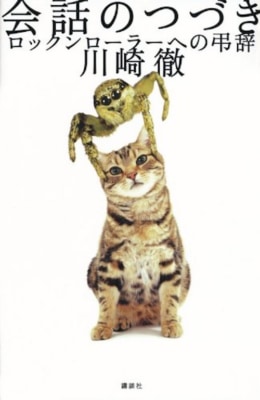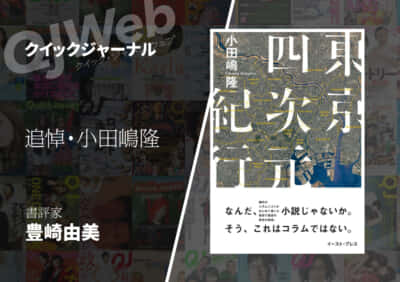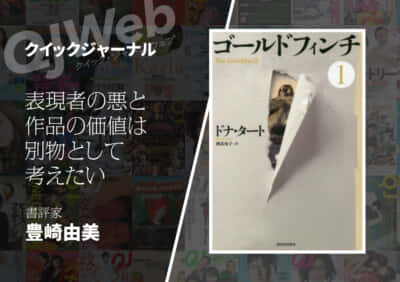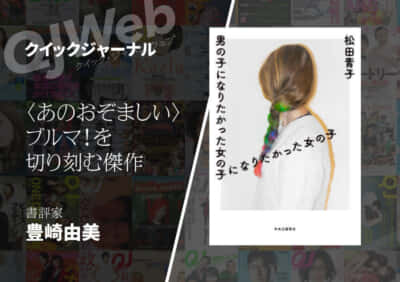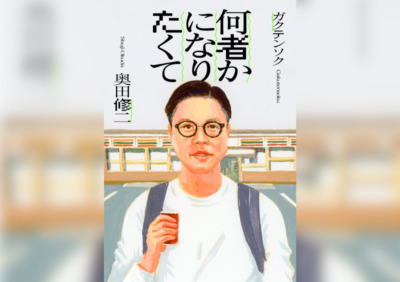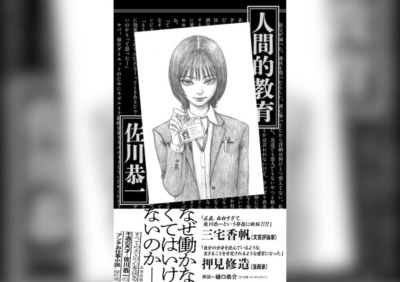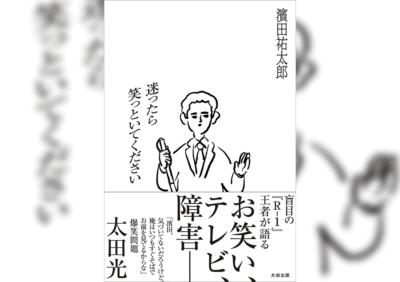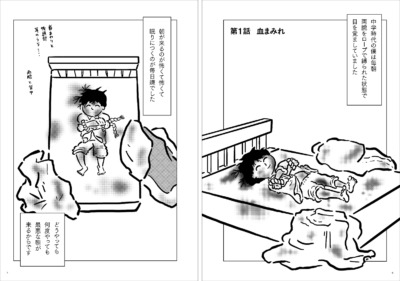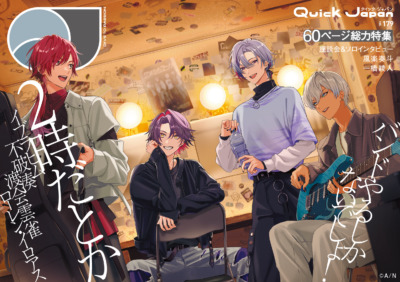小田嶋隆、宮沢章夫、6代目三遊亭圓楽、アントニオ猪木……悲しい死の報せがつづきます。「遺された人間ができるのは悼むことだけ。生者は死者を悼むことで慰撫し、死者は生者を思い出によって慰藉するのです」と、故人を偲びながら、書評家・豊崎由美が送る生者のための読書ガイド。
宮沢章夫さんの思い出
6月24日に小田嶋隆さんが亡くなったばかりだというのに、9月12日に宮沢章夫さんまで彼岸に逝ってしまわれた。
劇作家にして演出家にして小説家。1961年生まれであるわたしの世代にとって、宮沢さんは、たった5歳しか違わないのに常に仰ぎ見るサブカルスターでした。ウィキペディアには記載されてないけれど、まだ有名になる前から、1980年代当時の最先端のクリエイターや文化人が集う原宿のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」に出入りしていたことこそ、わたしにとっては宮沢さんのその後の活躍と活動を裏づける眩しいエピソードだったりします。ピテカンってそのくらい敷居の高い、サブカルクソ野郎(愛着と自嘲をこめての呼称)にとっての憧れの聖地だったんです。
宮沢さんとはその後何度かお目にかかって話をうかがうことができたんですが、一番の思い出は、ライターとして初めてインタビューにうかがった時のこと。マガジンハウスから出ていた『鳩よ!』というカルチャー誌で竹中直人の特集を組むことになり、竹中さんの大学時代からの友人である宮沢さんに話を聞くことになったんです。
憧れの人に初めてお目にかかるんですから緊張もしましたし、失礼がないよう事前の調査怠りなしで臨んだインタビューだったのですが、始まってみると話ははずまず質問を聞き返されることしばしばで、「ああ、失敗だったなあ」と意気消沈。同席した編集者もそう感じたのでしょう、宮沢さんに「昨日のインタビュー、何か粗相があったでしょうか」と訊いてくれたんです。そしたら——。
「いやー、インタビュアーの方の声があまりにもユニークで聞き惚れちゃって、質問の内容が入ってこなかったんだよねえ。彼女は声優か何かなの?」
子供の頃から自分の声が嫌いで、テープ起こしも苦痛でしかたなかったのですが、なんだか宮沢さんから褒めていただいたような気がして嬉しかったことを覚えています。後年、酒席でその時の思い出話をすると、宮沢さん、「あの時はごめんねえ」と謝りながら、「トヨザキさんの声はいいよ。おもしろいよ。記憶に残るよ」と言ってくださいました。ありがとうございます。宮沢さんのおかげで、あんなに嫌いだった自分の声が、今では耳に入っても苦ではなくなりました。
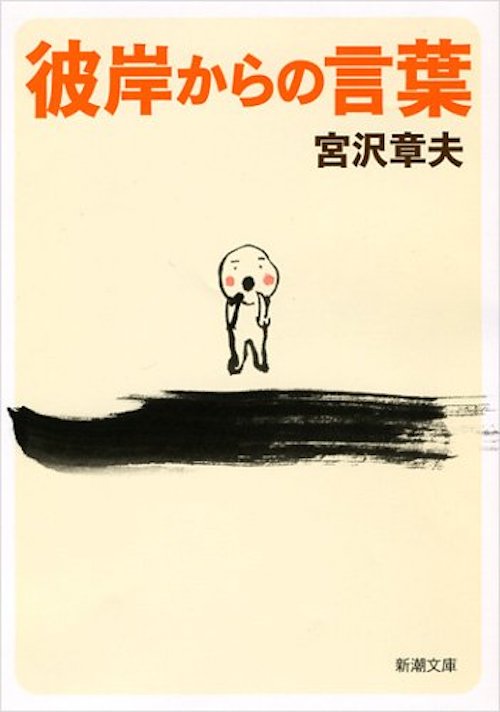
無名の人々の生涯『死者の百科事典』
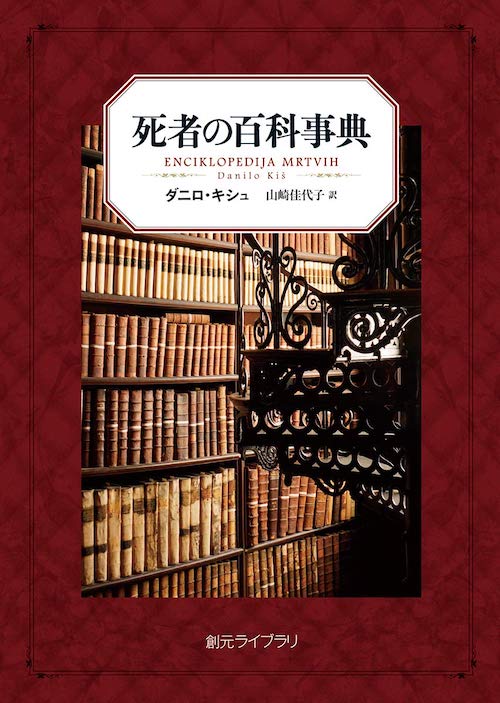
9月30日には6代目三遊亭圓楽さんが、10月1日にはアントニオ猪木さんが逝去。それぞれのファンの方は、小田嶋さんと宮沢さんの死に呆然となるわたしのように、喪失感に打ちのめされていることと思います。もちろん、有名人ばかりではありません。家族や恋人、友人、ペットを失って悲しむ人が、毎日、世界のどこかにおられます。遺された人間ができるのは悼むことだけ。生者は死者を悼むことで慰撫し、死者は生者を思い出によって慰藉するのです。今回はそのきっかけになってくれるかもしれない本を紹介します。
まずはユーゴスラビアの作家、ダニロ・キシュの短篇集『死者の百科事典』(山崎佳代子訳/創元ライブラリ)から表題作を。
語り手は、演劇研究所の招きでスウェーデンを訪れた〈私〉。深夜、王立図書館に連れていかれた彼女が見つけたのが「死者の百科事典」。〈私〉は「M」の項目のところに、最近亡くした最愛の父の名前を発見します。そして、そこに父のすべて(!)が記載されていて、自分も知らなかったエピソードの数々に驚くと共に、あることに気づいて深い感銘を受けるのです。それは〈この『死者の百科事典』に収録されるための唯一の条件──(中略)、その条件というのは、他のいかなる百科事典にもその名前が出ていないということ〉。
つまり、これら千巻もの百科事典に収められているのは無名の人々の生涯だったんです。
〈人間の歴史には何ひとつ繰り返されるものはない。一見同じに見えるものも、せいぜい似ているかどうか、人はだれもが自分自身の星で、すべてはいつでも起きることで二度と起きないことなのです。すべては繰り返される、限りなく、類なく〉
この物語を読んだ1999年以来、この言葉は身近な人や動物の死に際しての深い悲しみの底から、わたしを幾度も引き上げてくれました。かけがえのない人や飼っていた動物たち。わたしの記憶の図書館の中で、彼らの比類なき生が、この小説の中の百科事典のように完璧なものではないにしても、大事な思い出として収蔵されていて、いつでも引っぱり出して読み返すことができる。それは大きな慰めになってくれるのではないでしょうか。
死者の街『終わりの街の終わり』
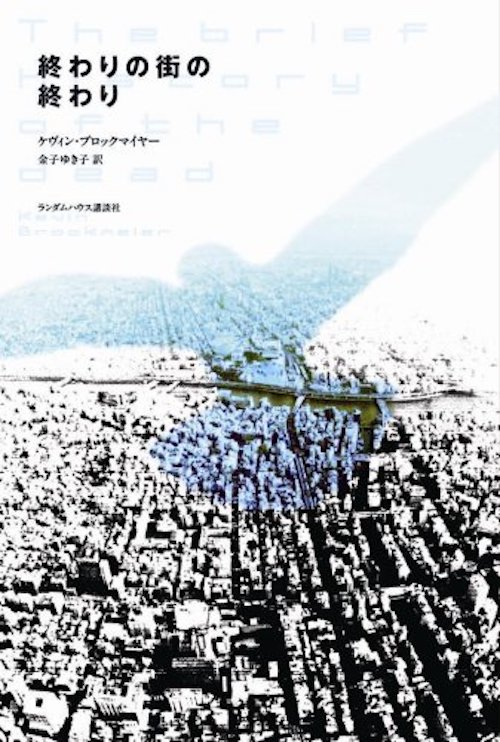
飼っていた猫を亡くしたばかりの頃、わたしを慰めてくれたのが、ケヴィン・ブロックマイヤーが『終わりの街の終わり』(金子ゆき子訳/ランダムハウス講談社)で創出した死者の街でした。それは、自分のことを記憶している人間が現世にひとりでも存在していれば留まることができる街なのです。
ところが、その街はどうやら縮みはじめているらしい。人口も減ってきている。なぜか。〈まばたき〉と呼ばれる人為的な伝染病によって、世界が滅亡に向かっているからです。
ところが、にもかかわらず、死者の街から消えない人々もいる。なぜか。コカ・コーラ社の仕事によって南極にいたおかげで、厄災から逃れたローラの生存ゆえです。
南極で独りサバイブしているローラが孤独のうちに思い出す、過去に袖すり合わせた人たちのエピソードが、死者の街にいる人々のそれと重なり合う。ローラの性格が悪い上司が、彼女が自分の家族や親戚に会ったことがないせいで死者の街で自分は独りぼっちだと恨んだり、ローラの幼なじみが死者の街でローラがかつてほんの一時期つきあった男性と愛し合うようになったりと、ローラと死者の街のシンクロ具合が絶妙な構成になっているんです。
死者の街という寓話と、世界の滅亡というデザスター小説。ふたつの読みごたえを備えたこの物語の読後感は、世界の終わりという悲劇を扱いながら、とても温かい。読みながら思い浮かぶのは、先に逝った家族や友人や動物たちが、死者の街ですれ違ったり、わたしを介さず仲よくなったりしている幸福な光景なんです。そして、わたしもまたいずれその街でみんなと再会できるのだとしたら……。そんな空想にしばし浸ってしまうのです。版元が消滅してしまったせいで長らく絶版なのが残念な、素晴らしい小説。どこか復刊してくれませんか。
忌野清志郎を悼む『会話のつづき ロックンローラーへの弔辞』
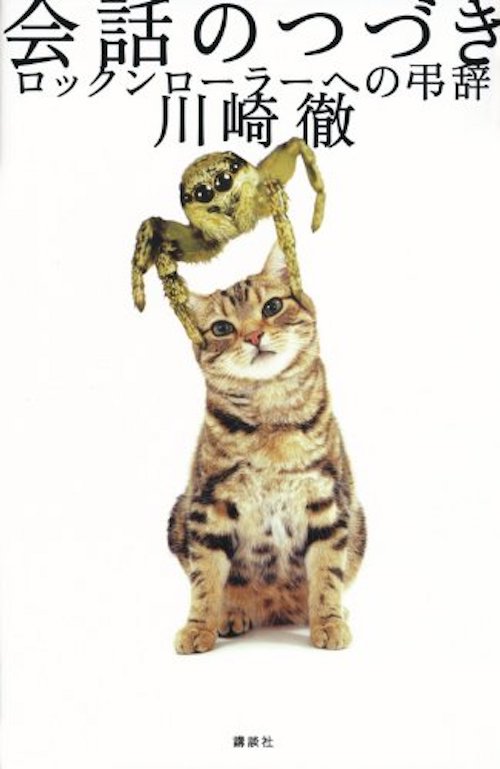
最後に、遺された者の心象風景が胸を打つ作品を。若い頃から仕事で深いつきあいのあった忌野清志郎の死を、かつて高名なCMディレクターであり、今は小説家である川崎徹が悼んだ『会話のつづき ロックンローラーへの弔辞』(講談社)です。
著者は、この本の中で忌野清志郎やキヨシローという固有名を一切出しません。かのロック・スターの死を悼んで斎場まで長蛇の列を作る大勢のファンを眺めながらも、自らは参列しません。思い出を語りながらも、それに終始することはありません。実は、この本の中で忌野清志郎に直接関わる文章はとても少ないんです。野良猫の世話をするために通っている公園のベンチにいた男の死。その公園でたびたび目撃される兵隊の霊。母の命日に必ず現れる蜘蛛。母の死後、ひとり暮らしをしていた父との対話。子供の頃の思い出。刺殺された顔見知りのコンビニ店員。この本は、忌野清志郎以外の死者や話題に多くをさいています。
〈記憶の底の遠いむかしから、見送って間のない近い過去まで、気がつくとわたしが採用するのはすでにいない人々、彼等が残した空洞、それに伴う景色であった。非存在の力をわたしは見ようとしていた〉
そんな小説を書いてきた川崎さんは、サブタイトルに「弔辞」という言葉をおいたこの本の中でも、すでにいない人たちの気配を描こうとつとめているんです。そして、(やはり名前は出さないものの久世光彦だとわかる)今は亡き演出家との生前の交流を回想し、彼の死に接して〈会話とは話すことではない。聞くことだ〉と知った著者は、だからこの本で、すでにいない人たちの声に耳を澄ませようとしています。耳を傾ける姿勢で、忌野清志郎との、死によって断たれてしまった会話の続きを試みているのではないか。わたしには、そんなふうに思えるのです。
〈わたしの一方的思いなど去った者に届きはしない。いくら手を振ろうとあちらからは見えないのだ。それを承知でわたしは手を振る〉
聞こえない声に耳を澄ませ、見えないのを承知で手を振る。それが、弔意で弔辞。生者にできる、精一杯の追悼であることを伝えて、静かに胸を打つ一冊です。
この本で小説家・川崎徹に興味を持った方は、中短編集『彼女は長い間猫に話しかけた』(マドラ出版)も探して読んでみてください。これは、著者本人を思わせる〈わたし〉が、死の床についている老父を看取る、その数日間の出来事を綴った小説です。医師との命の瀬戸際をめぐってのシビアなやり取りこそあれ、波瀾万丈の展開があるわけでもなく、涙を誘う父子の劇的なドラマが用意されているわけでもありません。
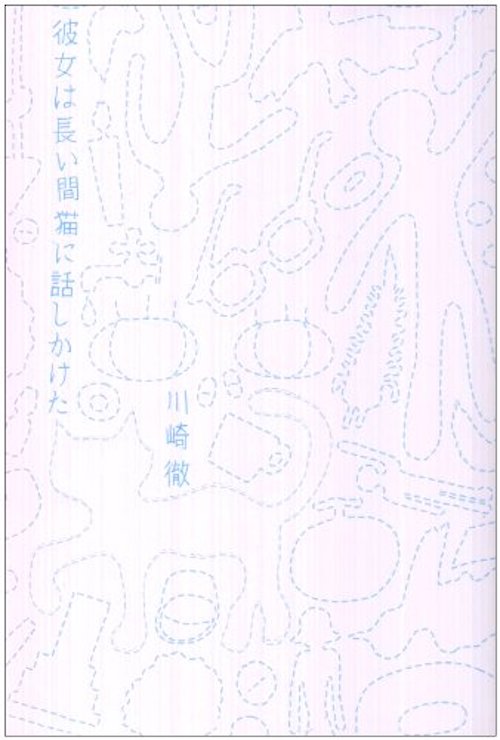
生から死へと少しずつ心身を寄せていくことで、その生き物としての在りようを変えていく父親の〈「自分」と「自分以外」の境界が曖昧になって、両者が融合し始め〉〈彼を彼たらしめていた人形(ひとがた)の境界線は、八十七年間の役割を終え消滅しつつ〉ある様を見つめている〈わたし〉の意識の流れを、端然と美しい日本語で記録した“ただそれだけ”の小説なんです。でも、その“ただそれだけ”がどれほど深い「悼む」行為になっているか。熱烈推薦いたします。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR