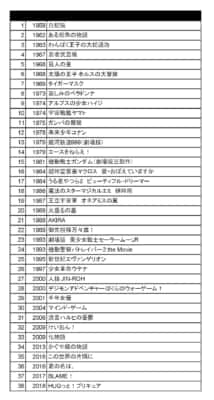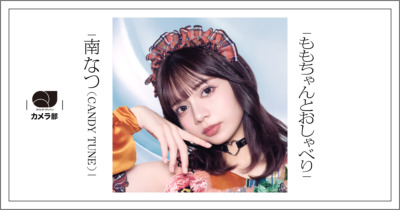2022年8月24日、公式サイトにて「令和4年度については、作品の募集は行わないこととなりました」と掲載、9月16日〜26日の開催をもって幕を閉じた文化庁メディア芸術祭について、アニメ評論家・藤津亮太が考察する。
メディア芸術祭、終了
文化庁メディア芸術祭が第25回で終幕となった。メディア芸術祭だけでなく、文化庁芸術祭も贈賞を廃止し(芸術祭そのものは続行)、文化庁映画賞も廃止ということで、アートやエンターテインメントに関する顕彰の仕組みそのものを見直すということだろうという観測も出ている。
僕自身とメディア芸術祭の関係はたいしてあるわけではない。最後となった第25回のアニメーション部門に審査委員として参加したのが一番大きな接点だ。
この審査員以外だと、2020年(第23回)には受賞作に関するトークに進行役などで参加し、2021年(第24回)はそうしたトークに加え、受賞作展覧会(会場:日本科学未来館)におけるギャラリートークも受け持つという縁もあるが、やはり審査に参加するとしないでは大きく違う。実際、審査に参加してみると、立場の違う審査員が集まっての議論はとても刺激的だったし、最終的にはメディア芸術祭の意味というものも実感できた。
今回はそんな自分の経験を踏まえつつ、「メディア芸術祭、終了」にともなってあれこれ考えたことを記したいと思う。自分はアニメーションが専門分野なので、以下記すことはみな、アニメーション部門に関したもので、メディア芸術祭全体にまつわるものでなないことをお断りしておく。

「その年のインデックス」になること
まず「メディア芸術祭による顕彰」の意味を確認しておきたい。
メディア芸術祭にかかわらずなんらかの賞にはふたつ機能がある。
ひとつは、作品や作家を顕彰することで世間に周知し、その業界を盛り上げることにある。これはとてもわかりやすい。そしてもうひとつは、その顕彰が「その年のインデックス」になることで、後世から現在を振り返ったときに、現在を理解するための手がかりとするためだ。
たとえば現在、オールタイム・ベストで1位に選ばれることが多い映画『七人の侍』(黒澤明監督)だが、1954年度のキネマ旬報ベスト・テンでは第3位。同年度の第9回毎日映画コンクールでも『七人の侍』の受賞は男優助演賞(宮口精二)に留まる。同年度のキネ旬ベストテンの1位も、毎日映画コンクール日本映画大賞もともに『二十四の瞳』(木下恵介監督)だったのだ。
これは「当時、『七人の侍』の真価を見抜けなかった評者たちの目が節穴であった」ということではない(そういうふうに言って溜飲を下げたい人が多くて、この記事にそういうコメントがつく様子が目に浮かぶ)。当時は「『二十四の瞳』のほうがよい、と考えたくなる時代や映画界の状況の背景」があり、それが時代の刻印としてキネ旬ベストテンや毎日映画コンクールに記されているのである。これが「顕彰」のもつもうひとつの機能である。
つまり「顕彰」には、審査当事者たちが自然と背負わざるをえない時代性などのバックグラウンドが無意識のうちに反映される。それがわかると、メディア芸術祭が海外作品も公募で募集されている意味が見えてくる。
「ユニーク」ともっと伝えるよう考えるべきだった
メディア芸術祭は国の「クールジャパン戦略」の中に位置づけられている。実際、メディア芸術祭の受賞作を海外で紹介する展示なども行われてきた。このときに、国内作品を国内の審査員で選んだだけでは、日本というバックグラウンドが持っている「価値」が伝わりづらい。日本の審査員が多様な世界の作品を審査することで、そこに「現在の日本が秘めている価値観」が、海外の人にも伝わる形で示されることになる。メディア芸術祭の「顕彰」は、世界に日本の価値観を発信する行為でもあるというわけだ。
自分としては、審査を通じてこのようなメディア芸術祭の「顕彰」の意味を実感はしたのだが、同時にこうした「顕彰」の価値が多くの人に伝わっていただろうか、と考えたときに、いろいろ足りていない部分はあったと、自分のかかわり合いも含めて省みるところはある。
メディア芸術祭のいいところは、顕彰して終わりではなく、先述のように受賞作品展が開かれるところにある。僕は昨年、今年とアニメーション部門のギャラリートークを担当したが、あれをやるときに、もっと「そもそもなぜ海外と国内、インディペンデントとメジャー(テレビ・配信・映画等)がひとつの俎上で議論されるのか」という大前提の話をしたほうがよかったのではないかと、今になって思う。あるいは、受賞作上映会で、大賞『The Fourth Wall』のMahboobeh KALAEE監督(イラン)と優秀賞『幾多の北』の山村浩二監督にお話をうかがったときも、「なぜこのふたりがこの会場で並びうるのか」という背景をもうちょっと説明するべきではなかったか。メディア芸術祭のユニークな点を「ユニーク」ともっと伝えるよう考えるべきだった。
こうやって考えると、「大賞」から「審査委員会推薦作品」まで全作品の触りを見せて、「なにがおもしろいのか」という受賞理由をフランクに話す配信などやってもよかったのかもしれない。それがメディア芸術祭(アニメーション部門)の魅力を広く伝えることになったのではないか(できるかどうかは別として)。そんなことを考える。
ちなみに、海外と国内、インディペンデントとメジャー(テレビ・配信・映画等)をひとつの俎上で審査できるのか、という疑問を持つ人もいるかもしれない。でもやってみるとわかるが、結局作品評価というのは「主題の選び方」と「手法への自覚」と「プレゼンテーションの巧拙」がポイントになってくるわけで、そうやって考えてみると、決して違うものさしが必要なわけではない。もちろん審査員ごとに出自が違うから、それぞれのジャンルの知識には偏りがあるわけだが、そこは互いが互いを補完し合いつつ議論をすることでカバーされるが、これもまた自分とは違う価値判断があるので勉強になるのだ。
「テレビアニメ」は絶対に組み込むべき
以上、つらつらとメディア芸術祭の審査に参加して自分が理解したことを書いてきた。メディア芸術祭はなかなか得難い趣旨の催しだったが、メディアアートにマンガとアニメーションが合流するというそもそもの建付けの難しさなどを含めて、「役割を終えた」(終了についての文化庁のコメント)というより「存在のユニークさを衆知しきれなかったこと」が本質的な終わりの理由のような気がしている。
今後、どのような建付けでどのようなアートフェスティバルが行われる(とりあえず概算要求には準備のための新規事業費の予算が計上されているとの報道がある)のかはわからない。そこはお手並み拝見だが、個人的に「アニメーション部門を作るときにここは大事だと思う」ポイントを挙げておく。
ひとつは「作品を顕彰する」こと。アニメーションは集団作業で、様々なスタッフの力の掛け合わせが印象的な作品を作ることが多い。しかし、芸術選奨のような個人を顕彰する仕組みでは、どうしても対象が監督に偏ってしまう。作品を顕彰する仕組みのほうが、アニメ業界にはプラスの影響が大きいはずだ。
そしてもうひとつは「作品」の中にちゃんと「テレビアニメを組み込むこと」。アニメーション映画は各映画祭の中に独立して賞を設けているケースが多い。しかし現在、ファン投票以外でテレビアニメを顕彰する仕組みはない。「アニメーション神戸」なきあと、メディア芸術祭アニメーション部門は極めて稀な「テレビアニメも対象」となっている賞だった。先述の「歴史のインデックス」の機能を考えたとき、「テレビアニメ」は絶対に組み込むべきだろう。
そして、これはでき得るならばだが、やはり「海外と国内、インディペンデントとメジャー」が渾然となっていてほしい。異質に見えるものの同質性。同質なものの中に潜む異質な要素。そういうものがあぶり出されることがおもしろい。そしてできれば顕彰だけでなく、決して普通なら交わり合わないはずの作り手同士が対面するようなそんな「場」を設けてほしい。
「クールジャパン」施策の中で文化庁が担うところは、「JAPAN is No.1」というものであるわけなく、煎じ詰めれば「私が何者であるかを語る自己紹介」と「見知らぬ相手を私なりに理解する姿勢」の組み合わせの中から「クール」が立ち上がるべきで、そのような場は、現在不足していると思うからだ。
もちろん文化庁が勧進元でなくても、そういうことが可能になるのなら、誰がやってくれてもいいんだけれど。