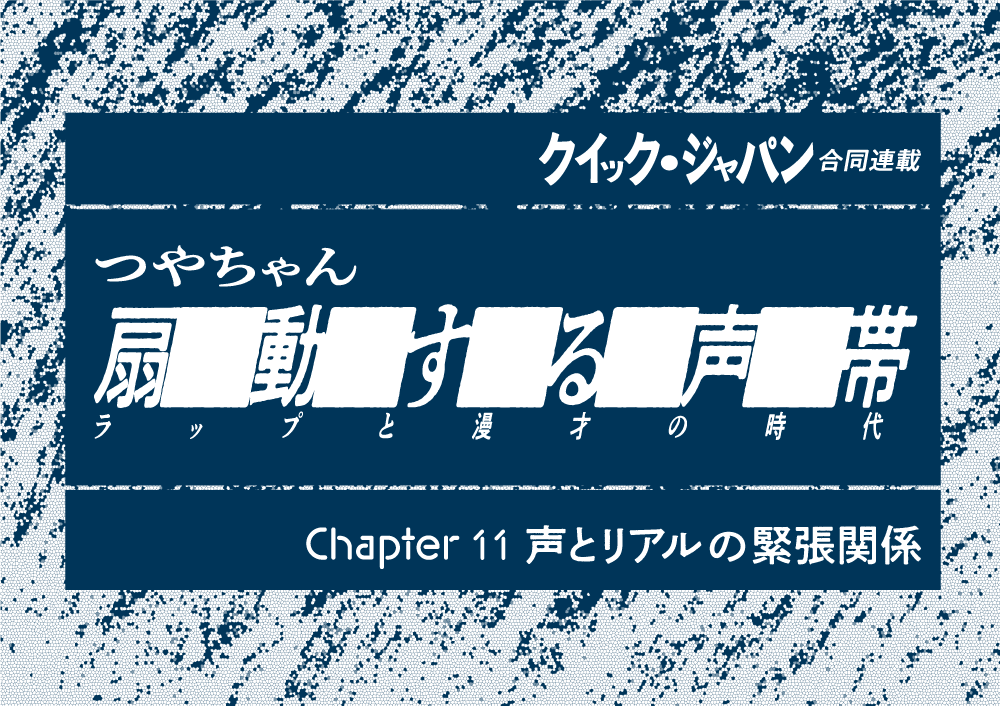新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」Chapter11。
漫才が求める声
「漫才に選ばれし声」というものがある。
劇場、ラジオ、TVなど漫才をどのような場所で披露するかによって最適な声は異なるが、どこであれ素晴らしい声はまっすぐに観客に届けられその場の空気を掌握する。特に、ツッコミの声は重要だ──笑い飯・哲夫のガラの悪そうなハキハキした声、ミルクボーイ・内海崇の決して埋もれることのない太く伸びる声、銀シャリ・橋本直のツッコミの滑稽さを引き立てるような真っすぐ安定した高い声──優れた例は多くあるが、実のところ私たちが「漫才に選ばれし」と認識する声は一体どういった類いのものなのだろうか。
たとえば、真空ジェシカ・ガクは、ラランド・ニシダとの対談で自らの声がツッコミ向きではないことを自覚しつつ次のような発言をしている。
ニシダ「あんだけ文字数少なくてバッて決められてるのは(アンタッチャブルの柴田英嗣さんは)やっぱりかっけえなって」
テレビ朝日YouTube番組「真空ジェシカガク×ラランドニシダ初対談…漫才を語る!!」より
ガク「それができる声質ってあると思うの」
ニシダ「ありますね」
ガク「僕はもう絶対無理なのよ。このモサモサした声で、なんでだよ!って言っても、なにも喋ってないのと同じ。煙状になってふわっと消えていく、僕のツッコミって」
ニシダ「ガクさんって、ボケの人っぽい声質ではありますもんね」
ガク「そう。刺すツッコミができないから、いっぱい喋ることでまず、(手を挙げながら)こっちが喋ってますよ~!をやらなきゃいけない」
ニシダ「声質ってやっぱり重要ですよね」
ガク「ニシダはそれができるから、いいなと思うね」
ニシダ「男女でコントラストもつきますしね」
「モサモサした声」「煙状になってふわっと消えていく」という表現に注目したい。つまり、ここではその対極として位置づけられる「こもらずに通りやすい声」が良い声として認識されている。遠くにいる観客にスッと届き、うるさい騒音になることのない「通る声」。ただ大きいだけの声は不快だが、「通る」声は、優れた落語の語りのようにむしろ心地良さすら感じられる。
また、「こもらずに通る声」にもさまざまなバリエーションが存在する。先述した笑い飯・哲夫/ミルクボーイ・内海崇/銀シャリ・橋本直のそれぞれの声色は、橋本をニュートラルと置いた際に<ザラついた哲夫の声>と<なめらかな内海の声>という形でグラデーション的にマッピングできるように思うが、重要なのは、彼らの声が相方の声と対比させられることでより一層個性が際立つ点である。笑い飯もミルクボーイも銀シャリも、高い/低いという音程差、太さ/細さという厚み、ザラついた/なめらかなというテクスチャ、いずれかの指標でコンビ間の声の違いが明白になっており、それによって双方がマスキングし合うことなく共存し変化を生み出すことができている。
さらに述べるならば、変化を際立たせ個性ある声を生み出すというのは、つまり声にキャラクター性を吹き込むことにも近い。漫才においては、ふたりの声の差異がそのままキャラクターの違いを形成していく。先の例に加えて、漫才に適した「こもらずに通る声」を持つブラックマヨネーズはコンビ間で声の太さ/細さという厚みがはっきりしており、同時にそれが社交的で明るい/内向的で暗いというキャラクターの違いにもつながっている。その点、コントは漫才以上に声質の差異が作品上の人格造形に結実する領域だろう。好例はGAGで、三人の声の違いがそれぞれのビジュアルの違いとも相まって各キャラクターを鮮明に印象づける。声は、あらゆる面において作品の物語性を規定するのである。
「リアル」なヒップホップの声(という虚構)
一方でラップもまた漫才同様に声質が重要であり、キャラクター性を決定づける大きな一因となるに違いない。むしろ、鍛錬を重ねスキルを磨いていくラッパーにとって声とは磨くことのできないギフテッド=純然たる才能であり、残酷だが、ラッパーは生まれた瞬間からラッパーであると言えよう。岩下朋世は、「「リアル」になる キャラクターとしてのラッパー」(『ユリイカ』2016年6月号特集=日本語ラップ)において、次のように論じている。
「リアルなラッパー」に求められるのは、まず自分の人生を物語化し、自己を魅力的にキャラ立てしてゆく私的な能力であり、描き出された「自分というキャラクター」を体現してみせるパフォーマーとしての能力である。単に実物として「リアルである」というだけではなく、まるでラップで描かれた世界から飛び出てきたような、虚構的な存在感が、ラッパーとして「リアルである」ことによっては大事になってくるのだ。
『ユリイカ』2016年6月号特集=日本語ラップ
つまり、ラッパーは本当にラップの中に出てくるみたいな人物なのか、という評価点でギフテッドである声の査定を受けることになる。その点、BADSAIKUSHの声もYZERRの声も、そしてguca owlの声もラップの中に出てくるキャラクターとしての声質を持ち合わせていると言って良いだろう。なぜなら、彼らの声はしゃがれていて、枯れており、物悲しさがあり、同時に凄みもあるからだ。
ラップで描かれた世界から飛び出てきたようなヒップホップ的虚構性を有しているがゆえ、ラップ・ゲームにおいて“キャラ立ち”する。そしてコントにおけるGAGのように、その個性の対比をグループ内で行なっていたのはSCARSである。彼らもまた、虚構的な存在感を示すだけの声をそれぞれが持っている。
ヒップホップ/漫才という虚構を裏切れ
ところが、そういった声とキャラクター生成によるヒップホップ的虚構性に亀裂を生じさせる演者がいる。それは例えばdodoであり、valkneeであり、彼ら彼女らは決して“ラップの中に出てくるみたいな”人物造形に寄与する声を持ち合わせているわけではないのだが、むしろそれを逆手に取りつつヒップホップ/ラップそれ自体を自らの<声世界>へと引き寄せるのだ。
dodoは「im」というタイトルで、まさかセルフボースティングではなく「LINEはゲットできてないし/いまだにえっと、彼氏じゃないし」と実らない恋について歌い、「town」という曲では地元へのレペゼンを歌わずに「家からは遠いけど/何故か見慣れたこの街を/歩けば思い出すあの日のこと」と過去に行った遠い街について歌う。そもそも“ラップの中に出てくるみたいな”世界を描こうとすらせず、朴訥とした声で一つひとつの言葉を丁寧に紡いでいく。BADSAIKUSHやYZERR、guca owlと同様にdodoの声は枯れていて物悲しさがあるが、決定的な違いとして“凄み”がない。
「俺は旅立つよこの町から/もう興味はないゲームの勝ち方」(「nambu」)と謳う通り、ラップゲームから降りているのが彼だ。けれども、このラッパーがそれでも自作で執拗に踏み続ける韻が、ラップのリアルとdodoという存在を繋ぎとめる。声とキャラクター生成によるヒップホップ的虚構性を裏切りながらも、「韻」という決定的にラップたり得る要素を外さないdodoは、その声──ラップの世界から遠い声──を、ぎりぎりで“リアルなもの”として見せる。
そして、ぎりぎりでヒップホップを成立させているdodoのように、漫才らしからぬ声を駆使しながら際どい形で芸を成り立たせているお笑いコンビも存在するのだ。2022年の『M-1グランプリ』でキャリアハイとなる準決勝へ進んだハイツ友の会は、声質・声量という点においてお世辞にも漫才に向いているとは言い難い。だが、決して通るわけではないその声はローテンションな漫才の内容と合致しており、キャラクターと声が見事なまでに絡み合っている。
彼女たちはコントと漫才をどちらもやる中で「漫才は漫才でしかできないことをやりたい」と述べ、出身地の京都弁を使ってただただ素朴な「会話」を重ねていく。これからさらに売れようともTVやYouTubeではなく劇場で芸をしていくことをメインに置きたいとも語る(Lmaga.jp「お笑い界の新鋭「ハイツ友の会」、想像の斜め上を行く共感ネタ」)。方言という発話形式で、京都弁に合った淡々とした芸を劇場で行なっていくという野望──決定的に漫才たり得る要素にこだわるハイツ友の会は、「漫才に選ばれし声」を堂々と外しながら、それでも作品を優れた形でぎりぎり“リアルなもの”として見せるのだ。
ラップや漫才に選ばれし声/そうではない声を対比させていくことで、なにがラップや漫才をそれとして成立させているかが浮き彫りになる。dodoやハイツ友の会がなににこだわっているか──それは恐らく、ラップや漫才にとって最も大切な要素に違いない。