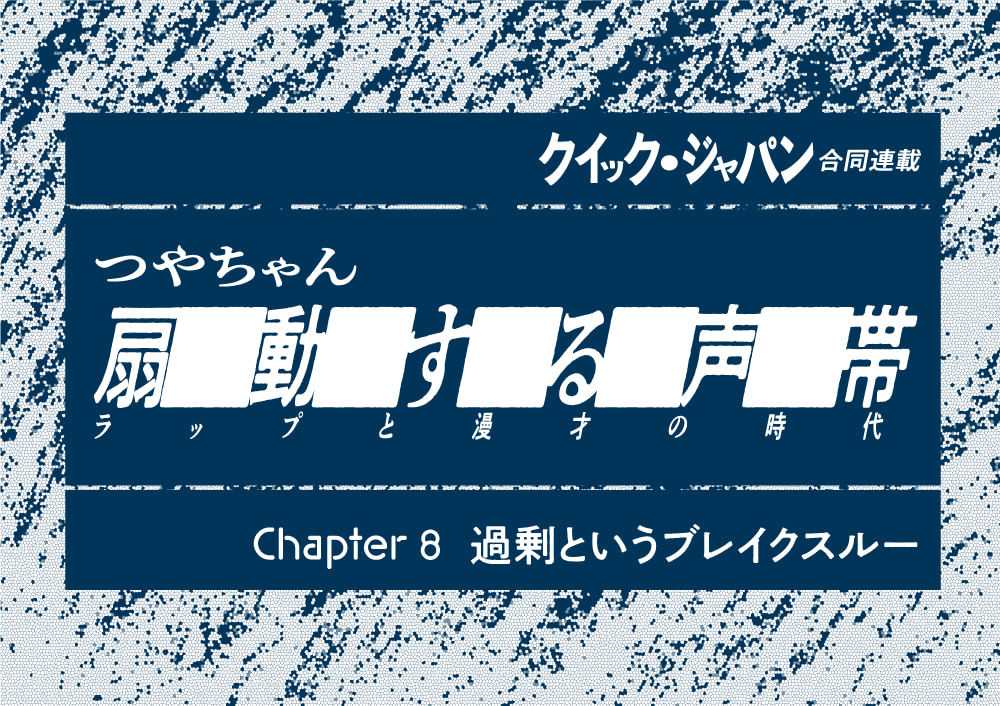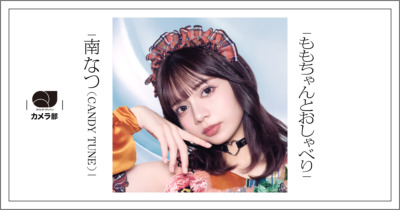新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」Chapter8。
※この記事は『クイック・ジャパン』vol.164に掲載の連載記事を再構成し転載したものです。
Chapter8「過剰というブレイクスルー」
去る11月30日、『M-1グランプリ2022』ファイナリストとして決勝進出が決まった面々に、ウエストランドの姿があった。今号が発売になるころには『M‐1』のチャンピオンも決まっているはずだが、結果がどうであれ、私は彼らの漫才に宿るリアリティを支持する。
ウエストランドの漫才とは、なぜかくも哀しく切なく、感情に訴えかけるのだろうか。ツッコミ担当である井口浩之の、愚痴を長く引き延ばした畳みかけるようなぼやき漫才は、その一つひとつが痛切な叫びとして舞台の空気を連続的に凍らせる。そこにはある種の同情にも似た笑いが、助け舟のような形で次第に客席に満ちていくのだ。ウエストランドの漫才は、感情が起点にある。井口の不平不満、哀しみ、つらさといった行き場のないエモーションがしゃべりを駆動させる。パフォーマンスを身体に叩き込み役者を演じるような昨今の漫才には見られない、自分自身という存在がそのまま舞台に降り立った説得力が漂う。漫才中にあまり笑うことのない井口の表情からも、感情起点ゆえのリアリティが伝わってくる。彼らの漫才を支えるのは過剰なまでの愚痴と不満であり、それらが井口に憑りついた瞬間からウエストランドの漫才ははじまる。
過剰性が生む憑依──。注目度を高めているランジャタイに象徴される通り、近年の漫才において“憑依”というアプローチはひとつの潮流となってきている。事実、ほかにも強烈な大声ツッコミを披露し『M-1グランプリ2020』準優勝に輝いたおいでやすこがや、22年秋に惜しまれつつ解散した赤もみじがそれらの代表格として挙げられるだろう。
なにかに憑りつかれたようにしゃべり出す芸のルーツをたどると、行き着くのがチュートリアルの諸作品である。たとえば『M-1グランプリ2006』で優勝したネタ「チリンチリン」は、それこそ徳井義実の過剰な反応がキャラクターの憑依へとつながり奇妙なパラレルワールドとして展開される名作だ。自転車のチリンチリンを盗まれたと言う福田充徳に対し深刻なリアクションを返す徳井は、口調や表情を駆使することでただならぬ空気を作り上げていく。ここでは、過剰さが憑依を生み、それらが徐々に観客の想像力を借りながら舞台―客席の関係性によって架空の世界を創出していく様子が観察されるだろう。『笑いの方程式』(2007年、化学同人)において、著者の井山弘幸はそういった状況を福田の視点に立ち次のように説明している。
なにか釈然としないながらも、徳井の一途な真剣さについ話に聞き入ってしまうが、ふと彼がもらした「そんなところにいるはずもない」を聞き漏らさなかった観客は、チリンチリンが擬人化されていることに気づく。そう思い直してみると、チリンチリンを連呼する場面では、中国風の女性名のようにも聞こえてくるから不思議だ。観客の想像力を借りて徳井は女性としてのチリンチリン」の架空世界をつくり上げる。(p.122)
感情の希求/ウエストランドとちゃんみな
さて、私は本稿の冒頭で「ウエストランドの漫才に宿るリアリティを支持する」と書いたが、一方でチュートリアルの漫才が構築するフィクション性についても当然ながら支持している。両者のスタイルは、ある種の過剰さを加速させたうえで憑りつかれたような芸を見せていく点で、技法としては近い。ただ、演者自身の容器を満杯になるまで感情を膨張させるウエストランドと、そもそも容器から感情をあふれ出させ擬人化というまったく異なるレイヤーへと結合させるチュートリアルで、着地するゴールが大きく異なる。端的に言うならば、前者は熱望の漫才であり、後者は欲望の漫才なのだ。
得も言われぬ感情を熱烈に訴求するウエストランドと、熱烈さを妄想へと拡大していくことで架空世界に引き込もうと欲するチュートリアル。そして、同じく口語による感情起点の表現として、ラップ表現においても似たような状況を見ることができる。たとえばウエストランドの漫才のような熱望するラップ、そのエモーションの過熱と熱烈な願いを体現している最も代表的な歌い手はちゃんみなではないだろうか。ちゃんみなはルッキズムをテーマにした代表曲「美人」やその収録アルバム『ハレンチ』(2021年)のインタビューにおいて、次のように語る。
「ブサイク」から「きれい」までの評価を経験したからこそ、この曲が書けたんだと思いますね。
CINRAインタビュー「ちゃんみなが経験した、容姿に基づく中傷と賛美 自らラップで切る」
この感情を長いこと溜めすぎたし、色んな感情の色が混ざっているので、どのサウンド感がしっくりくるのか自分の中であんまり分からなくなってしまって。
人間の感情には一応名前が付けられているものもあるけど、名前がつけられていない感情もたくさんあって。(中略)私の場合は、その感情に音楽として名前をつけることもできます。
RealSoundインタビュー「ちゃんみな、スランプ乗り越え辿り着いた新境地 今だからこそ追求できた理想のJ-POP」
自らの中に沸き起こる感情を起点にしつつ、その気持ちをラップ/ボーカル表現で形にしていくのがちゃんみなである。彼女の独自性は、それを具体化する力強いラップや繊細なラップ、多彩なフロウや声色に宿っている。強度もバリエーションも過剰なまでのグラデーションと幅を有しており、ゆえにリスナーは感情移入しやすい。本人が「色んな感情の色が混ざっている」と述べる通り、ちゃんみなの歌唱法にはきめ細かい色のカラーパレットが揃っており、筆先の種類も豊富だ。その結果、圧倒的なリアリティを打ち出すことに成功している。
過剰な憑依/擬人化するチュートリアルと般若
かたや、チュートリアル的な過剰性がフィクションへと膨れ上がっていく超俗のムードを持ち合わせているラッパーとして、般若がいる。彼もちゃんみな同様にさまざまな声色やフロウをスキルとして身につけているが、歌詞世界の中の役に憑依することで分身として自身を浮き上がらせていき、しまいには過剰さが度を越しユーモアと狂気の間を行き来する事態へと発展していく点で異なる。そして興味深いことに、チュートリアルの漫才で導入される擬人法を、般若も同様に披露するのだ。たとえば「ケータイ」(2009年『HANNYA』収録)では携帯電話を自分自身へと擬人化し、「オレを開けたらダメだ奥さん/見ない方が絶対得だ」「あ~疲れた/だって電池がもう1ケタ」といったコミカルかつどこかホラー要素も感じさせるフィクション世界を匂わせる。
ちゃんみなが自分の感情にぴったりの色を探し、それを圧倒的に過剰なラップや歌唱で「熱望」するがごとく表現する一方で、般若はその表現だけに飽き足らず、異世界を構築することまでを「欲望」する。これらの事例は、口語表現という手段において過剰な形で表出した漫才やラップが、一時的な感情を越えた次元でのエートスとして、熱望や欲望を孕みながら究極のリアリティと究極のフィクションを創造してしまうことを証明している。重要なのは、中途半端の殻を破り突き抜けることだ―過剰なまでに。その彼岸において、憑依という形で突如固有に切り離された作品が生まれ、未だ見ぬ口語表現の未来を形作っていく。