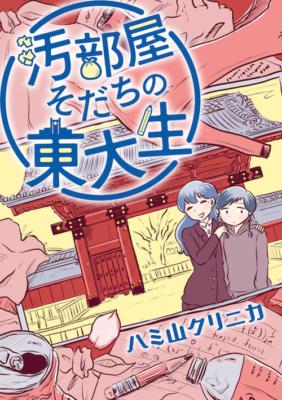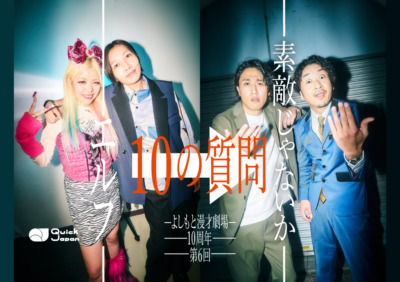ママへの愛憎と、家事放棄のリアリティ
丸みを帯びた親しみやすいキャラクター造形とテンポのよい展開、さらに汚部屋の描写自体もグロテスク度は低いため、怖い描写が苦手な方でもスラスラと読み進めることができる本作。
しかしながら、美人で愛嬌のある人物として描かれているママが、ユウに対して時に暴力的に豹変する「圧」の表現の強烈さに、この作品の醍醐味があると言える。また、汚部屋と東大というワードのインパクトを読者への引っかかりとして巧みに用いながら、実母の持つ二面性=ギャップと、それに苦しみ、身動きが取れない主人公の姿を物語の真の主題として見せている。
そうした複数のレイヤーが重なり合う、立体的で精密な構造も本作のポイントだろう。

「半自伝的マンガ」の名のとおり、作者もユウと同様、汚部屋状態の実家で勉学に励みながら東大への切符を手にした人物だそうだ(厳密には、東京藝術大学中退→東大理学部卒というさらに複雑なプロセスを経ている)。
当然、作品においては誇張や虚実入り交じった表現もあるだろうが、趣味や食べ物に至るまで子供を支配しようとする母親との確執や、トイレが壊れても「修理の人を入れるのが恥ずかしい」という理由で修理もできずさらに悪化が進んでいく汚部屋には、それを体験してきた本人にしか描けないであろうリアリティがある。
ユウの場合は、両親の関係性破綻が大きなトリガーとなっていたが、常識やモラルというのは、ひとつのボタンのかけ違いであっさりと崩壊していくことを、痛みをもって示してくれている作品だ。
パパとママの隠された事実が、主人公の自立を促す契機に
すでに第1話の冒頭から「愛すべき美しいママを捨ててしまう物語」と予告されているように、母と娘の関係性がドラスティックに変化して結末を迎えることは約束されている。
ここからは少しネタバレになるが、9月9日に公開となる第7話では、余命幾ばくもないパパとの再会をきっかけにして、ママとパパの歪な関係性を知ることとなる。ユウは、今まで見て見ぬ振りをしていたこの家を蝕む「違和感」の原点に、ようやく触れることになったのである。

加えて、パパの死は援助の喪失を意味しており、彼女が一家の大黒柱として稼がねばならない立場となる。これまでは金銭的な面で(パパを通して)ママの庇護下にあったユウであったが、なし崩し的に訪れた経済的な自立が、結果的に彼女とママの関係を変えていく大きな契機となったのだ。

そんな激動の変化の中にありながら、汚部屋で暮らしていても美麗さを失っていないママの描写からは、ユウがママを完全な悪人としては捉えていない感情も窺える。
心から嫌いになれないからこそ、毒親と距離を置くことや親を捨てることに対して葛藤がありながらも、「普通の生活」を手に入れるために前進していくのだ。
家族、血縁とは厄介なもので、無償の愛を注ぎ合える幸福な親と子の関係もあれば、その存在自体が呪縛となり、やがて骨肉の争いに発展することもある。たとえ関係が悪化しても親は親でありその事実は揺るがないが、人生は誰のものでもない、自分自身のものである。

この物語の主人公であるユウが母を捨てるとき、事情を知らない者からすればそれは残酷な行為に見えるかもしれない。だが、親離れこそがユウの成長を示す第一歩であり、ママに対する真実の愛であり、祝福されるべき出来事だということを、私たち読者は物語を通して知っていくのである。
-
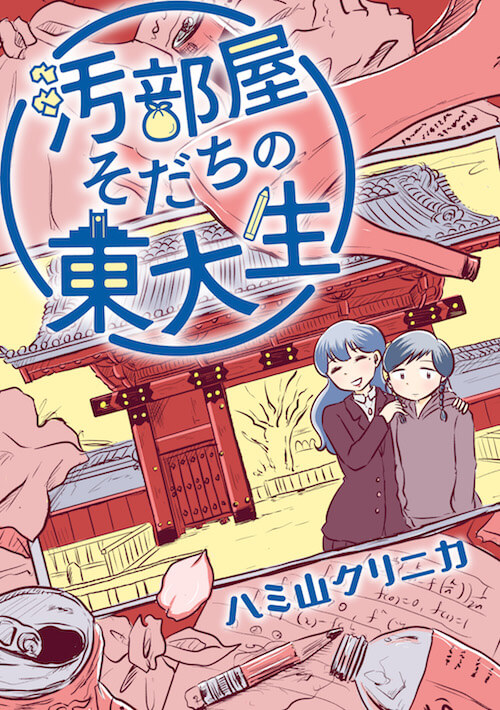
ハミ山クリニカ『汚部屋そだちの東大生』
「東大入って自分だけ幸せになろうだなんて、ママ許さないからね」7年間壊れたままの自宅トイレ。包丁やまな板はゴキブリの通り道。そんな家にやがて「パパは来なく」なり、私は美しいママとふたり暮らしに。センター試験前は極寒の部屋で、折りたたんだ布団を机代わりに受験勉強。ママが望むから東大に入った。…じゃあ私は? 私はずっと…ただただ「普通の生活」をしてみたかった――。東大卒作家の半自伝的、毒親との共依存ものがたり。
『マンガよもんが』と『LINEマンガ』にて同時配信中関連リンク