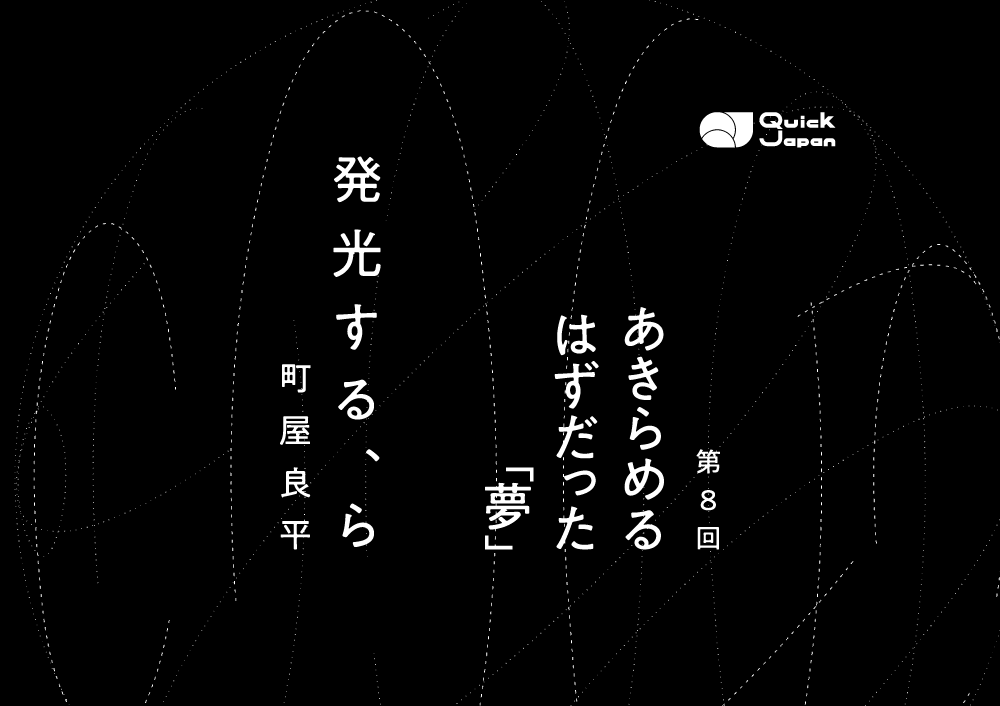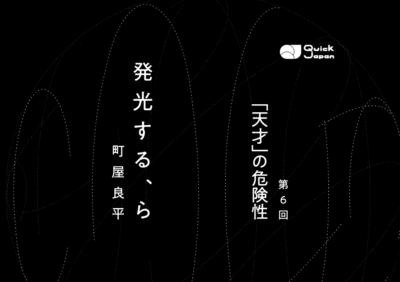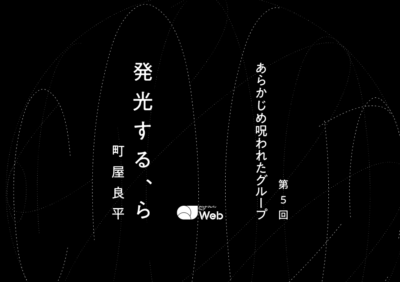メンバー間の仲も険悪、鳴かず飛ばずの6人組の弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。七十年後の世界からやってきた双子のアリスとキルトは、未来では禁忌とされた「夢」を追いかけてアイドルとして活動していた。
バンコクでのフェス出演動画のバズ以来、少しずつグループが軌道に乗ってきた最中、ふたりは未来に強制送還される。過去に戻るための条件として論文を課されたアリスだったが、執筆は一向に進まず──
前回までの連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
第2回 個性恐怖症
第3回 夢の功罪
第4回 被害者たちのスイーツ
第5回 あらかじめ呪われたグループ
第6回 「天才」の危険性
第7回 過去の改変
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
マサ 元メンバー。脱退後、韓国に渡り練習生として過ごすも怪我で引退。現在はエコブラのサブマネージャー。
憑馬(つしま)カート教授 七十年後の未来に住む十代にして、質的過去研究の第一人者。好物はオムライス。
第8回 あきらめるはずだった「夢」
~それから三年後~
「おい! なにやってんだよ!」
アリスの暮らすコクーンに送った二重身体転送によってキルト、というよりキルトの重身体(じゅうしんたい/過去の語彙で言うところの分身のようなもの)があらわれ、そう言った。
「いや、オムライスをつくってるんだけど」
「じゃなくて、いったいいつまでかかってんだよ? 今日まで言うまい言うまいと気をつけていたけどもう限界! たった一本論文を仕上げるまで何年かかってるわけ? おれはもう六本も書いてデータベースに吸収されてるっていうのに」
「三年だけど……そんなこと言ったって、おれはお前みたいにセンスのある研究者じゃないし、何本書いても査読を通らないんだよ」
「まあ、いいじゃない。学問は急がず。これは過去未来と変わらぬ真理だよ。どうせ過去に戻れるとしても、こちらで過ごした時間と関係なく、あの居酒屋で「マサ」っていうマネージャーが居酒屋に登場した場面の続きに戻れるわけだし」
憑馬(つしま)カート教授はアリスのコクーンに生身体(きしんたい)を置いていて、目の前に今日の「オムライス」(ここのところはデミグラス系のソースに嵌(はま)っている。コクを出すための生乳類やマッシュルームの産地・鮮度にこだわった一品)を供され、声によろこびを隠せぬ様子で言った。毎晩のようにアリスの居住する学生コクーンに生ワープしてきて、アリスに「オムライス」を強要した。
「そろそろ、一時期流行したという「B級」や「ご当地」系「オムライス」にも挑戦してみては?」
そしてそう言った。
「よくもそう飽きないもんですね。質的過去調査全般よりも過去料理研究に特化した研究の方が肌にあっているのでは?」
キルトの皮肉に憑馬教授は、「む……。まあ、実際どうなの? 先日AI査読の過半数がサジェストした件を受け容れるのは、オムライ……学籍番号一五四としては」と返した。
「もうアリスのこと「オムライス」って呼んじゃってるじゃん」
「AI査読の提案……論文ではなく創作……「小説」を書けというサジェストについてですか」
アリスは「フライパン」や「包丁」を洗いながら零した。こうした調理用具や「オムライス」の材料は憑馬教授のために仮想貿易で過去から取り寄せている。その交渉に時間が取られているのも論文がなかなか進まない要因のひとつではあった。
未来の技術をもってしても過去の調理用具、「オムライス」の材料を過去のそれらの中から吟味して仮想貿易の担当者とビジョン共有するのは過去人には想像できないほど難易度の高い専門性が要り、七十年前の野球選手にたとえると一六〇キロの球を投げつつ打者としても三割の打率を維持するようなものだし、棋士にたとえるなら十代で八つのタイトルを完全制覇するようなものだったが、なんとか専門家の知見も借りてようやく仮想貿易の発注も安定してきたところだ。
「てか、おれの論文がもう六本もアクセプトされているんだから、よくないか? はっきりいってアリスにはべつに、論文に対するセンスも情熱もないんだし」
「情熱、ないわけじゃないよ。ただ、まだ自分が書くべき、書きたいテーマに辿り着いてない感じがするんだよ。しっくりこないっていうか……」
「いや、やはり片方のテキストだけでは偏るというのが学会の総意。一五五番側の視点のみではなく、一五四側の成熟した視点もなければ、過去に戻った再調査はまず叶わないと思ってくれ」
「あと何年かかるんだよ! もういい、アリス、「小説」を書け。最高権威のAIがサジェストしてるんだから、普通に論文を書くよりもその方が通りやすいのは確実だろう」
「うーん……。「小説」? そんなの書いたことないし、もっと時間がかかるんじゃないかなあ。しかもなんやかんやでこっちに戻ってきてからも忙しいんだよなあ。キルトはおれの代わりに「オムライス」も作れないしさ」
「おれは自分の興味のないことは絶対にできないんだよ!」
「分かってるよ。だからこそキルトは研究者には向いてるかもしれないけどさ、過去でも体裁的に二人で暮らさなければ過去リアリティに欠けるだろうという判断から「ルームシェア」を始めた当初はさ、家事を平等に分担しようって話だったのに、結局ほとんどの家事はおれがやって、こんなベタな「過去あるある」に感動したのも最初だけ。まったくもう、ほんと、ストレス溜まるよ」
「あの時代の家事なんて、あんな高度に難しくてしんどいこと! おれにできるわけはないだろう」
「だから、じゃあもう少し待って。とりあえず「小説」に挑戦してみるからさ」
「言うまでもないことかもしれないけど「小説」を書くのならあくまでも「リアリズム」というものに徹してね。報告書としての役割も兼ねているから、過去にない現象やテクノロジーをいわゆる「SF」や「ファンタジー」のように書くのは厳禁だからね。あと「エンタメ」色の強い要素もAIには難解すぎるので控えてもろて」
そう、七十年後の人間(ひいてはAI)にとっては、アリスとキルトが過去で触れてきたような「エンタメ」小説のほうが、文学よりよっぽど難解なのである。
憑馬教授は「オムライス」を食べ終え満足げな表情で注意を述べたのち、「では」と言っておそらく研究コクーンへとワープしていった。
「小説」……いまや廃れた文化とはいえ、一定数「文学」なるものを研究以外で創作する人間はいた。
「小説」というジャンルの、とくに「現代小説」と呼ばれるそれはAIによって一時期爆発的に技術革新が起きたが、AI身体群によって創作された作品は生身体には容易にその素晴らしさを読み解けず、次第に「作家」と「批評家」のメンタルヘルスが著しく悪化しているという研究報告が出され社会問題化した。
そのころから、しぜんにAIは生身体に配慮した「現代小説」を書き始めた。つまり、一挙に「新しい」認識を言語化するのではなく、小出しに小出しにまだ「言葉にされていないことを言葉に」。すると、「作家」のメンタルヘルスは一挙回復し、それどころかその技術にも爆発的革新が起きた。批評家は根絶されたが、その一部は優れた小説家兼AI技術者になった。つまりAIは「小説家」を爆増させ、その結果純粋な読み手は消え去った。現代では後者のほう、つまり純粋な創作だけをする「小説家」よりも、元「批評家」としてAI研究を多少なりとも踏まえた小説家のほうが評価される傾向がある。
AIが生身体と足並みを揃えて発展することができた「表現」の幸福な例として、「文学」は一部の芸術とともになんとか歴史を繋いでいるが、このような好例は少ない。たとえばダンス&ボーカルの生身体文化が完全に潰えているように。どうやら批評のほうの歴史的蓄積がその鍵になるといわれていた。
たとえば「エンターテインメント小説」のジャンルではAI身体の創作がある時期に席巻した。だが、その結果生身体は、数十年かけてゆっくりと、なにがエンターテインメントとして「面白い」のかが分からなくなっていき、その分野の感情が著しく衰退した。それは七十年前の「現代アート」に触れた生身体の反応に似ていなくもないらしい。
つまり反応が逆転した。「エンターテインメント」は「難解」とされ、「文学」はまだギリギリ親しめるというふうに。
だからもう厳密には七十年前のような純然たる「エンターテインメント」はない。アリスのように過去のダンス&ボーカルコンテンツに情緒反応が表れる(感動する)ような個体は極めて稀なのだ。だからこそ「エンターテインメント」の過去コンテンツは古いデータであればオークションで高額取引されるほど人気がある。もう自分たちには「面白くない」ものの希少価値は、まだかろうじて面白い「文学」よりはるかに上だった。
「文学」が現在の生身体にもギリギリ「面白い」という感情を呼び覚ます理由は、現在と七十年前を繋ぐ語彙や価値基準ではまだそれこそ「言葉にできない」。その謎の中にこそ「文学」に残されている可能性がある。それゆえなんとか生き長らえられているというのが有力な仮説としてあった。つまり文学はもともと一部に「難解」といわれる要素があったから逆に救われた。当時「読みやすい」とされていた作品のほうがこんにちでは遥かに「難解」なのだから。
だから時間の問題なのだろう。
しかしいま書かれているものの多くは七十年前の感覚でいうところの「小説」ではない。アリスは過去への情緒反応が強すぎる個体だから、論文ではなく「小説」の提出をサジェストされた。
「夢」も「権威」も「プロ」という概念すらもなくとも、まだ書く人間がいる「小説」というジャンルの謎に、はからずもアリスは挑むことになった。
「と、いっても、七十年前の価値基準に照らし合わせるとだいぶ「エンタメ」よりの「小説」になっちゃうんじゃないかなあ……だって「文学」って、いくらなんでもアレすぎるよね。アレ」
~さらに七年後~
「できた!!!!!!」
アリスが六六〇〇四文字の「小説」を書き上げたとき、すでに憑馬カート教授の風貌は青年風になっていたが、ますます熱心に「オムライス」に耽溺していた。
すでにブームを何週も回り、さいきんでは頓(とみ)に「ケチャップイズベスト」と述べるようになった憑馬教授は、アリスの書き上げた「小説」をケチャップオムライスを食べ終わるまでのあいだに通読し、「うーん、これではまだリジェクトされるだろうなあ」と言った。
「くそがーーーー!!!!!!!!」
キルトはキレた。
この七年でいつからか毎晩「オムライス」を作る役目をキルトが代わるようになり、仮想貿易のノウハウにも詳しくなって、日々ダンス&ボーカルの練習を反復するあいまに書き上げる論文はスルスル通るのに、毎晩「オムライス」の味に苦言を呈され「だったらお前が作れ」という言葉が喉まで出かかっていた。
生身体の基準では「成長期」真っ盛りの憑馬カート教授は、食べる量が七年前の四・五倍ほどに増えてい、アリスとキルトの身長もいつしか追い越した。
この数日前、教授が「もしかするとおれって、ビジュイイ?」とつぶやいた。
「は?」
アリスのコクーンでフライパンを振っていたキルトが、「ビジュですか。さすがは憑馬教授、過去研究の第一人者でもなければそのような暴力的な言葉は出てきませんあ」と皮肉を言った。
「われわれが行った過去の基準に照らし合わせますと「ビジュイイ」です。念のため、AIにも審議させましょうか?」
「いやいい。そんな野蛮なことAIにさせるなんてエネルギーとテクノロジーの無駄。そうか。ビジュイイのか……。そうか。そうかぁ……」
それで、二人は久しぶりに過去のことを思い出したのだった。
「そうそう、小説に書いていて思い出したんだが、そういやエコブラの周辺の人間に多重タイムトラベルの人間、過去スパイが混じってるんだったよな」
アリスの言葉を聞いたキルトはフライパンを持ったままで、ハ!!!!!!!!!!と言った。
「ハア。そうだった。すっかり忘れてたわ」
「小説であの場面に差し掛かったからさ、思い出したんだ。懐かしいわ」
「つまり、アリスが書いてるのはシショウセツってやつなわけね」
「そう。私小説。それしか書けないし」
「うーん。ま、それはそうとしてその「小説」を仕上げるのが先決だろう」
「もうすぐ書き上がるよ! これは傑作だからアクセプトされちゃうだろうなあ」
「って言ってったのに!!!!!」
キルトはその数日前の光景を憤怒とともに一挙、思い出したというわけだった。
「では教授、また「主題」やら「人称、語り手」などを変えて一から書きなおすべきでしょうか」
「うーん、さっそく仮査読にかけたんだけどな、おれの直観とおなじく問題は「主題・その他技術的観点」ではないんだよな」
「ではどうすれば……」
「ちょっとなあ、どうやら「リアリティ」がないんだよ。小説っていうのは難しい文化でね、ほんとうにあったことをそのまま書くと却ってリアリティがないんだよな。ちょっとしたスパイスみたいなもんがいるってわけ。出来事を日記やエッセイではなく小説としてそのまま書くとリアリティが生まれないから、それをリアルにするためのなんらかの工夫に、千年以上も人は悩んできたのよ。その工夫のひとつを人はかつて物語と呼んだよね。でも物語は出来事をほんとうらしくするけど、ほんとうらしい嘘にまでにしかしない装置ともいえる。これがフィクションは嘘と呼ばれていたことの真実かな。つまり、小説と物語のちがいというか、両方存在する意義ってのはそのあたりにあって、その葛藤や蓄積こそが小説の「リアリズム」なんだよ」
「なんてこった! 難しすぎます!」
「いや、しかし一五四の書いたこれはこれで、「味」というか、オリジナルな一五四ならではの「文体」ができていて、いまおれの言ったこともある程度クリアできているから丸ごと書き直す必要はないかも。むしろおれ個人としても、AI査読仮施行としても、一五四は個性恐怖の発作を乗り越えて、よくぞここまで頑張ったといった評価だな」
「憑馬カート教授……」
じっさい「小説」を書く日々でアリスの個性恐怖の症状はすこしずつ落ち着き、隙間時間に練習を積んでいたボーカルにも変化が生じはじめていた。
楽曲のいろを声で表現し、それを使い分けるよろこびを味わい、ダンスとともに音楽の「解釈」を身体表現するアリスなりの技法が確立され始め、キルトとともにするダンス&ボーカルの練習も充実を極めていた。
当初「小説」を書き始めたころは無味無臭かつ精確な描写のみを心がけていたアリスだったが、人の感情や五感、とくに過去人のそれを描くにはいまの自分が考えられる精確さだけでは表現できない壁に突き当たり、というより、過去で出会った出来事を精確に書くには論文のような無味無臭の文章ではズレが生じることに気づく。
少しずつ、アリスという人間の個の底が抜けるように、まるでエコブラの楽曲に取り入れられていた一部の歌詞みたいな言葉の詩的飛躍を「小説」に取り入れると、ようやくあの日の出来事をうまく表現できたような気がした……その日からアリスはすこしずつ個性恐怖の症状に脅かされることが減った。
そして「小説」の進捗とともに、ダンス&ボーカルの「表現力」が格段に上がったのだ。それからはダンス&ボーカルの練習が楽しくて、身体を動かすと「小説」のアイディアが浮かぶという好循環が生まれるようになった。それがここ三年のことだ。
「いいだろう。おれの一存でこの「小説」のつづきを文学専門AIの製品に書かせてみよう。おれの考えでは、それでアクセプトされるのじゃないだろうか」
「え、全面的にですか? それでテキストとしての「強度」が維持されるでしょうか」
アリスが問うと、「ここまで一五四の「文体」が安定していれば、いけるのではないだろうか。まあ、おれの教官としての立場は罷免されるだろうけどね」と応えた憑馬教授は、ちょうど未来から戻ってきたころのアリキルと同年齢になっていた。十代のうちは七十年前とほぼ同じ生長変遷を辿るが、成年になってから死ぬまではほとんど見た目が変わらず「年齢」という概念がなくなる。
「たしかに、論文をAIに書かせるのはむしろ七十年まえより重罪だわな。ほんとに優れたものを書いてしまうのだから。むしろ拙さから滲む真理を読み取るためだけにまだ人間が下手な論文を書いているというのに。でも「小説」はな。アリスの書いた元の出来と大きくは変わらないだろうな」
キルトはその「拙さ」のなかでもどういう類いの「下手さ」が学界に好まれるかよく分かっている。それがこの時代における論文のセンスと呼ばれるものだった。
「しかし教授! 質的過去研究の天才と呼ばれる教授にそんなリスクを負わせるのは」
「いや、じつはおれはすでに別の学科の再試験を受けていて、転学届けも受理されてるから、あとは一五四の論文がアクセプトされるのを待つだけの立場なんよ。おれは学生に戻る。だから仮に君たちが過去に戻れたとしても、担当教官は変わっていると思うよ。いずれその者から過去へと連絡がいくだろうね。これは十年前のあの日、一五四と一五五の、いや、アリスとキルトのダンス&ボーカルを見て感動の涙を流した日から、なんとなく分かっていたこと。おれの身の内に、教授としてはふさわしくないほどの「夢」が澱のように、溜まっていくのに抗えなかった。ふふ、おれもずいぶん研究者としては甘っちょろいってことだね」
「てか、十年も過去料理を食すような人間が教授としてやっていけるワケはないと思ってたよ。おおかた過去料理の研究がしたくなったんでしょ。というか、過去に行って本場の「オムライス」を食べたいだけだろう。絶滅料理の魅力はおれにも重々分かるからね。おおかた教授はおれがいつまでたってもアリスほど「オムライス」をうまく作れないから物足りなくなったんだろう」
「え、まさか教授がそんな個人的嗜好で「夢」を濫用しようとするだなんて、それがもし学会に知られたらコト……」
「あとは教授は「動画クリエーター」になりたいんじゃないかな。最近妙に過去のYouTube動画を観ているよね。それにビジュを気にするだなんて、なかなかこの時代の想像力では難しいことですよ。おおかた過去研究を兼ねて過去に渡りグルメ系ユーチューバ……」
「ハイ! AIが書いた「小説」の続きができました。大体一五四の書いたものの二・五倍の分量で算出されたね! では学会に提出しま~す」
その「小説」にはアリスとキルトがまだ経験していない七十年前のあの日のつづき、つまり「過去の未来」が書かれていた。
ふたりはそれを読むこともなく、学会が即座にギリギリ過半数の判断で受理を決定した、その瞬間、過去へと戻った。
意識を欠いたふたつの肉体が自動的に栄養カプセルに移送されると、AIの書いた「小説」を通読した憑馬カート教授は「あー、なるほどあの人物が。そういうことだったらおれらにはもはや手出しできないね」とひとりごちた。
*
「やからね、大阪っていってもミナミとキタでは言葉も大分違うし、だいいち大阪弁ってちょっと「やってる」っていうか、わざと大阪人が大阪に寄せているような、げんみつにいうて関西弁いうのとも微妙に違う気がするんよな。吉本がな、それを助長してるんよ。まったく。たしかにヤスの関西弁は関西弁っていうより吉本弁やね、ぼくに言わせると。やからこそ絶対に大阪育ちなんやなって確信はできる。関西の人間とてべつに方言そのものには連帯感もないわけ。罠なんよ。たとえばあのオーディションで受かって本家グルの方にメンバー入りした大津家大河(おおつやたいが)は滋賀やけど、「滋賀」っていうた瞬間の関西の人間の「あぁ……」って感じ。わかる? そもそも大阪出身だからって「なんかオモロイこと言えや!」って言ってくるやつ、マジで実在するからね。ほんとやんなるよ……。オーディションのときにもSNSに「サトシは大阪人らしくない」ってめっちゃ書かれて、え、ぼくがなにしたん?ってあの時ばかりはちょっとムッとしちゃったもんね。だからといって大阪以外の関西人のようには振舞えないし、ようするに大阪臭みたいなのはまったくは隠せない。ハア、まるで故郷がないみたいな気分だよ」
ふだん寡黙でどちらかというと沈思黙考型のサトシがそんなに長く喋っているのは初めて見たのだったが、そもそも会うのが十年ぶりだったので、少し泣きそうになりながらキルトは、「へ、へ~」と言った。
「あー……正直、もっと穏当な、特徴のない地に生まれたかったな。やれやれ……」
「苦労したんやな! せやかてサトシええんやで、おれらのまえでは無理に明るく振る舞わんでええんやで」
そしてサトシにいきなり抱きつき、「でもやっぱそういうエセは許せん」と迷惑そうにされているのをアリスがむりくり剥がした。
キルトの目の前に置かれた氷だらけのグレープフレーツジュースを、アリスは一口飲んだ。
*
未来での十年自主練というチートが利いてか、とくに時間を持て余していたキルトのダンススキルがリュウに次ぐほどにまで急激に伸びたうえ、かんたんな振りを考えるクリエイティビティまで身に着けていた。
くわえてラップスキルまで上達していたため、ゲスト出演したフェスでいちど五曲ほどを生披露した際にSNSがざわつき、#双子覚醒がトレンド入りした。じつはメンバーたちよりも先に「ハッコウ」つまりファンたちのほうがキルトとアリスの異常なスキルの伸びに目ざとく気づき、さざめいた。
アリスはダンススキルこそ見違えるようだったものの、「個性恐怖」の症状が出なくなりつつあるというのに却ってボーカルが不安定になっており、その要因と対策をAIアシストに訊ねても「回答不能」とのことだった。
そこで上層部と話しあった結果、レンとともにボイトレを受けるべく急遽マサと三人で渡韓することになった。
メインボーカルの一員であるシンイチが「え、だったらおれも韓国がいいんだけど」とつぶやくと、マサに「シンイチはボーカリストとしてというよりいまはダンス&ボーカル特有の技術と身体能力を伸ばすべき。日本でリュウたちと追加公演前に配信される新曲の振りをしっかり入れて、余裕をもって歌えるようにすることが最善」とピシャッと言われ、ぐうの音も出ない冷静きわまる表情で「ですよね」と言った。
アリスの顔はだれが見ても不自然なほどしろく、まるでそこに居ないみたいな表情をしていることが増えた。
韓国にきて三日ほどたち、マサに付き添われて行われたトレーニングセンターでのボイトレは順調で、レンの発声は明確に良くなっていった。その変わっていく声を自分で聞いて、トレーナーに「もっと顔を使う」といわれ、「声を前に出す」といわれ、「ここはしっかりスタッカートを切る」といわれ、基礎を叩きこまれるとレンはますます伸びた。コンタクトインプロヴィゼーションというペアで踊る即興ダンスのような動きをしながら発声したり、ブリッヂをした状態で歌ったりなど、ありとあらゆるトレーニングを受けて、「ボーカル」という概念そのものが拡張されたようだった。
レンはもともとマサに懐いていたし、ボイストレーナーも人を委縮させる経験を知らないような明るい女性だったので、レンは伸び伸びと声を出すとじょじょにボイトレへの苦手意識が消えていき、基礎が底上げされると自己表現の幅が増した。謎の漢方を与えられると、どれだけ声を枯らしてしまった翌日でもまたフルで発声できた。
だがアリスは違った。やれと言われたことはぜんぶその通りにできるのに、本番通りに楽曲を歌うとすぐに元通りの弱い声質に戻ってしまう。だけど綺麗に声は出ているから、レンはその度「できてるよ!」「すごいよ!」って言う。
だけどトレーナーは言い方を変えて何度も「もっとあなた自身の表現を」と伝えた。
「なにが自分の声を抑えてるのか、この滞在期間のどこかで絶対に、吐き出しなさい。それができないとボーカリストとしては頭打ちと思いなさい」
トレーナーの助言をマサが通訳するその声も、アリスのあたまにはろくに入ってこない。
こんなことはオーディションの時から何度も言われてきたことで、アリスはそもそも「個性」が気色わるかったから直す気もなかった。だから、オーディションでもじょじょに参加者が脱落していって楽曲を披露するグループ数が減ったところで、高音で楽曲を支える役割に徹することにも飽きられた瞬間にアッサリ落ちた。主宰には、「アリスには自分の声を愛してあげてほしい。だって唯一無二のこんな素敵な声をしているのに」と言われ、アリスはそのときは心に響かなかった。
「もっといろんなパフォーマンスや、アートとかにも触れて、自分の奥底にあるものを見つめなおします」
そう言って番組を去った。すべては予定通りだった。
だけどいま。未来に戻って十年論文を、「小説」を書いて判明した。
もう未来は変わってしまった。レンが喉をボロボロにしてエコブラが自壊する未来はおそらく来ない。
エコブラ周辺のだれか。おそらく自分たちより先の未来からだれかがこの時代に来ていて、未来の法でこの時代の過去改変がなされていて、いつ、なにがどうなるかもうふたりにも分からない。
この状況で、あるいみ「現代人」と同じ状況で見知らぬ明日を生きる自分たちの「夢」への道はいつまでつづき、いつ途絶えるのか。「未来」はまったく分からない。
でも過去人にとってはこんなの当たり前のことだ。昨日まで追い続けた「夢」を今日あきらめなければいけない、そんな日はとつぜんにやって来る。
だけど、アリスにとってこれは最初からあきらめるはずだった「夢」だ。ただこの時代の「夢」にあこがれて、ちょっとだけ噛ませてもらうつもりで来た。過去人の「夢」にまつわる執着とその功罪をまとめて卒論として提出し、無味乾燥な未来の生に戻る。二十歳を過ぎれば身体も安定し、供給される充分なセロトニンで何不自由なくずっと幸せだ。人々が幸せならAI労働の需要もだいぶ減る。病気すらも医療テクノロジーの進歩云々とも関係なくしぜんに減る。
だから、アリスにとってはエコブラは論文執筆にかこつけた束の間のアトラクションみたいな「夢」だ。
オーディションで落ちるのも知ってたし、エコブラの結成もその後の低迷もぜんぶ知っていた。
だけどいま、運命は覆った。過去人にとって当たり前のこと、「明日が分からない」という過去人にとっては普通過ぎることにいま、アリスは恐れ慄いている。
「アリス、韓国久しぶりだもんな。ここんとこ暑いし、ちゃんとクーラーつけっぱで寝ろよ」
とマサは優しい。しかしアリスの気持ちと身体はバラバラで重い。マサは未来からきた? ついうっかり、世間話のような温度感でそう聞いてしまいそうになる。レンにも。レンはこの時代の人間じゃない? しかし怖かった。未来人であるかどうか拘らず、なにが目的なのかどうかも関係なく、それを聞いたらすべてが変わってしまう。目の前の人間の表情がAI予測を越えてくらく、冷たくなることがなによりも怖かった。
それに、おれはもっとやってはいけないことをした。
ボイトレを終え、レッスン室を出たレンがマサに「この後、ゴッシュにマウンテンモチきな粉を食べ行かない?」と誘った。
「ゴーセンのきな粉モチマウンテンな」と訂正したあとでマサは「行かない」と言った。
「えー。なんで?」
「てかレンはメシ前によくあんなん食えんな」
「きな粉とアーモンドは美容にもいいんだよ、シンイチが言ってた」
「とにかく今日はちょい無理なんだわ。明日か明後日に行こか」
アリスがその会話を黙って聞いていると、マサが「なあ、アリスは新曲の振りで不安なとこない?」と肩に手を置いてたずねた。
これから始まるツアーの途中に配信シングルの初披露が予定されていて、おとといコレオグラファーから振り付け動画が届いていた。日本にいるメンバーは今日からすでに振り入れを行っており、レンに比べると振り覚えの遅いアリスの進捗が心配された。
帰国したらすぐにスタジオに集まってツアー全体の演出を頭に入れなければならないため、新曲を合わせる時間がいつもより少ない。だから上層部でもアリスを韓国に行かせるか日本に止まらせるかは一部意見が割れた。マサが「自分が現地で一緒に振り入れする」と提案したことで、ボーカル強化のための渡韓派が多数を占めてアリスはいまここにいる。
「振り? うーん」
「うん。念のため。今回簡単そうに見えてちょっとテクいとこあるから」
「テクい……、ああ、難しい……そうかもね」
「難しそうなとこだけ早めに入れとこうか。まだ体力余ってる?」
「うん」
「そっか。じゃあレッスン室予約しといたけど、いっしょに行けるか?」
「え? なんで? ワイも今日からいっしょにするよ」
「レンはだめ。もう自己流で振り入れしてるの知ってるから。これからはショートスリーパーぶるの禁止」
レンは一度見た振りはほぼ完璧に覚えられる。たしかにボイスレッスン中に即興ダンスをした際に、新曲のコレオが含まれているのを見た。きっと深夜に送られてきたコレオをろくに眠らずにすぐ踊って自然に入れてしまったのだ。
これだからいやだ。「才能」は。どうしてこんな気持ちにならなければいけない? アリスは戸惑った。自分がどういう気持ちで、どういう状態でいまここに立っているのか、なにもかも分からなくなっていた。
それに、マサが自分を気遣い、優しくされるごとに声が、身体が萎縮していくのが分かる。なぜ? アリスは元々マサのことは怖くなかった。むしろマサの自他に厳しくしなければ生きてこられなかった出自と性格にどこか気持ちが同調していた。
けど自分は優しくされるに値するような人間じゃないんだ。
アリスはうすうす気づき始めている。ほんとうには出せるはずの自分の声がうまく出せない理由。
「えー……ワイめっちゃつまんねえじゃんー」
「また明日な。いまから出歩いてもいいけど、行き帰りは必ずタクシーアプリ使って、日焼け止め塗って、ちゃんと飯食って早く寝ろよ。明日はボイトレの前にダンスレッスンもお願いしてるから」
「はーい」
そしてレンと別れたあと、無言がちに同じトレセンの地下一階から三階に移動し、ダンススタジオに入った。
つづく
町屋良平「発光する、ら」は『Quick Japan』最新号にて連載中!