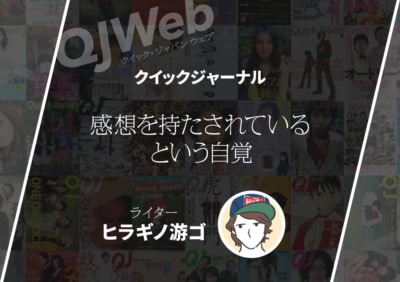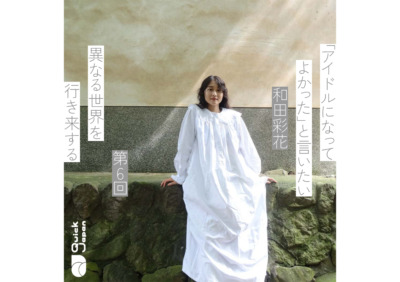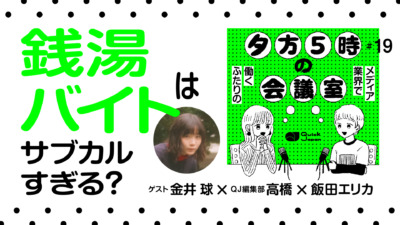女は女だから「女らしいもの」が好きなのか? 男は男だから「男らしいもの」が好きなのか? 音楽やゲームなど多彩な趣味を持つモデル・俳優のイシヅカユウが、子供のころを回想しながら、現在につながる「好き」の源流を考える。
目次
音楽好きになるきっかけとなった『音楽ファンタジー・ゆめ』
私って好きなものがいっぱいある。特に幼いころからずっと好きというものが多かったりする。
覚えている限りで、特定のコンテンツを「好き」と認識したのはなんだろうと考えて思い当たったのが『音楽ファンタジー・ゆめ』(1992〜1999年)というNHKの子供番組だった。
CG黎明期に作られたこの番組は大人になって改めて観ると、子供のころにこんな前衛に触れていたんだという驚きがある。毎回、クラシック音楽をCGアニメーションによるMVつきで紹介していく番組で、音楽はほぼ毎回、原曲を聴くと逆に「こんなだったっけ?」と思うほどにアレンジされている。特にお気に入りはハチャトゥリアン作曲「剣の舞」の回で、2〜3歳ごろの私は延々と星を切り続ける意志を持った剣の絵を描いていた記憶がおぼろげにではあるが残っているほど。
この番組の目的はおそらく幼い子がクラシック音楽に興味を持つことだと思うのだが、少なくとも私にはその試みが成功し、その後クラシックのCDを親に買ってもらって今に至るまでさまざまな音楽に親しみ、それがきっかけでクラシック以外の、民族音楽から現代音楽まで多様な楽曲を聴くのが好きな人間に成長している。
キックしか出せなくても楽しかった『鉄拳』シリーズ
その後にハマったのがテレビゲーム。父がゲーム好きだったので、幼稚園に入る前か入ったころに初めてプレイステーションに触れた。一番初めにやったのが『アクアノートの休日』(1995年)というゲーム。これは海の中をただひたすら潜水艦で探索していくもので、一応のエンディングはあるもののほとんどクリアという概念もない。とにかく珍しい魚や海底遺跡を見つけては楽しみ、時々ちょっと怖かったりする。
大人になって改めてやってみると、音楽の素晴らしさに感動した。海の深さや場所が変わるごとに少しずつ変わっていくBGMが海中探訪をよりワクワクするものにしているのだ。
その後すぐくらいに家に来たゲームが『鉄拳』(1995年)である。言わずと知れた今に至るまで続く格闘ゲーム界のモンスターシリーズ第1作! 初めてやったときは、ただただキックを出すことしかできなかったし、CPUと戦うのも怖くてひとりモードをやることができなかったのを覚えている。今思えば、まだ幼稚園にも入ったか入ってないかくらいだもんね! でも当時はなんとなく悔しかったような記憶もある。

その悔しさをバネに(?)私はこのあと、『鉄拳2』(1996年)、『鉄拳3』(1998年)とシリーズをやり続けて、すっかりハマっていった。しかしだんだん、少し普通と違う方向にハマり方が変わっていった。戦うのはもちろん好きだったのだけど、いつの間にか各ステージのBGMを聴いたり、キャラクターそれぞれに用意されているエンディングを観ることにプレイ時間……といっていいいのかわからないけれど、時間が費やされるようになっていった。
「シアターモード」でBGMにまで没頭した
特に『鉄拳3』からは「シアターモード」という、クリアして一度観たことのあるエンディングなどをいつでも観られるモードが搭載されて、遊んでいる時間の半分以上はそのモードでいろんなシーンを何度も観ることに費やされた。しかもそのモード中に過去作のディスクに入れ替えると、過去作の映像まで視聴することができ、私はどんどん夢中になった。

こういった短いイメージの集積のような(多くはセリフなどもなかった)映像をただ観るのが好きだった経験から、私は今でも古今東西のCMを観ることが好きなのかもしれないと思う。
この「シアターモード」では映像だけでなく、BGMも聴くことができ、私はそれにも夢中になった。『鉄拳』シリーズのBGMといえば、今でこそデジロック的な音楽が主流だが、その流れになったのは『3』からで、『1』『2』のころはもっとYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)的なテクノサウンド色の強い音楽だった。世界のさまざまな名所を模していた各ステージに合わせた民族音楽的アレンジが聴いていて、どれもかなり聴き応えのある音楽だ。
大きくなってから、私は民族音楽からエキゾチカというジャンルを知り、そこから細野晴臣にたどり着き、そしてYMOやその周辺の音楽を聴くようにもなるのだが、源流はこのときに触れた音楽がかなり影響したいるのだなと、大人になって改めて思う。
自分も変身する覚悟を決めた『セーラームーン』
『鉄拳』と同時期くらいから、私はセーラームーンにもハマった。ちょうど『セーラームーンS』(1994〜1995年)のころで、ウラヌスとネプチューンが出てきたころだったと思う。この作品はシリーズの中でも特に神話的で美しい物語だったけど、当時はそういう大事なところは少し怖いと感じていて、ギャグ的な要素がある回ばかりを好んで観ていたと思う。

セーラームーンごっこも当然のように友達と幼稚園などでやっていた。現実で起きた他愛もないことでも「悪者の仕業かもしれない!」と思って友達と無言で目を見合わせ、変身する覚悟を決めていた。今思うと本当にかわいらしい私たちだったと思う。
大人になって改めて、当時のセーラームーンシリーズ全200話を観た。特に『セーラームーンS』の物語と演出の鮮やかさやケレン味が好みで、調べると幾原邦彦さんがシリーズ監督をされていることがわかった。幾原さんといえば寺山修司さんの劇団「天井桟敷」に影響を受け、アニメーションの表現の中に舞台芸術的要素を取り入れていた方。10代のころから私は「天井桟敷」や寺山修司さんの作品にもハマったのだけれど、まさかセーラームーンでその種を植えられていたとは気づかなかったのでとてもおもしろく思った。
<男の子用><女の子用>で区別し、それを促す社会
3〜4歳くらいのころ、すでに私は出生時に割り当てられた自分の性別に違和感があり、そのことを家族やまわりに発露していた。そして、そのこととセーラームーンが好きなことをかなり関連づけて言われたり、セーラームーンのおもちゃを買うことを渋られたりした。自分でもかなり最近になるまでそのことは関連づけて語っていたと思う。
しかし改めて考えてみると、私に限らず、女の子は女の子だからセーラームーンが好きだったのだろうか?
逆に男の子は男の子だから格闘ゲームが好きなのだろうか?
今好きなもの、ハマっているものや、作品の見方の傾向に影響を与えてはいるけれど、ジェンダーアイデンティティに関わっているかといわれるとそうでもないというのが事実である。自身のジェンダーに関わらずあらゆるものが好きだった私は、子供のおもちゃやコンテンツがいまだに<男の子用><女の子用>で分けられ、そのとおりに子供を促している社会に違和感を覚えている。
兎にも角にも、自分の好きの源流をたどるというのはおもしろい。まだまだほかにも、幼いころ好きだったものが大人になって好きになったものと大きく関わっていたりするのかもしれない。
【イシヅカユウ「リサイタル」】
生誕33年および独立を記念し、これまでの活動で培った集大成、そして新しいことへの挑戦として、“リサイタル朗読劇“を開催。古今東西の音楽への造詣の深いイシヅカが自ら企画構成に携わり、舞台仕立てのオリジナリティあふれるステージを披露する。
日程:2024年7月5日(金)
時間:19:30開場/20:00開演
会場:LOFT HEAVEN
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR