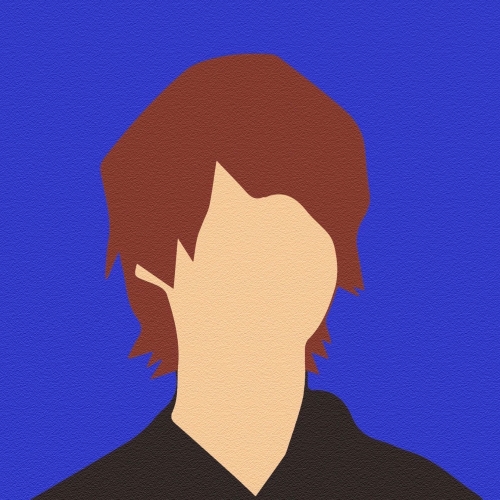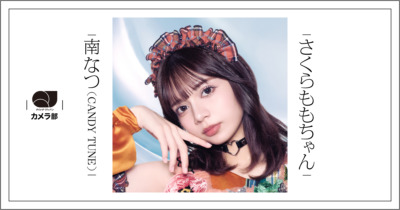構成作家・河谷忍による連載「おわらい稼業」。ダイヤモンド、ケビンス、真空ジェシカら若手芸人とともにライブシーンで奮闘する、令和のお笑い青春譚。
AO入試の課題に取り組んでいた河谷の前に現れた白衣の男。彼が持つ「相棒」が、この課題に大きな影響を及ぼす──。
高校生活最後の事件
横長の画用紙に縦長の四角い枠が横一列に10個ほどあった。「一番左の枠を真っ白、一番右の枠を真っ黒とした場合に白から黒へグラデーションになるよう鉛筆で順に塗っていきなさい」という指示がされており、これが美大のAO入試最後の課題だった。
教卓では折れた桜の枝で自分の板書を指しながらメガネをくいと上げる白衣の男が生物の教鞭をとっていた。私はこの男が生物教師であること以外、何ひとつ知識がない。名前も知らなければ家族がいるのかどうかも、なぜ生物を教える立場で桜の枝を容赦なく折って持ってこられたのかもわからない。ただわかることといえばこの男はその枝を始めの授業から使っていて、それを「相棒」と呼んでいたことぐらいだった。
「相棒」という言葉は江戸時代に籠屋がふたりひと組で棒の端と端を持っていたことに由来している。ほんまの棒を「相棒」って呼んでどうすんねん、といった明らかに優勢状態の合コンでも誰ひとり笑わないようなツッコミは、その場にいる誰もすることができなかった。その点、私の高校生活は笑いに恵まれていたのかもしれない。
入試の課題を授業中に済ませなければならないほど期限ギリギリまでほったらかしにしてしまっていた。私はとりあえず一番右の枠をここぞとばかりに濃い真っ黒に塗りつぶした。ここにめがけて左から徐々に濃度を上げていかなければならない。左からふたつ目の枠を鉛筆で薄く塗っていく。ここを濃く塗ってしまうとのちのち取り返しのつかないことになってしまうので、できるだけ薄く薄く塗っていく。呼吸を止めながら鉛筆をかなり浅く握ると力を入れないように紙の上で鉛筆を小さく揺らすような感覚だ。
真っ白なキャンバスの上になんとなく薄いグレーのレイヤーが重なったようになったので、次の枠を塗り始めた。先ほどより少し力を入れて、ひとつ左の枠よりはほんの少し濃くなるように鉛筆を紙にこすっていく。同じことを順に繰り返していき、いよいよ右から2番目、ラストひとつ前の枠に来たところで気がついた。徐々に、徐々に濃くなるよう濃度のレベルを小さく上げすぎたせいでラストひとつ前の枠とラストの枠の濃さが全然違うものになってしまっていた。このままいくとやたらと薄いグラデーションが続いて最後のひと枠で一気に濃度が上がる。ご飯に集中しすぎたせいで、持ってきてもらってから時間が経って底にアルコールが溜まり散らかした梅酒のソーダ割りみたいな作品になってしまうと思った。いや、思ってなかった。
私は再びB2のマドラーを手にもう一度左から順番に徐々に濃くなるように少しずつ上から塗り足していった。何度も試行錯誤を繰り返してようやくきれいなグラデーションが完成した瞬間、その紙が一瞬で真っ黒になった。きれいなグラデーションを塗っていたはずなのに一色の黒に染まった紙が不思議で、なんのことやらと顔を上げると紙を覆った黒いものは桜の相棒を手にこちらをにらむ生物教師の影であることがわかった。
「こんなのは休み時間にやりなさい」
生物教師が枝で紙をトントンやると、再び教卓に戻る。しかし任務はすでに終わっている。あまりにもきれいなこのグラデーションを提出すれば入試担当も腰を抜かして「ぜひ入学してください」と向こうから頭を下げに来るに違いない。私は紙を大事に片づけようとカバンから入試書類の入った封筒を取り出そうとしたそのとき、異様なものが目の端に映った気がした。赤い。なんだ、赤いぞ。きれいなグラデーションの上に、赤い色がポツポツと虫刺されのようにできていた。
私は全身に脂汗をかいた。あの枝の先についていた赤いチョークの粉がきれいなグラデーションの上におじゃましてきたのだ。この生物教師を杉下右京とした場合の神戸尊(シーズン7最終回~シーズン10)がよけいなことをしでかしたのである。私は赤い粉をこするが指では取れない。六角、いやせっかく塗ったこの枠に仕方なく消しゴムを入れる。今までの努力は警視庁、いや帳消しになってしまった。その記憶は今も特命、いや克明に覚えている。
深い絶望と憎しみが同時に押し寄せ、その日の昼食は購買のカツサンドを2個食べた。いつもは1個なのに。「いつもは1個なのに今日は2個? 彼女でもできたんか? ああん?」購買のおばちゃんが聞いてきたのできれいな無視をした。二度と話しかけてくるなと思った。
ちょうど普通の大学生活へ
私は無事美大の映画学科に入学した。映画学科の教室は本学からは少し離れた場所にあった。住宅地にひっそりと佇むその校舎はとても静かで、少しでも誰かが叫べば苦情が入るような立地だった。入学初日、教室で先生を待っていると唐突に扉が開き、スキンヘッドでフレームが大きなメガネをかけて髭を生やしたステレオタイプのAV監督のような人が入ってきた。どうやらこれは講師のようだ。
「聞いて」
第一声だった。 何を? 全員が思った。
「まわりの音、3分あげるから聞いて、そこからどんな物語を想像する? ほら、聞いてみて、スタート」
全員が耳を澄ませる教室に、私の鼻で笑う音だけが響いてしまった。
大学生活は順風満帆ともいえず、最低ともいえない本当にちょうど普通の毎日がただ流れていた。美大は卒業論文ではなく卒業制作を行う。私は自ら監督に志願して80分ほどの探偵映画を1本作った。昔から『名探偵ポワロ』や『古畑任三郎』を観ていた私にとって、エンタテインメントに富んだ探偵映画はいつか挑みたいジャンルだった。この先、自分が映画監督になるのか、そうなった場合いつ自分の撮りたい映画を撮れるようになるのかもわからない世界であることは卒業生やまわりの環境を見てすぐに理解できた。もしやるなら今しかない、そう思った。
合評で4~5グループほどが自分たちの作った映画を上映していき、講師にボロクソ言われていく。誰がこんなに言われて映画の仕事をやりたいと思うのかと感じたが、講師なりの「これに耐えなきゃ将来はもっと厳しい」という優しさだったのかもしれない。もちろん私の卒業制作にも講師陣からは厳しい意見が飛んだ。言われすぎて何を言われたのかも覚えていない。上映後に全員の前に立たされ公開の説教を受ける。後半は白目を剥いていたに違いない。生涯を賭けて本気で映画をやりたい人にとっては何クソ根性を掻き立てられるのかもしれないが、私にとってはそれが「お前はもうやめておけ」という半ば呆れの混じった声に聞こえたのだ。やりたいことはやった。自分が進むべき道は映画ではないとそのときに確信した。
個別の進路相談会が開かれ、ひとりずつ担当の教員と就職の話をする。ほとんどの人が大学から勧められる映画やCMの制作に携わる会社にエントリーシートを出していくなか、私はテレビのバラエティ番組を作るためテレビ番組の制作会社への就職を決めた。映画は好きだった。でもそれ以上にお笑いが好きなのだと大学生活をもって痛感したのである。
ここから私のおわらい稼業が始まる、そのときはたしかにそう思っていた。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR