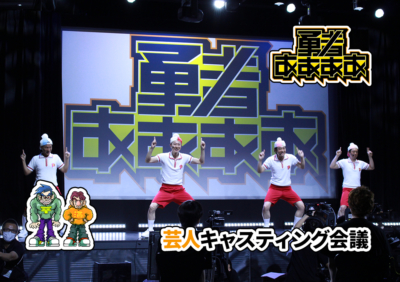人生で最も死を目の前に感じた瞬間
そして決定的な事件が起こった。
グオゥ!!という音を立てて猛烈な風が吹いた。先を行く幹事長の匍匐によって染み出した水が巻き上げられて僕の顔を強かに打つ。後方で「あ!」という小さなうめき声が聞こえた気がした。
振り向いて目を疑った。
T君が運んでいたはずの2リットルのペットボトルが、凄まじい勢いで氷上を移動しているのだ。空じゃない。天ぷらの衣を作るのに必要だからと持ってきた未開封のミネラルウォーターが、風に吹かれて滑っていくのだ。「シューーーーー!」と音が聞こえるような、マンガ的な滑り方だ。冗談じゃなく、僕は目を疑った。高密度の2kgの物体が、いくら強風とは言えこんな速度で滑っていくなんて。
T君のほうを見て、またしても僕は目を疑った。
なんと、彼はそのペットボトルを追いかけようと、体を起こそうとしているのだ。
ペットボトルはすでに遥か遠く、目視できないほどの距離まで飛ばされている。
「もういいから! 先に進もう!」僕は叫んだが彼の耳には届かない。強い責任感と強風とで、彼の鼓膜はもう音を聞き取ることをやめていた。
そして悲劇は起こってしまった。
T君が、飛ばされたのである。
3人の中で最も体重の軽いT君は、見事に二足で立ち上がった途端、全身に風を受け、ペットボトルが消えた方角へあっという間に滑り果てていったのだ。確かに、見えなくなったペットボトルを追いかけるには最も効率的な方法だったに違いないけれど、僕はこのときの光景を死ぬまで忘れないだろう。人間が風に吹かれて滑って消えて行く様———。
幹事長はもう遥か先を這っているからこの珍事を知る由もない。
僕は静かに前を向き直し、ゆっくりと匍匐を再開した。
T君のことは、諦めたのだ。
僕はこのとき、本当に自分が死んでしまうかもしれないと思っていた。
そしてT君が風にさらわれていったとき、本当に彼は死んでしまうだろうと思っていた。今までの人生で最も死を目の前に感じた瞬間はこのときである。
対岸近くの入江の影に命からがら辿り着き、僕は幹事長と合流した。
「俺たちは生き残ったんだ」
汗と湖水でびしょ濡れの肩を強く組んだ。
「T君は?」そう聞く幹事長に、僕は無言で首を振った。幹事長はすべてを察したようだった。
そして僕たちはテントを立てて、氷に穴を開け、釣り糸を垂らした。
少し気持ちが落ち着くと、T君がそこにいないことをひどく恐ろしく感じ始めた。
「ちょっと探してくる」僕はそう言い残してテントから這い出し、岸沿いに風下へ歩いていった。
T君の遺体の第一発見者になることを覚悟していた。
しかし、それは僕が缶コーヒー収集ヒョロ男の生命力を過小評価していただけのことだった。
まるで映画『アルマゲドン』で、生き残ったクルーたちが地球に帰還してくるあのシーンのように、T君がこちらに歩いてきたのだった。スローモーションがつけられたかのようにゆっくりとした足取りで。
「ごめん、ペットボトル見つかんなかった」涙や鼻水の跡が縦横無尽に走った顔で、彼はそう言った。
「どうせ湖の上なんだから、水はいっぱいあるよ」僕はそう言うとそそくさと踵を返し、彼の先を歩いてテントへ向かった。
泣いているのを気づかれたくなかった。なんだかボロボロと涙が出てきたのだ。
T君を見捨てて自分たちだけ安全な場所に辿り着き、現実から逃れるかのようにしばらくは捜索することさえしなかったこと。それなのに、彼はペットボトルを失ったことを謝罪したこと。総じて、自分の心の賤しさを感じざるを得なかったこと。本当に恥ずかしかった。僕なんて、マザコン人殺しエゴ男だ。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR