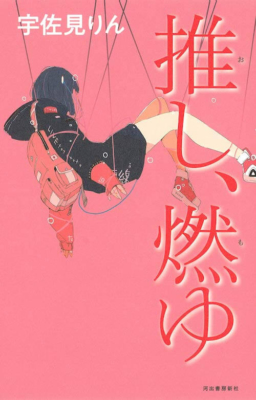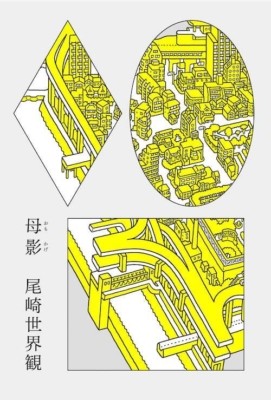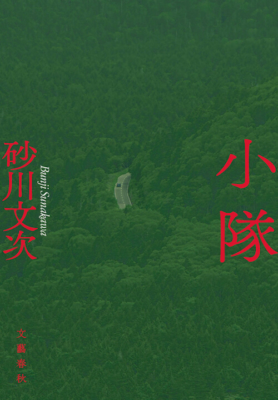人称の混在が気になった「小隊」
砂川文次(1990年生まれ)「小隊」(『群像』2020年12月号/講談社)2回目(第160回、「戦場のレビヤタン」で初ノミネート)
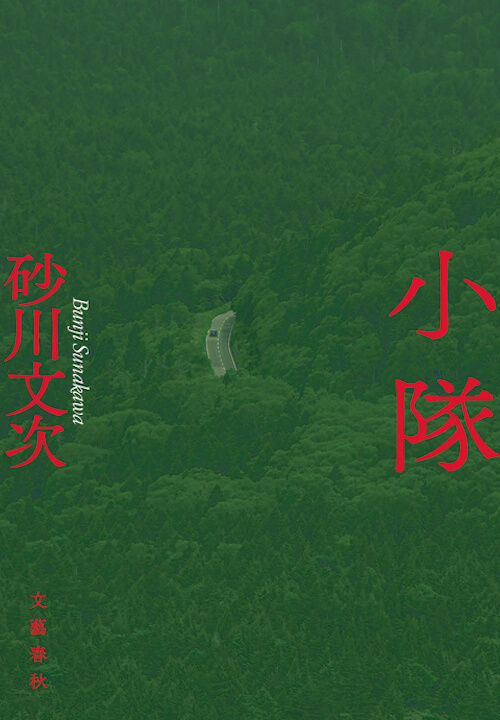
舞台はロシア軍が攻めてきている北海道。自衛隊の初級幹部であり小隊長でもある主人公の安達とその部下の立松が、釧路は別保でいまだ残留している住民に対して避難勧告を行っている、のどかな場面から物語は滑り出します。安達の小隊の任務は別保一帯の陣地を防御し、敵であるロシア軍の侵攻を阻止し、味方の第5旅団の戦いを援護するというものですが、安達らが釧路駐屯地から派遣されて1カ月、敵は音なしのまま停滞した時間が過ぎていくばかりです。
が、戦闘はいきなり始まります。陣地内の地形が変わるほどの烈しい攻撃。部下である隊員たちはどんどん死んでいきます。おまけに航空攻撃の接近まで知らされ、戦車の砲撃も受けることに。安達は指揮を受ける中隊CPまで撤退しようとするのですが、逃げている途中で遭った軍曹から「もうCPはない」と告げられ絶望。途中で恐怖から動けなくなっている部下の木村を拾って、帯広まで逃げるための車を求め、冒頭に出てきた残留住民のアパートまで行くと、そこにいたのが小熊でした。小熊はもうすぐ定年を迎える小隊の最古参で、安達は階級は下ながらも頼りにしていたのですが、怖くて逃げたと明かすみじめな姿に呆然。一緒に連れて行ってほしいと懇願する小熊を置いてパジェロで走り去ります。物語は、川で全裸になって身体を洗った安達の「おれは生き残った。生き残ったのだ」という心の声で幕を閉じます。
〈戦うとか戦わないとかいう選択肢はそもそも安達ごときの立場にあっては、選択の俎上に上ることはなく、せいぜいがちゃんとやるか、ふてくされながらやるか、くらいの違いでしかない〉と主人公がうそぶくように、誰も本当の戦闘なんてやったことがない自衛隊の若者たちが直面する戦争を、さすがは元自衛官というべきリアルな描写で描いていて、戦闘が始まって以降は巻おくあたわずのおもしろさ。安達たちがとんでもない状況に置かれているにもかかわらず、そこからちょっと離れた街ではAMラジオが放送されていて、日常が営まれているという不条理も生々しいといえましょう。
気になるのは三人称と一人称の混在。気にしている人はあまりいないかもしれませんけど、最近、特にエンタテインメント作品でその傾向が強いと、わたしは感じているんです。三人称小説なのに、〈立松が、不安そうにこちらを見ている〉という一人称視点がしょっちゅう入ってくる。かと思えば、〈不安だ。安達は、思った〉みたいな正しく三人称の語りも混じる。自由間接話法に似てるけど、そこに話者が事実をそのまま語る場合に使われる直接法が入ってくる「体験話法」と言われるものなのかもしれませんが、作者がいったいどの程度その語りを意識して使っているのか。これは、わたしのような「視点警察」じゃない人にとっては読みやすさを伴う語り口なので、それゆえに使ってしまいたくなるのでありましょう。ただ、使うなら狙って自覚的にねと、老婆心ながら。
涙腺決壊しそうになった「旅する練習」
乗代雄介 (1986年生まれ)「旅する練習」(『群像』2020年12月号/講談社)2回目(第162回、「最高の任務」で初ノミネート)

小説家の〈私〉と、サッカーとオムライスが大好きな姪の亜美(あび)。ふたりは、亜美の中学受験が無事終わった春休み、コロナの緊急事態宣言が発令される前に我孫子から鹿島までの徒歩旅行に出発します。目的は、亜美が去年の夏サッカー合宿に訪れた鹿島の施設から、持って帰ってきてしまった本を返すこと。
〈私〉にとっては途中で見た光景をスケッチのように書き留めていく描写の練習、亜美にとってはリフティングをしたり、ドリブルしながら走ったり歩いたりするサッカーの練習を兼ねた〈歩く、書く、蹴る〉ための旅です。
2020年3月9日から始まった旅の2日目、ふたりはやはり鹿島までの徒歩旅行仲だという大学4年生のみどりさんと出会い、亜美がこの女性にすっかりなついてしまったことから以降行動を共にすることになります。
徒歩旅行のあれこれが〈私〉の視点で描かれるなか、〈私〉が書いたスケッチ文+亜美のリフティングの回数や、訪れた土地に関係する文人の紹介と引用と考察を挿入。この小説全体が、旅から帰ってきた〈私〉が書いたものであることが作中で律儀に明文化されています。
品のいい端正な文章で綴られる、「山の手小説」とでも呼びたくなるような育ちのいい物語。サッカー小説でもあり、鳥類図鑑小説でもあるといった盛りだくさんな内容の作品になっています。
前に候補になった「最高の任務」は叔母と姪、今回は叔父と姪。なんでも知っている聡明な年長者に導かれる若者という構図は変わっていませんが、姉妹小説というよりは鏡像反転小説になっていると、わたしは思います。
テーマは「忍耐と記憶」。ジーコゆえに鹿島アントラーズのファンになったというみどりさんが作中紹介する〈「ジーコはつらかった肉体改造を振り返ってこう言います」(略)「もし「もう一度同じことができるか」と問われたら、迷わず「できる」と答える」(略)「そのために大事なのは、忍耐と記憶だと」〉というエピソード。佐原の町で想起した小島信夫の小説「鬼」に出てくる「忍耐」という言葉に思考を立ち止まらせて、〈本当に永らく自分を救い続けるのは、このような、迂闊な感動を内から律するような忍耐だと私は知りつつある。(略)この旅の記憶に浮ついて手を止めようとする心の震えを静め、忍耐し、書かなければならない〉と記される決意。
しかし、なぜ〈私〉は繰り返し、この旅を記す行為にできるだけ喜怒哀楽を入れない〈忍耐〉を強いるのか、そもそもなぜ姪との旅の記憶を文章化したのか。その答えは最後に用意されています。もしかしたら、この「最後」に選考委員から批判が来るかもしれないと、読後懸念を覚えたのは確かです。わたしも最初は、せっかくの抑制がここで破綻してしまうと思ったのですが、それはまったくの逆で、この忍耐の劇的なほつれを描くための、そこまでの忍耐の記録だったのだと2回読み返した今は思います。
とにかく亜美という少女の魅力が破格。読み進めば読み進むだけ好きが募っていくキャラクターで、3人でテレビアニメ『おジャ魔女どれみ』の話で盛り上がるシーンで、魔法のセリフや身振りを真似ながら〈「パパ、ママ、せんせには怒られちゃうけどさ、そんなの実はどーだっていーじゃんってことなんだよね。サッカーできてたらさ。だから、テストで3点、笑顔は満点、ドキドキワクワクは年中無休なの」〉と元気いっぱいに宣言するシーンは、小説を最後まで読んで、またここを読み返すと胸と喉が詰まって涙腺決壊しそうになります。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR