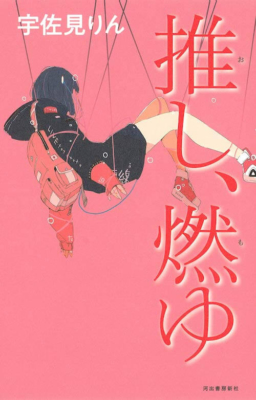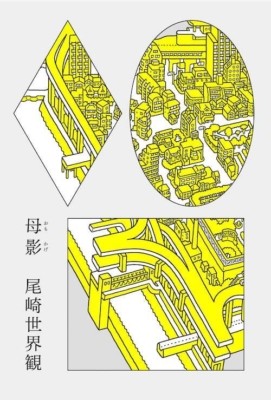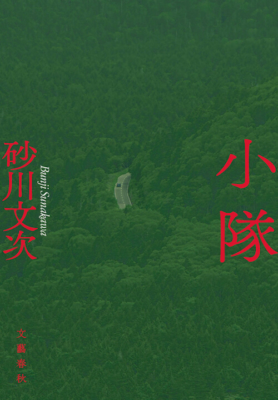「母影」の真っ暗ではない〈茶色い夜〉
尾崎世界観(1984年生まれ)「母影」(『新潮』2020年12月号/新潮社)初
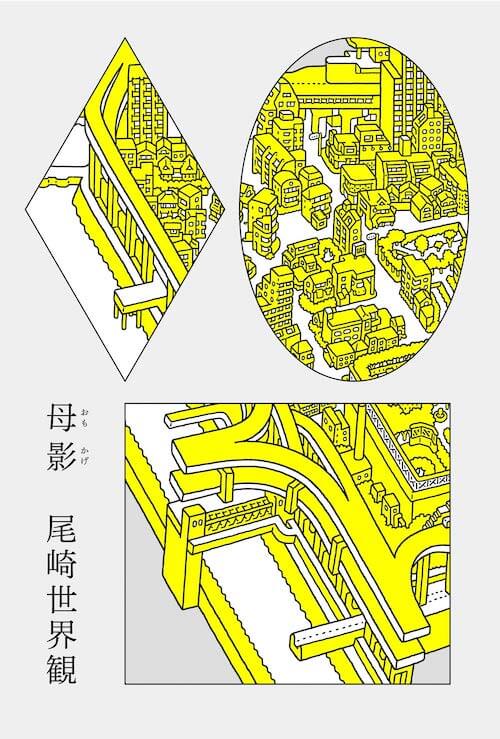
語り手は、マッサージ店で働く母親とふたりで生きている小学校低学年の〈私〉。でも、そのマッサージ店は客からの「ある?」という符牒で、手でイカせてやるファッションマッサージ店だということは町の住民には周知されており、〈私〉はそれゆえにクラスで仲間外れにされています。
母親の仕事中も隣のベッドで宿題などをしている〈私〉はカーテンを通して常に母親の影を見守っています。まだ幼いから具体的に何をしているかはわからないし、お客の「イッていい?」をしゃべるほうの「言っていい?」だと勘違いもするけれど、カーテンの向こうにいる母親と客が〈恥ずかしいことをしてる〉ことはわかっている〈私〉なんです。
母親に子供の問題点を挙げ、こんな仕事をしているからなんじゃないかと説教しながらも、手こきのサービスをおそらくは無料で受けているゲスい担任教師。給食の杏仁豆腐の上にハムスターのフンを乗せる意地悪なクラスメイト。やはり母子家庭に育ちながらも、「おい。お前、死ねです」という独特の口調で〈私〉の肩をグーで殴ってくる男子児童。
この小説は幼い〈私〉の五感を通して、真っ暗ではない〈茶色い夜〉のようなわびしい、さびしい、でも不思議と悲愴感はない日常を丁寧に描いています。
母親とお出かけし、初めて自動改札機を経験して切符に開いた穴から外の世界をのぞく場面や、カーテン1枚で常に母親と遮断されているような気持ちを描く場面、「お前、死ねです」男児の家に上がり込んで自分の家と同じくらいの貧乏を冷蔵庫の中に発見する場面、その家で邪険に扱われている、おそらくは認知症のおじいちゃんを「これ、いらないなら私にちょうだい。ちゃんと大事にするから」と欲しがる場面など、印象に残るシーンが多々あるものの、語り手のキャラクターが今村夏子の傑作『こちらあみ子』(筑摩書房)の主人公と重なってしまって、どうしても比べてしまう自分がおりました。

クリシェを超えて独創的な「コンジュジ」
木崎みつ子(1990年生まれ)「コンジュジ」(『すばる』2020年11月号/集英社)初

「コンジュジ」とはポルトガル語で「配偶者」の意。
主人公は11歳のときに深夜の音楽番組で知った「ザ・カップス」という1970年代に人気を誇ったバンドの伝説のリードボーカリスト、リアン(1951年生まれ)に20年間恋をしつづけている31歳のせれな。しかし、リアンはせれなが知るずっと前に32歳の若さで死んでいます。
せれなの母親である妻に逃げられ、そのあとに同居した無口だけどしっかりしていて女子プロレスラーみたいに強いブラジル人女性ベラさんにも出ていかれてしまったあげく、まだ小学生のせれなを陵辱し、せれなが17歳のときに、それを知ったベラさんによって殺されるまでずっと性的虐待を行ってきた父親。せれなにとって、リアンとの脳内生活はその忌まわしい時間からの逃避でした。
というわけで、この小説は「父親による性的虐待とそこからの再生を描いた現実」と「脳内におけるリアンとの妄想生活」と「せれなが本を読むなどして知ったリアンとバンドの評伝」の3つのパートを行き来して展開していくことになります。
リアンとの妄想生活が、せれなの現実にどんな影響を与えていたのかを後半で明らかにする展開が巧みですし、時々顔をのぞかせるユーモアに文章表現のセンスのよさも感じます。娘のことを「せれなちゃん」と呼んで依存してくる父親の造型の気味悪さ。その父親にようやく「死んで償えよ!」と抵抗する中盤以降の烈しい暴力を伴う場面が、リアンとのお花畑のような脳内妄想の世界から一転地獄絵と化し、その落差の描き方も秀逸です。
宇佐見作品の中に〈推しは命にかかわる〉という名言が出てきますが、まさにリアンはせれなにとって命綱というべき存在だったにもかかわらず、後年、成長したせりながリアンという人間の欠点とも向かい合い、リアンの兄でけっして妻と家族を裏切らなかったジムのほうに心を寄せ、疑似父親の妄想を抱いていくようになるという変化も、納得のいく展開。父親からの性的虐待と、そのフラッシュバック、心的後遺症による摂食障害の描写や、リアンであったはずの幻がやがて父親を思わせる黒い物体と化し、せりなの体の上で人間のシルエットになっていくシーンは、症例を調べて書いたようなクリシェを超えて独創的とも思います。
ラスト、リアンの墓を掘り起こして自分も棺の中に入り蓋を閉める場面から〈どうせ明日もまた五時半に起きて、バスに乗って仕事に行くのだから〉という一文につなげるくだりは再生とも読めるし、再生の先にあるリアンもジムも存在しない厳しい現実の人生を予感させて不穏でもあり、物語の締め方としては上々というべきでありましょう。
関連記事
-
-
マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR -
ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】
『DAIENKAI 2025』:PR