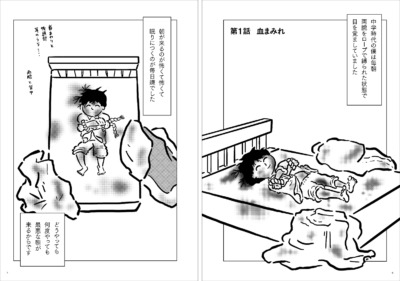狡猾な人間が橋下徹
人間ばかりでもありません。平安時代の少女・柳のもとに、現代からさまざまなものを運んでくる片方の羽が赤い不思議なカラス。霊の存在を感知するワイヤーフォックステリアのケイク。過去の光景を見ることができる黒猫のトム。
そうした大勢の登場人物らの1~3ページほどと短い各エピソードが、ゆるやかに他の挿話とつながっていく。空間的にも時間的にも遠く離れた他人同士であるキャラクターたちが、知らないうちに他の登場人物と袖振り合っていることが、読者にはわかるように描かれていく。ちょっとどうかと思うほど、大勢の(しかし、実はほんの一部の)キャラクター名を挙げたのは、『去年の雪』がそういう紹介の仕方を要請する作品だからです。
人物とエピソードが濃淡さまざまに重なり合う。過去と現在の人々と光景が有機的に交差する。誰もが固有の生を生き、「誰かが誰かと」「何かが何かと」つながっていく豊かな世界。この小説を読んでいると、わたしは独りではない、独りで生きてきたのではないということが、しみじみと了解できるんです。
「分断」や「世代間対立」なんてものは、見えるものしか見ない人にとってのデマゴギーにすぎない。見えないけれど、確かにそこにあるものに目をこらす術を知っている人こそが、無数のつながりによって成立している世界の真実を語ることができるんです。その語り手たらん人々を「インテリ」と雑にまとめて揶揄し、わたしたちに無意味な争いをけしかける狡猾な人間が橋下徹なのです。
妻を亡くして以来、スマホでたくさんの写真を撮るようになった綿貫誠司という老人が作中で呟く〈心に訴えかけてくるものというのは、存外そこらじゅうにあるのだ〉という言葉が、心に残ります。デマゴーグに煽られることなく、自分がそういう豊かな世界に生きている大勢の成員のひとりなのだということを、忘れないようにしようと思う次第です。