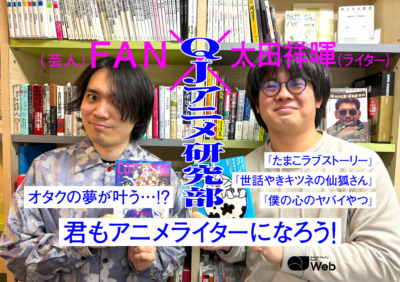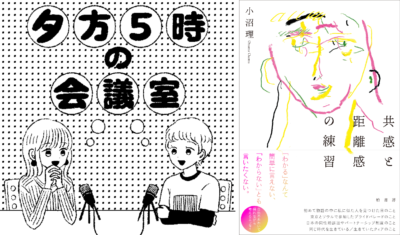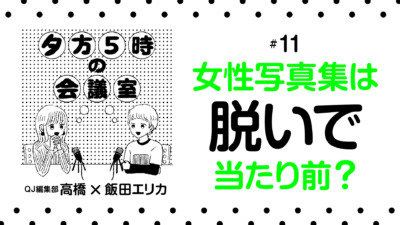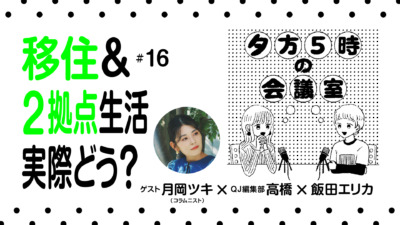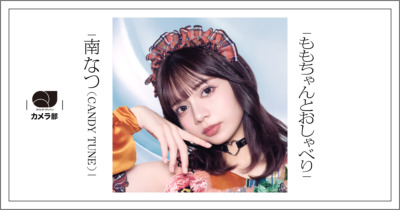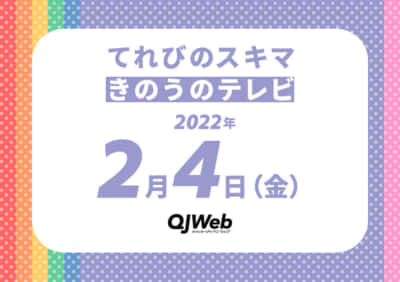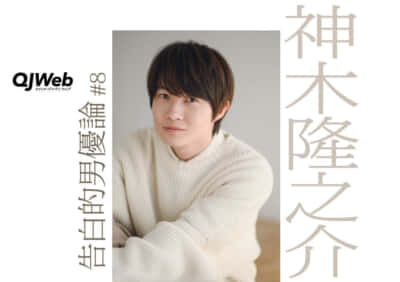『オードリーのオールナイトニッポン』のチーフディレクターを務めたことで知られ、2024年2月には同番組の東京ドームライブも成功させた立役者である、プロデューサーの石井玄。4月16日に上梓したエッセイ集『正解のない道の進み方』(KADOKAWA)では、先の見えない道を歩み続けてきたプロデューサーとしての4年間の日々や仕事術を綴っている。
「ラジオは斜陽産業である」と強く意識した上で、大規模イベントを実施したり、異業種とのコラボによって幅を広げてきた彼に、これからメディアが“延命”ではなく真に生き残っていくためのヒントを聞いた。

石井 玄
(いしい・ひかる)1986年埼玉県生まれ。2011年に、ニッポン放送の深夜番組制作を担当する番組制作会社・サウンドマン(現・ミックスゾーン)入社。『オードリーのオールナイトニッポン』『星野源のオールナイトニッポン』『佐久間宣行のオールナイトニッポンニッポン0(ZERO)』などにディレクターとして携わり、『オールナイトニッポン』全体のチーフディレクターを務めた。20年、ニッポン放送入社。『東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館』『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのプロデュースを担当。21年にはエッセイ『アフタートーク』(KADOKAWA)を刊行。プロデュースした生配信舞台演劇ドラマ『あの夜を覚えてる』が「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ACCグランプリ、Amazonオーディブル『佐藤と若林の3600』が「第4回 JAPAN PODCAST AWARDS」大賞を受賞。24年、株式会社玄石を設立。25年4月16日に『正解のない道の進み方』(KADOKAWA)を刊行。
「苦労したほうが楽しい」というマインド

──新刊の『正解のない道の進み方』では、正社員としてニッポン放送に入社してから現在までの歩みが綴られています。前代未聞だった『オードリーのオールナイトニッポン』の東京ドーム公演を企画するなど、そこには「誰も実現したことのないことのほうがおもしろい」という石井さんのマインドが貫かれていますね。
石井 最初は誰しも、「やったことのないこと」の連続だと思うんです。でも毎週同じ番組を担当していると、発見や挑戦はありつつもある程度はルーティン化されていくもので。2019年に『オードリーのオールナイトニッポン』で日本武道館公演を開催したときの成功体験は、その中で異質の喜びがあったんですよね。
やったことのない規模感でのライブは超大変だったけど、終わったあとの達成感を若林(正恭)さんや春日(俊彰)さんと分かち合った時間は忘れがたいものだった。あの感覚をもう一度味わいたいという気持ちがずっとどこかにあったんだと思います。ラジオにはないイベントの特性は、目の前のお客さんの笑いや拍手などの反応を受け取れること。それは突き詰めていくと、高校時代に文化祭を作っていたときのライブ感に近しいものがあると思います。
──文化祭に熱心な高校生だったのですね。
石井 文化祭がすごく盛り上がる学校に通ってたんですよね。僕自身は消極的ではあったんですけど、部活も引退した3年生のときだけ、初めて学校に泊まって徹夜で準備をするみたいな経験をして。それがすごく楽しかった思い出があるから、自分が見たことのないお祭りを作ってみたいっていう気持ちがずっとあります。
そのころから一貫して「苦労したほうが楽しい」というマインドはあると思います。スタートした時点で最短距離が見えなかったり、非効率な道を歩んだりするほうが成功したときに絶対に達成感がある。東京ドーム公演も、当初は2daysの開催にしたいと目論んでいたんです。なぜなら、想像がつかないし、絶対無理だと思ったから。不可能だと思うことを実現したほうがおもしろいという感覚は、どんどんエスカレートして常軌を逸しつつありますね(笑)。結果的に、東京ドーム公演は1日開催でもじゅうぶん大変だったのでよかったんですけど。
──マラソンや登山のように、苦労してたどり着いたからこそ見える景色があるのでしょうか。
石井 それが、僕も富士山に登ったことはあるんですけど、全然楽しくなかったんですよね(笑)。おそらく、ひとりで達成するものだからだと思うんです。マラソンよりは、タスキをつないで走る駅伝のほうがたぶん性に合っている。何かを作ることが単純に好きというよりは、誰かと一緒にチームで取り組む過程が好きで。ひとりで黙々と作業する職人のような仕事は僕には向いてないと思います。
根拠のない指摘には、オウム返しで対応

──前人未到の領域にチームで立ち向かっていく石井さんの仕事ぶりにおいては、「即興性」や「直感」のようなものがキーワードになっていると著書を読んで感じました。
石井 準備するのが嫌いなんですよね。プレゼン資料をつくったりするのもひとりでやらないといけない作業だから、会議で直接、相手と話を進めていくような方法が合っていて。ラジオの生放送というものはそもそも即断即決が必要な場所で、その場のアドリブでさまざまな困難を乗り越えてきたことで鍛えられたのかもしれません。
──前例のないことを企画するには、決定権のある人を説得する必要も出てくると思いますが、その際にはどうやって不安要素を解消しているのでしょうか。
石井 やったことのないことを説得するのって意外と簡単で。「チケット売れるの?」と聞かれたら、「売れないんですか?」ってオウム返ししてたんですよね。誰もやったことがないわけだから、できない根拠も誰も持っていない。だから「〇〇だからチケットが売れない」と言いきることは誰にもできないんです。これで不安要素をフラットにしたあとに、ラジオイベントを東京ドームで開催する成功例になるといった、実現したときのメリットを伝えるとみんな乗ってきてくれる。
あとは、ニッポン放送の上層部やタレント事務所、スタッフといったそれぞれの立場の人たちに対して、何を不安要素に感じているかをつぶさに感じ取り、それぞれに別の方法で説明するということはある程度細かくやっていたと思います。
裏方がSNSで発信するべき理由

──石井さんは著書の中で「ラジオ局にいると外部の人と関わる機会を自ら狭めてしまうこともあるが、このままだとラジオ局もラジオ文化も衰退してしまう」と語り、他ジャンルとの積極的な関わりを重視されてきたといいます。異業種とうまくコラボする方法や関係性を広げるためのヒントを教えてください。
石井 我々裏方の人間が、SNSなどで目立つ発信をしていくことが大事だと最近は思っています。スタッフが表に出ることに対して、うしろ指を指される時代はあったけど、発信したほうがメリットは圧倒的に大きくて。SNSが名刺になるので、僕に興味のある人が寄ってくるから初対面でも抜群に仕事がしやすいんです。逆に、発信している人に僕から近づいていくこともありますが、その際の情報共有の早さは強く実感しています。
現在はマンガ編集者の林士平さんや料理人の鳥羽周作さんのポッドキャストを制作していますが、異業種の人と話すのは本当におもしろいと感じます。ラジオは誕生してから100年が経っているから、もう進化しきっている面があって。ラジオ文化の中で新しい見せ方を探すよりも、他の業界でトップに位置している人たちのノウハウをラジオに活かすほうが可能性があると思うんです。今のエンタメの最高峰はアニメやマンガで、そこに知恵が結集している。その編集者やプロデューサーたちの話を聞くと、めちゃくちゃ勉強になります。
──『クイック・ジャパン』も斜陽の出版業界の中で雑誌を刊行し続けていますが、石井さんが感じているラジオ業界への危機感はそのまま出版業界にも当てはまるように思います。うしろ指を指されることに臆せずSNSなどでの発信に注力するというのは重要な示唆ですね。
石井 僕がプロデューサーを務めているポッドキャスト番組の『少年サンデーのフキダシ』が今年の3月からスタートしていて、これは『少年サンデー』の編集者たちがマンガについてゆるく雑談する内容です。これも裏方が発信している一例で。目的としては、ポッドキャストを広く届けて『少年サンデー』の発行部数を上げるというよりも、新人漫画家の投稿数を増やすことにベクトルが向いています。そのためには数を取りに行くんじゃなくて、狭くても深く刺さるひとりに届けることを重視していて。編集者たちの人間性を知ってもらいやすい音声コンテンツという手段を選んでいるんです。
「ブランディング」と「収益化」はセットで考える

──目的を明確にした上で発信していくわけですね。
石井 目的はブランディングとも言い換えられるかもしれません。最近、『ビリギャル』の著者である坪田信貴先生と知り合ってよくビジネスの話を聞くんですけど、「結局はブランディングとUI(ユーザインターフェース)が大事ですから」と言われて、すごく腑に落ちました。
ブランディングに関していえば、僕が『オールナイトニッポン』を立て直す立場にいたときも、「オールナイトニッポンってどこに独自の価値があるんだっけ?」と改めて問い直すところがスタートしましたから。僕がリスナーとして好きだったオールナイトニッポンは、“なんかよくわからないけどおもしろい人がしゃべっている場”だったので、佐久間宣行さんや水溜りボンドのような異色なジャンルの人に担当してもらうのがふさわしいと思ったし、原点に立ち返りながらも新しいものを混ぜていくことを大事にしていたんです。
ただ、「ブランディング」に対して予算をつけるというのは、実はかなり難しくて。僕の場合は、ブランディングのためにイベントを打ちたい場合でも、グッズで収益を上げる仕組みを作ることで説得したりしていました。東京ドームライブをやれば、収益は出るし、ブランディングもできるし、広報にもつながるという、そうしたアイデアを提示できれば、上層部も安心して予算をつけてくれるようになります。『クイック・ジャパン』にも積み上げられたブランドはたしかにあるはずで、それを見つめ直すことが斜陽産業を立て直す際の第一歩になると思います。
──石井さんは東京ドームライブを成功させたあとすぐに独立し、2024年4月1日に株式会社玄石を立ち上げられます。その際の決意についても著書で触れられていますが、独立後のビジョンについてはあまり考えていなかったというのが「苦労したほうが楽しい」という石井さんらしいと思います。
石井 まったく先が見えないほうがおもしろいと思っていましたね(笑)。でも会社を立ち上げて1年が経って、改めて今後について考えてみることもあります。このままいけば、『オードリーのオールナイトニッポン』が20周年を迎えたときに、きっともう一度オードリーさんと何かをやるときが来るだろうと。その際はもう番組の関係者ではないので僕に話が来るかどうかもわからないけど、呼んでもらったら役立てるように、レベルアップしておかないといけないわけですよ。うっすらとそうした目標を持ちつつ、人脈を増やして仲間集めをしたり、スキルを高めたりしている状況にある。いつか大きいイベントをやるときに、自分のチームや経験を総動員できればいいなと思っています。
-

石井玄『正解のない道の進み方』(KADOKAWA)
「知ってる仕事」ばかりやっていたら、ここにはいなかった。
ラジオからイベントへ、イベントから未知の世界へ。
「わからない」を武器にする方法、教えます。『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』製作総指揮が送る、石井玄氏のお仕事エッセイ第2弾!
未経験のイベントプロデュース、ゼロからの企画立ち上げ、誰も教えてくれない世界で、どう動き、どう進むのか?
『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』、『あの夜を覚えてる』、
『東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館』など、
さまざまなチャレンジを行ったイベントの舞台裏で経験してきた仕事術について、エピソードとともに余すことなく綴っています。さらに、漫画編集者の林士平さん、声優の佐倉綾音さん、動画クリエイターのとしみつさん(東海オンエア)、高比良くるまさん(令和ロマン)との対談も収録。
ジャンルを超えて活躍する人たちと語り合います。著者と関連の深い人物からのコメントも収録。リアルな仕事の一端を知れる内容です。
<コメント掲載者>敬称略・順不同
岸田奈美/佐渡島庸平/宮司愛海/鳥羽周作/前田裕太(ティモンディ)/
橋本直(銀シャリ)/佐藤満春/橋本吉史/内田浩之/安島隆/高橋雄作(TP)/
飯塚大悟/宮森かわら/高井均/高橋ひかる(※「高」ははしごだか)/千葉雄大/
オークラ/Naokiman Show/Nakamu/カンタ(水溜りボンド)カバーイラストは『月刊!スピリッツ』で『スノウボールアース』を連載中のマンガ家・辻次夕日郎さんが担当。
正解のない道を進み続けるすべての人へ贈る1冊。
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR