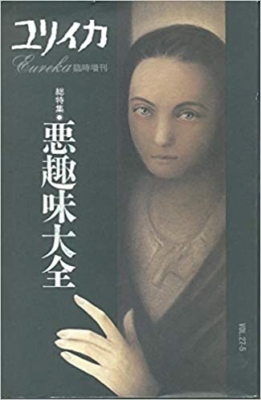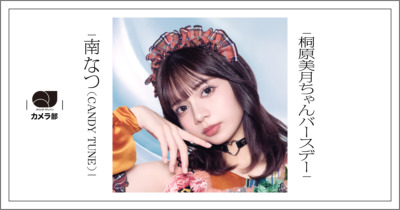90年代「悪趣味ブーム」の知られざる功績
『7』が組んだ熱い特集は、『クイック・ジャパン』への移植を経て、潜在的なジョージ秋山に対する興味を押し上げたと思う。誰もが知っているのに、誰も知らない風変わりな作家だったと気づき、焦った人は多かったはずだ。その背景として、この時期のカルチャーをめぐる動きがあった。
1990年代前半、それまで軽んじられてきた大衆映画や大衆音楽のストレンジな面に焦点を当てた、アメリカの『Re/Search』誌の特集が話題となった。日本の好事家たちは価値観を揺さぶられ、その振動は複雑に変換拡大し、出版に伝播した。映画でいえばムック版の『映画秘宝』(洋泉社)、音楽でいえば『モンド・ミュージック』(リブロポート)、総合的なものでは『ユリイカ』増刊の『悪趣味大全』(青土社)として結実し、これらのすべてが1995年の刊行。あえて目の向けられてこなかったイージーリスニングやビデオスルー作品などが掘り下げられるきっかけとなった。件の『7』の刊行は1996年。このムーブメントが、漫画ファンにも届き始めたころだ。
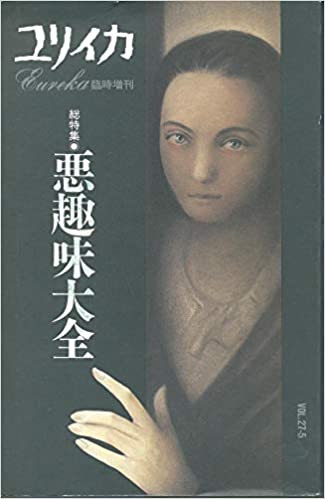
『映画秘宝』のテイストを模した漫画評が増え始め、復刻プロジェクト「QJマンガ選書」(太田出版)の開始された年でもある。この見直しと調査の時代が、「悪趣味ブーム」と雑に括られることもあるが、確実に以降の文化の捉え方は豊かになった。そして、この動きのなかで本格的に魅力が検証された現役の大物は、マンガにおいてはジョージ秋山だけだったと記憶する。ジョージ秋山はこのころ、全盛期を知らない新規のファンと、ファンであることを再認識したファンたちによって、カルト作家となった。これが前述した、わざわざ語られることのない、ジョージ秋山の作品を熱く支持するもうひとつの層だ。
地獄のフィーリングを忘れない。
ジョージ秋山作品には、氏の敬愛した二宮尊徳の言葉だという「水車のたとえ話」がよく出てきた。水車は、半分は水流に従い、半分は水流に逆らって回る。水に浸かれば流され、水から離れれば回らない。これを人の道のたとえとした。古くは60年代『ほらふきドンドン』(講談社)に挿入され、90年代初頭の有害コミック規制問題にも「表現の自由不自由は、たとえば水車の如し」と始まるコメントを寄せたほど、重宝していた。
「水」を「マンガ」に書き換えて漫画論を語るくらいのことはとっくにやっていたのかもしれない、とにかく使い勝手のよい訓話だが、何やら、ジョージ秋山の作品の模型のようなものを想像させられる。流れに逆らうものと、流れに任せるものが、それぞれを動力に回転する永久機関。悪か正義か。聖か俗か。愛か憎しみか。本当か嘘か。『浮浪雲』でさえ、優雅な遊び人の裏側に、権力に仕えた過去の殺伐な気風が顔を見せるのだ。『銭ゲバ』に登場する小説家・秋遊之助(ジョージ秋山自身がモデル)は、工場廃液を垂れ流す主人公・蒲郡風太郎をペンによって糾弾する宿敵だが、共通する何かを感じ、それを言葉にする、
「あんたは独特のフィーリングを持っている…地獄のフィーリングってのかな。」
そうだ、地獄のフィーリング。ジョージ秋山のマンガの、ぞわぞわとした風変わりな魅力にピッタリな言葉。久々に思い出した言葉を合図に、さまざまな場面が浮かぶ。闇の中でばら撒かれる紙幣が。涙を流す巨大なロボットが。ギラギラのネオンの下の照れ笑いが。焚き火の中の赤ん坊を見つめる狂女が。振り上げられる鎌が。そびえ立つ白い太腿が。画面の端に佇む仮面の男が。吹きすさぶ豪風が。驟雨が。だめだ、これじゃいつまで経っても終わらない。ラストシーンに辿り着けない。とにかく、俺は地獄のフィーリングを忘れない。