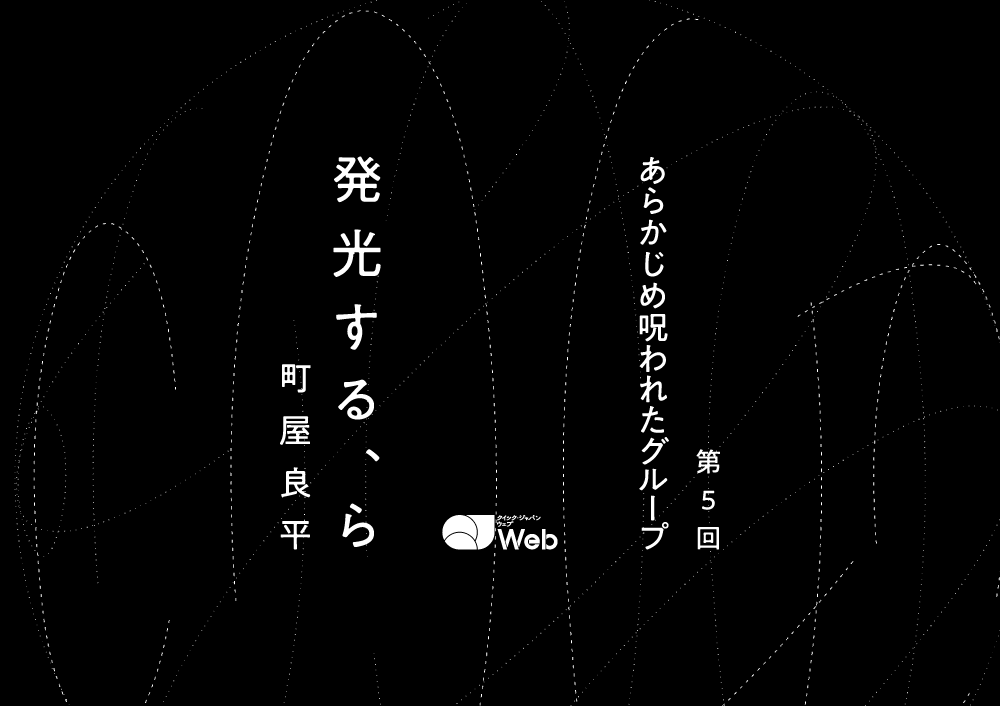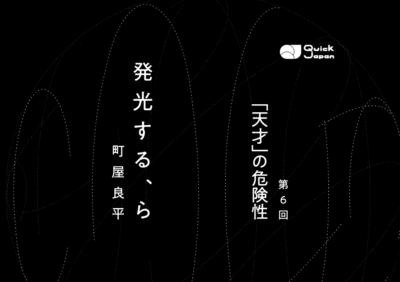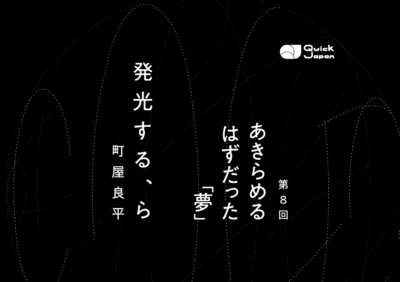メンバー間の仲も険悪、鳴かず飛ばずの6人組の弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。七十年後の世界からやってきた双子のアリスとキルトは、未来では禁忌とされた「夢」を追いかけてアイドルとして活動していた。
バンコクのフェスでふたりから秘密を告げられ、その重さにひとりで耐えるメンバーのサトシに、社長のヤスは声をかける。
前回までの連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
第2回 個性恐怖症
第3回 夢の功罪
第4回 被害者たちのスイーツ
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
朱里(あかり) シンイチの妹。キルト、咲世、十季の四人で定期的にスイーツ巡りをしている。兄のことはまったく尊敬していない。
咲世(さきよ) レンの姉。早くに両親を亡くし、ひとりでレンを育てる。シスコンぎみのレンに若干引いている。
十季(とわき) リュウの弟。兄のことはわりと慕っている。キルト曰く「リュウよりビジュがいい」らしい。
第5回 あらかじめ呪われたグループ
西日が差すと畳まれた長机の足の部分に溜まっているほこりが光った。事務所の会議室。レンリュウが二人で自主練をしている。
ほんらい今日はオフなのだったが、昨日のミニアルバム制作に向けた振り入れの休憩時間に、韓国の中堅ボーイズグループが出した新曲のMVを見たリュウが、「この踊りは華がある。バズるかもしれん」と思い立った。ついでに流行っている振りは片っ端から入れてしまい、いつも後手後手に回っているコンテンツ制作の現状を打破すべく早めに「踊ってみた」に取り組むべきだとレンに言い寄りいくぶん強引に付き合わせていた。
本来の練習日ではなくレッスン室がトレーニーの予約で埋まっていたため、会議室の机を折りたたんで端に寄せスペースを確保した。片方が動画を確認しつつ、ふたりで交互に踊りながらそれぞれのクオリティを上げていく。レンを誘ったのは、今回取り組む振りの難易度が総じて高いこともあって、ダンスが得意でないアリキルやシンイチのようなメンバーにうまく教えられるのがレンしかいないからだ。リュウは自分が踊れても、人に踊らせることはできない。
そこにノックの音が響いた。ふたりがビクッとしてそちらをみるとアリスの半顔がドアの隙間から覗き、「あのー。おれも、参加させていただいてもよろしいでしょうかー……」と言った。
レンは「アリスじゃん!」と声を上げた。
「おじゃまじゃ、なければ……」
「おー」
と声を上げたリュウはよろこばしい気持ちと、正直面倒臭い気持ちとが半々だった。なぜならアリスは目で見た振りをひとりで踊れるようなタイプではなく、だれかが教えながらでないとまだ振りを入れられないため、リュウとレンが練習する時間がそちらに割かれてしまうことが予想できたからだ。
「いや、きょうはおれはなんとなく、全体の雰囲気を摑んで、あとでなるべくあしでまといにならないために来ただけだから……。ふたりは振り入れに集中してほしい」
アリスが言うとリュウは内心安堵した。
「おいレン、アリスの言う通り、今日は自分の振り入れに集中しろよ」
それでも、レンは自分の練習時間を割いてでもアリスに教えるだろうと思った。
リュウが今回すこし難しめのダンコピにいちはやく挑戦しようと思ったのには理由がある。これまではダンススキルにバラつきがあるエコブラのメンバー数人で「踊ってみた」動画を出しても反響はたかがしれていたのだが、今回は振りがバズるポテンシャルが高いことに加えて先日タイで行われたフェスでレンの代わりをアリスがつとめた動画が、違法アップロードながら伸びつづけており、コメントでも新規が大量についていることが分かった。
そこでリーダーとしてリュウはここがチャンスかもしれない、と思い、TikTokをはじめとした各種SNSに改めて力を入れていこうという方針が固まっていた。
「アリは早めに振り入れしてこっそりうまくなって、みんなを見返してやろうぜ」
アリスは苦笑した。「見返してやる」はリュウの口癖である。
エコブラ結成のきっかけとなったサバイバルオーディション番組は、すでに韓国で不動の人気を誇るボーイズグループの日本人メンバーであった小松が主宰兼プロデューサーとして票を半分、番組視聴者がもう半分の票を持つ形で、人気と実力と人間性のバランスが平等に判断されるシステムとして大きな話題を集めた。しかしもちろん番組に映る分量は平等ではないため「運営の推し」はとうぜんのようにSNSで噂される。レンを除くメンバーは全員「運営に推されていない」とされ「分量」が少ない参加者だった。
それでもリュウは視聴者票でほとんどトップ層に食い込んでいたのに、主宰の評で下位に落ち込み落選した。
番組では明かされなかったがファンの間では常識となっていたリュウの生い立ち。それは事故で両親を同時に亡くしたレンとある部分では近いが、実態はおおきく異なる。悪徳企業で鬱病をわずらいながらも休職させてもらえなかったリュウの父親は首を吊った。母親はその後、会社に忍び込み当時の上司を刺して捕まった。刺した相手は一命をとりとめたが、母親は執行猶予がつきそのまま精神科病院に入院した。総従業員数十名の小さな会社であったため、当時大きなニュースとなりその会社は倒産した。
リュウと十季のきょうだいにとって、問題なのはその後であった。当時七歳だったリュウと、まだ三歳だった十季ではその認識に差があるが、リュウは両親を亡くしたあと親戚筋から明確に“選ばれなかった”感覚を持ち続けていた。数ヶ月の間、親戚のだれがきょうだいを引き取るかで一族は揉め、その空気感はリュウにははっきり伝わった。
結果ふたりを引き取った叔父は優しく、経済的にも充分な環境を与えられダンスも習わせてくれた。だから感謝している。それでも独身の叔父に自分の恋愛や仕事があるときは、ふたりは当たり前に“選ばれなかった”。なにかあったらまず優先してもらえないという自覚が強固にあった。それでも恵まれていることにつねに感謝しつづけなければならず、まず毎日のように叔父に礼を言いながらリュウは育った。
「ボーカルは未経験だけど……できないと思ってる人を、いつか見返してやりたい、そんな強い気持ちで頑張ります!」
番組で明るく言ったリュウのその台詞は炎上した。だが炎上すればするほど、リュウへの投票は増していった。それなのに。
「あの時主宰に落とされた。その判断を間違いだったって、ぜってえ見返してやる」
リュウには番組そのものへの憎悪がある。大人たちの金儲けのために集められて、委縮しているところに恫喝まがいのことを言われて泣いている参加者を愛でる。あるいは純粋に参加者全員に幸せになってほしくて応援してくれている視聴者。気持ちもさまざまにお金を落としてくれるファンたちに、感謝もしているが、どうじに憎んでもいる。
リュウの心に巣食うその昏(くら)い気持ちをいちはやく見抜いたのが、主宰の小松だった。
「リュウは踊りは正直うまい。この中で断トツうまいかもしれない。だけど、みんな本気でリュウのことを応援してる。ハッピーになってもらいたいと思ってる。そのことを心の本当のところではリュウはわかってないよ。これはエンターテインメントなんだ。リュウはある種、芸術肌なんだと思う。学究派といっていいかもしれない。だけど、エンターテインメントではそこを割り切らないと、どこかで通用しなくなるよ。この際はっきりいうけど。おれらが元気を与える対象の多くはマジョリティ相手になってしまうんだよ。だから、なんていっていいか、言い方がむずかしいな……。リュウは、はっきりそこへの愛と信頼が足りないと思う。だから今回は苦渋の決断で落とす。けど、オレのことは恨んでくれていい。だけどこれから、そのことを真剣に考えてほしい」
それはどこか、視聴者に向けての言葉だったように思う。この後プロデューサーが大炎上した。リュウは炎上とともにのし上がり、炎上とともに“選ばれなかった”。
落選が決まったあとで、リュウはメンバーを罵倒した。
「お前らがちゃんと努力しないから、おれたちは……」
そうして胸ぐらを摑むシーンの動画は番組至上最悪の修羅場としていまだにTikTokなどに落ちている。だからこれでも、さいきんのリュウは「丸くなった」といわれ、リーダーとしての生長を子を見守るような思いで見つめる年長のファンが多い。
しかし実際、あのときメンバーを罵倒したリュウがもっとも罵倒したかったのは自分自身だったから、審査終了後の本番中に合宿所を抜け出してカメラから映らないところへ走った。涙が汗とともに横に流れた。パフォーマンス後の疲弊した自分の肌が冷え切っていくのが分かる。あれは冬の軽井沢で行われた合宿審査での出来事だった。
がむしゃらに逃げた。なにから? スマホも没収されていたため、帰り道が分からなくなったリュウは我にかえると途方に暮れた。
その肩を叩く人物がいた。
「え……なんでここに?」
そこにいたのはヤスだった。
「それはこっちの台詞やで。今日四次審査やなかった自分?」
ヤスは三次で落選しており、聞けばすこし周辺を観光して今日大阪へ帰る予定だったのだという。
「こんななんもないとこ観光だなんて、酔狂だな」
「いや、せっかく皆と仲ようなれたんに終わってしもて。感傷にひたってたんや。リュウはどないしたん?」
「べつに」
しかしヤスは気まずそうな様子を欠片(かけら)も見せず、リュウが座る横、なにもない公道のアスファルトに腰を下ろした。
「安心しいや。ぼくこっから合宿所への帰り道分かるから。分かりやすいとこまでつれてったるさかい」
「や、べつに……」
しかし内心きわめてほっとしていた、リュウは「ありがとう」の代わりに冷え切った身体で、「どうして……。どうしてできないのに努力しないんだ? どうしてみんなありのままの自分でいられるんだ? おれは一ミリでも上達できなかった日は頭がパンパンになってうまく寝つけないんだ。あれを練習すればよかった、あそこの筋肉を鍛えればよかったんじゃないかって、後悔ばかりでぐるぐるして。どうしてみんな……」と言った。
「リュウもありのままでええんよ。ぐるぐるして、努力しつづけないと倒れてまう。みんなをアッと見返したい。そのままでええ。さいわい、身体も柔かいし、免疫とかも強そうやしな。でもほんまはリュウこそが、自分のそういう部分を人に押しつけてまうところ、いやなんやろ?」
「……」
リュウは黙った。それを認めてしまえば自分は自分でなくなる。ヤスがポケットをまさぐり、「これ、餞別」といってガチャガチャで手に入れたヘビのキーホルダーを渡した。
「これは……! 『爬虫類サンクス』関西地区限定の微妙に斑紋の違うヤマカガシさん関西ヴァージョンじゃんか!」
リュウは爬虫類が好きだった。皮膚がつめたい生き物しか愛せないのだ。
「せやで。リュウとおそろやったのなんとなく気づいてたけど、ぼくほんまはそんなに『爬虫類サンクス』好きちゃうねん。やから、もしかしたらリュウのほうが大切にしてくれるんちゃうかなおもて」
「ありがとう! ヤス! これメルカリとかでもすぐ売り切れだしそもそも転売しかないし、うわ、めっちゃうれしいわ」
キーホルダーをリュウに手渡すヤスの手が冷え切っていたことを、リュウはよく覚えている。
「やからな。できないやつのありのままでいる感じも、ちょっとは愛せるようになるとええな。ま、どっちにせよ人は簡単には変われんのやから、無理せんことや。じゃ、そろそろいっしょに合宿所かえろか。皆心配しとるで。安心せえ、だれも怒ってへんよ。リュウはだれより努力しとるし、ちゃんとスターになれる人間や。たとえ性根が捻じ曲がっとってもな、ぼくはそんなリュウのこと愛しとるで。やから一つだけ忠告しとくけど、いまは嘘でも仲間とハグして謝るんや。君には次がある。ぼくはカメラに映っちゃあかん人間やから、てきとうなとこでアプリでタク拾うけどな」
リュウの渇ききらない目尻の涙をすくうヤスのつめたい指。リュウはヤスの言う通りに合宿所に戻ると皆に「ごめん、今までついてきてくれて、ありがとう、いっしょにいてくれて、ありがとう。ほんとにごめん」といってハグすると自然に涙があふれた。リュウの涙は美しかった。だからこのときの印象を忘れられないファンたちが初期エコブラをメインで支えることになった。
リュウはエコブラ結成を企てたとき、けしてダンスやラップボーカルの実力ではなんら見るべきところのないヤスをまずメンバーに入れることをすでに決めていた。
*
「アリス、うめえじゃん!」
三人でもう一度最初から振りを確認しているときに、アリスの動きをチラチラ見ていたリュウは思わず感嘆し声を上げた。
「や、昨日ふたりが話してるの聞いてたから、家でコッソリ自主練して……」
「まじか! おまえー!」
リュウはアリスをハグした。汗だくのうなじからかすかにレザー系の香水が匂った。
アリスは見ていられなかったのだ。リュウがレンを酷使してしまい、休養を与えなかったせいでレンは壊れた。これはいくつもある史実のいち側面だ。だがエコブラの解散後にリュウはそのことで一生自分を責め続ける。
だがそれがきっかけで主宰が言うようにリュウは「真剣に考え」て、良心的でやさしいダンサー兼指導者として、大きく羽ばたくことにもなるのだ。結果、いま懸念している十季の大学進学の費用を捻出することも充分にできる。だから未来は変えられないのは自明のことであるとともに、リュウに関しては変えないほうが良かったりもするのだ。レンも解散を機にしっかり休養をとってから韓国へ渡り、練習生として数年過ごしたあとで再デビューする。
はっきりいって、エコブラのメンバーは解散したことでその時こそそれぞれに大きな傷を負うが、その後の人生はよりよい方向へ進む人間が多い。それはシンイチやサトシでさえそうだった。
そういった意味ではエコブラはあらかじめ呪われたグループである。だからアリスとキルトはエコブラを選んだ。まるで「推す」ような気持ちで、自分たちがそっと参入したところでなにかメンバーの幸不幸に大きく関与することはできないが、どうしても彼らの「夢」に参加したくて、自分たちの金銭と時間を託すように過去へと渡ってオーディションに参加した。
キルトはそのことをしっかり割り切っている。
「おれたちはただメンバーの夢を間借りさせてもらってるだけなんだから、しゃしゃり出んな」
だがタイの地で「Three-Body」の高音パートをアリスに、代わるよう提案したのもキルトだった。帰国してからもなぜだかアリスは「なぜそんなことした?」とキルトに聞くことはできず、フィジカルAIの算出としてもナイーブコミュニケーションの判定が出ていたために控えた。
キルトは今日、予定通りメンバーのきょうだいたちと趣味のスイーツめぐりをしていて、その出しなにアリスがリュウとレンの自主練に参加しに行くというと、「へー! めずらし」としか言わなかった。
だけど、あの提案からすこし、未来がズレ始めているのはキルトも分かっているはずだった。たとえば今日、リュウの提案でレンを誘い自主練をすることは、ほんらいはレコードされていない史実で、きちんと過去管理局からの警告がきた。だから比較的ログを読まずにこの時代へ来たキルトでさえ、今日が予定された今日とは違うことは知っている。それでもまだ大きな過去改変に繋がるものではないと判断されているために自動メッセージにとどまっているが、いつ本局に目をつけられるかは分からない。
娯楽に飢えたアリスら未来人にとって、政治家こそがもっとも、ある程度の過去改変はいたしかたないとあまく見ているところがある。過去人の運命を変えること、それが未来人の数少ないエンタメになっていること、どちらにせよどこか暗黙の了解で見逃されている。
これは大きい社会問題だし、研究者の共通見解としては過去トラベル資格取得の試験を厳しくすべきという意見が口に出すまでもない常識だったが、過去トラベル業態に大きなスポンサーがついている現状、いちどガバガバにした権利を再度厳しくすることは難しい、資本主義時代の名残がまだまだあった。七十年後のスポンサーはほとんどが匿名の一個人なのだが、厄介なことに資本主義時代にノスタルジーを持つ陰謀論者にほぼほぼ統一され、そして政治家もほとんどがおなじ人種であることがこの問題をややこしくしていた。
アリキルも未来ではほとんど絶滅した「アイドル」という暴力的な装置の、それこそ暴力性にこそ目を輝かせ、過去にきたクチだから咎人(とがびと)の自覚はあった。やっぱ「おもしろい」ってなんてインモラルで暴力的で「おもしろい」んだろう。だけど、それも変わり始めている。「アイドル」という過去の遺産たちの、アリキルが舐めていた覚悟や翻弄される運命をじっさいに目の当たりにして。グループ全体としてもメンバー個人の人生としても、この時代特有の加速する資本主義に人権や身体が丸ごと振り回されるようすをみて。
だけどそれは「アイドル」じゃなくてもみんなそうだった。
「レン、膝。冷やしな」
アリスは持ってきた保冷剤を叩き割り、レンに差し出した。
「耳も。音楽を聴きつづけるだけでも喉を傷めるらしいから、耳栓あるし」
「ありがとう。アリス、ワイは大丈夫だから。もういっかいしよ、通し練」
しかしレンは壊れはじめている。声と動きをアリスの身体アシストに投影して解析した結果、レンにある痛みはこの時代の八割の人間が鎮痛剤を飲む選択をするものだった。そして熱発もある。
「アリスなんか最近、めっちゃママ感強くなってるね。これプラメに書かなきゃな」
「やめて」
つまりレンはアリスに優しくされたことを、ファンに送るプライベートメールに書いて報告すべきかな、という意のことを言った。アリスはそれを即時で分かる自分に、すっかりおれも“過去人”みたいだな、とふと思った。
思いやりすらもまるで“過去人”の非効率で、見当外れのそれなのかもな。
「レンはマインドが時代すぎる。いずれほんとうに体を傷めるぞ」
「なんそれ?」
ほんとうにはこの令和にしても「時代遅れだ」ということを言いたかった。だけどAIで語彙修正をかける気持ちの余裕がなく、思ったままに口にしたアリスの言葉。
レンはふと、バンコクから帰国してそれぞれの家に帰る道中で、ともに京成の特急に乗っていたサトシに「なあ、アリスとキルトのこと、どう思う?」と聞かれた日のことを思い出した。
「どうって?」
「いや、なんかアリキルってちょっとおれらともノリが違うからさ。レンはどう思ってんのかなってちょっと気になって」
「うん? サトシくん珍しいね、人のことをそんな風に気にするなんて。アリくんには今回歌を支えてもらって申し訳なかったけどさ」
「あー。気をつけろよ。いろいろな。あ、もうすぐ日暮里か。じゃ、おれはここで」
「え、うん」
あれはどういう意味だったろう? だけどレンは本心では、自分の歌唱パートはだれにも奪われたくなかった。だって、どれもレンが歌うべきレンの思想が曲、詩、コレオ全体として楽曲を作るクリエイターチームのそれぞれと混ざりあう身体として、歌い踊るべく割り振られたパートなんだから。
それはたとえ喉を潰してもだ。
「アリス。こないだはごめん。バンコクで。でも、もう二度とあんなことにはならないから、安心して」
アリスは黙った。しかしレンは、あのときのアリスの声は異質でまるで自分を凌駕するような、圧倒的パワーがあった、だから、まるでレンの身体ごと代わりに歌ってくれたみたいで、あまり悔しくなかった。アリスにはレンとまた違った才能がある。だけど、それでも、パートを奪われたくはない、というより“代わられるべきではない”、これは世界の理みたいにあらかじめ決まっていることだからだ。
リュウはアリスとレンが休憩しているあいだ、ミニアルバム収録曲のダンスブレイクのコレオを作っていた。汗をとばし息を張り詰めて、疲労でフルには動けない身体を酷使して創造性に集中する。本当は座り込みたいのを無理に動かして、ゆっくりと音楽に導かれるようにあたらしい動きをこの世に生み出そうとする意志の身体。それは他人にはどうあってもいたわれない。
世界からの厚意を拒む、これがエコブラと「ハッコウ」の共通点であり、そして絆だ。
*
アリキルから未来人宣言を受けたサトシは、バンコクから帰った翌日、一睡もできないまま撮影に向かった。YouTubeでもTikTokでもオフショット撮影でもすべて引き攣(つ)った表情でそこにいたサトシに「ハッコウ」の面々は
…… わが推し今日も病んでてカワイイ
…… ワシも布団から出られんくてこれ見てる
…… サトシの病み顔にしか癒されない疲れがあるわ
…… 温泉旅行券を贈りてえ
などなどのコメントで盛り上がる。
不自然になりすぎないようにアリキルから積極的にサトシへ近づき、手を繋いだり恣意的でない範囲でそれぞれの推しケミへのサービスになるよう適度なスキンシップを図ったが、背後からハグされたとてサトシは自称チャームポイントである「ヘヘ……」という暗い笑いでお茶を濁す。それにしてもアリキルからはいつもよく分からないいい匂いがする。ヘアスプレーや香水のたぐいとも微妙にちがう、これも未来のあたらしいテクノロジーかなにかなのだろうか……サトシは頭がぐるぐるし思考がパンクしていた。
いつものようにギスギスしがちの撮影現場で、手作り縁日遊びにいそしみ水風船の作成に苦戦していても、これまでは大事なところで沈黙を埋めてきたサトシ本来の役割をこなせず、キルトとシンイチがガチ喧嘩一歩手前の言い争いに発展した際も(綿菓子の色を何種類にするかという論点で)、ぼうっと黙っていたサトシ以外にうまく「まあまあ」の空気にまで持っていける人材がなく、撮れ高の問題と動画の流れからそのまま使うしかなかった。
おおかたはスルーされていたが
…… キルさすがにワガママすぎじゃね?
…… シンイチってやっぱ大人げないよね
といったコメントもいくつかついてしまった。メンバー同士がはんぶん本気でケンカするというのは毎回の撮影に欠かせないノリだったのだが、この日のことでサトシがちゃんとしていないとしっかり険悪な空気になってしまうことがよく分かった。
テレビ出演の打ち合わせや販促用コンテンツ撮影などの個人仕事がなく、他のメンバーよりやや早くオフショット撮影を終えたところで、サトシは社長のヤスのもとへ行き、「ちょっと相談があるんやけど」と告げた。
手作り縁日動画をニコニコ眺めていたあとで皆にひと声かけ、みずから片づけにいそしんでいた社長のヤスは元メンバーで、体力不足ゆえに結成初期の多忙スケジュールや練習についていくことができず脱退した。そこから一念発起してエコブラをマネジメントするための会社「キャッツクレイドル」を立ち上げ、さまざまなコンプライアンス研修や経営者ミーティングなどに参加していまではいくつかのTikTokerやYouTuberのマネジメントにも関わりつつエコブラをメインで売っている。多忙なインフルエンサーの案件仲介や動画編集で稼ぎつつ、自らのつてでエコブラのマネージャーである伊佐木真希を雇い何人かの将来有望なトレーニーをヘッドハンティングしいまにいたるのだから、元々頭の回りがよく経営者に向いていたのだろうヤスは、この会社随一の「陽」のオーラを纏っていた。
いつかのリュウに聞いたところ、ヤスをエコブラに誘った理由もそもそも「あいつは目端が利くから」ということだった。けっしてダンスやラップボーカルに長けたところはないが、そこにいるだけで全員がまとまる、そんな人間が世の中にはいるものだ。自分を消して場のために尽くせる人間。そのうえで頭の回転がよく気の使える人間。
スキルも体力もないが、しかしだからこそ、エコブラが結成された当初は皆を励まして、スポンサーや取引先にも積極的に話しかけて場を明るくできる精神的支柱だったから、ヤス個人のファンこそ少なかったけれど、その抜けた穴は大きかった。現にヤスが脱退して結成直後という「確変」を終えたエコブラは、新曲をリリースする「カムバ」のごとにじわじわと反響がなくなっていき、それはさまざまなSNSでのインプレッションやチケット、グッズの売り上げやファンクラブの加入者数に如実に表れた。
しかしその下がりっぱなりだったすべてが、バンコクでのフェスをきっかけにジワジワと上昇しはじめている。
「どないしたんサトシ。相談?」
「うん。今日このあとって時間ある?」
「や、実はむずいねん。このあとストレス系美容TikTokerのスジトリちゃんから相談があるって、マネージャーと三人でサムギョプサルたべいくから」
「あ、そうなん。そんならええわ。またこんど……」
「明日は? 自分らオフやろ? サトシまた寝れてないんちゃう? 右瞼んとこピクピクしとるもん。明日はもう予定ある?
急にごめんな」
「いやこっちこそ。明日は空いてるけど。それこそ休養にあてようと思っててん」
「せやったらヘッドスパ予約しとくわ。そのあと茶でもしながら話さへん?」
「え、いやそういうんじゃなく……」
「ええからええから。じゃ十六時に表参道で待ち合わせしよか」
サトシとヤスは会社内でふたりだけ関西出身なので、お互いがいる場でだけはコテコテであった。
つづく
町屋良平「発光する、ら」は『Quick Japan』最新号にて連載中!