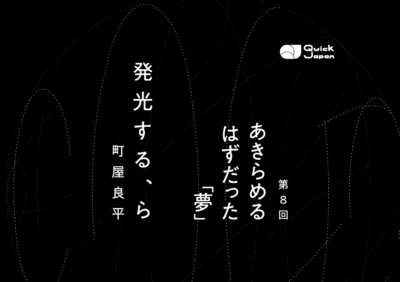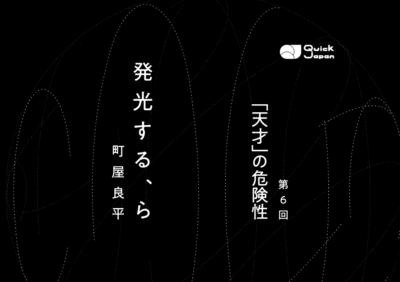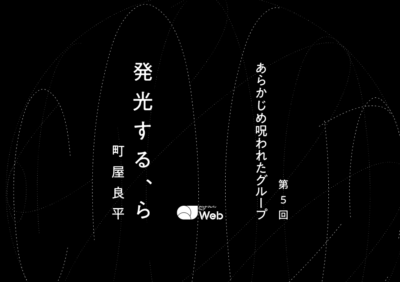メンバー間の仲も険悪、鳴かず飛ばずの6人組の弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。七十年後の世界からやってきた双子のアリスとキルトは、未来では禁忌とされた「夢」を追いかけてアイドルとして活動している。
メインボーカル・レンの喉の不調など大きなトラブルに見舞われたバンコクでのフェス出演を終え、帰国の途についたエコブラのメンバーたち。束の間の休息期間、キルトは、エコブラのメンバーのシンイチの妹、リュウの弟、レンの姉らとスイーツを食べに出かけるが……。
前回までの連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
第2回 個性恐怖症
第3回 夢の功罪
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
朱里(あかり) シンイチの妹。キルト、咲世、十季の四人で定期的にスイーツ巡りをしている。兄のことはまったく尊敬していない。
咲世(さきよ) レンの姉。早くに両親を亡くし、ひとりでレンを育てる。シスコンぎみのレンに若干引いている。
十季(とわき) リュウの弟。兄のことはわりと慕っている。キルト曰く「リュウよりビジュがいい」らしい。
第4回 被害者たちのスイーツ
2
シンイチがキャリーバッグの持ち手を摑む反対の手で家のチャイムを押すと、「なによ」と言いながら中から妹の朱里(あかり)がドアを開けた。
「ただいまー」
「ただいまー、じゃないんだよ。鍵持ってんでしょ」
「荷物が多くて、取り出すのが面倒だった」
「甘えてんじゃねえよ」
中から母親も現れ、「あらお帰り、あらーなんか韓国の匂いがするわぁ」と言いながら、キャリーの足を拭くための雑巾を用意した。
「てか韓国じゃねえから。タイだから」
「あらそうなの? なんか食べる? チャーハンなら温めればすぐだけど」
「食う」
シンイチは母子家庭に育った。とくに十三歳のころまでは母親に慢性的な鬱症状があり収入も不安定だったため、ややネグレクト、あるいは虐待に近いところがあった。しかし知り合いにデパート販売員の仕事を紹介されてからは母子関係も安定している。
朱里はその時期父親と同居していたため、貧しかったころの険しい母親のことをあまり覚えていないが、シンイチはよく覚えている。三食菓子パンで学校へ行っていた、あのころに出来たニキビ跡を直すためにずいぶん無理して美容医療に通っていた。スキンケアについてもアイドルを志してから熱心に勉強し、だからいま美容担当として単独のラジオ仕事や雑誌、テレビに呼ばれることもある。
「朱里は? 炒飯要る?」
「要らなーい。てか、アニーなんかお土産とかねえの?」
「あ、キャリー夜までに二階上げとくから、いまはここ置いといて。土産などねえわ。年に何回海外行ってると思ってんだよ。金いくらあっても足りねえわ」
「ケチくせえな。タイは一年ぶりでしょ。レンくんなんかお姉ちゃんにエルメスのピアス買ってあげてたのに」
「え?」
たしかに、スワンナプーム国際空港でチェックインしたあとの空き時間に、レンとキルトが伊佐木マネとどこかへ買い物に行ったのはうすうす知っていた。まさかそのときに免税店でエルメスを? そんな高給を貰っているはずもないのに。だがメンバーのなかでレンだけ単発のドラマ仕事があったり、作曲した楽曲が他グループのミニアルバムに収録されるなど、突出した個人収入があるのは当然というか分かっていたにしても、「なんで? なんで朱里が知ってんのそんなこと。SNSにそんな怖い情報出回ってる?」
「いや、キルくんから聞いた」
「は? キルト? なんで? なんでキルト?」
「キルくんとレンくんのお姉ちゃんと私と十季(とわき)くんで定期的に流行のスイーツを食べに行くグループLINE作ってるから、それで聞いた」
「十季ってだれ?」
「リュウの弟」
「え? え? え? なんでそんな仲良いの?」
「べつにいいでしょ。キルくんは甘いモノ好きだし、いろいろメンバーの家族同士で情報交換して盛り上がってるだけ。グループ名も“エコブラ被害者の会スイーツ”っていうの。てかいまだに実家に寄生してるのはお前だけだけどな」
たしかにレンは両親を早くに亡くし、姉の収入で高校まで行っていた。だから「お姉ちゃんに、ワイを、育てて、くれてありがとう、いままで苦労ばっかり、かけて、ゴメンね、って言いた……」まで言って感極まり泣き崩れているのを、オーディションの二次選考を通過したときのカメラにバッチリ抜かれていた。
シンイチも「母親に、いままですっごい苦労をかけて……感謝を伝えたくて、ウー」と嘘泣きしたがそれは本編ではカットされYouTube行きになっていた。嘘泣きはバレる、ということをシンイチはその時に学んだし、SNSやコメント欄でもシンイチの涙の嘘っぽさが「萎える」「むしろ推せる」の二派に分かれ喧々諤々(けんけんがくがく)の議論となった。
「といっても、最近はエコブラもかなり忙しくなってきたらしくて、マリトッツォを食べに行ってからもう半年ぐらい行ってないかな」
「半年前のマリトッツォってすでに遅れてるだろ」
TikTokでバズっているダンス動画を見ながらシンイチは言った。そこに母親が「はいはいお待たせー」と言いながら炒飯を持ってテーブルに置き、ラップを剥いた。
「夜は? こんな中途半端な時間に食べてどうするの?」
「これから仮眠したあとで予約してた皮膚科行って整体行くから、夜は食わないで平気」
ニキビと美白とシミシワ対策として皮膚科で二種のレーザーをあててもらい、ドクターズコスメを補充したあとでタイの公演でバキバキになった全身を整体で解(ほぐ)し、夜はサプリと甘酒と豆乳と卵を混ぜたチャイを飲むだけで胃腸を休める予定だった。シンイチはマリトッツォなど食べたらたちまちニキビが出来るし太る。幼少期の食生活が壊滅的だったこともそれに起因しており、だから他のメンバーより徹底した栄養管理とスキンケアで自分の自由にできる金は少なく、ましてエルメスなど手が出ようはずもなかった。
タイ二日目にフォーメーション確認を提案して断られ、カオマンガイを食べに行くといった時のキルトの顔を思い出す。だんだんとムカムカしながら炒飯を口に運び動画を眺めていると、「もしかしていまさらそれ踊るの?」と朱里がたずねた。
「そうだけど」
「おっそ。それもう二ヶ月以上まえに流行った振りでしょ。なんでエコブラっていつもやることなすこと遅れてるの?」
「うるさ。いいだろ別に。流行遅れ、それすら愛おしいだろ。流行りに乗れない鈍感さも魅力だねって、そう言われてるの。マーケティングなの。わざとなの」
「は? 盲目のファンに甘やかされて、ダサイだけなのに、まったくやんなるわ」
もともとシンイチはボーカル志望でオーディションに参加した。振りの覚えはキルトと並んで遅いほうで、この程度の振りなら当日に入れてパッと踊れてしまうレンやサトシやリュウに迷惑をかけすぎないよう、せめて観るだけでも予習しておかなければ、メンバーの時間を奪うことになってしまうからいま確認していた。
明日はアリスとレンとそれぞれペアを組んで二本ずつの動画をまとめ撮りするので、二人とも人にダンスを教えるのが比較的うまく優しいだけにまだ気が楽だった。キルトは身についたコレオなら人に教えられるが覚えがシンイチ以上に遅いし、リュウは振り付けも担当しているくせに典型的な天才肌で、踊りを人に教えることができない。「なんで二回も見てもできないの?」とか平気で言う。だからその二人と踊るときはいまだに緊張する。しかし、「シンアリ」や「サトシン」「シンイレン」よりも、はるかに「シンキル」「リュウシン」派のファンのほうが多いのだったから、ファンはちょっと萎縮したシンイチのほうが愛せる。
「てか、レンくん本当はお姉ちゃんとふたりで暮らしたいのに、怖ファンが家のピンポンを押して手紙を渡して来たりするから、一人暮らしにさせられて不安だって言ってるのに、お兄といったら。二十三歳でぜんぜん実家を出ていこうともしないで」
「おれがいなきゃこの家は不安だろ」
「心にもないことを。マジで学校とかでもレアなシンイチ推しに執拗にお昼誘われたり、手紙渡されたりしてマジで怖いんだけど」
「推しの手紙? くれよ。返事書くから」
「お母さんが燃やしたよ」
「よく燃えるのよー」
母親が笑いながら言った。
「やっぱ情念がこもってるからかしらね」
シンイチは引いた。
「あのー……こう見えてファンは大事にするタイプなので、次からは燃やさないでください」
そして炒飯の皿を流しに戻して水につけ、メイクと日焼け止めを落としてからシャワーを浴びて自室のベッドに潜りこみ、引きつづきダンス動画を見ながら二時間だけ寝た。
*
「そう。本音としては売りたい。けどさすがに思いとどまった」
レンの姉である咲世(さきよ)が言うと、朱里は「わかる」、キルトは「オモロ」、十季は「うそ」とそれぞれ言った。
二十分ほど並んで入った店内のそこここで、スマホのシャッターを切る音が鳴っていた。
四人はそれぞれの飲み物と、まったく同じ四つのケーキ(切り株を模したガトーショコラの上にクマのスポンジケーキが乗った、最近よくTikTokやInstagramで流れてくるそれ)の写真を思い思いに撮り、フォークを入れた。
“匂わせ”ととられないよう、ようするに少ないながらも一応有名税の納付義務のあるキルトは投稿しないが、他の面子も念のため各々が他にそこにいた人間の痕跡を消した写真を撮り、時系列とアリバイを切り貼りして各自のSNSに載せる。現代SNSのマナーはタイムトラベラーのマナーにどこか似ているとキルトは内心おもった。
「レンのセンスってけっこう、言うてアレだからね。アレ」
キルトはガトーショコラに乗っているクマちゃんの、顔はカワイイのにやけにパティシエの腕によってリアリズムの技法の駆使された臨場感のある毛並みが表現されている首をざっくりフォークでいきながら、そう言った。
「うれしいはうれしいよ。でもまだまだ生活費にも窮しているのにエルメスって」
「それだけ姉を愛してるってことなんだろうけどね、レンは」
「けどねー」
咲世、十季、朱里はそこで口を揃える。
「重いよねー」
レンはエルメスの免税店で、「どれがねえちゃんに似合いそうかな?」と言ってキルトに咲世の写真を見せた。あまり慣れていないコミュニケーションだったためになんと応えてよいか分からずAIによる情緒検索をかけた結果、「きれいなお姉さんだね」という応答がサジェストされた。
……初見のご家族の見た目をいきなり褒めるとか。大丈夫か……?
「きれいなお姉さんだね」
半ば賭けに出るつもりでサジェスト通りの台詞を言うと、果してレンは「キルありがと」と言った。キルトは、なんかこの遠征でレンはメンバーのとくにアリスと自分に心をひらくようになったな、と思った。
「レンも稼ぐようになったし、夜の仕事のほうは辞めようかなって思ってたとこだから、うれしいけど、複雑」
咲世は高校を卒業した五年前から昼は営業職、夜はバー店員として働いており忙しい。それもレンの学費とデビューのためのレッスン費を稼ぐためだった。
「レンはねー、さいきんは作詞作曲もするでしょ。繊細で人との距離感がよく分かってない典型的なボーカルタイプの人間ね。ビジュも人気が高いし、あれで緊張癖がなければ確実に本家のグループにいけたのにな。性格だっておれらのなかじゃ例外的に素晴らしいし」
キルトが言うと、咲世が「たしかに、膝と喉の調子を同時に悪くしたりしてメンタルダウンしたときに自分でも言ってたわ。『ワイは本番に弱いからこれから先もきっとなにをやってもダメだー』って」とレンを真似て言う。
「さすが姉、似てる。でも、レンくんの圧倒的にハイパフォなのに自信なさげなニュアンスって、あんまり他にいないからすごい強みだと思うよ」
十季は朱里の台詞を聞いて、自身の兄であるリュウのことを考えていた。
リュウはダンススキルにおいてはグループいち高いのだが、勉強ができず運動でアイデンティティを築いてきた人間特有のフワフワした俺様気質があり、自信がないできない人間の気持ちが分からない。
リュウがリーダーになったのはそのダンススキルと振り付けの腕あってのことだが、事務所側としてはもう少しできない側の気持ちを慮(おもんぱか)れる人間になるよう、期待されているからだ。だがいまのところその期待に応えられてはいない。ダンスの上手い人間は往々にしてダンスのできない人間の気持ちを分かろうともしない傾向がある。それは悪意あってのことではなく、見たばかりの動きをまったく真似できないということが真剣に分からないからである。
しかしそれを分かってしまうとダンサーとしてのパフォーマンスは変わってしまう。外界の光を吸い取って自分が輝くような身体から減退してしまう。踊りというのはときに考える前に出来てしまう動きがもっとも魅力的であったりもする。だからそれはある意味いいダンサーである証左でもあった。
「……兄貴が、リュウがレンの自信を奪ってるんじゃないかなあ」
十季がつぶやくと、キルトは「それはあるな」とはっきり言い、朱里と咲世は口だけの「そんなことない」を言う羽目になった。「レンは踊りも上手いのに、自己流だからリュウみたいな基礎のきれいなダンスを見ると、ちょっと萎縮しちゃうんだよな。リュウがうまいことレンに基礎を教えてやりゃいいのに」
「教えてないの?」
「教えてるけど、先生のほうが教えるの上手いから。リュウはリュウでダンサーっぽくないタイプの振りに課題があるし、人のことにかまってられないほど努力してるってのが実情かな」
「たしかに、レンは『リュウは優しいのに怖い。パンダみたい』ってよく言ってるわ」
咲世が言った。
「どゆこと?」
朱里が疑問を呈する。
「パンダってかわいいのに狂暴でしょ。そういうことじゃない? しらんけど」
「たしかにリュウの顔ってパンダっちゃパンダよね。色白でアイメイク映えるからかな」
「レンはね、緊張しいなんだけど、音楽があるところでは自信に満ちた表情するでしょ? ステージ映えするっていうか。だけどねー、なにかしら試されてる場面ではそれがマイナスになるんだよね。その落差にたぶん、当時オーディションを見ていた人たちも驚いただろうね。ボイストレーナーの檄(げき)で追い込まれた末に委縮して、泣きながらレッスン場で転がりまわったシーンは有名だからね」
キルトが最後のひとくちの熊の足を頬張りつつ、言った。
「あれね。号泣芋虫」
「いやでも目に焼き付いてる」
「トレーナーも一瞬怒り役を忘れて、引いちゃってたもんね」
「そんでそのあと、『あんたたちもやりなさい! メインボーカルの孤独を知りなさい!』とか言って、それでそんときのグループメンバーの六人全員がもらい泣きしながらレッスン室でゴロゴロと転がるっていう地獄絵図が放送されてたよね。いまではあれ、YouTubeとかインライとかでメンバーもよく真似してるけど。ウケるから」
「レンもめっちゃ笑ってるしね。そう考えると派生グループとしてでも、ほんとデビューできてよかったわ」
「いちばんはね、レンってやっぱ才能は凄いけど、存在とか性格としてはすごくマンネ(韓国語でいうところの末っ子)らしいマンネだし、レンがリラックスして楽しそうにしてくれていれば、おれらもリラックスするんだけどね。そこまでうまくもってける人徳と実力を兼ね備えた人間がいないんだよね。やっぱこういうのっていくら優しい人間がついてても、実力が尊敬できるメンバー同士じゃなきゃ究極気持ち分かってあげらんない」
「レンくんもアリスには比較的、懐いてるんじゃない?」
「うーん、アリスは見かけ優しいけど、まあ基本他人と距離感があるし、なにより、やっぱボーカリストとしての格が違うからねえ。シンイチもレンにはライバル心あるっぽいから、それをうまく信頼にもってけたら、レンも多少安心するんじゃないかなあ」
「アイツには無理」
朱里が言った。
「自分のことしか考えられないタイプだから。一昨日も私とお母さんがマジでファンに脅かされてるのまったく、分かってなかったし。そのくせ自分が空港でファンに追い回されるのとかはいまだに愚痴すごいからね」
「まあシンイチも典型的なボーカリストだよね。そういう意味では。でも昨日はYouTubeのバラエティ企画とTikTokまとめ撮りで一日中籠(こも)り仕事だったんだけど、肌艶的にも身体的にも疲れを見せずにやっていて、プロ意識高いなって思ったよ。何回かはムカついたけどね。油っぽい弁当の具を当然おれが食べるものとして寄越したり、自分がよく映ってるカットをサムネに採用するよう伊佐木マネに粘って交渉してた。ちくわ天はありがたく食べたけど」
「食べたんだ。ねえ、声、だいじょぶ?」
十季はそれとなく周囲に見られていないか気にかけつつ言った。キルトの声のボリュームがしぜん上がっていたからだ。
メンバーのきょうだいたちとキルトの仲が良いことは、ファンにもある程度認知されていることといえ、明らかにあまり内容を聞かれない方がいい会話をしている。バンコクでのパフォーマンスが話題になってからテレビなどでも少しずつ露出が増え、認知が上がっている現状にまだメンバーも会社のスタッフもついていけていない。
「あそっか。ありがとね」
そして面々は一気に声のボリュームを落とす。それでも話は尽きなかった。
「てか、アイツは自分磨きに命と金はかけてるからね。家族にエルメスなんてうちに関してはありえない話」
「まあレンは最年少の割にそのへん無頓着でめっちゃ日焼けしたりもしてるから、そういう意味ではシンイチくんを見習ったほうがいいと思うよ」
「でもレンが地黒なのはギャップあってすごくファンにも評判いいよ。そこを活かしてファッション的にも異彩を放ってるしね。一説では色白一択から一転、自然な色のブームきてるともいうし」
「中高で陸上やってたからね。お金ないから」
「それがたぶんあの肺活量とハイトーンボイスに繋がってるけど、独学によるあの個性的な声質とボーカルレッスンで教わることとをうまく両立させられなくて、喉を傷めやすいんだよね」
「キルくんはめっちゃ色白いけど、レチノールとか使ってるの? アルくんもだけど」
「レチノール?」
十季に問われたキルトはすかさずスマホで検索した。過去語彙辞典によるとレチノールとはこの時代で大流行した美容成分で、ターンオーバーを活性化してシミシワ対策に効果的とのこと。だが敏感肌には刺激があるため代替成分としてバクチオールがある。こういうときに、この時代の常識的な語彙なのか、はたまた過去人の間でも知る人ぞ知るワードなのかとっさに判断できないと、リアクションを間違えてしまうことがあるからすぐに検索するようにしている。
「いやこれは保湿と日焼け止めを兼ねた下地だけ。おれ肌が疲労しやすいから。けど子どものころからおれら日焼け止めを塗る習慣があったから、たぶんそのせい」
アリスとキルトの生まれた七十年後には生まれた直後から日焼け止めを塗る習慣が徹底されている。それが常識となったのはその二十年前に日光浴不足によって欠乏しやすいビタミンDの生成を疎外しない日焼け止めの技術が発見され、それからはむしろ赤ちゃんにもシャワーミストを塗布する技術で日焼け止めの徹底を行う習慣がついたせいだ。調べによるとこの時代の日本人の約八割に不足しているといわれているビタミンDは、筋肉増強にも欠かせない栄養素ということでそれからは男性や小児の日焼け止め使用率が大幅に上がった。よって七十年後に日焼けする人間は一部のファッションとして褐色を取り入れている者以外ほぼいない。
「うらやまー。おれも小学生から日焼け止め塗るべきだったよな」
十季が言った。
「でも毎回思うけど十季くんって、なにげお兄さんのリュウよりビジュいいよね」
キルトが言う。十季はよろこび、「ありがとうー。キルめっちゃ好き!」と抱きつくが、たとえビジュやらなんやらが良かったとしてもアイドルやらボーイズガールズグループとして生きる人生など絶対にごめん、それが「アイドル」を家族に持つ十季、朱里、咲世の確固たる共通見解としてある。
十季はリュウとふたりで食事に行った帰りに、二人組のファンに顔をさされていっしょに写真を撮るなど丁寧に対応した後で、なぜかリュウの一人で暮らす部屋ではなく十季の親戚と住む家の方についてこられたことがあった。そのことはリュウには言っていない。
「あーあ、アイツ、マジ引っ越さねえかなあ」
朱里が言った。キルトはエコブラが一年後に解散するまでシンイチの給料が手取り十八万を超すことはなく、ゆえに絶対に実家は出ない、ということを知っていたが「それな」と話を合わせた。
「マジ、『アイドル』様とかって、人の人生狂わせてそれを幸せってことにしてて、なんかすごい。ずっと家にいたあの新一が、「シンイチ」になった途端、なんか……、ていうか新一ってはっきり言ってどっちか言うとモテないほうだったし。でもいまや『ビジュ担当』とか言われて、下手し人気上位だったりして、まったく信じらんない」
「そうなんだ……でも兄貴は、いまやリュウは、闇が深いってとこが売りになっていて。番組側すら伏せていた両親の情報を、SNSでかんたんに調べ上げられてから、そこからの熱狂的なファンがついたから、あんなの絶対無理。ありもしない不幸まで動画サイトで『創作』されたりして、それがかなり信じられたあげく、さらに過激な『創作』が信じられていって、もう無限だよね。いまではリュウの右足の甲にケロイドがあるのは、親がおれにお湯をかけようとしたのを庇ったからだっていう人がいて……。いや、まあそれに近いことはあったにせよ、足の火傷は型落ちの古い冷蔵庫の下にリュウが子どものころ、足を突っ込んで火傷しちゃっただけなんだけどな。それを、おれを助けたからとか言ってるひと見ると、なんか未知の気分? どういう気持ちになっていいかわかんなくて……、これって傷ついてんの?って、それすら分かんない」
十季が言うと、キルトはボーイズグループの習慣からマンネにするような仕草で頭をポンポン叩き、背中をさすった。
つづく
町屋良平「発光する、ら」は『Quick Japan』最新号にて連載中!