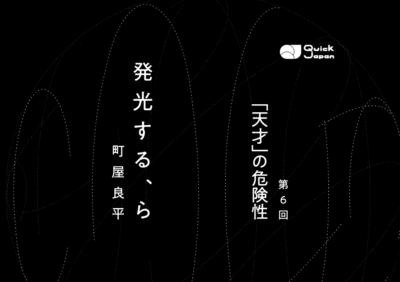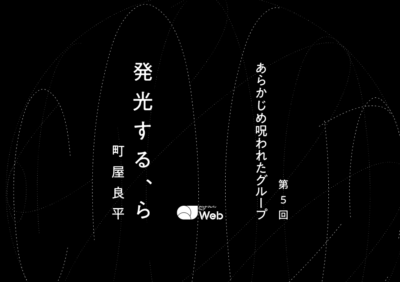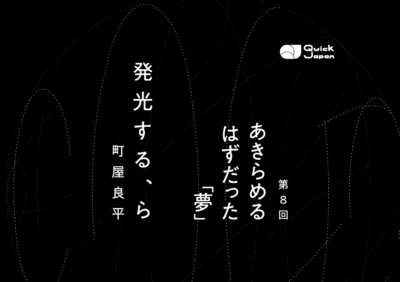弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」のアリスとキルトには、仲間に明かしていない秘密があった。それは、彼らが七十年後の未来からやってきたということ。8koBrightsのバンコクでのフェス出演のさなかにボーカル・レンの喉の不調が発覚し、キルトはアリスが代わりに歌うことを提案するが……。
前回までの連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
第2回 個性恐怖症
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
第3回 夢の功罪
ホテルの七階に戻り、キルトとアリスがふたりで三日滞在するツインルームのドアを閉めたところで、アリスは「おまえ、マジでやりたい放題だな」といつもより強い語気で言い放った。
「AIシステムの助けなしで、この時代のレトロなダンス&ボーカルグループに憧れておれらここまで頑張ってきたのに。台無しにするつもりか?」
めずらしく本気で怒っているアリスの迫力に気押されたキルトは「ご、ごめん……」と謝る。
「謝って済むなら警察は要らない、とやら、なんとやらなのだが」
「そうだよな。アリスはおれと違って、この時代の「個性」にノスタルジーや憧れがあるわけじゃないのに、ソロをさせようとしたのは、わるかったよ」
「違う。歴史を変えたらダメなんだ。お前はなにもわかってない」
「それは分かってる。分かってるからこそだ」
「じゃあ、お前は自分のせいで歴史が変わって、それで免許が失効してこの時代にいられなくなってもいいって思ってんのか?」
「違う。ただおれは、明日のことを気にせずに、いまに全力で向き合いたいんだ。未来ではそうできなかったことを、過去で果たしたいんだよ」
「その結果、明日にでも強制送還されても構わないのか?」
「構わないよ。「夢」が犯罪になってしまった未来に戻って、たんたんと生きるよ。だってそうじゃなきゃ、そもそも過去にきた意味がおれら、ないだろう?」
「夢」は未来では軽犯罪だった。ゆえに、AIシステムの助力もあってとくに若い世代で殺人や病死や事故や自殺が減り、健康に長生きできる社会が実現された。
「夢」は健康に悪い。時代が進むにつれ睡眠時間の減少がますます社会問題化し、加速するプライバシーの侵害や、あらゆる娯楽と労働の低年齢化が進み、それとなく一般層から「夢悪説」が流行しはじめ、それを政府が採用してしまった形だ。
だからこそ、表向きはそうでなくても、実際には「夢」を求めて過去へ行こうとする若者への批判も根強い。タイムトラベル免許も現在の十二歳以上から二十五歳以上へと、厳格な年齢制限を課すべきとする意見も多かった。AI政治家の計算より、むしろ生身体(きしんたい)を持つ政治家にその傾向が強い。AI側はむしろ「夢」という罪を犯した人間がそれ以降に未来ではほとんど嗜好されなくなっているアルコールや薬物依存に陥り、自死に至るケースが少しながらあるという問題のほうをより重視し、「夢」の禁を犯してからの更生に注力すべきという立場が多いようだった。「夢」から醒めたあとに、「夢」抜けして現実を生きる「夢なし」セーフティネットがもっと要るというサジェストである。
「理解できない」
言葉とは裏腹に、アリスは気づいていた。キルトは「夢」を満喫したいんじゃない。「夢」を長く楽しみたいのなら、あんな提案はしないはずだ。
キルトはきちんと「いま」を生きるこの時代の人間として、レンを救いたい。
「いや……もう寝ろ。どうせ明日にならないとなんもできん」
キルトは黙って風呂を溜めに行った。窓を全開にすると、生ぬるい風とともに入りこむ、かぐわしい匂いがする。これは過去臭とも言われるが、土地のスパイスや生物の体臭入り混じる、まったき自然の匂いだ。あらゆるものが除菌脱臭されている未来の没個性的な空気でなく、ありのままここにある歴史の繋がった土地の匂い。きっと、この中には「夢」の匂いもたぶんに含まれているのだろう。アリスはそう思った。
おれたち、この風を浴びにきた。
アリスがシャワーを浴びて戻ると、すでにキルトは睡眠アシストの恩恵も受けずに眠っていた。アリスは頭の中がごちゃごちゃしてい、ここのところ毎日そうしているように思考と交感神経のゼロ状態をアシストされようやく眠りにつくことができた。
「夢」はまず眠りに悪いのだった。
*
アクシデントは半ば予測されていた。
最終日の本番。レンは朝集合するなり、「みんな心配かけてゴメン。喉、治ったっぽい。伊佐木ちゃんのくれた漢方が利いた」と言った。それを証明するように、基本流して動作確認するリハの最後に、『Three-Body』の綺麗なブリッジを披露した。
「よかった! でも無理すんなよ。昨日までだって、本調子のボーカルってワケじゃなかったろ」
シンイチが言い、しかし内心メンバーの全員がホッとしていた。アリキルを除いて。
レンは嘘を吐いている。喉の調子は昨夜のままだ。踊りながら五曲を披露してリハと同じ高音を披露するコンディションではまったくない。
そうした意味で伊佐木を含めたメンバーは全員がまだまだプロ意識に欠けていた。そう思いたかっただけなのだ。いつもみたいに、レンの才能を信じて乗り切ってくれるはずだと楽観的に。
案の上本番がはじまると『Three-Body』まで持たないどころかより悪い状態に陥った。あからさまに声は掠れてい、それをカバーするようにより無理してがなり、喉を潰すような歌唱法に頼った。何事もなかったかのようにパフォーマンスは続いたが、むしろレンとアリキルを除いた他メンバーに動揺が伝わり、歌詞が飛んだり、しっかりマイクに声を乗せられていなかったり、一目でわかる振りの間違いまで発生したりと、ボロボロになっていった。
アリスとキルトはこの事態を知っていた。昨夜の時点で運命チャットに質問しておいたので、リハ後にはレンの声がまったく回復していないことを知っていたのだが、それを他のメンバーやスタッフに伝えるわけにはいかなかった。伝えたところで、その不自然な状況に警戒されるだけで、なにも改善されはしないだろうとチャットにも書いてあった。
すでにタイムトラベラ―であることを知られているサトシにだけは知らせるべきかとわずかに話し合ったが、それもやめておくべきだとキルトが言った。「Three-Body」におけるサトシの歌割りはそう多くなく、レンのボーカルをカバーできる力があるわけではないため、かえって動揺を誘うだけだろうと、キルトのほうが終始冷静だった。
そして六人はそれぞれになんとなしの不安を抱えたまま本番に入ったのだ。
「We are 8koBrights、発光する、ら!」
本番前に気合いを入れ、このときばかりは普段近づきたくもないメンバーと力強くハグを交わし、いきおい持ち上げたり、握りつぶさん勢いで握手したり、メンバーにしか分からない方法でメンバーにしか分からないナーバスをほぐす。
もともとは「We are 8koBrights、発光するお、れ、ら!」だった掛け声が、レンが一人称の「おれ」を一瞬言い淀み「発光する……ら!」と省略した。それがその場にいた全員に受け、のちにファンにも受けて定着した。マンネ(韓国語でいうところの末っ子)であるレンの一人称が「ワイ」であるのは有名である。結成当初の勢いのある時期とはいえ、メンバーとスタッフの心がひとつになって笑いあえた貴重な、宝物のような時間だった。
もはや六人は、自分たちの勢いが落ちているから雰囲気が悪いのか、自分たちの雰囲気が悪いから勢いが落ちているのか、それすらごっちゃになってしまっている。
*
三日目でずいぶんこの奥行の狭いステージにも慣れた。
六人の自我が一つにまとまるような不安のなか、「Three-Body」の音源が流れ始めたとき。
イントロはいつもどこか怖い。これから歌声だけが入っていない音源を完成させる。そのためだけにあるこの六個の身体だと、六人であることの怖さと心強さが入り混じる。
世界にあるべき足りないピースを、毎回、その場その場で埋めていく。それこそがLIVEシステムであり、この恐怖と快感が麻薬みたいで、レンは生パフォーマンスにこだわった。大人や社会に試されるようなオーディションで、ことごとく自分の力が発揮できなかったからこそ、自分の味方である「ハッコウ」たちの前では世界を構築するなまの臨場感を共有したい。ただたんにそのことが気持ちいいから。
だけど、歌えない。どこか予想していた、当然のように出ない高音に、身体がよりこわばり普段だったら風邪を引いていても出せる音域すらままならない。
しかしここへきて、レンの声の不調を補うように、「Three-Body」の音源のなかでだけ強く連帯するメンバーのパフォーマンスがひかった。
レンの不調によってはじめて、発揮される五人の強気のパフォーマンスで、「Three-Body」の世界観をなんとか作ってゆく。キルトは余裕をもって踊りながら、アリスにつねにつよく身体で訴えた。
「お前が歌え」
アリスはそれを充分に分かって、しかし応えるつもりはなかった。いつもより抗生物質を多めに飲んでいたとはいえ、不調を覆い隠すようなシンイチの個性がアリスの吐気を促す。
レンは声の調子が出ず、持ち前のメンタルの弱さが発動し泣きそうになっていることがわかった。
すべての面においてメンバー全員を上回る能力を持っているとはいえ、まだレンは十九歳なのだった。
このままだと、落ちサビの最後はほぼ無音になるだろう。冷静にアリスは分析した。
でもまあ、べつに、いいだろう。
どうせ、エコブラの一員でいる時間も、そう長くない。
必死にサビのクオリティを支えている、レンの声を拾うように聞く。アリス自身も参加しているが、レンの声がなければこの曲はこれほどたよりない。
いつもレンが人一倍、あのイントロの不安に立ち向かっているんだと気づく。「Three-Body」の重厚さを、リュウがダンスのニュアンスをいつもより微妙に強めることで、なんとか支えているが、まるでハリボテだと思う。レンの声がなければ、「Three-Body」の重厚感なんてむしろ自分たちが押しつぶされるための装置のようなものだ。
怖い。アリスはゾッとした。いざラストへ向かうブリッジに入った途端、その世界の頼りなさはまるで、はじめてタイムスリップした日に、キルトを待った。あの数秒間のようで。だけどその一瞬だけ、たしかに吐気がなくなり、フワッと身体が軽くなるようなあの感覚は、なんだったろう。
未来ではけっして味わえない。
あれは、まるでいにしえに言われる〝全能感〟みたいな。
「光の刺さらない心で 残酷な夢をおれら永遠に 追い求めるよ」
その、追い求める「よ」でいきなりハネ上がるCから引き摺るようにさらに上がっていく、D#の高音。アリスは急き立てられるように、自分の意志ではない自動機械のようにしぜんに、「追い求める「よ」」をレンの声にかぶせて、歌った。
レンの高音がすぼんでいくその範囲の「よ」一音のみをカバーするように響く、C音から引き摺らずに、ほぼ一息にD#まで出す。アリスのプレーンな高音が、これまでにはありえない声量で、会場を沸かせた。何故だろう。アリスはダンス&ボーカルにおいて原理的反個性論者で、自分たちのいまの状況にマッチしたこの歌詞に感情移入して歌うことは信念に反する行為だった。だけどここは未来ではない“いま”で、自分たちは束の間過去を旅する未来人だけど。
だけど、エコブラのメンバーとしてステージに立つその時間だけは、未来人じゃない。
音楽が鳴っているときだけは。
ただの六人のなかのひとり、音楽をつくるに欠かせないピースに徹するんだって。
それがおれの使命というか。
生まれてきた意味だろ?って。
思っちゃったなーー
だけど身体がついていかない。そこからいきおいラスサビまでを歌い上げ、アウトロを踊るために後ろを向いた瞬間に、アリスは吐いた。その嘔吐を予測していたキルトがアリスを抱きかかえるようにして、衣装に仕込んでいたエチケット袋でアリスの吐瀉(としゃ)物を受け取って六人の後方に隠し、立ち位置を入れ替えてアリスをセンターのリュウに被さる位置へと促したからお客さんにはほぼバレなかった。アリスが吐いたことをメンバーは分かったが、だれの衣装もステージも汚さなかった。しかししっかり動画に撮っていた「ハッコウ」たちに公開・検証された結果、キルトの見事な手際も含めて「#アイドルなのにゲロ」「#だがステージは汚さないアイドルの鑑」といった不本意な形でバズることになる。
低く重くひびくバスドラムが畳みかける、音楽が止むとアリスは青白い顔で客席に向かい、笑った。
ステージ裏で汗だくのレンが、「アリス! マジでありがとう! 身体は、大丈夫? ほんと、ワイだけの声ではまったく大事故になるところで……、」と言って声が詰まり、そして泣いた。
「結果、強がって、騙すことになって、ごめんなさい。ワイ、ほんとはすごく不安だった。声、出ないんじゃないかってほんとは分かってた。けど、どうしても「できる」って自分を誤魔化して、みんなも自分も騙して……」
アリスはきわめて動揺したまま、「いや、おれは……ほんとは……、もっとレンを助けてやらなきゃいけない……だけど、いや、ちゃんとそういうのはレンはメンバーに言わなきゃだめだ」と、息を切らしながら言った。
「だけどおれの実力不足で、いつもカバーしてもやれない。申し訳ない。さっきのはたまたま。やっぱりもう、きょうと同じことは二度とできないよ。ほんと喉を、大事にして」
「うん。わかった! ありがとう!」
シンイチにも「やるじゃん」と言われ両手グータッチを促されて、その仕草のくささと古さにアリスは再び吐き気を催したがしかし、なんとか笑顔で応じた。
リュウにはバシバシ背中を叩かれ、「おまえー! できるじゃねえか」と言われた。
そしてキルトと目が合い、アリスは小声で言った。
「おまえ、分かってたのか? おれが、レンの代わりに歌って、そして、吐くって」
「まあ、いいじゃん。結果オーライよ」
「いいわけねえだろ」
ひとり暗い顔で、それを聞いていた、というか聞きにきたサトシが言った。
「おまえら、ちょっと来い」
そしてアリキルの腕を引っ張り、ステージに隣接するセントラルワールドモール内の人気のない一角まで連れ込んだ。
「知ってたのか?」と言った。「レンの喉が回復していないって。分かってたのか?」
「分かってたよ。けど、その話あとにしてくんない? アリスは体調が悪いんだよ」
キルトが応えた。たしかにアリスは青い顔をしている。冷房に晒された腕がきわめて冷たい。アリスの身体AIが自律神経系アラートを出し、強制仮眠をサジェストした。それを却下し、アリスは「ごめん、けど、おれにもキルトにも、あれ以外できることはなかった。いまは休ませてほしい。ごめん」と言った。
言いながら、「サトシには「友愛の橙(だいだい」がマジで覿面(てきめん)に効いたんだな」とアリスは思った。こんなにかんたんにおれらが未来人であることを信じるとは……。子どもの玩具みたいなもんかと思っていたが捨てたもんじゃないなと再評価するとどうじに、サトシが極めて「友愛」に飢えた個体であることもよく分かった。
「できること、あるだろ! 少なくともおれは、知らせてほしかった。力にはなれないとしても……。なあ、おれたち、うまく人に頼れない、人を信頼できない、そんなメンバーの集まりだけど、だけど」
「それ過去人の典型的なロジックだね。そんなことをいま話してなんになる? サトシのいまのそれはじこまんぞ……」
「なんだてめえ」
サトシはキルトの衣装の胸ぐらをつかみ、言われかけた「自己満足」をキャンセルした。
「いや、申し訳ない。サトシにはおれらの正体を知られている以上、相談すべきだったと思う。けど、ほんとに時間も、余裕も、なかったんだ」
「そうだぞ自己満野郎」
誤魔化そうとしたアリスの言葉を無下にするように、キルトの物言いはさらに悪辣を極めた。
「いい加減にしろよ。相談してほしいっていう、おれら現代人のこの気持ちが未来では自己満足だっていうのか?」
「おお。でもべつに未来だからってワケじゃないぞ。現代の価値観でもサトシのその気持ちは自己満足の仲良しごっこだっておれは思うな。レンにしたって、もっと早くパートを減らす相談をすべきだったんだ。鍼(はり)治療やこの時代程度の医学的ケアだけじゃなんともならないところに来てるって、本人は分かっていたはずなのに。たしかにレンの声なしじゃエコブラは立ち行かないよ。だからこそ、もっと頑張らない努力をすべきだろ。才能があるんだから。おれみたいに才能がないやつは頑張るしかないけど、才能がある人間はときには頑張らない努力をすべきだろ! 同じことをやってもな、才能あるやつは身体にかかる負担が凡人とは段違いなんだよ。自明のことだ。だから未来では才能判定で高い数字が出た人間は、対象の競技や表現ジャンルにおいては、すぐにAIアシストがついて自己満足的な努力を強制的にストップさせてるの。才能が開花しなかったケースのリスクヘッジも兼ねているけど、なによりそうしたほうが才能開花しやすくもあるんだよ。はっきりいって、レンはそういうレベルのダンス&ボーカリストだよ。あーあ、なんで過去人はこう、非合理的で間抜けなのかな。まったくついてけないわ、そういうとこ」
胸ぐらを掴まれながらもキルトは饒舌にまくしたてた。
「マジ意味わからんけど、とりあえず殴りてえ」
だが、キルトがそこまで分かってダンスもボーカルも人一倍努力しているということに、サトシは複雑なおもいを抱きはじめてもいた。才能がないことに向き合いそこまでして、過去に来てこの時代のダンス&ボーカルにこだわる。 才能がないからこそ努力でき、どれほど努力をしても才能に遠く及ばない。キルトはそのことを完全に理解したうえで日々を精一杯生きている。そのことへの畏怖が、しかしなぜかいま殴りたさにもつながっていて、混乱した。目の前の身体はよく訓練された均整のとれたバランスでそこに在って、目尻に向かってゆるやかに吊り上がる目が自分を睨みつける、そのまなざしが強い。複雑でぐちゃぐちゃなメンタルに陥ったサトシは泣きかける。
「なんなんだよ。マジで、ここ数日、お前らが未来から来たって、強制的に信じさせられたみたいにへんな感覚で情緒ぐちゃぐちゃで、なおかつ、レンも調子悪くて、おれら、ようやくこれからってときに、なんでこんなボロボロなんだよ……」
「ごめん、そうだな、サトシにとったら、」
そこで再び嘔吐感を覚えたが、もう吐くものが胃の中に残っていなかった、アリスの体調が限界を迎えようとしていた。キルトは自分の混乱にアリスを巻き込むサトシの態度に怒りを抑えられない。
「あのなあ。はっきり言うけど。エコブラはあと一年で解散するんだよ。レンの身体が限界を迎えて、それに合わせて空中分解すんだ。そしておれたちはその史実に関与できないの。だから、アリスはレンのボーカルを代わることを躊躇(ためら)ったんだよ。おれたちはその未来を変えてしまったら未来に強制送還されるし」
「は?」
サトシはキルトの発言に動揺したが、それは言っているキルト本人にとっても同じだった。発言の強さに比して声が震えていき、未来人らしからぬ過去人への感情移入に身体が動揺した、これで双子ともども身体アラートがかかった。アンガーマネジメント物質の注入もサジェストされた、しかしそのすべてを振り切って、キルトは発言を続けた。
「その瞬間、おれとアリスはお前たちの記憶からも消え去るの。つまり、エコブラが一年後に解散しなかったり、もっとはやく解散してしまったりしても、免許失効とともに、メンバーの記憶からおれらいなくなるよ。おれらのタイムトラベル免許は二年で切れるし、そういう意味でエコブラは丁度よかった。お前らの「夢」の挫折をおれら、利用しにきた。それは申し訳ないけどな。人から忘れられるのはおれら慣れてる。けどなあ、いくら未来人っていったって、哀しいって感情に慣れることはないんだぞ」
アリスはふたりに聞こえるか聞こえないかの小さな、無個性な声で歌った。「光の刺さらない心で 残酷な夢をおれら永遠に 追い求めるよ」。絞った声でもまるで張り上げる声質と変わらず、プレーンにそこまでの高音が出せるのかと、動揺した心でサトシはしずかに感動した。
つづく
町屋良平「発光する、ら」は『Quick Japan』最新号にて連載中!