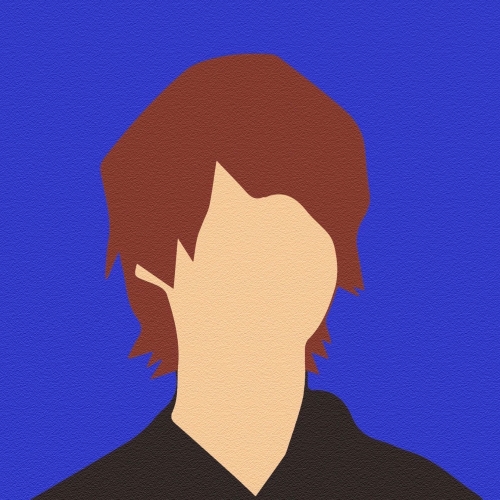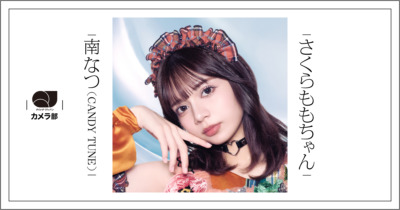構成作家・河谷忍による連載「おわらい稼業」。ダイヤモンド、ケビンス、真空ジェシカら若手芸人とともにライブシーンで奮闘する、令和のお笑い青春譚。
WEB連載の第1回は、出演者と同じ熱量で「おもしろい」を追求する河谷が、「おもしろい」を意識し始めた原体験を綴る。
忘れられない尿の記憶
私は、物心がついてから小便を三尿、漏らしたことがある。
一尿目は2、3歳時分の寝小便で、真冬なのに起きると股間まわりに妙な温もりを感じた。体を起こすと布団が濡れていて変な匂いがしたので、ははん、これはたしかに尿だなと思った。母親がテレビ欄以外は読みもしないのに購読を続けていた新聞をくしゃっと丸めては布団に押し当てる。そのたびに「ええ加減にしいや」とこちらをにらんできた。私は乾いた下着に足を通しながら「乾いてるってこんなにいいんだ」と思った。
第二尿目は4、5歳のころの出来事だが、こちらは放尿時からあと始末まで何ひとつ覚えていない。朝になって目を覚ますと母親がいきなり私を一発ビンタしたことで、「私は昨晩何かいけないことをしたのだ」と悟った。聞くところによると私は尿意で目覚めて、起きがけに寝ぼけて台所をトイレだと勘違いしたらしい。洗い場の下の戸棚を丁寧に両開きして、フライパンやら土鍋やらが入っているそこに勢いよく放尿したのだ。もちろんたこ焼き機も入っていた。
家族は慌てて私をそこから引き剥がすが尿(とき)すでに射出(おそ)し。すべてを出し終えて満足げにそのまま床に就く私を尻目に全員で大掃除となったようだ。過去に親戚のおじさんが寝ぼけて押し入れに小便をした話を何度も何度も聞いてきたのでそんな人間にはなりたくないと思っていたのに、わりと早い段階で似たようなことをしてしまったのが悔しくてその日の朝食はヨーグルトだけにした。はちみつをかけた。うちは母子家庭だった。
初めての勝利
もう一尿は忘れもしない、6歳の保育園での出来事だった。毎日のレクリエーションの最後に必ず“そのとき最も姿勢よく座れていた人の選んだ絵本を先生が読み聞かせてくれる時間”があった。私は特に読んでほしい絵本があったわけではないが、そこで選ばれることが園児にとって一種のステータスのようになっていたので、選ばれたいがためにうんと姿勢よく座っていた。目に涙が溜まるほどの力を込めて膝を抱き、背筋を伸ばす。このときはまだ尿意などからっきりなかった。これがまた不思議なのである。
「今日は忍くんやな」
選ばれた。私は勝ち取ったのだ。今日、この中で最も姿勢よく座れていた園児は紛れもなく私だった。思えば「競争」という概念が私の中に芽生えたのもここからかもしれない。すぐに機嫌が悪くなる姉に何かあっては一方的に殴られ続けてきたこの私が、ずっと争うことが苦手だったこの私が、唯一参加していた競争がこの「座り姿勢で勝ち取れ!絵本読み聞かせバトル!」だったのだ。ディズニーランドでアトラクションの行列に並ぶ人たちを悠々と抜き去っていくファストパス勢のように、ほかの園児の前を横切り本棚へと向かう。みんなの視線を浴びながら歩く私はパリコレのランウェイにでも立ったかのように肩で風を切る。
本棚から適当な一冊を選び、先生に手渡した。正直本なんてなんでもよかった。この中で一番を勝ち取ることだけが目標だった私にとって、これからの時間はなんの意味も持たない。
「はい、じゃあ今から読んでいくね」
適当に選んだ本なのに、そのタイトルは今でも忘れない。私が先生に渡した絵本は『はしる』というタイトルの絵本だった。先生は表紙のページをめくり、私たちに読み聞かせ始めた。そこにはデフォルメされた人間が、ただ走っているだけの絵が描かれていた。
「からだと、じめんについているあしが、まっすぐになるように、こしはひかないようにしましょう」
「こしをひいては、ただしいしせいとはいえません」
先生がページをめくると、そこには全身がピンク色で臓器丸出しのおぞましい姿をしながら走っている人間が描かれていた。全員がひいっと体をうしろに逸らす。宮崎駿が幼いころに弟と映画館のうしろに立って『ゴジラ』を観たとき、「初めてゴジラが山の奥から現れるシーンで観客がひいっとうしろにのけぞったのが波のようになって自分のもとにやってきた」と言っていた。と、岡田斗司夫が言っていた。それみたいだった。
「きんにくだけではありません、からだのいろいろなきかんが、はげしくはたらくのです」
その場がとんでもない空気になっていくのがわかった。前回読み聞かされた絵本は、くまさんと少女が一緒にクッキーを焼くかわいらしいものだった。その前は少年がドラゴンと大冒険をするファンタジーな絵本。そして今回は、臓器丸出し男が笑顔で走るイラストに筋肉や臓器の解説が描かれた、絵本というより「書物」だった。
「だから、はやくまっすぐはしるには、からだをつよく、からだをやわらかくしなければなりません」
何度ページをめくっても、走っている人間のイラストしか出てこない。文章は科学的に証明された「正しい」ことばかりで、かわいらしさやファンタジーは一切ない。我々に走ることの楽しさや正しく走る方法などをひたすらに教えてくれた。
私以外の園児たちが徐々に先生の音読を聞くのをやめていく。自分が選んだ絵本からみんなが興味を失っていくのがはっきりとわかった。それは臓器丸出しの人間なんかよりもおぞましい光景だった。やめてくれ、もう読まないでくれ。
「つまんない」
はっきり聞こえた。誰かがはっきり言ったのだ。はっきり言うなよ、と思った。
漆黒の翼が生えた悪魔の登場
気がつくと私はとんでもない尿意に襲われていたのだ。理由はよくわからない。思えば姿勢よく座っていたときは文字どおり、今日1位の「座」を勝ち取るために必死になっていたので、尿意にまで気が回らなかったのかもしれない。ひとつ目標を達成した瞬間、すべての意識が膀胱へと向かっていった。ただ、私は絶対にトイレに行くことができなかった。いや、トイレに行くなんて許されなかったのだ。
私の意思で選んだ本を読み聞かせてとんでもない空気になっている最中に、それを選んだ張本人がとんずらなんて許された行為ではないのである。次第に聞くことをやめていく園児たちの中で、私だけは責任を持って最後まで楽しまなければならないとその場にい続けた。この空気をどうにかしたい気持ちと尿意とが合わさって本当に早く終わってくれと願い続けていた。
「みんなは走るとき、こんなふうにちゃんと手を振ってるかな?」
先生がアドリブを入れてきた。おそらく先生も展開のない内容と園児たちのあまりの反応の薄さに焦りを感じていたのかもしれない。これを選んでしまった私の責任にならないよう必死にがんばってくれている。だが先生、今それはありがた迷惑になってしまっているのだ。私を含めここにいる全員が早く終わってほしいと願っている。この状況でのあなたのがんばりは誰の得にもならないのである。私は祈り続けた。早く終わってくれ。そして膀胱よ、耐えてくれ。
遊戯室の外に目をやると、女性の園長先生が大きな眼鏡の奥に優しい皺を作ってうしろ手を組み、にこやかな表情でこちらを見ていた。いつもなら温もりを感じるその表情も、この瞬間は悪魔のように思えた。
「さて、いつまで耐えられるかな」
そんな声が聞こえた気がした。園長の背後に紫色のオーラが立ち込め始める。初老の背中に漆黒の翼が生えると、舞い上がる数百の羽根が束となりこちらに襲いかかってくる。眼鏡の奥の瞳が赤く充血し始めると、大きな口を開けて鋭い牙を光らせた。なるほど、先生が急にアドリブを効かせたのはこの園長のせいではないか。園長が見ている手前、自分の読み聞かせに園児たちが食いついていない姿を見せるわけにはいかない。あの先生、全然好かれてないわねえ、といろんな先生に相談されてしまう。正真正銘、園長は大ボスであり今の私にとっては悪魔だったのだ。
「はい、おわりです」
絵本が終わった。ようやく終わった。一生続くのではないかと感じた長くつらい戦いに私は勝利したのだ。栄光のファンファーレが頭の中で響き渡ると、私はトイレに駆け込もうと立ち上がった。この絵本のおかげで走り方はマスターしている。最も早いスピードでトイレまで行くのだ。これは最初から私のために仕組まれた勝利への道筋だったのだ!
すると先生が言った。
「終わりなんですが、ちょっと今日はもう1冊読もうか」
その瞬間、私の膀胱のゲートが開いた。てっきり栄光を讃えるものだと思っていたファンファーレは、出走の合図だったのだ。各馬一斉に膀胱から飛び出すと、コーナーも何もない直線を駆け抜けそのままゴールした。ゆっくりと下着が温かくなっていき、それは着々と下着からズボンへ染みていった。今思うとそれは、春の訪れに似ていた。
勝ったと思い込んでいたこの勝負、私は鼻差で負けてしまった。ふともう一度外に目をやるが、そこに園長はいなかった。私は勘違いしていた。勝負に勝つ人間はすぐに姿を消すのだ。園長のように。それを私はなんだ、勝ち誇ったようにみんなの前を歩き、肩で風を切っていた。あの瞬間から私は負けていたのだ。
あの絵本を選んだから…
そのあとに読まれた絵本の内容はまるで覚えていない。きっと私が選んだあの本よりかは、いい意味でみんなの印象に残っていることだろう。読み聞かせの会が終わり、私が立ち上がると水分を含んで色の変わった洋服を見た先生が「どうしてそんなに濡れているの?」と聞いてきた。酷な話である。あなた方がこうしたのではないかと思いながら何も言えず、ゆっくりと先生に近づくと、先生は私のズボンと下着を引っ張って中を確認してきた。
「着替えてきなさい」
私はその日から、猫背になった。
みんなの前で漏らしてしまったことが嫌だったのではない。
先生に怒られたのが嫌だったのではない。
勝負に負けたのが嫌だったのではない。
あの絵本『はしる』はきっと素晴らしい絵本だった。
走ることの楽しさやおもしろさを図解しながら教えてくれる素敵な本なのに、私があの状況でたまたまあの本を手に取ってしまったばっかりに、私を含め数人にはトラウマ級の思い出を植えつけることになってしまった。結果、そのおもしろさがすべて伝わらないうちに「つまらない」認定されてしまったのだ。あの絵本そのものと、あの絵本を選んだ私に対して。
私が「おもしろい」を意識し始めたのは間違いなくこのころからだった。おもしろくなりたいのではない。「つまらない」と思われたくなかったのだ。この考え方は今でも変わっていない。おもしろいことをしたいというより、おもしろくないことをしたくない。だから必然的におもしろいことをしなければならない。そんなことばかりを考えながら、恥の多い生涯を送ってきました。
関連記事
-
-
4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ
Last Prince:PR