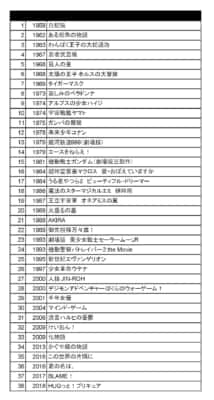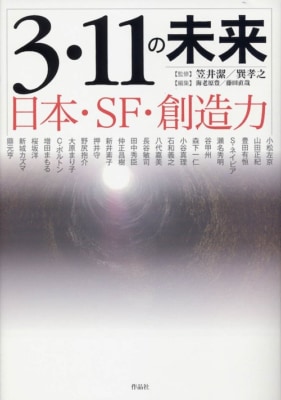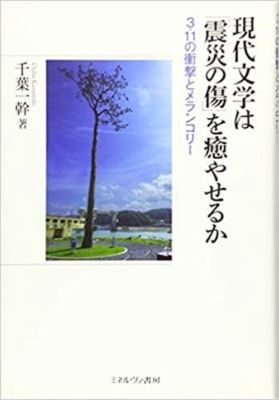新海誠の3年ぶりの新作『すずめの戸締まり』は、11月11日の公開以来、『君の名は。』『天気の子』の興行記録を塗り替える勢いで大ヒット上映中。アニメ評論家・藤津亮太は、東日本大震災を描く文芸の系譜の中で考察、『すずめの戸締まり』を震災文学として位置づける(ネタバレを含みます)。
ありきたりな発想を裏切る『すずめの戸締まり』
アニメではしばしば「そこにいない人の声が聞こえる」というシーンが描かれる。「不在者の声」が聞こえる(ような気がする)というのは、フィクションにおけるひとつのロマンといっていい。
「あなたの声が聞こえてほしい」「私の声が届けばいいのに」という、私たちの素朴な願い。それをロマンチックにも具現化してみせたのが「不在者の声」なのだ。物語の中で、死者の声が響いたり、具体的に生前の姿のままで現れるのも、この「不在者の声」を求めるロマンの延長線上にある。
『すずめの戸締まり』は、その点で非常に禁欲的な作品だ。「不在者の声」が登場してもそれはロマンの反映ではないし、登場するであろうと思われていた、主人公すずめの母(椿芽)の“幽霊”も登場しない。
本作は後半、日本神話のイザナギが黄泉の国のイザナミに会いに行くエピソードを彷彿とさせる展開となる。となればすずめが幼いころ東日本大震災で亡くなった母が、“幽霊”として登場し、それと対面することですずめの喪の作業が完成する──という展開が想定されるのも無理からぬことだろう。しかし本作はそういうありきたりな発想をスッパリと裏切ってみせる。
すずめは、東北の故郷(映像から推察するに岩手県南部の沿岸部ではなかろうか)で被災後、宮崎県の叔母に引き取られ、そこで成長した高校生。すずめは「閉じ師」という不思議な稼業の青年・宗像草太と出会い、ネコの姿で逃げ出した「要石」を追って日本を縦断することになる。草太は「要石」のネコ(のちにダイジンと呼ばれる)によって、すずめの母の形見である子供用の椅子(3本脚)の姿にされてしまっており、すずめと椅子の奇妙なロードムービーが繰り広げられる。ふたりは宮崎につづき、愛媛と兵庫(神戸)で、開いてしまった「後ろ戸」を閉じて、それぞれの土地を災厄から守る。後ろ戸とは、常世につながり、そこからミミズと呼ばれる災厄を呼び込む扉で、「閉じ師」はそれを閉じるのが仕事なのだ。
しかし中盤で訪れた東京で、草太は逃げてしまった要石の代わりとして、地震を防ぐ人柱として、常世に閉じ込められてしまう。じわじわと要石化していく草太。すずめは常世に赴き草太を救うため、子供のころ一度くぐったことがある東北の故郷にあるはずの後ろ戸を探して北上するのである。この道行きはまるで黄泉の国を目指した旅のようである。
『想像ラジオ』を補助線に
『すずめの戸締まり』を見終わって、東日本大震災を取り扱ったアニメや小説、評論などにいくつか目を通した。その中で、発売以来の再読となった小説『想像ラジオ』(いとうせいこう/河出書房新社)は、『すずめの戸締まり』を考える上でも、興味深い補助線を与えてくれた。

「想像ラジオ」とは、海沿いの杉の木のてっぺんから深夜2時46分になると発信される、「あなたの想像力の中」だけで聞こえるラジオ番組。案内役はDJアーク。彼は津波に被災して、釣り上げられた杉の木の上から音楽とメッセージを発信しているのだ。
想像ラジオがどのようなものかが第一章で書かれ、つづく第二章は被災地にボランティアとして訪れたグループの様子にフォーカスする。語り手である作家のSは、ボランティアの中で耳にした「杉の木の上に引っかかっていた人」のイメージに取り憑かれるものの、その声(=想像ラジオ)を聞くことはできない。その話をきっかけに、彼らは「死者の声を聞く」ということをめぐって議論する。「そういう声が聞こえるときは確かにある」「そもそも非当事者が、そういう被災者の心の領域に踏み込むことはおかしい」「でも耳を澄ますことは止められないのではないか」などなど。
再びDJアークがメインになる第3章を経て、第4章は男女の会話形式で書かれる。この会話を追っていくうちに読者は、男が第二章の作家のSで、そして女はSの(少々わけありの)恋人であることを知る。第二章は、Sが彼女にあてて書いた長いメールだったこともわかる。そして最終的に、女はすでに事故死をしており、このふたりの会話そのものをSが記していることが明かされる。
Sは次のように結論する。
「生き残った人の思い出もまた、死者がいなければ成立しない。だって誰も亡くなっていなければ、あの人が今生きていればなんて思わないわけで。つまり生者と死者は持ちつ持たれつなんだよ。決して一方的な関係じゃない。どちらかだけがあるんじゃなくて、ふたつでひとつなんだ」
そして、
「ふたつでひとつ。だから生きている僕は亡くなった君のことをしじゅう思いながら人生を送っていくし、亡くなっている君は生きている僕からの呼びかけをもとに存在して、僕を通して考える。そして一緒に未来を作る。死者を抱きしめるどころか、死者と生者が抱きしめあっていくんだ」
「死者の声」は生者の呼びかけをもとに存在する。それは、想像ラジオを聞くことができる、という想像力の働きとほぼ同じものだ。Sは想像ラジオを聞くことはできなかったが、恋人の声であれば書く(聞く)ことができた。「不在者の声」とは、想像力によって(作られるのではなく)キャッチされるものではないか。
『すずめの戸締まり』で草太は、後ろ戸を閉じるとき、その土地で暮らしてきた人の「声」を聴く必要がある、と説明する。映像を素直に受け取れば、「土地の記憶」とでもいうべきものを走馬灯のように感じながら「戸締まり」を行うという描写になっている。だが『想像ラジオ』で示された、「不在者の声」をキャッチするための想像力、というものを念頭におくと、これは草太なり、すずめが想像力を使って、その土地にいられなくなった人たちの「声」をキャッチしているのではないか。想像ラジオのリスナーたちのように。

「エンパシー(感情移入)」の重要性
想像力によって「声」をキャッチする、という発想のヒントとなったのが、やはり発売以来の再読となった『3・11の未来 日本・SF・創造力』(作品社)に収録された、作家・瀬名秀明の論考「SFの無責任さについて」である。この逆説的な意味合いを持つタイトルの原稿も、書籍のタイトルの通り、東日本大震災を受けて執筆されたものだ。
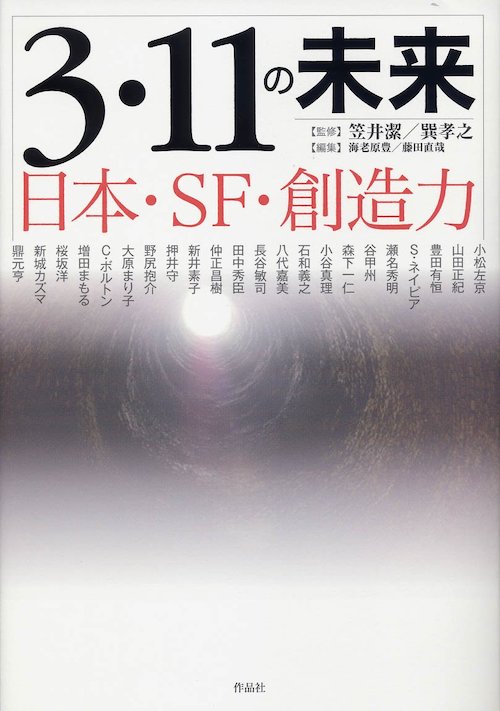
原稿中で瀬名は、人間の他者の気持ちを推測し、自分の感情を重ねていく働きを「行動的共鳴」「シンパシー(共感・同情)」「エンパシー(感情移入)」の3つに分けて整理し、とりわけエンパシーの重要性に注目する。
「同情、という日本語もSympathyと英訳されることが多い。震災の際、遠くにいる被災者を思って胸を痛めるとき、このシンパシーが深く関わっていることがわかるだろう。心の傷ついた友人の傍に寄り添い彼ないし彼女の話に頷き肯定するのもシンパシーであろう。私たちが互いに生きるときシンパシーは大切なやさしさとなりうる。
では三番目のエンパシーはどうか。やはり能力それ自体は生得的であろうが、こちらはある程度成長し、社会性を身につけてゆくなかで、より豊かに効果を発揮していく能力だと考えられる。自分とは境遇が違いすぎてシンパサイズできない相手でも、相手の内面に入り込んで気持ちを忖度し、理解し、その上で一体化していく。これがエンパシーの能力である」
すずめが他者の声をキャッチできたのは、知らない土地に住んでいた知らない人たちの生活や感情を、「忖度し、理解し、その上で一体化」していったからではないか。そのような想像力のあり方として、あの「土地の声」と呼ばれる「不在者の声」を聴くシーンを捉えることはできるはずだ。
そして「エンパシーを可能にする想像力」というキーワードが見えてくると、作品後半で見逃せなくなる新たなポイントがある。それは聴覚ではなく視覚、「他人の視線」というポイントだ。
『現代文学は「震災の傷」を癒やせるか 3・11の衝撃とメランコリー』(ミネルヴァ書房)の終章「視線の行方」で著者の千葉一幹は次のように記す。
「ビトにおいてもチンパンジーにおいても、愛する者同士はその視線を交差させることでその愛を確認していた。しかし人間は、愛する者に向けられた視線を逸し、外部へと視線を向けていく。そのとき、もう一方の者は、自分から視線が離れていくことを惜しむどころか、むしろ逸らされた視線の先にあるものを見ようとする。そして同じものに視線を向けることに喜びを覚える」
視線の見交わしと同じものを見ること(供視)。供視は「相手の見ているものを想像中で共有する」という点でエンパシーと重なる部分がある。また、千葉がここでは小津安二郎監督の映画『麦秋』を引きながら論を進めている通り、「見交わし」と「供視」は映像演出と深いところで結びついている要素だ。千葉はさらに「相手が何を見ているか共有できないこと(供視が不可能になってしまうこと)」を喪失の悲しみと結びつけている。『すずめの戸締まり』はクライマックスで、この「見交わし」と「供視」を重ね合わせてドラマを深めている。
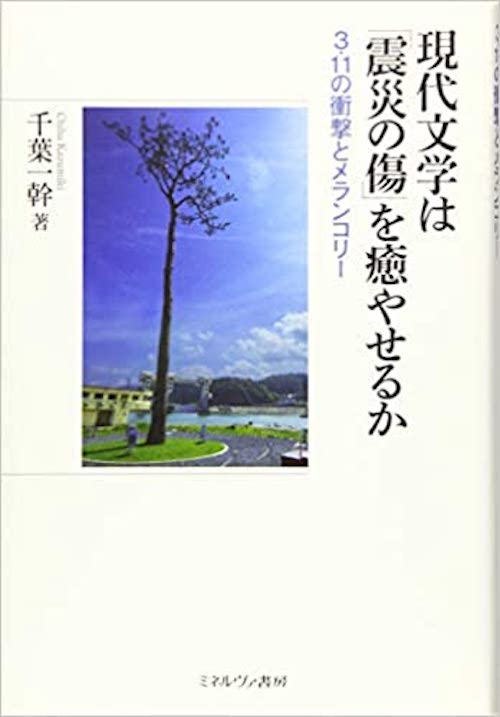
すずめは、自宅の跡近くに残された「後ろ戸」を開き、ついに常世へと赴く。燃えさかる山の上には「要石」となった草太がいる。山から草太を引き抜こうとするすずめ。そのとき、すずめは「草太の視線」で彼の記憶を体感する。
このとき映像は、いわゆる「記憶が流れ込んできた」と表現されるような表現をとるが、これは過去に後ろ戸を閉じるときにすずめが「不在者の声」を感じた「想像力によるキャッチ」が、視覚でも起きたと解釈することができる。要石となった草太が見ているものを共有できない喪失感。しかし、「想像力によるキャッチ」で彼の視覚を共有したとき、彼がなにを見ていたかがわかる。そこにいるのは、旅をともにしたすずめの姿だった。ここですずめと草太は「供視」すると同時に「見交わし」てもいるのである。
そしてこの体験を通じることですずめは、草太の心の底でうごめいていた「生きたい」という気持ちを拾い上げる。序盤、「不在者の声」で起こっていたことが、ここでは草太の視覚と心の声という形でスケールアップして起きている。そしてその生死の際で「生きたい」という思いは東日本大震災で死んだすずめの母の感情とも、深いところでつながっている。
すべてが終わったあと、すずめは常世で、被災し常世に迷い込んでしまった4歳の自分と出会う。このとき、すずめは「かつて出会った、母だと思っていた人物が、実は成長した自分であった」ということに気づく。
このシーン、画面どおりに受け取れば、時空を超えた自分同士の対面(視線の見交わし)になるが、先の草太との視線の共有を踏まえると、もうちょっと複雑な解釈もできる。
このとき、高校生のすずめは、あの日の「お母さん(と思った人)」の立ち位置にあり、目の前にいる幼いすずめは、あのころ、母親が目にしていた自分である。ということは、すずめはこの瞬間、あのころの母親と視線を共有し、かつ自分と視線を見交わしていることになる。草太と視覚を共有したことの延長線上に、母という「不在者の視覚」を共有しているシーンとして、新たな意味が浮かび上がる。
「不在者の声」から「不在者の視覚」へ。すずめの旅は、想像力の経験を積むことでエンパシーが高まり、キャッチできるものが深まっていったすずめが、ついに亡き母と視線を共有するに至る物語だったのだ。
高校生のすずめは、草太が人間に戻り、ただの椅子に戻った母の形見を、幼いすずめに渡す。
3本脚の子供用の椅子とは
『その後の震災後文学論』(青土社)で文学研究者の木村朗子はジャック・デリダの文章によるフロイトが提唱した「喪の作業」への批判を紹介する。
「(デリダは)正常な喪の作業としての体内化の過程、つまり死者をみずからのうちに取り込むことを拒否し、他者を他者のままに、生きている死者としてそれを守りつづけるためのクリプトを持ちつづけること、そうした病的な喪を積極的に評価している」
「つまり、失った大切な人を自分の歴史の1ページとして過去へ送り込んでしまうことなしに、心にずっと冷たい墓石を抱え込んだ状態でいつづけることを提案しているのだ。クリプトは、キリスト教の教会の地下などにあって、聖人や教会にゆかりの人が埋葬されている場所だ」
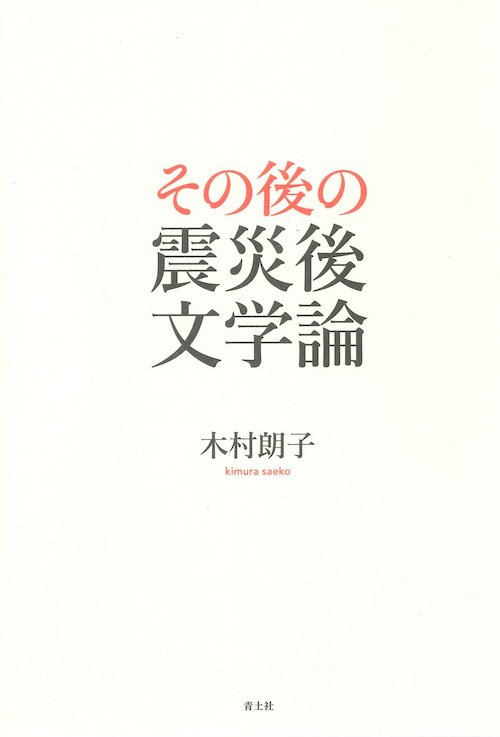
3本脚の子供用の椅子。それはすずめにとって母のクリプトだったのではないか。喪の作業を完成させ、「思い出」として昇華することのできない特別ななにかとしての「椅子」。これは喪の作業としては失敗なのかもしれない。しかし、それは死者と共に生きることでもある。幼いすずめはこうして、3脚の椅子とともに未来を生きていくのだ。
ここまできて、ようやく最初に引用した「想像ラジオ」の作家Sの文章と話題が繋がる。生者と死者はふたつでひとつ。しかし、死者は本来語りもしないし存在もしない、心の中の「クリプト」である。そんな不在の存在を、生者のそばに在らしめるのが想像力によって可能となるエンパシーなのである。
単に東日本大震災を扱ったからではなく、その未曾有の被害にエンパシーをもって対峙する様を描いたからこそ、『すずめの戸締まり』は「震災文学」と呼びうるのだ。