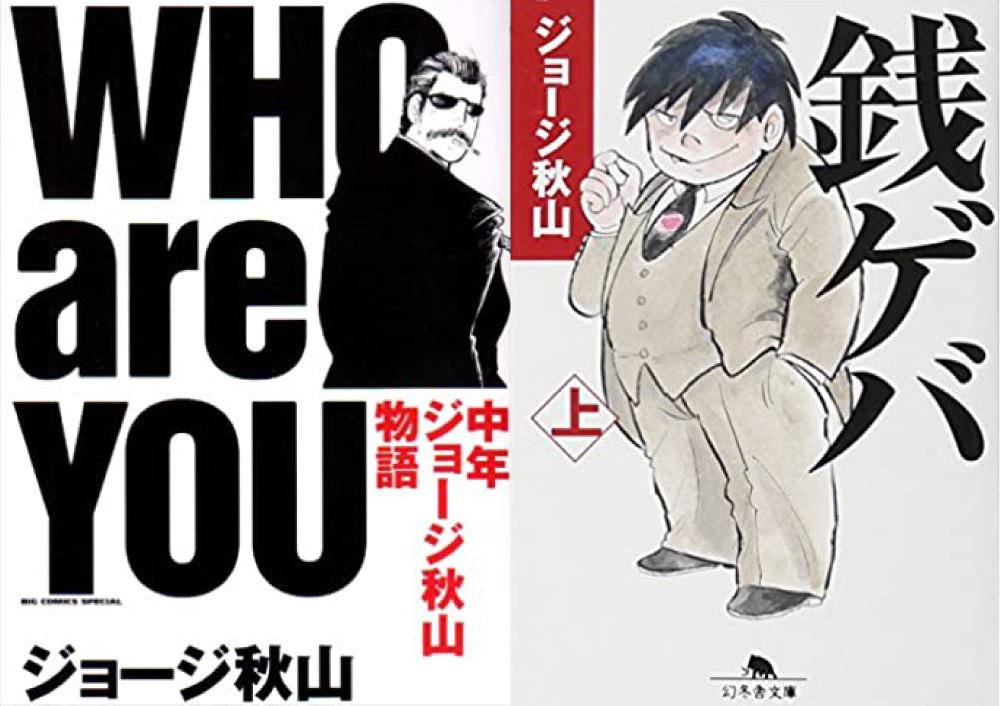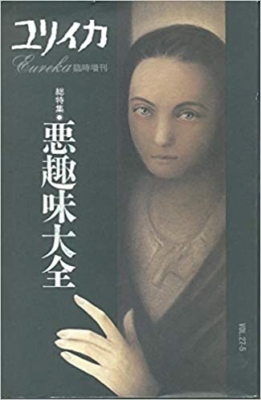6月1日、漫画家ジョージ秋山死去のニュースが報じられ、多くの著名人やファンがネット上で哀悼の意を表した。1960年にデビューし、失踪・復活を経て50年以上にわたってマンガを描きつづけたジョージ秋山。なぜ、彼の作品は時代を超えて愛されるのか。
『クイック・ジャパン』創刊当時よりライターとして活躍し、今日に至るまでのサブカルチャーの趨勢を知る漫画評論家・足立守正が独自の目線で、その理由を分析した。
地獄のフィーリングを忘れない。(足立守正)
なんの準備もなく、突然にジョージ秋山の訃報を聞いた。新型コロナウイルスによる非常事態宣言の最中、5月12日に没、享年77歳。なんだろう、この季節が変わったみたいな感じ。それほど大きな出来事だということだ。そして『QJWeb』から何か書くように、と連絡があった。作品を読み直す時間はなさそうだけれど、書き始めてしまった。
孤高の人気漫画家として
ジョージ秋山がどんな漫画家だったか、書き出してみる。1960年に、貸本漫画誌『風魔』(東邦漫画出版社)の創刊号でデビュー。忍者漫画のアンソロジーであり、そこに本名の秋山勇二の名で描いた『嵐と忍者』が掲載された。看板作家の白土三平から「秋山君の前途は明るい」とのお墨つきで、16歳の新鋭が登場した。
その後、ギャグ漫画家の森田拳次に師事し、間もなく少年漫画雑誌の人気作家として成長、DCコミックス『バットマン』をからかった(でも芯の部分では似通った)ようなメタヒーローマンガ『パットマンX』(講談社)で1968年に講談社児童まんが賞受賞。70年代になると、コロコロした三頭身のキャラクター造形はそのままに、物語は毒気を放ち、『銭ゲバ』(小学館)などの過激な話題作を連発。『銭ゲバ』は唐十郎の主演で映画化され、また、イラストレーターの和田誠はアラン・ドロンのポートレイトに重ねて描いた。寺山修司は、評論家の石子順造に「パットマンX」の扮装をさせて写真を撮った。永井豪は『ハレンチ学園』(集英社)に「デロリンマン」を登場させた。赤塚不二夫はライバル視をした。知識人にも愛される、時代の寵児だったが、露悪が過ぎて良識派の癇に触り、有害図書扱いされたりもした。
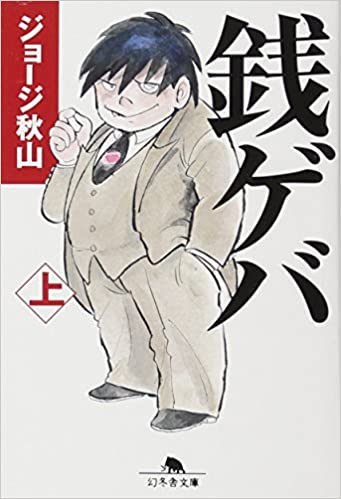
やがて華麗に失踪、華麗に復帰。青年漫画誌に発表の主軸を置き、国民的漫画『浮浪雲』(小学館)を生む。その国民的ぶりは、ドラマやアニメや舞台にもなり、主人公の雲さんを演じたのが、渡哲也、橋幸夫、ビートたけし、五木ひろし、という顔ぶれからもわかること。1978年に小学館漫画賞を受賞し、連載は44年間にわたり、単行本112巻が刊行された。そのほかにも『ピンクのカーテン』『恋子の毎日』など女性を主人公にした長期連載作があり、これらもメディアミックスに成功している。漫画家の組織に属さず、孤高を貫き通した。
語られてこなかったジョージ秋山ファンの存在
思いつくままに書き連ねても、間違いなく、偉大な作家としての勲章をいくつも持っている。ただ、描くマンガはとても風変わりだった。過激と言われた時期もあったが、そのこととは別に、風変わりだった。語り出しが絶品でワクワクさせられ、不思議なリズムで踊らされ、ラストシーンらしいラストシーンは、ない。
現在、ジョージ秋山作品を熱く支持する層とは、一般的にはふたつだろう。ひとつは、子供向けマンガの枠の破壊をリアルタイムに目撃したショックが忘れられない人たちの層。ひとつは『放浪雲』の自由な空気と滋味のある生活訓に魅せられた人たちの層。でも厳密には、もうひとつの層がある。
「消えないマンガ家ジョージ秋山」
1997年、『クイック・ジャパン』vol.12に「消えないマンガ家ジョージ秋山」と題されたロングインタビューが掲載された。取材は、大久保良太郎による。大久保は直後に『クイック・ジャパン』の編集者となったが、なったと思ったらすぐ消え去ってしまった(たぶんサブカルチャーの精霊だったんだと思う)。件の記事は、強烈な熱量でジョージ秋山の特集を組んだ、大久保が主催のミニコミ『7(セブン)』からの転載だった。どこの誰ともつかぬ若者による取材だったはずだが、ジョージ秋山は上機嫌。荒々しくインタビュアーを振り回す様子が活写されている。完全に聞こし召しており、言ったと思えばまったく逆のことを言い出す、本当か嘘かわからない内容のないことを延々と話している。大久保は、あの強烈でミステリアスな作品を生む作家が、ただの酔っ払いであることを見せ、この世の不思議を提示した。

それからずいぶん経ってから、自身を主人公に描いた『WHO are YOU』(小学館)を読むと、酒に溺れる自分を冷静に客観視した描写がまた不思議でならない。自分の作品に興味がないと見せかけ、評論家による批評は目を通していたと思しい。児童向け漫画で活躍中だったころ、評論ミニコミ『漫画主義』7号(漫画主義発行所/1969年)に掲載された初期インタビューのころから、批評に興味のあるところを見せている。「じつは、ぼくもノウガキを読むのは好きなんですよ」と、『漫画主義』の定期購読費をインタビュアーに差し出している。