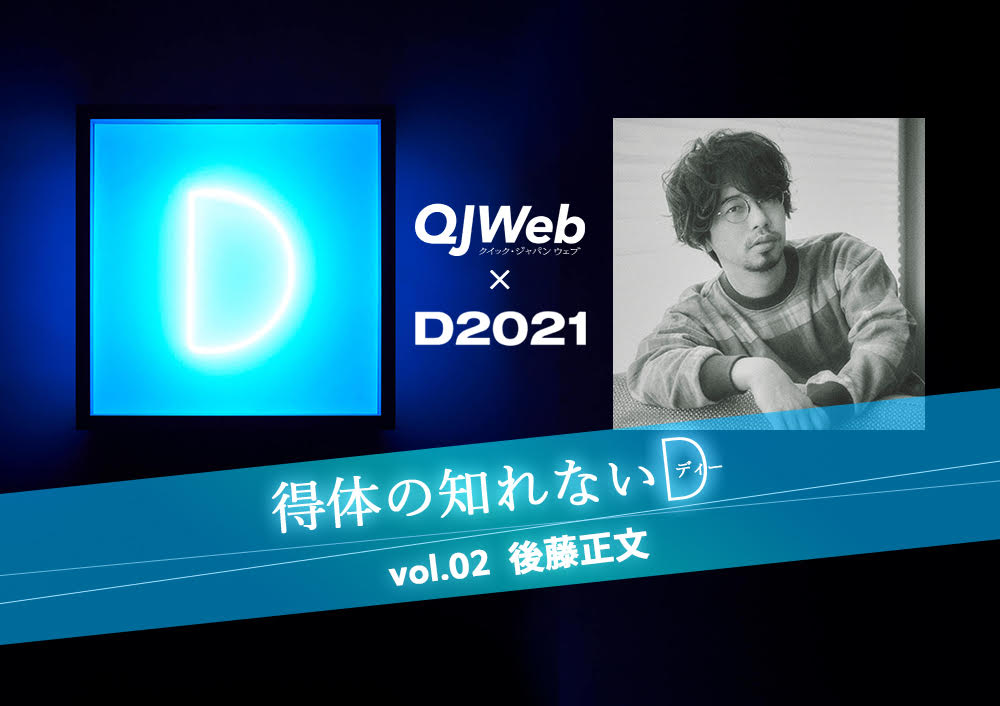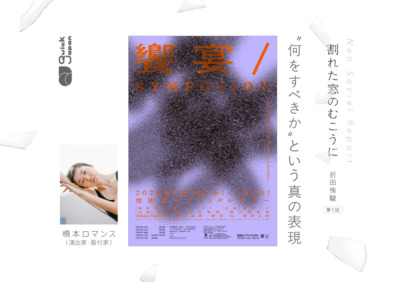2021年の3月、震災(Disaster)から10年(Decade)という節目にさまざまな「D」をテーマとしたイベント「D2021」が開催される。
連載「得体の知れないD」では、執筆者それぞれが「D」をきっかけとして自身の記憶や所感を紐解き、その可能性を掘り下げていく。
第2回の書き手は、坂本龍一とともにイベントを主催する後藤正文(Gotch)。ミュージシャンとして身近にある「Dynamics」(音の強弱)を皮切りに、「理想」のために行われる排除へと思いを巡らせる。
「D」はどんな意味を持つのか、「D」にできることはなんなのか。
波が岩場を削るように失われていった何か
まずは身近な「D」から考えてみる。
たとえば、Dynamics。これは音の強弱を表す言葉。
2020年の現在、僕の音楽的な興味の焦点は録音と録音物のミキシングに合っている。
音楽産業の最前線では、長らくリスナーに大きな音だと感じさせる競争に熱心だった。大きな音のほうが良い音だと錯覚する人間の性質をビジネスに利用したためだ。プレイヤーのボリュームを上げれば同じ音なのだけれども、マーケティングによって、再生ボタンを押した瞬間に大きく感じる音が求められた。
プラスティックの円盤に収めたコピーを誰がどれだけ売ったのか。それを競う裏で音楽における芸術性のすべてがないがしろにされたとは思わない。けれども、波が岩場を削るように失われていった何かがあったのではないだろうか。もちろん、僕もそうした時代に居合わせたミュージシャンのひとりとして反省している。
資本主義の要請に従って、大きな音は潰された。小さな音は、小さな音のままではいられずに、演奏者の繊細なタッチやニュアンスは、録音したままの状態ではいられなかった。そして、大きな音の近くにまで引っ張り上げられた。つまり、それぞれの音のボリュームの差が狭まった。それは音や楽曲の個性を、Dynamicsの面から奪ったのだと思う。
「理想」のために行われる排除
僕は連想するように、Diversity=多様性について考える。 それぞれの音が、それぞれの意図する音量のまま、その感触を保つように鳴る。そんな録音物の制作ができたらどんなに素晴らしいだろうか。たとえば、最高の演奏をした夜のコンサートホールをそのまま収録することができたら、なんて豊かだろう。
けれども、その理想を叶えるのは難しい。
録音物はありのままの空間を捕まえたものではない。何本かのマイクで収録した音を使って、その音が鳴ったときの空間を再現する、あるいは整理して作り直すような行為だからだ。記録するメディアや録音に使う機材の性質や性能の影響を大きく受ける。実際に鳴った音と、テープやハードディスクに記録された音は同じものではないのだ。

それでも、僕は可能な限り、感動的な空間の再現を試みる。
どこまで行っても、あの日のままの美しい空間ではない。だから、僕は自分で拵(こしら)えた「良さ」に向かう。完全な再現はできなくても、より「良い」空間として再現しようと努力する。ミキシングや録音は、音楽とその美しさについての個人的な考え方や感じ方を参照しながら行われる。美しさのために不要なノイズをカットする。たとえば、誰かの足音や衣服の擦れる音、遠くで微かに鳴るモーターの音、不意に出た咳、深く吸い込んだ息の音や唇から出た少しの破裂音を、あるいは演奏者のミスタッチを、音楽には関わりのない音だと決めて排除する。そうして、自分が思う美しい録音物としての音楽が完成する。
そう書きながら、僕は恐ろしい気持ちになる。