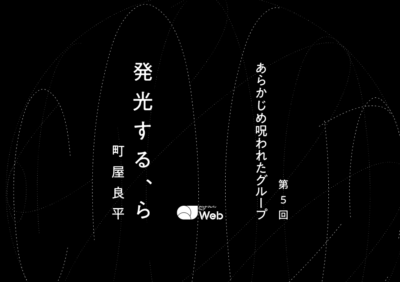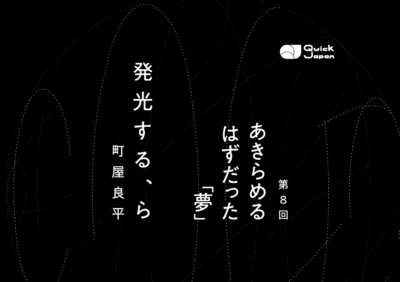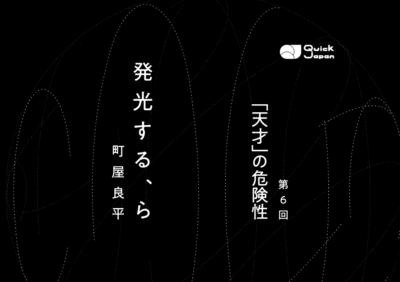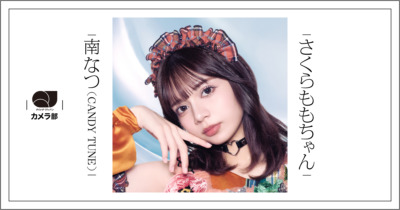テレビに出る機会もほとんどない弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。メンバーのアリスとキルトには、仲間に明かしていない秘密があった。それは、彼らが70年後の未来からやってきたということ。バンコクでのフェス出演の最中、キルトはタイムスリップする瞬間をメンバーのサトシに目撃されて……。芥川賞作家が贈る、衝撃の「アイドル×SF」物語、開幕!
前回の連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
#2 個性恐怖症
8koBrightsは現在世界レベルで活躍中の某ボーイズグループが結成されるきっかけとなったサバイバルオーディション番組の、三次選考にあたる合宿審査において協調性のなさが問題視され(それが直接指摘されることは、メンバーによってあったりなかったりしたものの)、かつ協調性に欠けても周囲を納得させる圧倒的な華があるわけでもない、と判断された面々がリーダーであるリュウの誘いに応じてなんとなく集まり、結成したグループだった。
メンバーは押しなべて複雑な家庭環境のもと育ったことが熱心なファンのリサーチによって暴露されていたことから、グループの支持者たちは公式のファンダムネームである「エイシス」ではなく「ハッコウ」、つまり「発光」というエコブラのコンセプトとそれを文字った「薄倖」というダブルミーニングが意図された自称を用いているが、いまやその由来を知る人は少なく、古参ぶるファンが好んで使うことから却って廃れない愛称となっていた。運営やメンバーは黙殺しているが、たまにレンなどがインスタやTikTokライブでうっかり口にしてしまうことがある。
「「ハッコウ」……あじゃなくて「エイシス」のみんなが楽しんでくれたらそれが一番だよ~」
のような形で。すると「ハッコウ」たちは歓喜し切り取り動画が大量に拡散されるから、公式のファンダムネームである「エイシス」のほうの認知がなかなか進んでいかない。ファンたちも家族の問題やメンタルに不安を抱える人が多いというのは音楽ライターなどからよく指摘される事実としてあった。
アリスとキルトは両親をすでに亡くしているが、現代ほどそれが愛着や人格形成に影響を及ぼすことなどはない。資本主義や国家の解体された七十年後では「家族」は現在ほど大きな役割を果たさず、AI技術や福祉の助成によって十代までの両親の有無が子どもの愛着形成に与える影響はかなり小さくなっている。ほんらいアイドル性に大きくかかわるはずの愛着形成が、しかし双子に限ってはそれほど大きく関係している印象はなく、
…… アリキルは薄幸というよりなんか……
…… ひねくれてるっていうよりなんか……
…… 我が強いっていうよりなんか……
…… 空気が読めないっていうよりなんか……
「おまえら、なんかズレてるんだよ!!!!!!」
合宿の四日目に、たまりかねたシンイチに言われたアリスとキルトは揃ってヒソヒソ、密談した。
全員参加で行われた基礎レッスンでの一幕だった。休憩中にオーディションの主宰が駄菓子類を差し入れた。するとキルトが支給された黒シャツが汚れること厭わず羽二重餅(はぶたえもち)を貪るように食い、キルトの口から零れる白い粉が隣に座っていたシンイチの顔に付着した。
ボーカル志望でダンスの苦手なシンイチは、いまや美容担当といわれるほど肌に気を遣っているのに睡眠不足からくる吹き出物に見舞われ、駄菓子などもっての外と内心思っているのに食べないわけにはいかず、そんななか無邪気に羽二重餅を貪るキルトが洩らす「うめえ……絶滅伝統菓子……たまらねえ……ハアハア」という声がハッキリ、マイクに拾われていた。
放送ではキルトのそのつぶやきはカットされ、シンイチの「おまえら、なんかズレてるんだよ!!!!!!」という心からの叫びだけが使われてしまった。テロップで「時に激しくぶつかり合うメンバーたち」と乗せられていたそのとき、アリスは「おい、過去のものをあんま珍しがるなっていつも言ってるだろ」と耳打ちしたのだ。
「だって、羽二重餅だよ?」
キルトの声量は変わらなかった。そこで最終審査を八位で通過し現在も活躍中の某メンバーが、「そんなに好きならオレのも食う?」と言い自分の羽二重餅を差し出すと、キルトはその某メンバーを抱きしめた。
某メンバーの好感度は上がり、シンイチとキルトの好感度は著しく下がった。キルトは単純に食べ方が汚すぎ、という指摘が多かった。汚れたシャツで抱きつかれた某メンバーはしかしまったくそれを厭うようすもなく、「キルトは餅がすきなんだなあ」と言った。その一連の流れをいまでもシンイチは恨みに思ってい、「キルトのことだけは許せねえ」とよくリュウやサトシに洩らしていた。
今回のステージでもキルトはたびたびシンイチに接触し、フォーメーション感覚に定評のあるレンが位置を調整して即興のファンサに走った。確実にバレて拡散されてしまうのだが、それでもなんとか失敗の印象は誤魔化された。
トイレでたまたま横に並んだときに、シンイチはサトシに「あいつなんか今日、とりわけ浮ついてなかった?」と苦笑しながら言った。
「そんなことねえよ!」
サトシの強い否定に、シンイチはぎょっとした。
「なにキレてんだよ。そんなんだからおれら情緒不安定なトコが逆に推せる~とか言われるんだぞ」
「あ、いや、すまん」
「明日の本番前にキルトと振り確認しないと、またグダグダになるわ。マジあいつ抜けてくんないかな」
「ハハ……」
キルトとアリスが未来人であることを聞いた直後であったから、サトシは気が気ではなかった。
事務所に所属せずフリーで地下や地方のドサ回りイベントから地道にファンを増やしていき、メンバーのヤスが体力不足から体調を崩して離脱し、そのまま社長となって株式会社キャッツクレイドルを立ち上げ、エコブラとしての活動も二年目に入るところだった。
*
「おいキル、ちょっと暗くなる前に、フォーメーション確認するから来い」
巨大駐車場で観客のほとんどが大人気女性アイドルグループを観に行っている、その隙にちゃちゃっと振り確認をしてしまおうと切り出したシンイチに、キルトは「なんで?」と応えた。
「今日も『Three-Body』でおまえが間違えてぶつかりそうになっただろ。あそこ成功率低すぎなんだよ」
「それは、シンイチがステージの狭さを考慮していないせいだよ。たしかに振りを間違えたのはオレだけど、ぶつかったのはオレのせいじゃないよ」
「は? だから練習しようって言ってるんだが」
「シンイチは目立とうとするのをおさえて冷静になればいいだけだよ。オレはこの後ホテルで個人練習するから、いまはいいよ。カオマンガイ食べたい」
そしてキルトは屋台のほうへと消えていった。
駐車場に取り残されたシンイチは、しばし呆然とした。
アイツは何故あんなに食いまくってるのに太らないないんだ!!!!!!!!!
そしてやや見当外れな憤りを口に出して叫びそうになった。シンイチは体質的に太りやすく、日ごろから糖質と脂質をかなりカットしてようやく他のメンバーと同程度の体脂肪率を維持していた。
たしかに、言われてみればそうだった。ステージのとくに奥行が狭いことはリュウからさんざん言われていたので、「ダンスはほぼフォーメーションと上半身だけでよい」とされていた。
「シンイチはステージで「俺を見ろ」の気持ちがよく出ているね。それはシンイチの長所だと思う。でも今回の曲のコンセプトをよく考えてみた? 我を出すことと華を出すことは、似て非なることだって、少しずつ気付けるといいよね」
かつてのオーディションで主宰に言われた、苦い助言が頭に残っている。だが、我を出して何が悪い、とシンイチはいまだに思っていた。自分はステージの上でしか自分自身でいることができない。そこだけが唯一遠慮なしの自分を表現できる場なんだ。
けっきょく日常でも安心して自己表現できる人間に、おれの気持ちなんて分からない。
人間性や内面のよさこそが天から与えられた才能だ。アイドルはそれを体現するみたいにキラキラして不特定多数にモテる。たくさんの愛を受け取って、輝いて元気になれる体。その体で愛をお返しする。だが愛されることに慣れていない、安心できない人間にはそれが難しい。
それでも唯一音楽が鳴っている時間だけは安心できる、平等な自己表現の場だって、音楽に救われたからこそシンイチは盲信していた。
本当はわかっていた。キルトは人一倍個人練習しているから太らない。シンイチは個性にかまけて肝心の技術がついていかない。それでもキルトよりは歌もダンスも実力は大分上なのだが。しぜんと足が、メインステージのほうへと向いていった。
ステージのキャパに間引きされるように動きを制限されたとて、会場を大いに沸かせている、まだデビューして間もない日韓混合の女性グループのパフォーマンスをシンイチはひとりの客として眺めた。ちゃんとステージのサイズに合った動きを、メンバーそれぞれがきっちりこなしている。
ふと右のほうを見やると、そこにアリスの姿があった。相変わらず白い半袖シャツを着ている。アリスは普段着のすべてが白の半袖シャツとジーンズという、冬場でもその無個性な恰好で現場に来る。小学生のころそういうヤツいたよなーって笑っていられたのは最初のうちだけで、それが永遠のように続くと驚きを通り越して呆れ、恐怖すら覚えるのだった。
ある日、なにげなく「お前、白シャツばっかだな」とイジるつもりでもなく素朴にオフで声をかけると、やや後ずさりするように距離をとられたあとでシンイチはこう言われた。
「ゴメン、おれ、個性恐怖症なんだ……」
その謎の恐怖症は初耳だったが、シンイチはそのときに、あ、だからおれはアリスから距離を置かれているんだな、と悟った。オーディションの時から、アリスがシンイチと同じグループにならないよう慎重に振る舞っているのはなんとなく分かっていたが、たんにボーカリストとしての相性の問題と思っていた。
だがボーカリストとしてだけではなく、明確に自分は避けられていた。正しくは、自分の「個性」が。
アリスの没個性的な声質と音域の広さは楽曲の骨格を支えている。とりわけ、シンイチのパートに透明感の強いファルセットを合わせるときに安定感と華が両立した。
シンイチとアリスの声は、ふたつ合わさって丁度いい。
これが我を出すことと華は違うってことなのかな。
とある日のシンイチは思ったのだが、しかしキルトほどではないもののアリスに対しても依然苦手意識がある。事務所の会議室でアリキルが談笑している場面にたまたま遭遇し、ドア越しに入るのをためらっていると、中からアリスの「シンイチのボーカルに声を合わせるの、どうしても怖気(おじけ)だっちゃうんだよね」と、とんでもなくひどい愚痴をおそらく本心から口にしているのを聞いてしまい、一気に気持ちが萎えたのだった。
シンイチがさすがに傷ついて急ぎその場を去ったあとで、「どうしたらおれの個性恐怖、治るのかな……」とアリスはキルトに相談したのだった。
「ま、現代病だからね。だましだまし付き合ってくしかないよ。投薬はしてるの?」
「してるけど、体質依存アラートが出ていて、ちょっと耐性ついちゃってるっぽい」
「ちょうどいいじゃん。シンイチみたいな我の強い過去人の近くにいて、慣れるんだぞ」
「シンイチぐらいの人なんてこの時代、ゴマンといるもんな。てかお前また過去人とか言って。口に出すなよ」
「へーい」
アリスは他のグループやさまざまな楽曲のことを知っているのみならずそれぞれの分析に至るまで的確で異様に詳しい。いまもステージ上のアイドルを眺めている表情はきわめて輝いていた。コイツは自分がステージに立っているときよりも人のパフォーマンスを見ているときの方がキラキラしている。それはシンイチにはとても考えられない価値観だった。
アリスは、夢にまで見たあのステージ!!! 女性グループならではのボーカル力の高さ、韓国で練習生経験を積んだメンバーが引っ張るダンスの質、ともに新人とは思えない……生で見られるなんてなんたる僥倖!!!とジーンとしていた。未来でも3Dデータとしては残っていない時代のアイドルだったために、生身が動いている奥行に感動し、思わず両眼からツーッと涙をこぼした。
キモ、とシンイチは思った。
*
「声が出ない?」
シンイチが思わず伊佐木マネージャーの発言を反復した。二日目のステージまでを滞りなく終え、あとは最終日を残すのみという夜にホテルでくつろいでいたところ、緊急MTGという名目で伊佐木マネージャーの部屋に呼び出され、告げられた内容はレンの喉の不調についてだった。
ここ最近のパフォーマンスからなんとなく予想がつく報告だったが、2nd配信シングル『Three-Body』の地方リリイベからシームレスにこのバンコク遠征と重なったレンの喉は相当酷使されていて、とくに同曲においてD#の高音を地声で三秒ほど伸ばすブリッジパートからラスサビへと移る歌唱に相当痛めつけられていることは分かっていたから、他のメンバーは神妙な様子でただ聞いていただけだったがシンイチは「うそだろ、そんなキツかったのか」とつぶやいた。
キルトがポンとシンイチの肩に手を置き、「そういうとこだぞ」と言って微笑んだ。
シンイチは一瞬ポカンとしたあと、「で、どうするんすか、『Three-Body』ナシでいきますか?」と言った。
「みんなごめん。最近は連日のステージがあるときは鍼(はり)の先生に帯同してもらってたんだけど、さすがにバンコクまで来てとは言えなくて」
レンがしずんだ面持で言った。喋りかたからして微妙にいつもと違っていて、なるべく声を出させないほうがいい。
レンはそのボーカル力と人気においてエコブラの圧倒的トップに君臨し、どこかの事務所の芸能コースなどに所属していたわけでもないのにダンスでも遅れをとることはなく、かつ動きながら歌うということへの適応力も非常に高かった。男子としては稀有なほどダンス&ボーカルに向いた身体なのだがしかし調子にムラがある。メンタル面にやや不安を抱えており、8koBrightsが結成されるきっかけとなった某オーディション番組でも実質のデビューがかかった最終審査ひとつ前のパフォーマンスにおいて、中間発表と本番ともに本調子のボーカルが披露できず脱落していった。
レンはその不安定さや自己流の身体性において発現する、稀有な声質と華があって人気が出た。その反面、柔和ながらの頑固さがより厄介で、周囲はおろか本人すらどう調子をコントロールすればいいか分からず、いまだプロのダンス&ボーカル、ひいてはアイドルとしては心許ない状況が続いている。ひとりだけ十代であることもそれに拍車をかけていた。
「さっき代表のヤスとリュウとわたしでオンラインミーティングしてたんだけど、尺の関係からも『Three-Body』は外せないし、かといって専属のマニュピレーターはまだ付いてないし急には被せも用意できない。だからどうなるかわかんないけど、みんなには色んな可能性を考慮しておいてほしいとは思ってる。とりあえず明日までにレンがファルセットで対応できるぐらいには回復するのを祈るのみだね。プレッシャーをかけるようなことを言って悪いけど、けど逆に言えばこれもLIVEの臨場感ってことで、エイシスは温かく許してもらえる部分もあると思うけど。みんな夜分にゴメンね」
「意地でも出してもらう」
じっと黙っていたリュウが、そこで重くひびくような声で発言した。
「プロだったら、いつでもつねに100%が出せるよう準備しとけよ。それでようやく、アクシデント時に八十%のパフォーマンスが維持できるんだ。というかほんとの本調子で迎えられるステージなんてそれこそその方が稀なんだからな」
「きびしー……引くわー」
シンイチが言った。
「リュウはいつも正しいよ。でも正論だけじゃ乗り切れない場面があるからこそ「プロ」なんじゃないか」
サトシが言うと、リュウは「これでも随分妥協してるつもりだわ。ここのところ、まったく人に見せられるパフォーマンスになってねえからお前ら全員」と言い放ち、ホテルの空調が聞こえるほどの静寂が漂った。
「……リュウは現実が見えてない。いまはレンをよりよいボーカリストとして延命させること、レンが幸せな気持ちで歌えることをみんなで目指すべきなのに」
アリスが言う。
「や、待って、揉めるのは止めようよ。けど、万が一ワイが明日裏声でも出せないなら『Three-Body』は外してほしい」
「レンはそれ言う資格ないよ。自分が招いた不調ではあるんだから。黙って喉を労りなよ」
キルトが言った。自分は到底レンに代われるボーカル力はないというのに、相変わらずの無神経な正論につづけて「だから、アリスが歌えばいいんじゃね」と言った。ケータリングから持ち帰っていたバナナケーキを咀嚼しながらの発言だったため、肝腎のアリスの名前がやや聞き取りづらく、シンイチが苛立たしげに「は? なんだって?」と聞き返した。
「だから、アリスが歌えばいいんじゃね? ボーカルとしては心許ないかもしれないけど、地声でレとかミまで出せるのは他にアリスだけだろ?」
バナナケーキを飲み込む猶予を待ちながら、メンバーはキルトの発言に耳を傾けた。
アリスの音域は広い。ピッチも正確だが個性恐怖もあいまって声量はなく声質も細い、なにより「表現」に心許ないというのがオーディションのときから通底する印象としてあった。ゆえに基本サビ以外のメロとハモリを担当するに留めていたし、それで個性恐怖の発作も防ぐことができていた。
個性恐怖。時代が進むにつれ自己主張が忌避されていった結果、七十年後の人類がカウンセリングにかかる名目として急増している疾患だが、そもそも歌唱の分野では「個性」というものの概念が現代と七十年後ではあまりにも違った。
きっかけは二〇四三年に発表される、とある論文によって提唱された「ヤシロアキ理論」と呼ばれる研究による。実在した歌手の歌と発言をもとに研究したAIと人間混合チームの掲げるその説によると、楽曲においてクリエーター側が歌詞にどれほど創作の重心を置いているかは関係なく、歌詞の意味に重きをおいて歌うAI身体の歌唱と、音楽全体の構造に重きを置いてAI身体の歌唱を聞かせた生身体(きしんたい/AI身体でない旧身体のこと。つまりこの時代における普遍的な生命のことだが、とくに研究分野においてAI身体との本質的な区別のためにそう呼ばれる)の情緒反応をはかったところ、後者のほうが圧倒的に感情が揺さぶられている、つまり感動していることが分かった。AI身体ではない生身体にも歌わせて同様のサンプルを取ったが、AI身体ほど顕著な差異は表れなかったものの、それでも歌詞より構造に重きを置いたグループのほうが「感動した」という情緒シグナルが得やすいことがわかった。
七十年後のボーカルに長けた生身体においても、歌詞に重きを置くことと構造に重きを置くことの差異を表現する出来に個体差が著しく、歌詞に重きを置かないということを無味乾燥のように歌うという表現で行うサンプルもあったため、より正確なデータとしてAI身体のほうを重視することになった。これは七十年後の研究においては定石である。
これはいわゆる歌手の仁(にん/その人ならではの個性やキャラクター、いわゆる「身体性」)とは関係なく、くわえて聞き手はあくまで歌い手の「音楽性」つまりバックグラウンドに重きを置いて聞くも自由だが、歌手のほうでは詞の意味に即して行う表現、分かりやすいもので言うならばテンポを揺らして歌うルバートのような技法を歌詞に応じて行うのは逆効果で、あくまで無心に近いような意識で目の前のフレーズに注力するのが最善手とされる。
ライヴシステムや歌い手と聞き手それぞれの「人生」タイミング、つまり場の環境に大きく左右される説であるのは自明のこととしても、それでも歌い手が歌詞の意味を「理解」「共感」することが必ずしも聞き手の感動を増幅させるわけではなく、むしろ音楽的な構造への理解のほうが如実に聞き手の情緒に響くという、七十年後においてはこれが常識となっていた。すでに身体の行うしぜんな発声や表情や集中に歌の魂はこもっており、そこに歌詞の意味まで乗せて強調するのは聞き手の共感や感情移入、ひいては解釈を奪う行為だと忌避された。
そんな未来の「常識」がむしろ「非常識」である現代においてアリスの歌唱は評価されづらく、しかし七十年後においてアリスの歌唱は生身体としてはまずまず上手い方に数えられていた。ところがこの時代で個性恐怖の症状が強く出てしまい、オーディションで旧態依然の精神論に曝され委縮した発声を繰り返したことにより細く弱い声しか出せなくなって、より下手な印象が根づいてしまった。
一方、キルトはシンプルに歌が下手だった。
「ハー……」
アリスは深い溜息を吐いた。このところ不用意なキルトの発言、行動がとみに増えている。こんなんじゃ、いつ免許が失効してもおかしくない。あとでキルトには厳重に注意しなければいけないな、とミーティングの主題とはまた別のことを考えていた。
「うーん、アリスはどう思う?」
伊佐木マネの中ではアリよりのナシ。そんな手応えの提案だった。アリスには大勢の注目を一身に浴びる場数が圧倒的に足りていなかったし、なにより本人にその意欲が乏しい。
「いや、危険だろう。あの落ちサビのとこの高音はしくじったら非常に目立つぞ」
シンイチが言うと、サトシが「お前、そんなプレッシャーを与えること言うなよ」と窘(たしな)めた。
「でもガチそうだろ。おれだってあそこは歌えないよ。レンに合わせたキーになってる」
「でも、ワイはアリスのボーカルすごいと思ってる。これまで以上にパートを増やしてもらえたら、それに越したことはないよ」
レンが言った。
実質のパフォーマンスとして、サビやブリッジの難易度の高いボーカルはおおかたレン、シンイチの二人で回している。サブとしてアリス、そしてオールラウンダーのサトシがメロとラップを担当する。そしてリュウがメインのラップパート、サブでキルトもすこしトリッキーな声を駆使したラップを担った。
レンの調子にムラがあることがここまで議論の俎上に上がってしまう現状、ひとり増やして三人でメインの歌割を構成できれば、少しはレンの喉を労わる余裕が生まれるだろう。
少しずつステージの回数も増えてきている。作曲経験もあるレンのボーカル力によっていい楽曲を作ってもらえてい、またリュウのダンススキルが注目を集めてコレオグラフィー(振付)もより難易度が高く、かつ真似したくなる華があるものに仕上がっている。とくに『Three-Body』はそれが顕著で、現にTikTokなどで振りコピされる数も今までになく多かった。
もしほんとうに、アリーナクラスを埋めるダンス&ボーカルグループを、目指すのであったら。
「アリス、どう? 明日の朝もう一度ヤスと現地のPAさんとは話し合うけど、今回ボーカルラインを担当してくれたトップライナーのC¥ドラさんはアリスのボーカルをかなり買っているよ。もっと我を見せてくれたらとは言ってたけど、でも、あまり出会えない不思議な感覚があって、それは磨けば強い個性になるんじゃないかって」
個性! アリスは白くなってトイレに駆け込み、吐きそうになったが吐けなかった。強制嘔吐のツボをAIの指示に従い鍼で自己押しするか迷ったが、とりあえず三分ほど瞑想することでなんとか調子を取り戻し、何事もなかったかのように元の椅子に座ったところで「無理っすね」と言った。
「うん、わかりました。ゴメンね、アリスも、レンも、いろいろ無理させちゃってるね。この件については明日また報告するので、リハ前にもう一度集まってもらいます。みんなちゃんとグループLINEを見るように。じゃ、おやすみ」
全員で伊佐木マネの部屋を出たところでレンがアリスを呼び止め、「マジで迷惑かけてごめん。でもほんとにお世辞とかじゃなくて、アリスの声、ワイは好きだから、その安定感、ワイにはないものでほんといつもすごいと思ってる」と言った。
レンはこのグループにおいて珍しく、すこし性格がいい。ただちょっと厄介なぐらいに内向的で、頑固なだけで。
「おれのほうこそゴメン。力不足で、レンを助けてあげらんない」
「いや、鍼さえ打てればぜんぜん、歌えるんだよな。今度から海外遠征でも帯同してもらえるよう、事務所に交渉しようかな」
「……そうしたほうがいいかもね」
つづく