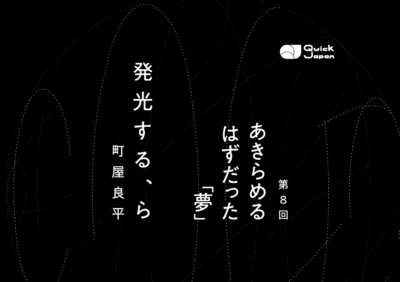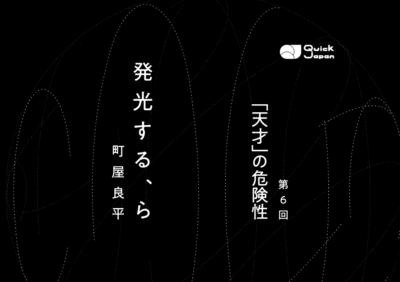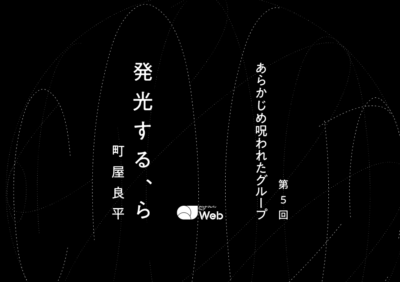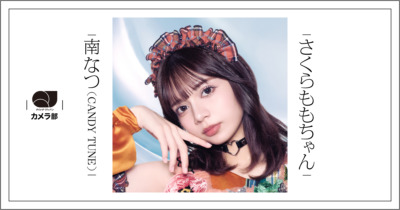テレビに出る機会もほとんどない弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。メンバーのアリスとキルトには、仲間に明かしていない秘密があった——。芥川賞作家が贈る、衝撃の「アイドル×SF」物語、開幕!
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
第1回 タイムスリップ
1
キルトがタイムスリップするとこをサトシに見られた。
バンコクで開催された『JAPAN FES 2024』の本番前で、すでにそれぞれの指先にアリスは黄、サトシは緑、キルトは紫のメンバーカラーの差し色が入ったネイルが塗られていて、アリスの双子の弟であるキルトがサトシの目の前で消えた。六月のバンコクに蒸しかえる熱もあいまって、サトシの瞳孔でキルトの爪に光る紫が陽炎のように揺れた。
サトシは、「ヒェ……」というような声を出した。
そのまま、五秒ほど黙った。驚いた表情なのだと思う。現代のひとの表情を読み間違うことはよくあるけれども、目をくりくりさせてその場に居合わせたアリスの方でもなく、消えたキルトの方でもなく、それよりやや奥の方を見ているような感じ。
これはたぶん、混じりっけなしに驚いている。
「違うんだ」
とアリスは言った。
キルトはまだタイムスリップ仮免中で、試験には合格しているはずだから決まった時間に本来の自分たちが生きているべき時代、つまり七十年後の未来に身体を置いていれば自動的に本免許に昇格されるはずだったのだが何度もそのタイミングを逃して、きょうの二十四時まで過去に身体を置いたままでは仮免失効となり三年間の謹慎処置がもたらされることになる予定だった。バンコクでのイベント直前にキルトはそのことを思い出し、「ヤベー! ちょっと行ってくる」と言って周囲もろくに確認しないまま未来に戻ったからサトシに見られた。
アリスはなるべく表情に内心のパニックを出さないよう努め、言った。
「これは、違くて、えーとごめんサトシ、誤解しないでほしいんだけど」
「えー! ちょっとー! 消えたんやけどー!」
サトシはいくぶん頓珍漢だと、七十年後からやってきたアリスにもすぐに分かる反応を上げた。
あとで聞いたところによると、サトシはその瞬間に「ドッキリ」だと思ったらしい。しかしアリキルの本来の戸籍がある七十年後にはすでに「ドッキリ」という習慣は廃れていて、一応タイムトラベル試験の過程で勉強していたからその存在は知っていたけれど、実際の「ドッキリ」の機微はあまりよく分かっていなくて、さっきサトシが言った「えー! ちょっとー! 消えたんやけどー!」が「ドッキリ」のリアクションとしてもかなり間違っているし、テレビに出る機会などほぼない弱小ボーイズグループであるわが「8koBrights」においてこんな大掛かりなドッキリが日常に紛れ込むことなんて本当にはありえなかった。
そして動揺するアリスがなんの対策も講じられないままあまつさえキルトはこの時代に戻ってくる瞬間までバッチリ、サトシに見られてしまったのだった。
「受かったよー」
キルトはそこにサトシが居ることを認めた。
そして「やべ」と言った。
そのころにはサトシはもうこれは「ドッキリ」ではないことは察したらしく、「え、これなにかの新しい演出? のお試し? とかそういう感じ?」と言った。
サトシはグループでサブリーダーのポジションにあり、ややマイペースで他のボーイズグループやメンバーへの関心が薄い、その割に周りがよく見えていて面倒見がいい。メンバーの平均が二十一歳という若年層にあるなか、まだしもしっかりしたところがあって実質リーダーのような、裏回しのような立ち回りをすることが多かった。
だから過去人に未来人ということがバレるなら、他のメンバーよりは比較的まだマシといえた。
「アリス! キルト! サトシ! どこ!」
メインマネージャーである伊佐木の声が響いた。まもなく本番だ。三人は顔を見合わせたあと、キルトが咄嗟に「サトシ、あとで説明する」と言い背中をぽんと叩いた。そのときには既に肚(はら)を決めていたらしく、本当のことを人に話すときのための準備信号をスマホと身体接触を通して同時に送っていたから、これで本格的にアリスはキルトに激怒することになる。
タイムスリップの現場を見られた、個室トイレで行えばまず問題ないはずの行為をその移動を面倒くさがって、人に見られかねない場所でそれをした粗忽さ以上に、簡単に過去人を懐柔しようとする、キルトの無計画さと素朴さによりムカついてしまった。
うまく人に頼れない、甘えることができないメンバーが集まって結成されたグループ「8koBrights」通称「エコブラ」においてもキルトが比較的おおらかで、愛嬌のあるキャラとして認知されていることへの嫉妬もあったかもしれない。未来において「個性」が人に認められることはありえず、じっさいに過去に来るまでアリキルのふたりは自分たちの「性格」がどのようなものかすらよく分かっていなかった。結果アリスが「クールなボスキャラ」でキルトが「奔放な努力家」としてファンに認知されると、お互いがお互いのキャラを羨ましがって、ときどき身体情報を入れ換えて数日それを楽しむなど、ギリギリ遵法だが悪趣味ではある未来人行為を楽しんだりもしていた。
メンバーと合流し、サトシが気が気でないのは明らかだったが、なんとかデビュー曲の「Time9ake」を含む五曲を披露した。MCも含めて出来は普通かそれ以下といったところで、ポジショニングやダンスやボーカルのミスが散見された。これなら完全生歌への拘(こだわ)りをもう止めればいいとSNSでは時々いわれていたが、生歌はグループ結成時にメンバー随一の実力派であるレンが加入する条件であったため、そのルールを崩すわけにはいかなかった。
本番直後の楽屋でサトシはパフォーマンス直後の上気したテンションで、「で、さっきの! なにのなんなの?」とキルトとアリスを外に連れ出した。放置した汗が日焼け止めとメイクに濁った色でポタポタ顎先から垂れ落ちている。キルトが「まあまあ、これでも使いなよ」と美容液を含んだトナーパッドを渡すと、ガサツに肌を擦り、サトシはキルトを睨んだ。
*
外に出て建物の裏に入り人目を避けた。六月とはいえ、バンコクは暑かった。七十年後にはすでにスーツクーラー(インナータイプが主流)で勝手に温度調節してくれるから、そうそう浴びないアジアの熱風を双子はあらためて嗅ぐ。先ほどまではこれから三日間予定されているステージの初日に緊張していたから、ろくにタイの空気を楽しめていなかった。あまり良い出来でなかったがなんとか初日のパフォーマンスを終えた解放感でいっぱいになったキルトは「アリスから説明してあげれば」と言い、首にかけたタオルで顎先から垂れ落ちる汗を拭った。
「なんで!」
「だって、こういう説明兄貴のほうがうまいし」
「だが、信頼のアクションを送ったのはお前のほうだ」
「あ! そうだった!」
「信頼のアクション?」
「しまったな、すっかり誤魔化す気満々だったのに、本番前に本免が取れたことについエモくなってしまい、ついサトシを信頼してしまったのだった!」
サトシは自分の発した疑問が無視され勝手に進んでいく会話に完全にムカついた。
七十年後の法律にはタイムトラベラーは原則そのことを過去人に秘して活動すべしという建前こそあるが、実際はそれを話すことじたいはそれほどタブーとされていない。タイムトラベラ―と接触した多くの過去人は記憶を消されることになるからだ。だが、そのことを告白した人間がだれか一人でもほかの過去人とその事実を共有した場合、即免許失効となり再取得はきわめて困難となる。
キルトは本番前に、これから真剣な話をすることを言語外信号によってあらかじめ報せ、自分の話を信じやすくする波動をサトシに送った。ほんらいは未来の子どもに使うもので、不当に傷つくことを防ぐためのコミュニケーションツールに過ぎない製品であり、キルトじしんそれを使ったのは生まれて初めてのことだった。
ようするにキルトは過去における「信頼」という、七十年後にもいちおうその概念はあるがこの時代とはかなりニュアンスが変わってしまっている、そのノスタルジーを試したかった、それだけなのだとアリスにははっきり分かって呆れた。
「サトシ。おれの言うことを信じてくれるよな。じつはさあ、うすうす気づいてた? おれとアリスはさ、タイムトラベラ―なのよ。七十年後の未来からきた双子ちゃんってワケ。ごめんね、隠してて」
キルトは言った。
「は?」
サトシは鼻で笑った。鼻で笑うって、こういうことなんだな~、とこの時代に来て初めてアリスは思った。フフッーっと、鼻だけの息が嘲笑の表情とともにアジアの風と混ざった。
「じゃなくて。マジだから。これ。マジマジのマジだから」
そうしてキルトはサトシの首から腕を回し、七十年後にはタブーですらあるスキンシップを図った。「信頼の紫」を送ってからすでに三時間以上たってしまっているし、実際この信号は過去人に効果があるのか。いちおう時代に左右されないという研究結果は出ているが、未来人はみな、なんとなくあやしいものと考えている。つねに偽科学あつかいされているグレーな製品ではあるのだ。だがスキンシップを通してふたたびキルトは「友愛の橙」を試してみた。するとサトシは言った。
「マ?」
時が止まったかのようだった。
そこへスフゥーッとひとすじ熱い風が吹いて三人の汗がより噴き出た。
「マ?」
キルトはスマホで「マ 単独過去語 二〇二〇年代」と検索した。そこには「死。マジの略。多くは疑問形として「マ?」と使われる。マジですか? 真面目に言っているのですか?の意。主に二〇二一年~二〇二二年ごろに流通」とあった。検索結果冒頭の「死」というのは「死語」のことで、実際七十年後ではほとんど聞かれない言葉だった。でも二〇二四年のこの時代にしてすでに死語じゃん。
だが過去語マニアであるアリスは内心きわめて興奮していた。サトシは大阪出身である。裏でメンバーといるときにはたまにイントネーションが「西より」になることはあるが、おおむね関東語を喋る。しかしいまの「マ?」は関東で言われる「マ?」と微妙にニュアンスが違い、「マジ?」のマと「ホンマ?」のマの両方を兼ねたサトシならではのニュアンスだったからかなりレア! 厳密には過去語というより「サトシ語よりの過去語」といった印象だ。
「おう。マ! めちゃマ! 超マ! だね!」
キルトが明らかに間違った使用法で言うとアリスは一瞬で興奮がさめてムカついた。
実際、下手に疑われたままでいると過去人のあいだで逆に噂になり、「危ないヤツ」として信じてもらえないまま未来から来たのでは?という疑念が笑い話として共有され、その結果免許失効するケースが意外に多いから、決定的な場面を見られ疑われてしまった場合はまず信じてもらおうとするのがセオリーではあった。冗談でも未来人であるという噂が立つだけでアウトなのだ。
だがエコブラはもともと仲の悪いグループだし、とくにキルトはダンスもボーカルも下手な上にメンバーへのダメ出しは積極的に行うという、未来人のよくない部分を濃く煮詰めたような存在だったから明白に嫌われていた。七十年分の時代の蓄積とテクノロジーの進化により、客観的事実を把握するのには長けていたが、それを自分で体現できるわけではないのだから、とくに個性の強いボーカリストであるシンイチには蛇蝎(だかつ)のごとく嫌われていた。
「わかった。絶対にだれにも言わない。てか言えない」
サトシはそう約束した。
あまりにも容易く信じた。サトシは「友愛の橙」と相性のよい身体らしく、いっぽう「信頼の紫」はそれほど利かなかった。こうした情緒補正シグナルの効果はもともとその者の素養に作用されるといわれ、ゼロのものをイチにすることはできないが、イチのものを百にできる可能性がある。サトシは簡単に人を信頼しない(というかキルトへの信頼はゼロである)が友愛にポテンシャルはある(キルトへの友愛感情はゼロではない)、そんな個体であることがアリスにはよく伝わった。
サトシはダンスもボーカルも下手なぶん誰よりも多く練習しているのがキルトだということを比較的評価しているメンバーだったからまだ見られてマシなメンバーと言えるが、もう二度とこんな過ちを犯してほしくない。アリスはホテルに戻ったらきちんとキルトに「バレてしまった過去人リスト」を未来に提出させ、サトシが家族を含めた他人に洩らさないための対策を二〇〇〇文字程度にまとめて提出させることを決意した。
「てか、未来ではどうなってるの? 過去に来てるときは。実際、本当の? ふたりの身体は?」
「寝てる。タイムトラベルセンターのカプセルで栄養点滴を受けながらスヤスヤ寝ているよ」
「へえ、すげえなあ。やっぱ七十年もたつと、過去に行けるようになるんだな」
「うん。未来はまだムリだけどね。本当はもう行けるんだっていう陰謀論は根強いけど」「
「なるほどな。じゃあ戦国時代の歴史の研究とかは、けっこう進んでるの?」
「じょじょにはね。けど過去へさかのぼる範囲は五十年単位で試験がとんでもなくむずくなっているから、実際には「昭和時代」以前に行ける人はそうとう天才的な研究者、それも専門的な分野に限った人しか行けなくて、そうするとどれだけ良いテキストが書けて動画や写真での記録が増えたとて、どうしてもその人の主観を信じる以外ないから、エビデンスに乏しいってことで正確な研究として認められるのは、ふつうに過去の文献を読み解くよりかえって難しいと言われているよ」
「へえ? なんかむずいけど、そんな簡単じゃないってわけね」
「うん。動画や写真などのメディアを捏造することって七十年後にはもうあまりに容易いことだから、AIのアシストを借りたとてかえってテキスト、つまり文章のほうがまだ参照しやすいっていうのが、皮肉なことだけどな。なんなら『昭和時代』とかのテキストはまだオールヒューマンメイドなわけだろう? 証拠としてはタイムスリップよりまだぜんぜん、重んじられているんだよ」
サトシはいまキルトが口にした「昭和時代」の発音で、時折り感じていたアリキルのイントネーションの違和感にすべて合点がいった。まるで自分たちが言う「平安時代」「戦国時代」みたいに「昭和時代」を発音している、七十年分の意識のズレにようやく気づいたというわけだった。
「じゃあ、七十年後でもダンスとかボーカルとかをめっちゃ簡単に上達させる発明とかはないってこと?」
「え? それは、あるよ」
「じゃあなんで……、あ、や、ゴメン、なんでも……」
そこでサトシは口をつぐんだ。
「うん? 言ってみ? なんで? ご遠慮なく。じゃあなんで、おれたち双子は? わかってるから。さあどうぞ」
「……なんでアリキルは、揃ってダンスがクソ下手なの?」
「そこまで言う?」
キルトは煽ったくせに傷ついていた。心拍や体温をもとに判定する身体アシストがカウンセリング要請を出している。それを三時間後に遅延させて、キルトは応えた。
「この数十年もうずっと身体レトロブームだから。そういうテクノロジーアシストの恩恵を受けてパフォーマンスを上げること自体が忌避される傾向があるんだけど、でももう明確に本人の身体のポテンシャルだけでするパフォーマンスと、テクノロジーアシストを頼ってするパフォーマンスを、はっきり区別することはできない。おれたちはあらゆる側面でもうテクノロジーアシストの恩恵を受けながら生きているから。たとえばおれだって、そのとき練習で追い込めばきちんと上達できる体調か、それとも却って疲労があって怪我するリスクが高い時期かっていう判定は、身体AIに頼ってるワケだし。だからスポーツとかはもう、趣味娯楽でするそれとテクノロジーアシストをフルに活用するプロフェッショナルとではおなじ競技でもまったく別のものとして扱われるし、きほんプロとアマチュアの境界がはっきりした世の中になった。だからこそ、おれもアリスもできるだけテクノロジーアシストの恩恵を受けないで自分の力だけでパフォーマンスする。それがエコブラの一員としての最低限の、マナーだと思ってるんだ」
サトシは思った。たしかにアリキルはダンスもボーカルも普通か普通より下。だけど。
実力は普通以下でも、未来人でも、こいつらはいまのエコブラに必要な、大事なメンバーだ。
「わかった。なんかあったら、こっそり相談してくれ」
サトシがそう言い残して楽屋に戻ると、キルトは「ほら」みたいな顔をしてアリスを見た。
「なんとかなったじゃん」
「キルトはサトシの信頼は得たかもしれないが、おれの信頼は失ったね」
「「信頼」! なんてノスタルジックな響き」
キルトは今日のステージで七箇所は振りを間違えていたのに、なにやら上機嫌で屋台のパッタイを購入しにいった。
つづく