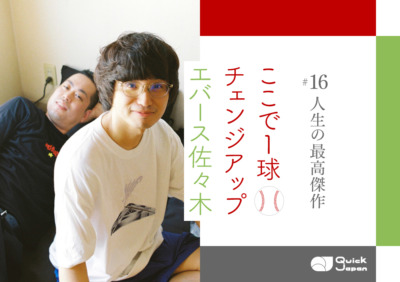「社会」を描かないものとして長らく揶揄の対象となってきた〈セカイ系〉。しかし、その誕生が2000年代初頭であったことを思い返すと、インターネットの普及によって「世界」の意味するところにドラスティックな変化が起きたことを鋭敏に捉えた想像力でもあったのではないか。
〈セカイ系〉をキーワードにアニメ・音楽・アート・哲学などを横断して論じる評論アンソロジー『ferne』が話題を呼んだ文筆家・北出栞の初著作刊行を記念し、冒頭から第一章までを無料公開。
はじめに

2020年代の始まりに、「世界の終わり」のような静けさをもたらした新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、結局のところ世界を終わらせなかった。あの日々が残したものは何だったのか。自宅にこもり続ける日々、たまの外出で見上げた青空はいつになく澄んでいた気がした。ウイルスに右往左往しているのは人類だけで、鳥は自由に空を飛んでいたのだ。あるいは街頭カメラが伝える、人っ子ひとりいない街の風景。世の中の混乱を思うと大きな声では言えなかったが、そんな「どこでもない」「誰もいない」イメージの群れは、スマートフォンを通じて常にソーシャル・ネットワークにつながれ、情報の濁流に流されながら「あなたは何者か?」と問われ続ける現代人に、安らぎをもたらすものだったように思えるのだ。
〈セカイ系〉という言葉がある。「君と僕」の間の小さな問題を、社会や組織などの描写を挟まず、「世界の終わり」のような大きな問題に直結して描くような想像力、などと説明されることが多いこの言葉は、世紀末ブームの熱が冷めやらぬ2000年代初頭に、アニメや漫画を評する言葉として、ある個人運営のウェブサイトから生まれた。当初は揶揄的な意味が先行していたそうだが、そのような意味を持った言葉が、作品を評する言葉として影響力を持ったということ自体が、ある意味でうらやましくも思える。
作品がひとつの「世界」を作るものなら、「世界の終わり」と無関係な作品などない。どんなに社会派を謳った作品でも、「終わりがある」ということが「作品」の条件だからだ。しかしソーシャルメディアが普及した現代においては、社会派だろうがファンタジーだろうが、作品は発表されるや否や、終わりなき「解釈」と「考察」のゲームに巻き込まれてしまう。個人がメディアを持ち、インターネットを通じて世界に発信できるという希望と、作品という「世界の終わり」の領域が担保されていたことが、今にして思えば奇跡的に重なっていたのが〈セカイ系〉という言葉が生まれた時代だったのだ。
人類史に必ずや刻まれるだろう疫病の蔓延に加え、2020年代に入ってから途絶えることのない、戦争・災害・気候変動などのニュース。それらを横目にぼんやりと蔓延する「世界の終わり」のムードは、ソーシャルメディアに吐き出される無数の言葉たちによって増幅される。しかし世界は結局のところ終わらないのである。しかも、本来同時代的なムードを切り離して「世界」を成立させることができるはずの作品という単位すら、リアルタイムのコミュニケーションの中に溶け出してしまう。これが「世界の終わり」を取り巻く現状の問題点だ。
まるで「世界の終わり」だと思わずつぶやきたくなる時代を前にして、まずは沈黙のうちに自分の感情と向き合えないか。〈セカイ系〉という言葉は、私たちにそんな問いを呼び起こさせる性質があるように感じる。すべてを包み込む大文字の「世界」があることなど信じられない、しかし「世界」について考えることを諦めたくない。ならばまずは「君と僕」という最小単位を、「セカイ」を考えることから始めよう……そんないじらしさが感じられるのだ。
そして、ただ沈黙するだけでなく、さまざまな問題を抱えた現代の情報環境にあってなお「作品=世界」を成立させるための思考も。〈セカイ系〉という言葉が生まれた時代は、一般家庭にコンピュータやインターネットが普及し、個人で映像や音楽を作り、発表することが容易になった時代でもある。〈セカイ系〉について考えることを通じて、デジタルテクノロジーがかつて人々に抱かせた、個人の「セカイ」が「世界」につながるかもしれないという純粋な希望に、出会い直すこともできるのではないか。
以下、本書の構成を示す。
1章では導入として、〈セカイ系〉について過去の議論を振り返りつつ、デジタルテクノロジーと「作品」との関係という観点から再整理する。これまで〈セカイ系〉の文脈では語られてこなかった作品にも光を当て、2020年代の現在、このテーマを扱うことの意味と意義を提示する。
2章・3章・4章では、〈セカイ系〉の代表的作品と見なされる作品を手がけた作家のうち、2020年代に入ってなおピークを更新し続けている作家として庵野秀明、新海誠、麻枝准の三人に光を当てる。デジタルテクノロジーとともに「作る」とは何か、それぞれの作品に込められたテーマ性も掘り下げつつ考えていく。
5章・6章・7章では、動画投稿プラットフォーム/ソーシャルメディアの登場以降、相対的に「作家」の存在感が小さくなっている現実を受け止めつつ、消費するだけのポジションに収まらず「作る」立場に立つにはどのような思考が必要か検討する。そこで問題になるのは、デジタル時代における「主体性」のあり方である。
8章ではエピローグとして、これまで追ってきたデジタルテクノロジーとともに「作る」ことの本質は何かという主題と、その過程で浮かび上がってきたスマートフォン/ソーシャルメディア時代の「切なさ」のありかという主題を統合し、いずれ来る本当の「世界の終わり」を待ち受ける姿勢としての「祈り」について考察する。
私たちの身体を取り巻く空気のようなものとしてではなく、雲の切れ間から差し込む光芒のように、「ここではない、どこか」から到来するものとしての「世界の終わり」。流れ続けるタイムラインに切れ目を入れ、逃げ場のない「今、ここ」から身を切り離す……「セカイ」のイメージを捉えるために、現在に至るまでの二十年間をたどり直していきたい。
1章 セカイは今、どこにあるのか
〈セカイ系〉とは何か
本書は「世界の終わり」をめぐる想像力のありかを、デジタルテクノロジーの進展との関わり合いにおいて探ることを目的とする。そのために注目するのが〈セカイ系〉という言葉だ。〈セカイ系〉とは何か。その誕生から使われ方の変遷まで、多くの資料をもとに丹念に追った随一の著作である、前島賢『セカイ系とは何か*1』の記述を参考にまずは整理したい。同書によれば、『新世紀エヴァンゲリオン』(1995、以下『エヴァ』)の後を追うように発表された「エヴァっぽい」作品群に対して、個人運営のテキストサイト「ぷるにえブックマーク」の管理人の主観に基づき、揶揄的な意味を込めて使われたのが発端とされる。その後、言葉だけがひとり歩きし、「主人公と(たいていの場合は)その恋愛相手とのあいだの小さな人間関係を、社会や国家のような中間項の描写を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」といった大きな問題に直結させる想像力*2」といった定義が与えられ、サブカルチャー評論の世界でも取り上げられるようになった。その当時に具体例として挙げられ、今なお代表的な作品として名前が挙げられることが多いのが、秋山瑞人の小説(ライトノベル)『イリヤの空、UFOの夏』(2001)、高橋しんの漫画『最終兵器彼女』(2000)、そして新海誠の短編アニメーション『ほしのこえ』(2002)の三作品である。
当時の時代背景に目を向けると、1995年には阪神淡路大震災、オウム真理教による一連の事件があった。また、いわゆる世紀末であったために、「ノストラダムスの大予言」に代表される終末思想がブームとなった。西暦のケタ数が一気に変わることによるシステムダウンが懸念された「2000年問題」というものもあった。
〈セカイ系〉について評論家が問題視したのは、「小さな問題」と「大きな問題」の間に本来あるはずの「社会や組織などの中間領域」が抜け落ちており、それゆえに「複雑な現実」が描けていないという点だった。あるいは男性主人公の視点で描かれる作品の、「君」に当たるヒロインだけが「世界の終わり」に対峙させられる──つまり「僕」に当たる主人公は傍観者の位置にとどまる──構造を取り出し、男性中心社会の根本的な搾取構造を、センチメンタルに美化しているのではないかという点だった。
しかし、そもそも〈セカイ系〉を代表するとされる三作品のいずれもが、こうした条件を満たすわけではないと『セカイ系とは何か』で論証されている。とりわけ『イリヤの空、UFOの夏』については、作者である秋山がもともと伝統的なSFファンコミュニティの期待を集めながらデビューした作家である点や、「あえて主人公の少年から見える範囲の世界に絞った」という旨のインタビューでの発言、そもそも作品の中核をなすボーイ・ミーツ・ガールの構造自体が、戦闘機パイロットであるヒロインに「守るべき存在」としての主人公を与える軍部の策略だったという作中での種明かしなどを踏まえ、意識的に「エヴァっぽい」作品を目指して書かれた、言わばメタ〈セカイ系〉と言える作品であることが指摘されている。
以上のことから言えるのは、〈セカイ系〉とはそのものに定義すべき内実があるのではなく、むしろその空虚さゆえに周りを旋回する形で新たな作品や評論が生まれるという、ある種の「文芸運動*3」であったということである。
「距離」と「世界」に関する逆接
〈セカイ系〉は世界=セカイという語感のキャッチーさもあって、社会現象を論じる際にネガティブな文脈で使われることもある。たとえば、2021年に公開されたあるウェブ記事の中で、現代の若者はソーシャルメディアの意見を漠然と「社会」の総意として捉え、それを過剰に恐れる傾向があると分析する文脈でこの言葉が使われた。*4
しかし、もともと〈セカイ系〉はあくまで作品の特徴を抽出したものである。記事を読んで義憤に駆られたのであろう、「ぷるにえブックマーク」の元管理人はソーシャルメディア上に現れ、以下のような「再定義」を行っている。
「セカイ系、という言葉は、今でいうところの「あるある」です。アニメやマンガやゲームの物語や演出によくある類型のひとつ。少年と少女が出会うラブロマンスに世界の存亡が掛かるほどのスケールの大きな出来事が関係するというアレ」
「理解が難しいのは、セカイ系というのが単純に話のジャンルを指してるだけではないということです。テーマでありストーリーでありキャラであり設定であり、そういった諸々から醸し出される独特の「っぽさ」がセカイ系*5」
揶揄的な意味を含んでいたとはいえ、実際に作品を見た上で「っぽさ」を抽出していたのと、その言葉自体が単なる揶揄になってしまうのとでは大違いである。言葉は生き物とは言うが、すでにWikipediaにも項目が作られ、そこに具体例として並んでいる作品名もある以上、その内容には触れない形で〈セカイ系〉という言葉だけが揶揄的に使われ続けることは、各作品の作り手たちに対する敬意を失わせることを助長しかねない。筆者個人としては、「ぷるにえブックマーク」元管理人の憤りはよくわかる。
ところで、件の記事は現代に広まる映像作品の「倍速視聴」というスタイルの是非を問う連載の一部だった。本書を通じて述べていくことになるが、筆者の立場はそうしたスタイルが選択される背景─ソーシャルメディアの普及を背景にして、作品がコミュニケーションの「ネタ」としてインスタントに消費されること─には批判的な一方、「倍速視聴ができる」ということ自体に関しては、どちらかと言えば肯定的というものである。受け手が恣意的に編集を加えられるということは、デジタルテクノロジーを介した作品経験の基本的な条件だからだ。
わざわざこのような註釈を入れたのは、それが本書の主旨にもつながってくる話だからである。そう、筆者は〈セカイ系〉の「っぽさ」を、当時のデジタルテクノロジーの中に宿っていた独特の感覚を指すものだと定義したいのである。
〈セカイ系〉という言葉が生まれた1990年代末から2000年代初頭は、PCやインターネットが一般家庭に大きく普及した時期でもあった。ユーザーフレンドリーなOSとしてMicrosoftのWindows 95・98が各種PCに搭載され、カラフルで丸みを帯びた筐体のデザインがクリエイティブ職の人気を博したAppleのiMacが発売されたのも1998年だ。また、ADSL・光回線の普及が急速に進み、1999年には携帯電話(ガラケー)からインターネットにアクセスできるNTTドコモのサービス・iモードも開始した。
この観点から言って最も重要な〈セカイ系〉作品は、その成立自体がデジタルテクノロジーの恩恵抜きにしてはあり得なかった『ほしのこえ』だろう。本作は新海誠による個人制作の短編アニメーション作品だが、個人でアニメを作り、広く届けるということ自体が、制作ツールとしてのPCと、宣伝ツールとしてのウェブサイトなしには不可能だった。「「世界」っていう言葉がある。私は中学の頃まで、「世界」っていうのはケータイの電波が届く場所なんだって、漠然と思っていた。」という冒頭に置かれたモノローグは、この作品のアイデンティティが当時のデジタルテクノロジーとともにあることを端的に表している。
批評家の藤田直哉は『ほしのこえ』と同時代のデジタルテクノロジーとの共振について、以下のように整理している。
コンピュータやインターネットに象徴される、科学技術を得て、色々なものは拡大した。それは、ヒロインである長峰美加子が宇宙に乗り出していくことに象徴される。未知の、未開の、無限の領域が目の前に拓かれて、そのフロンティアに乗り出していくことができる。しかしそれは、キャッチコピー「たぶん、宇宙と地上にひきさかれる恋人の、最初の世代だ」の通り、二人の距離を開かせ、孤独と切望を高まらせていくことに帰結してしまう。*6
テクノロジーは「意識の拡大」をもたらすのではなく、人間と人間の間の距離(≒宇宙、セカイ、サイバースペース)を広げ、つながりを薄くし(≒ケータイのメールの頻度が減っていく)、孤独や寂しさを増大させるものではなかったか〔…〕実際、この頃のインターネットは、「世界とつながれる」と言われていたものの、画面は色の数も少なく、デザインも貧相で、ろくに動きもなく、音声や動画を見る機会もほとんどないようなテクストばかりの世界であり、人恋しさの飢餓感が募るものであった。*7
離れた場所にいる相手の言葉を「近く」に引き寄せるにもかかわらず、心理的な距離はかえって「遠く」なってしまったように感じられる……〈セカイ系〉に今目を向けることの意味は、デジタルテクノロジーが本来的に備えていたはずの、「距離」と「世界」に関する逆接を再発見させてくれるところにある。現在の高速化したインターネットは「近い」どころか身体を取り巻くものになっており、私たちはタッチパネル・インターフェースを介して文字通り情報に触れながら、リアルタイムに解像度の高い世界の情報を受け取ることに疲弊している。「距離」という概念自体が消失してしまっていることが、そこでは問題となっているのだ。
〈セカイ系〉と呼ばれる作品には確かに「社会や組織」に関する記述に不足もあるが、もしそこに紙幅が割かれていたなら、その部分だけを現代と重ね合わせるような読み方に縛られてしまっていただろう(コロナ禍でカミュの『ペスト』が読まれたように)。物語的にはあまりにも切り詰められた、「君と僕」を中心とした構造しか持たないからこそ、その二者関係を媒介するデジタルテクノロジーが、現代との差分として際立ってくるのだ。
後編へつづく
*1 2010年、SBクリエイティブより『セカイ系とは何か──ポスト・エヴァのオタク史』として刊行。その後2014年に、全編を改稿し、補論を含む「文庫版あとがき」を収録した文庫版が星海社より刊行された。本書では基本的に文庫版を参照している。
*2 東浩紀『セカイからもっと近くに──現実から切り離された文学の諸問題』(東京創元社、2013年)より。『セカイ系とは何か』の中では評論家による〈セカイ系〉定義の代表的なものとして、2004年に東の主導により刊行された同人誌『美少女ゲームの臨界点』に記述された定義が紹介されているが、本書ではその東自身によるアップデート版としてこちらを参照する。
*3 『セカイ系とは何か』文庫版の版元による紹介文より。https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000025641(最終閲覧:2024年3月12日)
*4 稲田豊史「「インターネット=社会」若者の間で広がる「セカイ系」の世界観」現代ビジネスhttps://gendai.media/articles/-/84364(最終閲覧:2024年3月12日)。同記事を含む連載は後に『映画を早送りで観る人たち─ファスト映画・ネタバレ コンテンツ消費の現在形』(光文社新書、2022年)にまとめられた。
*5 以下のまとめ(筆者作成)を参照。「テキストサイト「ぷるにえブックマーク」元管理人による〈セカイ系〉の再定義」Togtter https://togetter.com/li/2303729(最終閲覧:2024年3月12日)
*6 藤田直哉『新海誠論』(作品社、2022年)p.32。ただし、同書は新海のキャリアを「セカイ期(引用部分)」「古典期」「世界期」の三つに区分し、単線的な「成熟」の物語を描いていることは付記しておく。本書はこうした見方に対して、言わばそこで言う「セカイ期」のポテンシャルを独立したものとして取り出し、そのポジティブな可能性を解き放つことを目指すものである。
*7 同書、p.33