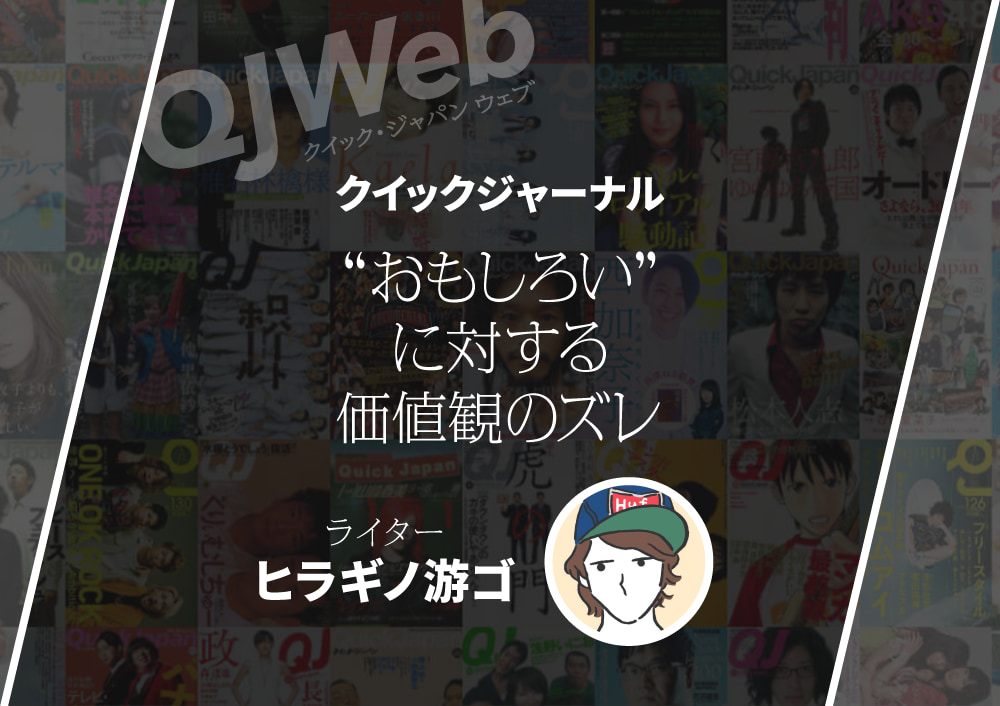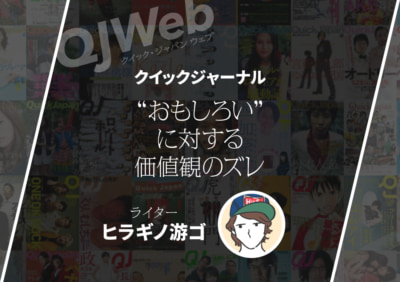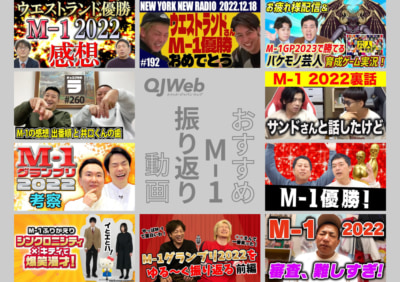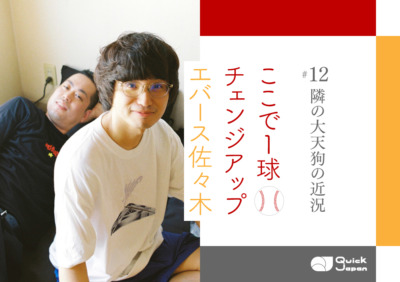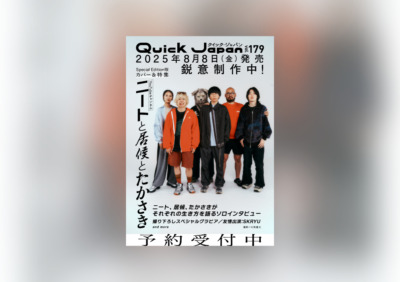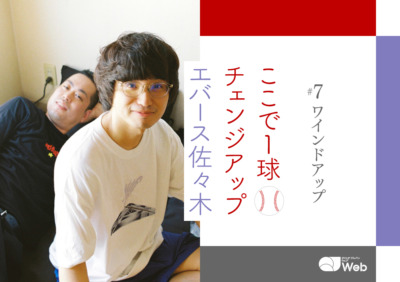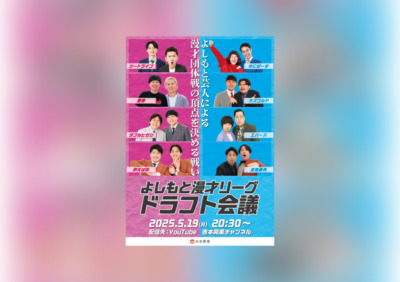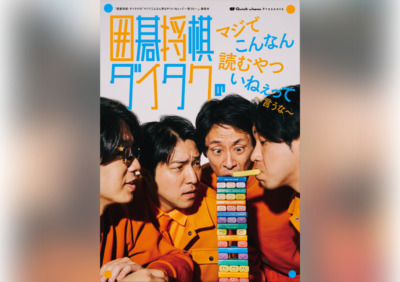『M-1グランプリ2022』はウエストランドが優勝。その「悪口漫才」と称されるネタに対して、あるいはそういったネタに高得点を与える審査基準に対して、ソーシャルメディア上では数多くの批難の声が噴出した。
しかし、同業者からは「人を傷つけるお笑い最高!!」「時代変われ!!」と、“窮屈な時代”への“反撃”の契機として歓迎する声も上がった。
こうした反応からはひとつの根深い誤解が窺い知れる。批難された側は「おもしろいのにケチをつけられた」という認識でいるけれど、批難はそれが「おもしろくない」から起こっている、という話だ。
ずっと「おもしろくない」って言ってる
ボケが弱い、ツッコミにキレがない、しゃべりのテンポが悪い、聞き取りにくい、笑いどころがわざとらしい、たとえがわかりにくい。そういったさまざまな要因が「おもしろくない」という評価に帰結する。同じことだ。ネタの前提になっている価値観がイヤ過ぎると笑えない、おもしろくない。それだけの話なのに、どうにもそれを認めようとしない。
まるで「内心おもしろいと思ってるくせに善人ぶって叩いてる」ことにしようとバイアスをかけるように。そういう価値観が覇権的な世界であってくれと祈るように。価値観がまともだと“攻めて”ないと評され、反面コンプライアンスを軽視することが“トガってる”“エッジが効いてる”と褒め讃えられる。人間が集まって何かやろうとするとこうなりがちだ。内向きに閉じた世界で自縄自縛に陥る。
方々にヘイトを喧伝する類の芸風が倫理的に褒められたものじゃない、不適切であり得ることは言うまでもない。それは大前提として、それゆえにおもしろくもないよね、というのが世の批難の大筋といえるけれど、審査員たち上の世代の芸人をはじめとして、演者の多くは旧来的な価値観を温存したいようだ。
このズレがお笑いシーンを追う上で心底だるい。本当に分厚い障壁になっている。ただ笑いたいだけなのに気を抜いて見ていられない。いつどんな角度から石が飛んでくるかわからない。日常生活でなるべく距離を取っている見ちゃいられないような惨めな価値観がジョークとして開陳される。
「時代変われ!!」という言葉の土台にある認識では、今はどんな時代なのだろうか。近年ようやくさまざまなエンタメについて最低限の人権意識が問われるようになり、社会が倫理的な成熟に向かってきてはいるものの、全体で見ればまったく優勢とはいえない。ところが、そういった気運を冷笑してみせる人々には、自分たちこそが世間から追い込まれ不当な扱いを受けているという自己像に基づく被害者意識が滲み出ている。
コンプライアンスが笑いをじゃましているんじゃなく、コンプライアンス程度もクリアできないほどに激ヤバな価値観が笑いをじゃましている、という発想に至らない。それどころか、コンプライアンス(彼らはおおむね「コンプラ」と略して言う)を共通の大敵として憎悪をアジテーションする。彼らにとってコンプライアンスは「オレたちの遊び場を盛り下がらすけったいな足枷」程度のものなのかもしれない。となると、そのコンプライアンスの根底にある“本題”、つまり人権意識やジェンダー論、反差別のロジックなどに話が進展するべくもない。
そういったシーンの風潮にうんざりしながらもお笑いというカルチャー自体は嫌いになり切れず、血の涙を流しながらライブに通い、配信チケットを買っている人が大勢いる。きっと演者の多くが想定しているよりは格段にたくさんいる。
カウンターという“約束事”
コンプライアンスという概念で大ざっぱに括られることの中でも、特にお笑いの世界において根が深いのが、ヘイトの向け先の問題だ。またその手前で注意すべきこととして、「人を傷つけるお笑い」「誰も傷つけないお笑い」というのは一種のバズワードであり、これを軸に思考を展開しようとすると本質からズレていくように思う。お笑いに限らず言葉はいつだって誰かを傷つけ得るし、その作用を効果的に利用することもしてきた。
日本的な「お笑い」よりももっと大きな括りで見た「興行としての笑い」でいえば、スタンダップコメディはその傷つける作用の効果的な利用を高度にシステム化している。
たとえば黒人コメディアンのネタにポピュラーなパターンとして、白人では思い至らないような社会の無自覚な差別構造を皮肉るというものがある。女性コメディアンでいえば、高圧的な男の振る舞いをデフォルメしてあるあるネタに昇華する。
それを受けて、「黒人」や「女性」はもちろん、ネタにされた「白人」や「男性」も笑う。アカデミー賞授賞式では、コメディアンが列席のセレブリティたちをネタに痛烈なジョークを飛ばすのが慣例になっているけれど、ここでもやはりセレブリティたち自身が笑う。笑う余裕があること、甘受する器のあることがセレブリティ自身にとってある種のステータスであり、人間的な成熟の証でもあるのだ。
こういった「興行としての笑い」の鑑賞体験、ネタを介したコミュニケーションにおいて、笑いは痛快な異議申し立てとして機能する。
場所をヨーロッパに移し時代を中世に遡れば、ジェスター(宮廷道化師)はもっとわかりやすく象徴的だ。いわゆるピエロの一種で、王に仕え、話芸や曲芸で宮廷の人々を楽しませることを生業とした。ただ彼らにはもうひとつ重大な役割がある。冗談めかして伝えることによって、圧倒的な権力者である王に唯一意見できる存在として、宮廷内の力学を左右する影の実力者でもあったのだ。
「白人」や「男性」「金持ち」「権力者」をネタにする、あえていえば「人を傷つける」これらのネタが笑いとして成立するのは、マイノリティからマジョリティへのカウンターだからだ。逆は「弱い者いじめ」あるいは「死体蹴り」と同じ構造になってしまい、引かれてしまう。笑えたものではない。
……というのが笑いのセオリーのはずなのだけれど、こと日本においては、地下の小箱から賞レースの決勝ステージまで、ミソジニー(女性蔑視)的なネタがついて回る。“ヘイトの向け先の問題”というのはこのことだ。人を傷つける要素があるにしても、「マイノリティからマジョリティへのカウンターであればおもしろいよね」という約束事を形成した上で行われるはずだった。それが逆転、破綻してしまっている。
となると、やはり「おもしろくない」のだ。本来的な笑いのセオリーから外れているわけなのだから。ミソジニー的なネタで笑えてしまうとしたら、日本社会ではそうした上から下へのヘイトが「おもしろい」ものだという稚拙な合意形成が蓄積し、倫理的に未成熟な土壌が強烈に確立してきてしまっているからだ。そして恐ろしいのが、こうした状況を誰より歓迎しているのが、ほかでもない業界のトップランナーたち自身だということ。
そろそろもう少しちゃんと約束事を更新したい。個々人の好みの範疇の手前の話として、倫理的にどういうものなら気持ちよく笑えるのか、あるいはさすがに笑えないのかという合意形成を社会全体で仕切り直していきたい。
もちろん明確に白黒つけられることばかりではない。線引きは常にグラデーションだ。ただ、その線の大まかな位置はもうとっくに大きく移り変わっている。たくさんの観衆がすでに新しい線の上で待っている。演者だってもう何人かこっちに来てくれてもいいじゃないか。常にその線の位置を見極めてフレッシュなネタを作る力が、芸人の腕というやつなんじゃないだろうか。