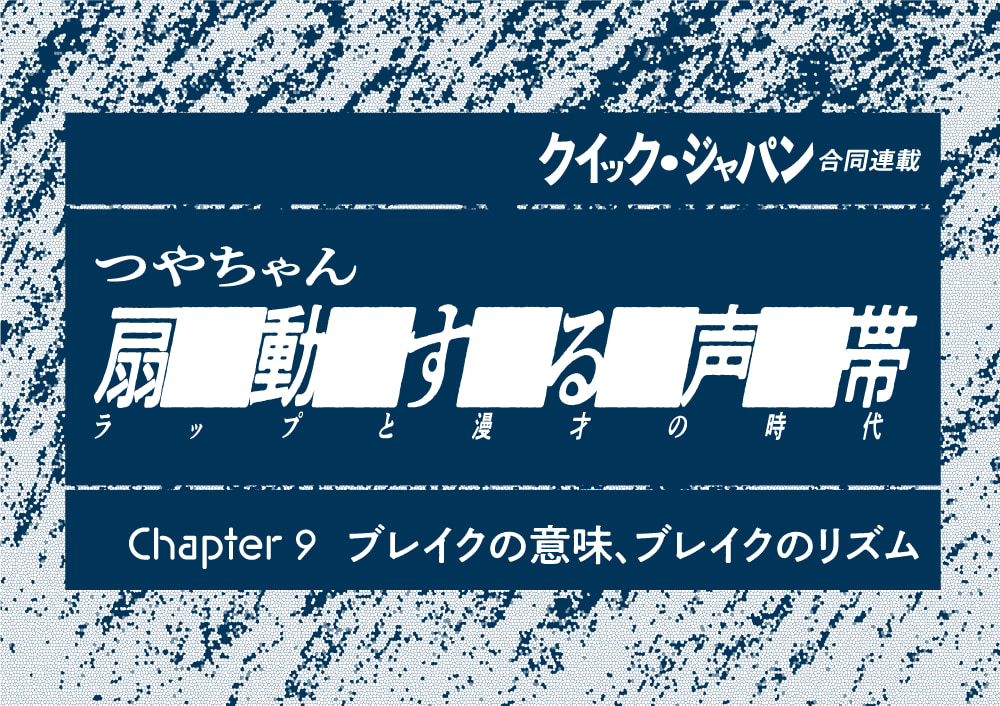新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」Chapter9。
※この記事は『クイック・ジャパン』vol.165に掲載のコラムを再構成し転載したものです。
Chapter9「ブレイクの意味、ブレイクのリズム」
たとえばOZROSAURUSが女性への愛をてらいなく綴った曲「Hey Girl」の冒頭で、「ホントの愛かは分からねえ」を「ホントの愛/●/かは分からねえ」と切断しラップしていることについて、私たちは聴き逃すわけにはいかない。このヴァースでは幾度となく不自然な切断=間(ま)の挿入がなされるが、好意を寄せる相手に対しての迷いや逡巡、揺らぐ心情、さらに肉体的な衝動までもが一瞬のブレイクによって仄めかされている。MACCHOは、1秒にも満たない間によってラップの呼吸が作られることを知っているのだ。
ラップ批評/ジャーナリズムにおいて、早口でめくるめく言葉が尽くされた“押し”の技と比べ、このような“引き”のテクニックは多くを語られてこなかったかもしれない。ラップとはいわば「リズミカルな演説」であるためリズムを導くにはまず言葉を発しないことにははじまらないが、逆に沈黙の時間である「間」を駆使することで、ラッパーはなにも言わずしてなにかを演説することができる。
日本語は(英語のような)強弱アクセントの言語ではないためリズムの生成について間の果たす役割が大きい。ゆえに日本語ラップにおいては、いかに間を絡めていくかという点で技術的に開拓され得る領域がまだまだ残されていると言ってよいだろう。
いとうせいこうが消した休符
日本語ラップ史をさかのぼると、実は1980年代にいとうせいこうにより休符の扱いについての実験が行なわれてきた歴史がある。いとうせいこう以前に主流だった“たたたた/たたたた/たたたたた・うん”のような休符が入る日本のラップについて、彼は「その瞬間に『古い』って感じる。だから、あそこの休符を消すにはどうしたらいいんだろう」と述べ、「“たたたた/たたたた/たたたたた・たたた”のような感じで、単に休符になっていたところを詰めればいいじゃん」と対応したことを明かしている(※)。
※いとうせいこう「自転車に乗ってどこまでも」聞き手・構成=磯部涼(ユリイカ2016年6月号『日本語ラップ』)
加えて、次のような指摘もある──日本では休符=間は五七調リズムの考え方の前提となっており、この間が認識されることで私たちはそれが詩歌であると認識する、と。つまり、いとうせいこうは自身のラップを日本語詩歌の延長として捉えられることを回避するために間を埋めていったという解釈もできるのだ(※)。
※西口太郎(2019)「「ラップ」をする身体をめぐる価値観の多様化と分散」
いとうせいこう以降の日本語ラップは、本来の日本の詩歌との連続性を一度絶つことでラップの可能性を広げ、次々に英語のリズムを導入し進化を遂げていった。特に英語のリズムを大胆に日本語へ持ち込んだDOBERMAN INC、さらにバイリンガルラップで日本語ラップに大きな変革を行なったSEEDA以降、ラッパーたちは日本語の文節にとらわれない間の取り方を試行錯誤するようになる。
2010年代、日本語/英語といった二項対立を完全に無視した間をふんだんにトラップ・ビートへと取り入れていったKOHHの存在は決定的だったと言えるだろう。その後、近年の日本語ラップにおいては、1980年代にいとうせいこうが試みていた日本語詩歌との断絶を試みた休符の扱いとはもはやまったく異なる次元での間の取り方が多く試されるようになった。LEXやShowyRENZOの手数の多い間の導入は、新時代のリズムとも言うべきノリを生成している。
間が生む意味とリズム/和牛とSEEDA
一方で、“間を制する者は漫才を制する”と言われる通り、ゼロコンマ一秒単位での間隔の取り方が漫才においても出来/不出来の鍵を握っていることは言うまでもない。
近年、絶妙な間の操作によって優れた漫才をより一層鋭く磨き上げているコンビが和牛である。たとえば2015年の『M-1グランプリ』で披露されたネタ「花嫁」は、結婚式を抜け出してきた新婦に対してそれがいかに自分勝手な振る舞いであるかを半ば屁理屈まじりにしつこく非難し続ける内容になっているが、その指摘内容の気まずさを川西の作る間がうまく表現する。
水田のまくしたてるような勢いのある発言に対して間を差し込むことで緩急がつき、リズム的にも相乗効果が生まれているのだ。ここでは、間によって「気まずさ」という<意味>の面でも「緩急」という<リズム>の面でもともに一定の効果が観察できる点が重要である。優れた漫才は、<意味>の面においても<リズム>の面においてもその作品内で間が有効に作用する。
2000年代後半以降、『M-1グランプリ』を中心とした賞レースでは漫才において徐々に間を埋めていく傾向が強まっていった。もちろん、そもそも漫才のテンポ自体が速度を速めていったことも関係しているだろう。テンポと間は必ずしも相関があるとは限らないが──たとえば2002年『M-1』のおぎやはぎはテンポは遅いが間は詰めてある──、多少は歩みをともにしている。『M-1』を制覇したNON STYLEやキングコングの漫才はスピードアップが指向され、ほとんど間を差し込む余地を与えなかった。
彼らが2000年代後半に間を詰めたスピード漫才を完成させたのち、2015年以降の『M-1』においては徐々にテンポの速い/遅い、間がある/ないというそれぞれの指標を組み合わせた新たな実験が試されるようになる。その象徴的な存在が速いテンポに間を取り入れていった和牛であり、同様に2016年のさらば青春の光による漫才「能」も成功例のひとつに数えられるだろう。
漫才における和牛のような優れた技術が、ラップにおいても観察できる事例をもうひとつ挙げたい。SEEDAの「TAXI DRIVER」(『BREATHE』収録)は、的確に挿入される間がまさしく<意味>と<リズム>の効果作用を生み出している。冒頭の「山に止まった鳩は飛ばない」というラインを、SEEDAは「や/ま/に/と/ま/た/は/と/は/と/ば/な/い」と均等に間を差し込みながらラップする。
ここではワードとワードの合間に間を入れるという形を超えて、「音」と「音」の合間に間を入れる奇策を採用することで躍動感あるリズムが生成される。音と音に間を挟むラップはメカニカルで棒読みな印象を与えることが多いが、SEEDAはこういったスタイルにおいても表情をつけニュアンスを与えることができるため、ヴァースの入りとして見事なフックになるのだ。そのうえ、間の力によって<意味>の面においても「山に止まった鳩」という微動だにしない様子が想起される。
羽をたたみ、動かない鳩──本曲は政治批判がテーマだが、このラインの“鳩”は当時の鳩山総理を指しているに違いない。丁寧に挟まれる一つひとつの間が、動かずに固まった総理の無策ぶりをあぶり出すのである。SEEDAの手にかかれば、さりげなく施された間の技巧がリズムを組成しながらメタファーと手を結び、ポリティカルなメッセージへと即座に昇華されるという一例だ。
優れた漫才やラップは、間を操ることで<意味>と<リズム>を有機的に接続させながら作品を深化させる。けれども歴史を紐解くと、このテーマにおいてさらなる大胆なアプローチを見せた猛者がほかにも存在したことを忘れてはならない。
次回は間を操る魔術師・スリムクラブの表現を事例に挙げながら、その巧みな技術と、同様の試みがラップにも観察できる旨を論じていきたい。