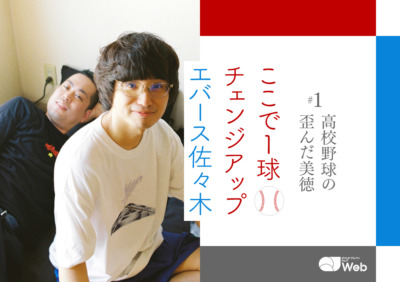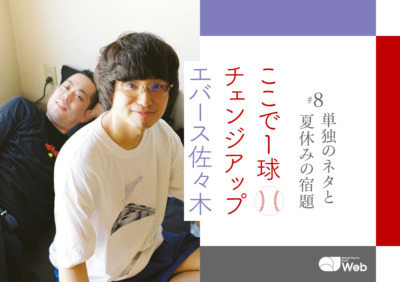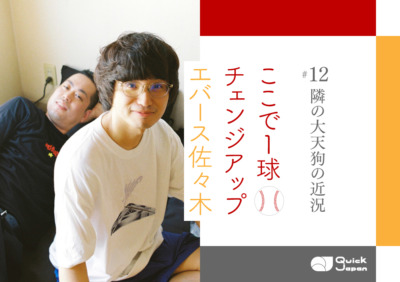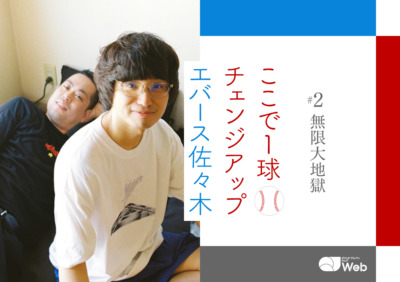新たに始まった「大島育宙のドラマ脳内再放送」。これは歴代の傑作ドラマを当時の視聴者と一緒に脳内で再放送(=プレイバック)する“ドラマ論考”連載である。第2回となる今回取り扱うのは『MIU404』(TBS)。社会構造への批判を軸とした本作品は、現在上映中の映画『ラストマイル』につながる滑走路として機能していると大島は言う。傑作ドラマと映画を行き来しながら、野木亜紀子という脚本家の人間の愛し方について考える。
※『MIU404』『ラストマイル』の展開に触れる箇所があるのでご注意ください。
“王道”ドラマに存在する闇、その周到な配置
『MIU404』は警察組織内のはぐれ者たちが新設された部隊で初動捜査にあたるという設定の刑事ドラマだ。こう聞くとわかりやすい王道ドラマのようだが、けっして王道ではない。
むしろ、王道を歩けなかった者たちの癒やしと再生のドラマだから愛されている。
そして、その熱量が大ヒット中の映画『ラストマイル』に直結している。
まず、メインキャラに、陰があるどころか、深い闇がある。
情熱の伊吹藍(綾野剛)と冷静な志摩一未(星野源)という静と動、わかりやすく対照的なキャラクターのバディかと思いきや、早い段階でふたりが同じ危うさの縁に立っていることがわかる。テンポよく、それでいて苦味を残しつつ、一応1話完結スタイルで進行してはいくのだが、ぼんやり視聴していても見過ごせないほどの暗さが、優秀な刑事・志摩の背後にはずっと蠢いている。権力の濫用に敏感で法令を遵守する志摩は、伊吹を注意する兄貴分のような役回りだが、ふと自分の命を露骨に危険にさらしたりする。
6話「リフレイン」で闇の正体が明かされる。後輩刑事の香坂義孝(村上虹郎)の死だ。連続毒殺犯の疑いがある女性に籠絡されながら不法な捜査に手を染めていく香坂の過去パートは、死や絶望の匂い漂うこのドラマ全体の中でも独特な質感と湿度で異彩を放っている。
汗ばんだ肌にじっとりとまとわりつくような、蒸すような夏の夜の空気が、志摩を呪う執着とシンクロする。酒が飲めなかったはずの香坂の遺体から「香るほど」多量のアルコールが検出された、という九重世人(岡田健史/※現在は水上恒司に改名)のセリフが視聴者の五感にも絡みつく。
この回が全11話のど真ん中、6話というの位置に埋め込まれていることに周到な意図を感じる。ドラマ全体の印象からは巧妙に隠されている、湿度と暗さ。だからこそ、私はこの回が大好きだ。夏ドラマとして放送されたことの証拠のような味わいもある。妖婦の部屋に招かれた若手刑事を主人公とした怪談のような、ゾッとするような怖気が漂う。
捜査に失敗し警察官としての賭けに負け、全てを失いかけた香坂の自殺を止められなかった、と志摩は思っていたが、実は複数の人命を救う過程での事故死だったことを知る。志摩が少しだけ、過去の呪縛から解放され、バディである伊吹にもまっすぐ向き合うきっかけとなる回だ。
8話では伊吹が大きな傷を負う。身体ではなく、心にだ。高校時代にやさぐれていた伊吹を更生させ、警察官という職業に導いた「ガマさん」(小日向文世)が凶悪な罪を犯す。止められなかったことを悔し泣く伊吹にガマさんは「お前にできることは何もなかった」と言い捨てる。
伊吹と志摩が「大切な人を救えなかった」という傷と絆で結ばれる。変な言い方になるが、ある意味で「6話と8話が第1話だ」と言ってもこのドラマのファンの多くは賛同してくれるだろう。だから私は「見始めたけどノれなくて途中でやめてしまった」と言う人には「じゃあまず6話と8話を観て」とお願いしている。
私の記憶が正しければ、村上虹郎や小日向文世の顔は他の話にはほとんど映り込まない。(小日向は少しだけ映るが、それも最小限だ)豪華キャスト感を増すためならいくらでも回想シーンを挟めるのに、しない。見逃されがちな連ドラの中盤も大事に完走した視聴者だけが、志摩と伊吹の心の闇に寄り添える、通行手形のような大事な大事なふたつの回だ。7話以降、二人が過去に呪われずに前進している、ということでもある。6話と8話を覚えている人だけが、伊吹と志摩の背中を見ることを許されている。
野木ドラマは仕事現場から社会を描く
野木亜紀子という脚本家は「お仕事ドラマの名手」とよく言われる。『MIU404』でも各キャラクターが立体的に深掘りされるわりに、仕事場以外でのプライベートはほとんど明かされない。それでいい。それがいい。伊吹と志摩、それぞれの呪縛となる香坂とガマさんも、警察機構の中での後輩と先輩だ。主人公らの仕事と人生をメロンパン号に乗せて走る。降りる先々で、犯人や容疑者の人生から社会を照らす。
仕事と人生にフォーカスしながら社会を描くスタイルとトーンは、新井順子プロデューサー×塚原あゆ子監督という布陣が再集結した映画『ラストマイル』にもわかりやすく継承されている。巨大物流倉庫のセンター長に着任した船戸エレナ(満島ひかり)とチーフマネージャーの梨本孔(岡田将生)。連続爆破事件に対処すべく奔走する二人のプライベートはほとんど見えない。
そんな彼らの過去の闇もまた、中盤に照らされる。孔は外資系巨大企業に転職してくる前は「日本の会社のよくないところを煮染めたような会社」で、時間外労働によりとある特殊技能を搾取されていたことを告白する。エレナもメンタルの不調で休職していたことが明かされ、登場人物全員を包み込む「社会構造」が映画全体の敵、ラスボスだったことが判明する。
『ラストマイル』は社会批判と社会変革の物語だ。これほど明確に思想性を帯びた映画が日本実写映画史上有数の興行収入を叩き出していることを、ドラマ『アンナチュラル』(TBS)も含めた豪華キャストで「シェアード・ユニバース」と謳った設計や宣伝の巧さだけで説明するのもったいない。先行するドラマとの思想の連続性があってこそ、同じ世界観を支持するファンの熱狂を映画館に持ち込めたのだ。
『MIU404』と『ライスマイル』に通底する巨悪とは
極端な自己責任主義と経済合理性の名の下に、市民生活が一極集中的に強者に掌握されること。そういうグローバル資本主義への抵抗ともいうべき映画は、いきなりは存在し得なかった。「クズを見捨てる、久住」と自認する悪役(菅田将暉)のような、明確な悪役は映画には登場しない。志摩は久住を『ファウスト』に登場する悪魔・メフィストフェレスになぞらえる。しかし、本当に厄介な悪は悪魔などではなく、誘惑される側の人間なのではないか。映画には『ファウスト』の主人公、欲望する側の人間の名前が印象的に登場する。『ラストマイル』で射程となった巨大な構造悪の滑走路として『MIU404』は確実に機能している。
テレビ映えする求心力のある悪に見えるのは菅田将暉が演じていたからで、実はラスボスにしては不完全燃焼なキャラクターだ。久住自身が「お前らの物語にはならない」と言ったとおり、ヴィランとして人気を集めすぎない一線が引かれている。
SNSやドラッグを駆使して、弱い個人や大衆を玩具のように弄んできた久住は、同じく人間の弱さによりしっぺ返しを食らい、お縄になる。かなりダサい。「集団に埋没した個人は当てにならない」という身も蓋もない事実が、悪を助長もするし、悪を封じもするのだ。人気ドラマの結末とは思えない、ざらついたアンチ・カタルシスで現実的なオチだ。映画『ラストマイル』から遡ると、現代人が逃れきれない構造という悪を描くために、久住を「答え」のようなスッキリした悪として描かなかったのではないか、と納得がいく。久住が扇動した『当てにならない』個人たちが『ラストマイル』ではより個人としても集団としても強調され、久住よりもよっぽど手強いグローバル資本主義という魔物に少しだけ立ち向かう。
人は簡単に“がらくた”になり得てしまうから
映画『ラストマイル』を貫くもうひとつ重要なテーマは「有能な人間はその能力を何に向けるべきなのか?」という問いだ。非正規雇用労働者たちを文字どおり高所から見下ろし、高給を稼ぐ二人の主人公は「持てる者」である。そんな優秀な人間がシステムやポジションにあぐらをかいていていいのか? その交渉力や行動力を社会を動かす方向に、なぜ向けないのか?
使う側に見える人間も、さらに上の人間に使われている。権力を持っているように見える人間も、結局は利便性幻想という城の奴隷だ。エレナの上司・五十嵐(ディーン・フジオカ)は緊急事態の報告を受けてもしばらく、ランニングマシーンから降りずに走り続ける。「世渡り上手」なプレイヤーほど、ベルトコンベアーに乗せられた荷物のように在ることを規範として内面化している、という皮肉な場面だ。
志摩も伊吹もエレナも孔も、ベルトコンベアーから落ちたことのある人間だ。『ラストマイル』の主題歌で米津玄師が歌う「がらくた」とは、全員のことを指しているように聴こえる。『アンナチュラル』も『MIU404』も、犯罪や死によって正常な世界からドロップアウトしてしまった人たちの人生を照らしていたが、「ラストマイル」ではその射程も広がった。人は事件がなくても、簡単に「がらくた」になる。社会が個人に要請し許容する「人間」の形のバリエーションは少ない。その少なさ、狭さが、愚直にがんばっている生活者を追い詰め、勝手に検品し、勝手に「がらくた」にする。
(MIU404)4話「ミリオンダラー・ガール」のゲスト主人公・青池透子(美村里恵)は「献金もらった政治家も、賄賂もらった役人も、起訴されないんだって。金持ちの世界どうなってんの?私なんて手取り14万で働いてるのに」とSNSに綴る。
最終話「ゼロ」では久住が五輪開会式のチケットを高額転売する計画を電話で話している。するとテレビから「復興五輪では無償のボランティアを募集しています。国民一丸となって成功させましょう」というニュースが流れ、久住はテレビを睨む。
いずれも「持てる側」と「持たざる側」の感覚が分断されていることを示す場面だ。3年経ってこのふたつのテレビニュースの場面を対比して見ると、『ラストマイル』の主人公二人はどちらかといえば青池より久住っぽい。勝ち負けが分断する経済の中で、システム自体が正義か否か、などという金にならない問いには思考停止して器用に乗っかれば、スマートに生きられる。久住の悪を無自覚に引き継いだようないけ好かない二人の物語が、構造悪という巨大な敵を迎えて大ヒットしている。久住、ありがとう。
人間が「がらくた」かどうかを選別するのも、そういう権力者や勝者の都合だ。最終話のラストは新国立競技場の輪型の輪郭に「ゼロ」というタイトルが重なって終わる。東京五輪へのストレートな批判に見える。
王道に乗れなかった、降りた、こぼれ落ちた人間を、フィクションから取りこぼさない。そんな志が、野木ドラマには大前提として常にある。「クズを見捨てる久住」をヒーローにさせない野木ドラマは、まずそもそも、人を「クズ」なんて呼ばせない。