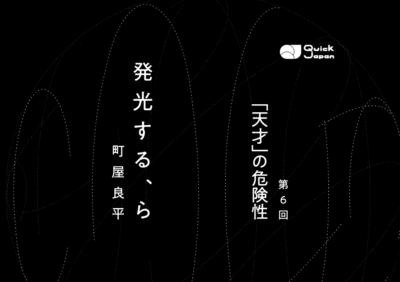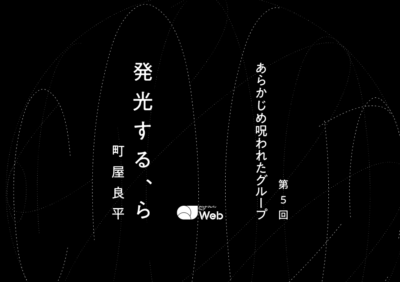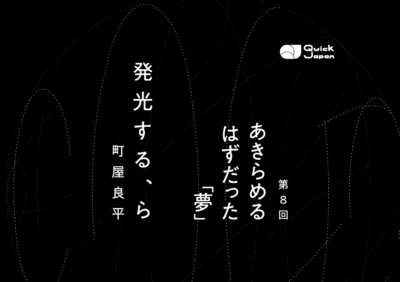メンバー間の仲も険悪、鳴かず飛ばずの6人組の弱小ボーイズグループ「8koBrights(エコーブライツ)」。七十年後の世界からやってきた双子のアリスとキルトは、未来では禁忌とされた「夢」を追いかけてアイドルとして活動していた。
バンコクでのフェス出演動画のバズ以来、少しずつ軌道に乗ってきたエコブラだったが、未来人のアリスとキルトは「過去」の歯車が狂いはじめていることに気づき──
前回までの連載はこちら!
第1回 タイムスリップ
第2回 個性恐怖症
第3回 夢の功罪
第4回 被害者たちのスイーツ
第5回 あらかじめ呪われたグループ
第6回 「天才」の危険性
<登場人物>
キルト 七十年後の未来からやってきた双子の弟。過去の菓子に目がない。メンバーカラーは紫。
アリス 七十年後の未来からやってきた双子の兄。過去語マニア。個性恐怖症。メンバーカラーは橙。
レン ダンス、ボーカルともにエコブラの絶対的エース。しかし、実力を試される場ではうまく力を発揮できない。メンバーカラーは黄。
シンイチ 個性の強いエコブラのサブボーカリスト。美容担当。メンバーカラーは青。
リュウ エコブラのリーダー。ダンスの実力はピカイチだが、かなりの俺様気質。メンバーカラーは赤。
サトシ エコブラのサブリーダー。ダンスもボーカルもラップもこなすオールラウンダー。アリスとキルトのタイムスリップを知ってしまう。メンバーカラーは緑。
ヤス エコブラが所属する事務所、株式会社キャッツクレイドル社長。元メンバー。
伊佐木 エコブラの頼れるメインマネージャー。メンバーのプライベートにおける相談役。
マサ 元メンバー。脱退後、韓国に渡り練習生として過ごすも怪我で引退。現在はエコブラのサブマネージャー。
憑馬(つしま)カート教授 七十年後の未来に住む十代にして、質的過去研究の第一人者。好物はオムライス。
第7回 過去の改変
次のリリースイベント会場である大阪に前乗りしてホテルにチェックインしたのち、遅い夕食をそこしか空いていなかった近くの個室居酒屋にてメンバーと伊佐木とでとっていたところに、社長のヤスが襖をフルの勢いで開けて現れ「じゃーん」と言った。全員のテンションがほぼ底辺だったのでリアクションもなく白ける空気を意に介さずに、元気いっぱいでヤスは「みんなお疲れー!『Bagombo Snuff Box』調子ええでー! めっちゃ売れてます!」と言った。『Bagombo Snuff Box』愛称バゴンボックスとは「Choreo after death【死後のコレオ】」をタイトル曲とする五曲入りミニアルバムのタイトルである。
シンイチが「ヤス? 現場に来るなんてめずらし。どういう風の吹き回しよ」と、口の中に飯がある状態で言ったので、アリスは顔をしかめた。もちろん白の半袖、デニムの姿である。
「地元だし、きちゃった。みんなに報告があるんよな」
「報告?」
「東京大阪それぞれでのアリーナ二公演が追加公演として正式に決定しました! これはまだ内密情報だから、よそでは言わんといてな! ヒュー!」
「え!?」
メンバーは驚き湧き上がるうれしさ、よろこびでしぜん互いの顔を見合わせながらぎこちなくハグを交わしたが、内心「ああ、だからカメラを回してたのね」と冷静に思った。帯同していた伊佐木が穏やかな笑顔でメンバーを眺めていた。プライベートなのにGoProが回されていたから、なにかの特典映像かVlog等で流すのだろうと思っていたが、だれかの誕生日でもないしなんなのだろうと、メンバーは全員プロとしてのスイッチを「半押し」しているかのような、ちゃんとかっこいいがちゃんとプライベートでもある絶妙な空気感を維持していた。
「なんだよー! だからカメラ回してたの? おかしいと思ってたんよぼくー!」
サトシが珍しく、華やいだ声を出した。
しかしメンバーが集う場においては、カメラが回されているときのほうがエコブラはむしろリラックスした。矛盾するようだがそれぞれの「素」のようなものが出た。カメラがあるほうがメンバー同士思いやれるし、話せるし、触れ合える。なによりそれぞれの「性格」や「我」、「個性」すら、カメラの前のほうが顕著に表れた。しかしそれはあながち嘘や演技とかではないのだ。仲良くもなく信頼もないメンバー同士だが、しかしカメラの前でだけ培われた時間、緊張と弛緩の連続するステージでの経験から、まるで結実するみたいに嘘とも本当ともいえない「友情」「信頼」が芽生える。これは未来人であるアリキルにとってさえ、ふしぎな現象と思っていた。
実際、ヤスが来る前の時間でシンイチはキルトに「醤油とってくれん?」と言った。キルトも「うん」と応じた。だがカメラがなければ普段、そんなことすらシンイチはキルトに言わない。
「にしても、アリーナで追加公演て、ついにそんなとこまで来てんのかおれら!」
リュウが珍しく、顔をほころばせて言った。
たしかにバンコクでのフェス動画のバズからはじまり、配信シングル「Three-Body」のテレビ披露やインプレッションランキング上位復活などの布石はあった。くわえてレン単独の歌ってみた動画やリュウやアリスを中心にしたダンス動画などもいくつかバズり、シンイチの美容担当キャラが広く認知されテレビのレギュラーが決まったりもした。事務所も弱小ながら積極的に人気グループとTikTokコラボを打診するようにしていたから、ファンクラブ「エイシス」の申し込みがこの三ヶ月で結成当初の勢いを超えて伸びているのは知っていたけれど、まさか結成以来ずっと遠ざかっていた東阪のアリーナクラスでの公演に復帰できようとは。
だがアリスとキルトの驚きはメンバーのそれを上回るものだった。言葉もなく口をあき絶句しているキルトに、レンが「キルー! めずらしいないつもうるさいキルがこんな黙るなんて、めっちゃウケるんだけど!」といって背中をポンポンと叩いた。
「あ、いや。え? ほんとですか?」
キルトの言葉に、ヤスは「スーパーほんとでーす!」と言った。
「だからみんな、カムバからまたすぐツアーの練習とかもろもろ入って大変やと思うけど、とりあえず東京戻ったらいったんオフにしよ。リュウ、絶対ちゃんと身体休めるんやぞ」
名指しで釘を刺されたリュウは、「分かってるよ、さすがにな」と言い、それでもしぜんに顔がにやけた。
レンとシンイチは店に配慮した範疇の動きで「フー!」と叫び舞った。だれも飲酒していなかったしすでにリリイベで全国五箇所を回っており疲労は溜まっていたが、カメラが回れば全員元気なふりぐらいはできる。
それでもアリスとキルトの顔は引き攣(つ)ったままだった。
「なんで……」
思わず、アリスがつぶやいた。
こんなことは過去レコードにない。
「だな」
どこか達観したようなキルトがグレープフルーツジュースをアプリでお代わりした。
もう未来から帰ってくる再計算結果を待つ必要はない。
確実におれたちは、過去を改変してしまっている。
だけどそれなら、もう未来に強制送還され、現代人の記憶から消えていてもいいはずだった。
「どういうことだ?」
アリスがおもわずひとりごちると、レンは「アリスのおかげだよ!」と言った。
「アリスが最近さ、すごい実力上がってて、すごいファンのみんなにもパフォ褒められてる。ワイもアリスの声に影響受けてめっちゃ楽になった。バンコクでのアリスのボーカル聞いて、ちょっと発声変えてみたんだ。なんか、すっげー感動したからさ。だからすこし楽に、もっと声が通るようになった。しょせん独学だけどね。ねえ、これまでの曲とか、ツアーの歌割もプロデューサーと作曲の先生に相談していっしょに考え直そうよ」
「おれのおかげ?」
「うん。アリスも「死後コレ」みたいにぜったいメボの一員として参加する曲増やしたほうがいい」
「それは待って。急いで考えないで、一瞬待とう?」
シンイチが焦って釘をさした。
「それって……」
おれが過去を変えてしまったってことか? アリスは絶句する。それなら過去からアラートが届いているはずだ、いや、厳密には届いていたが、それは【警告】ではなく【注意】にとどまるもので、そんなのこの時代のスパムメールみたいに一日に三十通も来るようなものだったから、ちゃんとは確認していなかった。
「キル」
「後でまとめて話そう。わかったろ? 多重タイムトラベルだ」
「つまり……」
「おれらの他にも、未来人が混ざってる」
「だれ? いつの時代からきた?」
「さあ。少なくとも、おれらより先の未来。けど、確実にこんなかにいる、いや、これから姿を現すだれかなのかもしれない」
「ちょっとアリキル、二人で話し込まんといてー! あ、あと皆もう一つ! ぼくは社長を退任します! 後任はそこにいる伊佐木ちゃんに頼んでるから。ていってもこれまでもぼくはそんな現場に関わってこなかったし、最近はいろいろ伊佐木ちゃんまかせだったからね。そんな実質は変わらないから、メインマネージャーは伊佐木ちゃんから新しい人に交代してもらうことになっちゃうけど。もちろん、これまで通りぼくも伊佐木ちゃんをサポするし、メンバーもなんかあったらすぐにぼくを頼ってええんやで」
「え」
「だから、新しいマネージャーをいま紹介するわ。ちょっと仕事も増えてきたし、伊佐木ちゃんに代わるメインマネは新たに近く採用面接する予定やけど、まずは雇用契約が済んだサブマネからね。おーい、入ってきてー!」
個室居酒屋のふすまがスーッ……と開いた。そのあいだをやや気まずそうな男の顔が覗く。
*
「マサ!」
リュウが声を上げた。ほかのメンバーも、声を上げはしないまでも同様の驚きをしめした。
「久しぶりじゃん!」
リュウが立ち上がり、本番前以外には滅多にしないようなハグをかました。マサの背中に手を回してボンボン叩き、目を瞑る。マサは無表情でそれを受け容れた。
マサはヤスと同様、エコブラの元メンバーだった。8koBrightsはその名の通り当初八人で結成されたグループだったが、そこからマサが脱退し、ヤスが健康上の理由から裏方に回り「株式会社キャッツクレイドル」を立ち上げ現在の六人に落ち着いた。公式の設定では裏方スタッフたちが七人目のメンバー、ファンである「エイシス」たちが八人目のメンバーということで、それら全部で[8]koBrightsなのだということになっている。(非公式ファンダムネームを名乗る「ハッコウ」の間では、自分たちが「八人目の光」つまり八光【ハッコウ】なのだという解釈がメインである)。
マサの脱退理由は「会社との方向性の違い」としてくわしくは公にされていないが、「ハッコウ」の間では不仲、契約における揉め事、モチベーションの相違といわれることが多かった。しかしその実際はヤスとの大喧嘩によるものであった。
マサは基礎のダンススキルが高く、オーディション番組放送時からリュウととくに気が合った。だがどこか自尊感情の低いところがあり、それが原因なのか出来ない人間にはリュウ以上に厳しかった。ゆえにリュウと同じような経緯で主宰により落とされたが、視聴者のあいだではその恵まれた体躯もあり早くから「デビュー当確」と言われていた人物だ。リュウとマサの落選は番組当時の二大サプライズであり、大炎上に繋がった出来事でもあった。
ゆえにリュウが8koBrightsの立ち上げを計画した際にヤス、レンとともに真っ先に勧誘したのがマサだったのだが、デビューに向けて合宿しているときに振り覚えが悪いシンイチ、キルト、アリス、ヤスを名指しで批判し「こんなんじゃその四人にはいますぐに脱退してもらって残る四人でデビューしたほうがまだいい」と言った。
その発言は匿名で行われたものだった。合宿時にギスギスし始めたメンバー一同、忌憚ない意見交換するための覆面座談会用に投書されたものだったことも、問題をより大きくした(匿名での意見交換を提案したのもマサだった。顔を見ると情が湧いて言いたいことが言えないからという理由で)。マサはとくにヤスに対して「一見努力家に見えるんだけど、実はかなり手前に限界を設けてる」と書き、ヤスはミーティングの場でそれを読み上げられた際に「おいマサ! お前なのは分かってんやぞ!」「匿名とか覆面とか知るか! おいシンイチ、アリス、キルト、こんなこと言われて黙ってることねえぞ」とめずらしく語気を荒らげて暴れた結果、匿名も覆面もクソもない、ただその場で八人入り乱れての大喧嘩が勃発した。
その後何度も話し合いを重ね、リュウもリーダーとしてうまくマサと両者間をとりもとうと努力したがけっきょく適わず、マサのほうから脱退の意思が告げられることとなった。リュウは心情としてはマサの肩を持ってしまっていたから、本心からマサに謝ることを促せなかったし、対応がなあなあになってしまったのは否めない。ヤスはそのときに、「このままマサやリュウのやり方に付いていったら、絶対に全員がどっか身体を壊す。そんなグループにファンがついてくることなんて絶対ない。ふたりが本心のところで反アイドルなのはわかる。でも、ダンスも歌もラップもうまくない子が、ゆっくりいっしょに少しずつうまくなっていくところを見せることもプロなんやで」と言い、「だからマサも大人になってほしい」と言ったが、マサの脱退の意思が覆ることはなかった。
「あんときはぼくも若かったし悪かった。いろいろ覚えも悪かったのも勿論、そうやったけど、体力とか体調に問題を抱えてたことを、くだらない意地張って、メンバーに打ち明けれんかったのもよくなかったしな。それからすぐにぼく自身も脱退することになって、それからずっとマサのことが気になってたんや。それで最近ようやく連絡をとりあって、聞くといまマサは膝をいわしてほぼ引退状態だっていう。だったら、とりあえずなにか別の道を探す繋ぎとして、マネとしてエコブラを支えてくれないか?ってぼくのほうからお願いして快諾してもろたんよ」
「ヤスは和やかに言ってるけど、こいつメンバーのために頼むって土下座までしたんだぞ。あんときは悪かったって。そんなんされたら断れないだろ」
メンバーは唖然とした。当時からリュウとレンを除いた全員がマサのことを「怖い」と思っていて、ヤスもマサのことは珍しく毛嫌いしていた。そんなヤスが土下座してマサに和解を申し出るだなんて。
「そんじゃマサ! またいっしょに活動してくれるのか? でもおまえ、膝いわしたって、じゃあ……」
リュウはハグのポジションのまま、そう言った。
「リュウ、だるいから、離れて」
「おいって」
「最近もパフォーマンスを見ていたけど、やっぱり皆さんには努力が足りないと思います。生歌を売りにするダンス&ボーカルとして世界はおろか国内のレベルとしてもまだまだ二流以下です。楽曲はすばらしいものをもらっているのだから、もっと意識を高く持ったほうがいいのではないかとおもいます」
マサはまっすぐにメンバーひとりひとりの目を見て言った。
「えー……っと、マサはこの一年韓国で練習生として頑張ってたんやて。でも怪我して最近は向こうで療養に努めてたとこ。さっそく、レンのために韓国の腕のいいボイストレーナーに見てもらう約束を取り付けたから、さっそくやけどレン、このリリイベツアーが終わったらいったん韓国行こな」
「え? ワイ?」
「レンは自己流での発声でただでかい声だして喉を苛めすぎ。声の良いところを残しつつ発声を鍛えてくれる腕のいい先生が知り合いにたまたまいたから。すでにレンの映像は見てもらってて、いろいろ体の使い方とか、緩急とか、喉のメンテナンスから、改善のプランを練ってあるから。文句言わずに来る」
マサが言うと、レンはほんらいボイトレに嫌な顔をする(過去に番組でパワハラまがいの指導を受けてきたため)のだが、いまは過去の記憶より目の前のマサのほうが怖く、素直に頷いた。
「はー。あのマサがねえ。人は一年会わないとずいぶん雰囲気も変わるもんですな。一年前はもっとトゲトゲしてて、まあいまも感じは悪いけどさ、比じゃなかったよな。こういうのなんていうんだっけ? アレ、アレ、えーと、アレだよ、そうそう、ギザギザハート……、触るものみな傷つける感じ? まあ映画版ジャイアンよろしく、ふだん悪いヤツほどちょっとした善行が評価されて好感度爆アゲってわけね。未来の授業で習いましたわ」
キルトがわざわざAI検索までしてきて過去のミームを引用して言い、呑気にグレープフレーツジュースを飲みながら「ちょっとお、この店ソフドリに氷入れすぎなんだけどー」と悪態を吐(つ)いた。いっぽう、アリスの顔は引き攣った。マサのマネージャー採用? ヤスの社長退任? そんなの未来で読んできた過去レコードにはなかった。
「もしかして、マサ、が未来から……」
「おい、いまそんな話すんな。おれらより先の未来から来てる以上、おれらの想像力とテクノロジーの限界まで考えて対策したとて、向こうには屁でもないんだ」
「じゃあ、どう、どんな顔をしてればいい?」
「笑えばいいと思うよ」
アリスは真に受けて笑った。キルトは旧友との再会であからさまに波動が柔らかくなっているリュウやサトシに「ケッ」と吐き捨てる。
マサは生活や礼儀にだらしないキルトに当時もっとも辛辣だった。警察官僚の婚外子として生まれたというマサは、幼いころから母親に厳しく躾(しつ)けられたため、キルトのだらしなさを目にするたび「ありえない」と言った。
「そんなんでよくこれまで生きてこられたな」
正確にはキルトはまだこの時代で生まれてさえいないのだが、他のメンバーにはうやむやに誤魔化すキルトもマサに睨まれたらその都度泣きそうになっていた。
だけど、それもそういう「設定」なのだとしたら。
キルトはますます気分が悪くなる。
「きほんマサは、レンとリュウの仕事に優先的に帯同する感じで、グループ全体の仕事はしばらくまだ伊佐木ちゃんと、近く採用する新マネにお願いする予定やから。キルトはそんなこわがらんでええんやで~」
「べっべつに怖がってねえし」
マサがリュウの横に腰を下ろすと、入れ代わりにあたらしく社長になった伊佐木が立ちあがり、「私じゃ力足らずな部分もあるけど、ヤスとも変わらずいろいろ相談していくし、マネージャーの皆やメンバーにも協力してもらって、これからも、ますますがんばってエコブラを推していくから、そのつもりで行くよ!」と明るく挨拶して、メンバーはみな「伊佐木ちゃん~」とつぶやいて和んだ。
「せやで~。「死後コレ」のヒットでグッズの売り上げとかもめちゃくちゃ上がってきてるから、ちょっと先行投資させてもろてる。みんなにはまだまだもっと上手くなってもらって、ますます魅力的なボーイズグループになってもらうからな。向こう三年は全速力で走ったってや! もちろん、適度に休むこともふくめて仕事やで」
ヤスが言うと、キルトがサトシに、「ねえ、ヤスって前からあんな関西臭強かった? 七十年後にはあんな人いないからすげえ新鮮なんだけど」と耳打ちした。
サトシは、「そうなん? たしかにヤスは大阪っていうけど、言われてみるとあれは大阪弁っていうのとも微妙に違う気するかな~」と呑気に応えた。
アリスはそれを耳にして、いくらバンコクにいるときに信頼や友愛の信号を送っていたとはいえ、サトシはよく双子が未来から来たって事実をこうまでスンナリ受け容れたな、という違和感が生じた。
冷静に考えれば、すべてが違和感だらけだった。
その瞬間、アリスとキルトはその場から消滅した。
*
「あっ!」
アリスが思わず声を出した。
そこでスイーとカプセルの蓋が開き、上から覗き込む少年がいる。
「おはよう、学籍番号一五四」
少年はゆるやかに微笑んでいた。
「これは……、強制送還ですか?」
半ば叫ぶようにアリスが言う。
横のキルトのカプセルを覗き込むも、まだ開いてはおらず、「私だけですか?」とアリスは訊ねた。
「いや、隣の学籍番号一五五はいまは寝てるだけ。見てごらん」
アリスがカプセルの中を覗き込むと、たしかにコーコーとキルトは寝息と鼾(いびき)の中間のような音をたてていた。
「過去から送還されてきたあとに寝てられる学生は初めてだよ。まさか過去で「アルコール」を飲んでいたワケでもあるまいね」
「まさか。おれたちは仮にも未来人であるわけですから、いくら過去へ行っていたとはいえそんな罪は犯しません」
七十年後では「アルコール」の摂取、ならびに所持は重犯罪であった。
「だろうね。そもそも意図的に「アルコール」なんて口にしていたらその時点で強制送還だから」
この少年はアリスとキルトの担当教官であり、まだ十二歳にして人文学部未来工学科質的過去研究の権威である憑馬カート教授である。世界に五人いると言われている質的過去研究の専門家のなかでも、よく言えば積極的学究派、わるく言えば研究のためには過去改変も辞さないと噂される過激派として名を馳せている人物だった。
「憑馬教授、われわれは免失ですか?」
質的過去研究の学会において、著しく悪質に歴史を改変している、またはその可能性があると判断された場合強制送還され過去トラベル免許失効に処される。われわれは良かれと思って時折り、異星からきた宇宙人めいた所業を過去人に対し働いている。まるで過去人をつかったある種の思考実験みたいに。
ある意味、安価で過去へ行ける技術が発明されてから、われわれはただしく宇宙人になったといっていい。民族や宗教、果ては国家、資本主義、愛などの概念を根底から覆され、あらたな歴史を自分たちで「みつくろう」必要があった。その際邪魔になった「人間性」をAIアシストによって補完され、足りないところ過剰なところを継ぎ接(は)ぎしなんとかこんにちの人類に至るというわけなのだ。
ようするにわれわれは旧世代からの歴史を汲む「人間」の顔を維持することにたいへん苦労していた。ゆえに、宇宙人が人間のふりをするみたいに過去人に接する、実際に過去人と対面することはないとしても、過去人の多くの暴力的な所業に対し「引いて」しまわないよう日常的に注意していた。人はいつの時代でも野蛮な行いの延長線上に自分たちがいま在ることを、つい忘れてしまいがちなのだ。
「一五四は一五五が目を覚ますまで待機」
「憑馬カート教授、身長がずいぶんお伸びになりまして」
お伸びになりまして? 最初の質問が無視されたことに気づいたアリスは「雑談」のつもりでそう述べた。自分より年若の者に敬語を使うことへの違和感がふと生じたアリスだったが、それは過去の価値観に染まっていることのあかしで、そもそもこの時代に「敬語」なる言語の派生を用いる習慣は言語学派のよほどの変わり者でもなければありえないのであった。
教授が学生より若年であるケースはまったく珍しいことではないどころか多数派を占める。生まれたときからAIアシストに慣れた脱人間性世代にアリスやキルトなどの両親がまだ「人間性旧世代」だった者が知能面でかなうことはありえない。
「憑馬カート教授、あのー……」
「んー。学籍番号一五五がめざめてから説明するから」
キルトが目覚めたのはその三時間後だった。
「フワ―……」
とキルトは言った。
「もう朝?」
憑馬教授とアリスは顔を見合わせ呆れた。だがこの常人離れした感覚により、学籍番号一五五、つまりキルトは学籍番号一五四のアリスよりはるかに優れた未来工学研究者として質的過去調査の論文をいくつも書いており、ようするにアリスのほうが落ちこぼれだった。未来において平凡な能力の人間のほうが過去では優秀であるというのは常識であるから、キルトとアリスのように優秀な学生とそうでない学生をペアで過去に送るケースは多い。アリスとキルトは双子だからペアで送られたのでもなければ、「ボーイズアイドル研究」という同じ論文テーマに取り組んでいるからそうなったわけでもない、ただ論文の出来や研究センスの差によってAIに最適と判断されふたりで過去に送られた。
「結論から伝えるけど、一五四と一五五の免許は失効していないよ。だけど学会でも意見が分かれていることから、一度こちらに戻して新たな論文を提出してもらうことになった感じ。一五四はよくレコードを読む学生だから分かっているだろうけど、いくつかの歴史が変わっていることは事実で、ほんらいならこの時点でアウト、免許失効だけど、どうもそれは一五四と一五五の行動によってではないような直観が何人かの教授とAIとで共有されていて、私もそのひとり。これはなんらかのイレギュラーの可能性が高いと踏んでる。ふたりには過去に戻った経験を基に論文を書いてもらい、査読を通ったらもう一度過去に行けるかもしれないし、行けないかもしれない。この機会に学籍番号一五五はもともとのクリティカルなセンスに頼らず、きちんとレコードを読み込んでね」
「そのことですが教授」
「アリス」
キルトはアリスに「アイコンタクト」した。いまは言うな。未来にはない身体情報の直観的交換である。
「なにか? 一五四」
「あ、いや」
ともあれアリスはひとまず、一発免失とならずまた過去に戻れる可能性が残されていることにホッとした。
「そうですか。てっきり過去改変の法に抵触したものかと……」
「過去改変は起きてるけど、いくらアリスが計算より無自覚に過去に感情移入していたとて、学会に問われるほどの影響が及んでるとは思えない。レコードよりエコブラは不仲じゃなくなってるし、ボーイズグループとしての技術も上がっている。アリスが計算より過去人に介入していたところで、おれがサトシに未来人であることを打ち明けていたことが、かえってバランスの取れた行為として計算されただろ」
「おれが? 過去人に介入?」
「自覚なかったろ? 研究そっちのけで、グループのために行動しすぎてた。それマジで危険だから気を付けてくれよ。まったくアリスは「人情」派だよな。未来人としてはなんか、危なっかしくてハラハラするよ」
「学籍番号一五五が「サトシ」という過去人に未来人であることを打ち明けたのはもちろん軽率な行為。でも一五五がいうようにそれが結果オーライになっているのは事実。一五五のその行動によって過去改変が起きている要因が絞れているからね」
「要因……」
未来に戻ったとたん、アリスは元の落ちこぼれ研究者メンタルに戻った。もっと想像力を働かせなければいけない。教授とキルトが危惧していたように、アリスは過去と相性が良すぎるのだ。おもえば自分でも気が付かないうちに、いくつかの場面でエコブラにとって状況がよくなるよう無意識に行動してしまっていた。
自分たちにとっては研究対象にすぎない、エコブラのメンバーに「感情移入」してしまっていた。
「まあ、私としては一五四の過去とのシンクロ傾向はむしろそれを伸ばしていくべきという立場。いまのところ過去が変わりかけているファクターの特定が急務ね。これからふたりに課す論文からわずかでもその萌芽が見つけられたら、もう一度過去に送ることは難しいことじゃないよ。しかし私の学生でなければまず免失だったことをよく考えて」
「ヨッさすが憑馬カート教授! 過去テロリストの異名は伊達じゃないね」
「一五五は口を慎みなさい」
「あの、憑馬教授、ところで、しばらくこちらで論文を書くのは承知しましたが、ダンス&ボーカルの自主レッスンはこちらでも続けていいですか?」
アリスがおずおずと提案すると、キルトはやや苦いような顔になった。
「おまえ、いつからそんな「努力」が好きになった?」
「えっ、あ、いや、その……、キルトのが移ったのかな?」
「おれはもちろんしたいよ自主練習。ていうかこっそりするつもりだった。でもアリスの研究の対象はあの時代のアイドルにおける「努力」の方向性じゃなく、「才能」とか「天才」とか、そういう過去幻想にまつわるもろもろだろ? なんでアリスも練習する必要があるんだ?」
「いや、だって……」
エコブラはいま大事な時期だ。ひとりひとりのスキル向上がそのままセールスに結びつく、限られたグループにしか訪れえない稀有な「確変」のような時期。
なにより、アリスはレンの声に魅せられている。
自分もあんな風に歌いたい。それも踊りながら。
本物の「ダンス&ボーカル」をやってみたい。
「だっだから、つまり……、その、そう! ダンス&ボーカルの奥深さに気づいたんだ。ダンスとしての身体表現の自由度とか、ボーカリストとしての表現の幅とか、双方を犠牲にすることで生まれる相乗効果。踊りにも歌にも集中しすぎないことで却ってすごくなる稀有な表現について。一点集中や一極崇高の否定。これは過去のいくつかの芸術にも見受けられる条件。そう! それを確かめるには、自分ができるようになるのが一番だなって」
「ごめん、ダンス&ボーカル? 理論はもちろん知ってるけど、実際にはどのようなことをするの?」
「え、えっと、こうやって、こんな。こんな、あとこんなです」
キルトとアリスはカウントを打ちながら8koBrightsの新曲「死後コレ」の一節をかるく披露した。
双子より四十センチほど身長が低い憑馬カート教授は、しばらくボーッとした表情でそのささやかなパフォーマンスを眺めた後で、両の眼からツーッと涙をこぼした。
「すばらしい……。このような拙さがありながら、しかし身体の限界といういまや過去の遺物と成り果てた概念を表現する生身体(きしんたい)が作る運動の古典的迫力たるや……。私じゃなければ見逃しちゃうね」
「そんな「ミーム」まで使いこなすとは……たしかに古典エンタメ研究の博士号も持ってるだけあるよな教授は」
「パフォーマンスのお褒めにあずかり光栄です。では、このような運動の反復「トレーニング」を論文を書きつつ行ってもよろしいですか?」
「いいえ。このような怖ろしいことはさすがの私も自分の権限では許可できないね。学会にいまの映像を提出して審議するから待って。まずリジェクトされると思ったほうがいいかも」
「アリスは「オムライス」を作れるけどね」
憑馬カート教授は一瞬キルトの発言が聞こえなかったような反応をしめした。しかしそのテンポの遅れこそが教授の心に深く「刺さった」あかしである。
憑馬カート教授は過去料理マニアである。ほとんどの未来人が口にしなくなった肉や人工添加物のたっぷり含まれるそれをとくに好み、しかし倫理的問題からその趣味を隠していて、実際にアリスは知らなかった。
「え、まさか教授は過去料理などをお好みなのですか?」
アリスが素朴にそれを訊ねた。
「あっあくまで研究的好奇心です」
「鶏卵はもちろんのこと、「トマトケチャップ」を大量に使用しますよ」
「あっあっ……」
教授は数秒沈黙したあと、「許可します……その、ダンス&ボーカルのトレーニングとやらを」と言った。
つづく
町屋良平「発光する、ら」は『Quick Japan』最新号にて連載中!