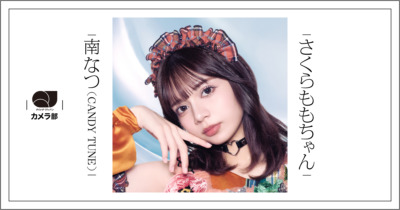「あのときの私と、あなたを救ってあげたい」──そう語るのは、歌手の和田彩花。15歳から24歳まで、女性アイドルグループのメンバーとして活動していた。
本連載では、和田彩花が毎月異なるテーマでエッセイを執筆。自身がアイドルとして活動するなかで、日常生活で気になった些細なことから、大きな違和感を覚えたことまで、“アイドル”ならではの問題意識をあぶり出す。
今回は、アイドル時代の撮影現場で抱いていた違和感から「被写体としての自分」を考える。
目次
「かわいいでしょ」って顔も、アヒル口も大嫌いだった
アイドルグループ時代の写真を見返すと、野良猫のような顔をしている。厳しい目つきで、強い警戒心を抱いているかのように写る私。
野良から家猫になった猫を飼っているので、よくわかる。人に心を開けるような環境ではなかったのは、私も家の猫も同じだ。

写真・映像を撮られるときは、いつも緊張していた。
自分がいい顔で写ることのほかに、絶対にカメラの奥にいる人たちに“受け身の姿の私”を撮られないようにするって心構えだった。
被写体として何かを表現するというよりも、愛想のいい姿で写りたくなかったし、「かわいいでしょ」って顔をして写るのも、アヒル口も大嫌いだった。
なぜこんなことになったのだろう。
アイドルの現場では「私自身」は求められない
ある撮影で、こんな指示をされた。「もっと追われているように」。
反射的に「キモい」と思った。そのときは感情をすぐに言葉にできなかったけど、心は気持ち悪さでいっぱいだった。
撮影用のシチュエーションでしょってひと言で終わらせることもできるけど、違和感を抱いた以上、何か問題があるのではないかと思い、ずっと頭の片隅に置いていた出来事。
そもそも、なぜシチュエーションとして“追われている姿”が必要なのか。誰から追われるのだろう? てか、日常で人から追われるなんて、ストーカー行為にしかならないけど。この写真を目にするお客さんは、どんな気持ちで見ればいいのだろうか。
普通に考えて理解できなかった。なんとなく「追われる」表情をするのが嫌だったので、カメラをにらみつけた。まるで、私を追いかけてくる誰かと敵対するかのように。

それからまたある日。「お姉さん座り(正座からどちらかに足を崩した座り方)で、上目遣いをしてほしい」と言われたこともある。
もちろんカメラは、私を上から撮ってくる。女性のカメラマンさんだったけど、気持ち悪さでうずうずしたので、カメラをにらみつけたまま撮影を終わらせた。
なんとなくわかったのは、アイドルの現場では「私自身」は求められていないってことだった。
どこかのアイドル、または若い女性としか見ていないような。私の個性が反映される必要はなくて、ただかわいらしい女性像が求められているように感じた。
カメラマンさんも不明瞭な指示のもと撮影しなければいけなかったり、慣習的な価値観に染まっていれば、性別関係なく私を“撮られる側”の存在としてしか認識してくれなさそうな世界だった。
もちろん私の個性を捉えようとしてくれる方々はいたけど、数少なかった。時々訪れる、私自身を求めてくれる現場が待ち遠しかった。
マネの描く“挑発的な女性像”に心を動かされた
こういった違和感の正体をどうにか暴くために、私が参考にしていたのは、やっぱり美術作品だった。
あるとき、絵画を見ているときに思った。絵画の中の女性って、アイドルをやっている私そのものではないか?と。
というのも、絵画の中の女性も受け身な姿で、時には謎に官能的に描かれているからだ。
視線を外していたり、にっこり微笑んだりしている絵画の中の“見られる存在”である女性像は、アイドルとして写真に写るときに求められる女性像と類似する点が多いと気づいた。
たとえば、アレクサンドル・カバネルの『ヴィーナスの誕生』(1863年)。サロン(官展)に入選したこの作品は、当時のフランス美術界でよいとされていたお手本のような絵画である。
女性は身体をねじらせて、寝そべっている。もちろん裸で。これは「神話の世界を描く際、女性のヌードを描いていい」という暗黙のルールに従っているのだ。女性は顔を腕で隠し、表情はあまり見えない。
あ、そうそう、美術のコラムではないので、女性の表象のみに言及する。
反対に、同じ年のサロンに出品されたエドヴァール・マネの『草上の昼食』(1862年)を見てほしい。女性ふたり・男性ふたりのピクニックの風景を描き出す。
注目すべきは、本作の中央に座る女性。カバネルの作品と同じように女性が裸体で描かれているのに、雰囲気は異なる。
体を必要以上にくねらせることなく、ただ頬杖をつき、裸体で座っている。そして、女性の顔は、鑑賞者である私たちのほうをしっかりと見つめるのだ。
実は、この女性像は現実世界の娼婦を描き出したとして、スキャンダルになった作品だ。
神話の世界で描かなければいけなかった裸婦像が、現実世界の娼婦に置き変わった。平面的な人体表現など、批判された原因はほかにもあるけれど、女性の表象だけ見ても特異なことがわかるだろう。
20代前半だった私は、マネが描いた女性像に心惹かれた。特に、この挑発的な目線。マネがどんな意識でこの女性像を描き出したのかは想像するしかないけれど、この視線に心を動かされた。
「受け身な女性像」として撮影で消費されないために
こんなふうにして、美術の世界で見ていたさまざまな女性像に、アイドルの私を重ねるようになった。
なるほど、肖像画に描かれた人物の体が斜め45度だったり、視線が画面の外に外されているのは、鑑賞者が見やすい、視線を画面に這わせやすい、そういう感覚を考慮しているのかもしれないとも思った。
受け身な一女性像として写真撮影で消費されないためには、常にまっすぐ堂々としていればいいのかと気づいた。眉を下げて困り顔をする必要も、アヒル口をする必要もないのだとわかった。
私は、マネが描いた女性像のような視線をすれば(マネが描いた女性像のすべてが能動的なわけではないが)、受け身な姿にはならないのではないかと考えるようになった。
そうやって、若い女性やアイドルのひとりではなく、和田彩花として見てもらえる姿勢や振る舞いをしていくようになった。
シャッターを押されるその瞬間さえも、こんなにもいろいろな考え事をしていた。

時々訪れた素敵なクリエイターの方々との出会いは、私を勇気づけた。
雑誌『i-D JAPAN』のフィメール・ゲイズ(女性のまなざし)の特集に呼んでいただいたり、グループを卒業するときに作っていただいた『アンジュルムック』は、そんな私の恐れを解放してくれた、心強くなれる場所だった。
悩んだ時間も多かったけど、私らしさを大切にしてくれたり、汲み取ってくれる場があったからこそ、自分が歩むべき道についての思考を止めずにいられたし、大人になる道筋を感じられた。
“和田彩花”というロールモデルを作り出す
しかし、グループ卒業後にひとりで仕事をしていても、やはり考えさせられる表現には何度か出会った。
というか、芸能の世界の多くのイメージが、男女のどちらかに当てはまるように、またはその人のパブリックイメージに合わせるかたちで企画されているような印象を受けた。
ひとりで仕事を始めたばかりのころは、なんとなく「力強い女性像を示してほしい枠」の中で仕事をしている感覚があった。
力強い女性像というのも、誰かがイメージした男女の対比の中で、または従来的な女性像と対比するかたちで湧き上がるイメージでしかなく、これを私のパブリックイメージにするのはなんとなく違うと思った。

知り合いの尊敬するアーティストに、私の立ち位置について、こんな声をかけてもらったことがある。
「ミュージシャンでも、アーティストでもなく、和田彩花というロールモデルを作り出さないといけないんだと思う」
私という存在が写真に写るとき(というのは私の姿が世の中に伝播されていくものという認識)、表情や振る舞いに男性や女性という分類は必要なく、ナチュラルで強くも弱くもある姿が必要だ。
そんな自分のイメージをようやく表現できるのは、30歳になった今からなんじゃないかな。
まだまだ学ぶことはたくさんあるけど、私自身を写したいと思ってくれる方々とお仕事をするたびに、もっと素敵な自分になれるといいなって思える。
考える時間が長い人生ではあるけど、私自身を表現できる立場にいられることはなによりも幸せだ。
そんな私の姿を通して、この世の人間像にバリエーションが増えればいいと心から思ってる。年を重ねて、シワさえも魅力に写るような人間になっていきたい。