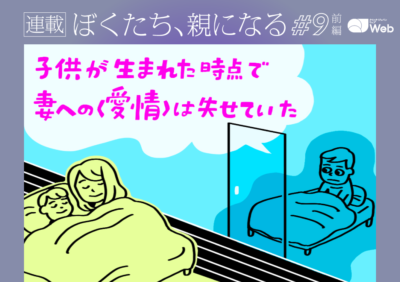かつては「大人になったら結婚をして家庭を持つ」というライフプランを築く人が大多数であった。しかし近年では、日本人の生涯未婚率の高さや、若者の結婚に対する意識の低さなどが度々話題となっている。果たして我々は、結婚して家庭を持たなければならないのだろか。「ひとり」ではいけないのだろうか。
アナキスト/フェミニストの高島鈴が「愛」と呼ばれるものを解体し、万人に開かれた革命を目指すコンテンツ批評。今回は、「ひとり」で生きることを選んだ女性が主人公の作品を読み解く。
※この記事は『クイック・ジャパン』vol.161に掲載のコラムを転載したものです。
必要なのは「ひとりで生きて死ねる社会」
婚姻なる制度は明らかに間違っている、とまずは述べておきたい。自らの親密圏を国家に対して申告し、それに対して承認を得ることが、愛の証明/幸福の象徴として認識されている状況は、極めてナショナリスティックであり、異性愛中心主義、戸籍制度、家父長制、ひいては天皇制を温存するものである。今後はまず同性婚の承認によって「家庭の再生産」という現行の婚姻制度の目的を破壊し、そののちに婚姻制度ごとなくしてしまうのがよいだろう。
私はこのような考え方に立ち、自分はひとりで生き、ひとりで死ぬのだと展望している──だが、「ひとり」という言葉に立ち止まる。そもそも婚姻制度の利用を選ばない人間が「ひとり」である、という数え方がおかしいのではないか? 婚姻制度を利用せずとも、豊かな人間関係のなかで生きることは十分に可能である。そして同時に、婚姻制度を利用しない状態を数字で過剰に強調する傾向も、愛の権威の弊害ではないかと思う。本当にひとりだったとして、それがなんだというのか? さらに踏み込んで言うなら、幸福かどうかを問うのだって大した意味はないはずである。誰からも愛されず、また自分で自分を愛せなかったとしても、あるいは幸福でも不幸でも、それらの問いかけを置き去りにして、勝手に生きて死ねる社会が必要なのだ。
長い前置きになったが、以上の理由を以て、今回は婚姻をせずに「ひとり」で生きていく女性たちの語りに焦点を当てていきたい。
よいよいライフコースとしての「ひとりでしにたい」
直球のタイトルとして紹介したいのは、カレー沢薫『ひとりでしにたい』(講談社)である。主人公は35歳の学芸員・山口鳴海。伯母が孤独死を遂げたうえ腐敗した状態で発見されたことから、うまく「ひとりで死ぬ」ために終活を考えはじめる。同作は社会状況を踏まえた実践的な終活の知識──親族との交際、両親の老後、墓の管理、投資──をしっかり搭載しながら、明確にコメディとして描かれている。鳴海に好意を持ってライフプランを一緒に考えようとする同僚・那須田くんと、那須田くんなりのアプローチをことごとく蹴っていく鳴海のディスコミュニケーションは特に軽妙だ。物語は婚姻・家庭形成を晩節のアテにする選択を徹底して否定しているため、2人は絶対に結ばれないと確信しうるのがうれしい。よりよいライフコースを自分で考えた末の「ひとりでしにたい」という鳴海の決意は、同じ道を選ぶ者を力強く勇気づける。

愛が手元になかったとしても、われらは生きていくことができる
幸福に関しては、ふたつの対照的な作品が挙げられる──まず永田カビ『迷走戦士・永田カビ』(双葉社)は、友人の結婚をきっかけにパートナーシップへの憧れを燃やした著者が「愛」を考えるエッセイマンガである。一方では人間同士の特別な親密さが現実に「ある」ことを認めながら、同時に著者自身が持っていた結婚・家庭への幻想を崩していく過程が丁寧に描かれる。著者が紆余曲折の果てに導き出した「自分はひとりでいるのが幸せだ」という結論は、実にさっぱりとしていて、極めて明るい。

そして一方には冬野梅子『まじめな会社員』(講談社)がある。主人公は30代の契約社員・あみ子。東北出身東京在住、仕事は単調、日曜にはなんとなく心細くなる。周囲に遅れをとっているような気がして自分なりに恋人を探しているが、なかなかうまくいかない。そうこうしているうちにパンデミックが起きた──どこで、誰と、どのように生きるか? 本作はあみ子の自意識と内省を、残酷なほど緻密に言語化して見せる。あみ子は結局求めていたものをなにも手に入れられない。だが一度は実家で暮らしていく道を選びかけたあみ子が足掻いていた自分を認め、「だったら私は自分で選んだ地獄に行く」「私は幸せじゃない/でもやっていく」と決意して東京に戻ってくるラストシーンは、すべてを振り切る爽やかさに満ちている。

これらの作品について、私は「対照的」と言ったが、それは決してどちらが良い/悪いという対比ではない。ひとりで幸せでも、ひとりで不幸でも、実のところそれらは独立した状態で、ベクトルの両端ではないのだ。「愛し愛される関係」の外側にいることを、過剰に重く見るでもなく、矮小化するでもなく、ただそのような状態として受け入れていく姿勢の表明に、私は希望を感じる。愛が手元になかったとしても、われらは生きていくことができる。
連載の最後に
愛を解体する──この巨大なテーマを据えた連載も今回で幕引きとなる。問いの大きさに比して、私が打ち返せたメッセージはごくわずかであったかもしれない。全3回を通じて取り上げてきたのは、愛と呼ばれるものの外側のことだった。では、愛の内側は? そこには分節して語られるべきもの、愛の名のもとに隠蔽されている複雑さが存在しているはずで、それを腑分けする言葉も、もっと必要なのである。それは海の水をペットボトルに詰め直すような作業で、本当に膨大な作品、膨大な語りが必要になるだろう。果たしてそれが私ひとりの手に負えるのか? 私が言いたいのは、これを読んでいるあなたにも手を貸してほしい、ということだ。愛という言葉であなたがなにかを括りたくなるとき、愛と名づけられた巨大な塊にぶち当たるとき、それがなにかを押し潰してはいないか、ともに立ち止まってほしいのである。
こうしている今も、愛はどこかで名前を呼ばれ、そのたびに肥大している。愛の専制をほどききったあとで残るものを新しく見つめ直すとき、われらはきっと、今よりずっと呼吸を楽にしている。
関連記事
-
-
政治家に学ぶ“絶対に謝りたくない”ときの言い回し。奇妙な「政界語」が生まれるワケとは?
イアン・アーシー『ニッポン政界語読本』(太郎次郎社エディタス):PR -