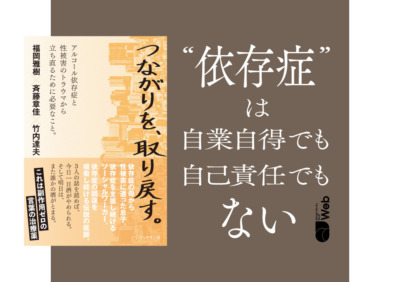大橋裕之のマンガを原作にしたアニメーション映画『音楽』が1月11日に公開された。岩井澤健治監督がその作画作業を本格スタートさせたのが2013年。そこから約7年、ほぼひとりによる個人制作で71分の本編をすべて手描きで仕上げ、完成した作品は2019年にオタワ国際アニメーション映画祭でグランプリを受賞するという快挙を成し遂げた。
そんな前代未聞の力作を「懐かしくて新鮮な感覚のアニメーション映画」と評する、気鋭のアニメーション評論家・土居伸彰のレビューをお届けします。
淡さのあとに人間として生まれ直すアニメーション
「ただそこにあって動いている」と形容したくなるような佇まい
岩井澤健治監督が7年もの年月をかけて完成させた長編アニメーション映画『音楽』。不良高校生3名が思いつきと初期衝動でバンドをはじめ、町内会のロックフェスでその演奏を披露する物語を描く本作は、とても新鮮な作品だ。その「新鮮さ」は、宣伝で大きく謳われているような「小規模(個人制作)での制作による長編アニメーション」「4万枚を超える手描きの作画枚数」が世界的にそれほどたくさんあるわけではないというポジション的な問題から生まれるものではない。それはむしろ、ロトスコープ(実写映像をトレースしてアニメーション映像を作る技術)が作り上げる「余白」の多い映像が、観客とのあいだに共犯・共作関係を作り上げる「ライブ感」が生み出すものだ。
本作は、静と動のダイナミックで瞑想的なコンビネーションがおもしろい。静のなかで、動が突如として噴出するような作品なのだ。本作はとても「乾いて」いる。坂本慎太郎演じる研二をはじめとするメインの登場人物たちは、感情で動いている感じがしない。その行動原理は、動物が本能に従うかのようで、彼らからは人間の感情の奥底にある湿り気のようなものが感じられない。
登場人物たちの動きもとても乾いている。アニメーションが一般的に目指す傾向があるゴージャスで表現豊かな運動は特に目指されることはなく、(これもロトスコープが可能にするものだろうが)人物たちの動きは物理的な現象の一部のように即物的に動きだけを伝える。主人公たちのフィジカルな動きには、マンガで言うところのスピード線のようなものが頻繁に添えられ、音もフォッ、サッ、フッ、と乾いている。まるでトップレベルのアスリートたちの動きのように、彼らの動きにはムダがなく、力強い。これもまた、登場人物たちの心理や意識というよりは、肉体やその運動こそが彼らのアイデンティティであるような印象を与える。本作は徹底的に、内面の深みに降りていこうとしない。見えるものがすべてである、とでもいわんばかりのがんこさで映像を組み立てていくのだ。
大橋裕之のマンガの描画スタイルをそのまま移植したような空白の多い画面構造も、その乾いた感じを高める。色使いも含め、とにかく本作は「淡い」印象を与える。観客へと過剰に働きかけるような甘ったるさは皆無で、登場人物たちも彼らのいる世界も、「ただそこにあって動いている」とでも形容したくなるような佇まいだ。沈黙を多用する演出も、その余韻ある空白を生み出すのに寄与している。
これらの特徴が合わさった本作『音楽』は、結果として、観客に不思議な感覚を与えることになる。アニメーションであるにもかかわらず、描かれている出来事が今、目の前で起こっているかのような印象を与えるのだ――その抑制の効いた手法ゆえに。