村山於藤から村山美知子へ
ちなみに、雑誌図書館の大宅壮一文庫の記事検索で調べた限り、「女帝」を比喩表現として見出しに掲げた最初の雑誌記事は、1965年に『週刊サンケイ』に掲載された「“朝日新聞”女帝の快気炎」という記事であった。ここで「女帝」と称されたのは、当時の朝日新聞社長・村山長挙(ながたか)の夫人で、同新聞の創業者・村山龍平の長女の於藤(藤子)である。翌年の『週刊大衆』の記事にも「大朝日王国の女帝村山於藤女史」という見出しが確認できる。
このころ、朝日新聞社内では、社主でもあった長挙社長とほかの経営幹部の間で、「村山騒動」とも呼ばれる激しい対立が生じていた。これは、長挙社長が、自社株の大半を所有する創業家の力をバックに物事を進めようとしたことに起因する。これに対し、ほかの経営幹部は、資本(創業家)と経営の分離を図るべく腐心をつづけていた。そのなかで、長挙夫人の於藤は経営陣を糾弾することが増え、世間的にも注目されるようになる。
この騒動は半世紀以上にわたってつづいた。この間、1977年に亡くなった長挙から社主の座を継承したのが長女の村山美知子だった。美知子は2007年、所有する株の大半を朝日新聞グループ側に譲渡し、騒動に幕を引くことになる。その美知子も、今年3月に99歳で亡くなり、朝日新聞からついに社主がいなくなった。最近出た『最後の社主 朝日新聞が秘封した「御影の令嬢」へのレクイエム』(講談社)は、美知子の最晩年、その身の回りの世話を務めた元朝日新聞記者・樋田毅が、彼女の生涯と共に経営陣との長きにわたる確執を綴った手記である。大阪本社社会部の事件記者出身である樋田は、社内で美知子社主について「母親の於藤さんと性格が一緒で一卵性親娘と呼ばれている」「“女帝”だった於藤さんと同様に、超のつくわがまま」などという噂も耳にしていたという。しかし実際に世話をするうち、彼女の魅力に取りつかれていく。
美知子は芸術、特に日本でのクラシック音楽の普及に当たり大きな足跡を残した。大阪国際フェスティバルの立ち上げと共にその運営に携わり、ストラビンスキーやカラヤンなど海外から多くの音楽界の巨匠たちを招いてコンサートを開催したほか、小澤征爾や佐渡裕など国内外の若い才能の発掘にも熱心だった。『最後の社主』によれば、彼女が亡くなる3年前、病院に見舞った小澤征爾は、久々の再会で話が弾むうち突然病室を飛び出すと、大声で泣き出したという。若いころの自分に対し、美知子が親身に世話をしてくれた思い出が次々と蘇り、感極まってしまったのだ。このエピソードからも、美知子がいかに芸術家たちに慕われていたかが窺えよう。
なお、村山美知子は、幼稚園から小学校、高等女学校まで地元の名門私立の甲南学園に通った。育った家格はかなり違うが、小池百合子も甲南女子中学・女子高校出身で、美知子の後輩ということになる。ついでにいえば『最後の社主』の著者・樋田は、1987年に起こった朝日新聞の阪神支局襲撃事件の真相を長らく追いつづけてきたことでも知られる。数年前に『NHKスペシャル』で同事件が取り上げられたときには、再現ドラマで樋田を草なぎ剛が演じている。
村山美知子の母・於藤が「女帝」と呼ばれて以来、マスコミでは多くの女性たちがそう称されてきた。その中には、芸能事務所・渡辺プロダクション(現ワタナベエンターテインメント)副社長の渡辺美佐や、ジャニーズ事務所の創業時より経理を担当したメリー喜多川なども含まれる。いずれも夫の渡辺晋、弟のジャニー喜多川と、男性社長をサポートする立場(表向きには)で経営に関与したという点で共通する。
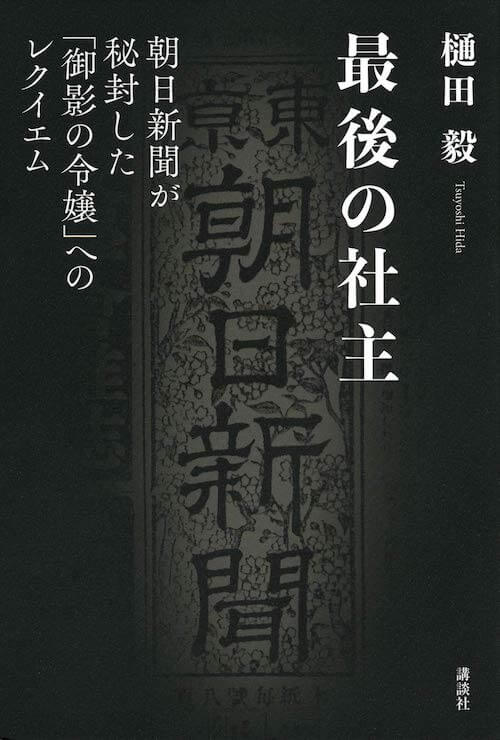
「なぜだ!?」流行語となった「女帝」
「女帝」とはネガティブなイメージがつきまとうため、そう言われて傷ついた女性もけっして少なくないだろう。事実、かつて自分をそう呼んだマスコミに、後年になって強く反論したアクセサリーデザイナーの竹久みちのような例もある。竹久は、老舗百貨店を舞台に起こった、いわゆる三越事件の渦中の人物だ。そもそもの発端は、三越と取引するなかで宣伝部長だった岡田茂と出会い、男女の関係となったことだった。やがて岡田は社長に昇進するのだが、そこでさまざまな問題が噴出するなかで竹久との関係も取り沙汰される。マスコミでは、部外者である彼女が三越の経営にも口出ししているなどといったことがまことしやかに伝えられた。結局、岡田は1982年に社長を解任され、特別背任罪の容疑で逮捕される。彼が役員会で解任が決まった瞬間に口にしたとされる「なぜだ!?」と共に、竹久を指す「女帝」は流行語となった。岡田と共に逮捕された竹久は、最高裁まで争った末に所得税法違反及び特別背任罪で実刑が確定した。服役後に著した『罪名 女』(ごま書房)と題する手記で、彼女は次のように書いている。
もし、私が断罪されるとしたら、それは、やはり私が“女”であったからだとしか思えません。/三越事件が起きたとき、私は五十二歳でした。あれからいたずらに馬齢を重ね、生きてきた私ですが、いまなお、女性が男性社会の中で仕事をしていくことが、いかに困難かを思い知らされました。(中略)そういう社会では、私もまた“ちょっと生意気な一人の女”としか思われていなかったのかもしれません。そのことに気づかず、私は仕事に打ち込みすぎ、かえって自分の墓穴を掘るような偏見と、誤解を生んできたのでした。
『罪名 女』(ごま書房)
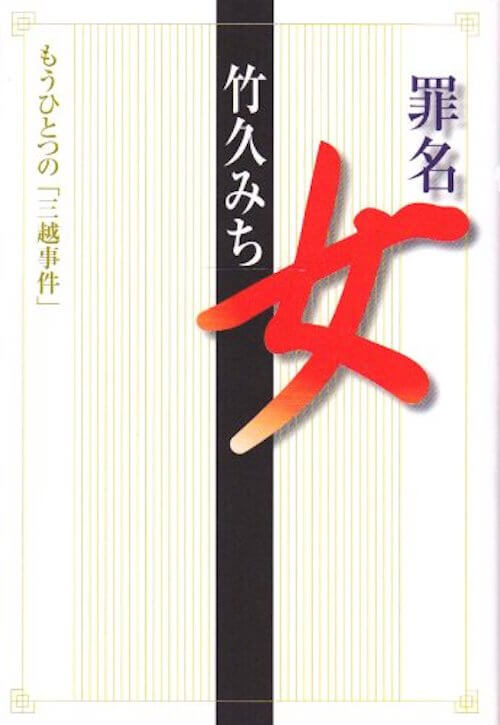
改めて小池百合子に話を戻せば、小池もまた男性社会のなかで仕事をしていく困難をじゅうぶん過ぎるほど知っていたに違いない。しかし、そこでの振る舞い方が、それまで「女帝」と呼ばれてきた多くの女性とは違った。彼女が選んだのは、その時々で権力を持つ男性たちに取り入りながら、自らも権力の座を目指すという道であった。『女帝 小池百合子』という書名には、そのようにして都知事にまでのぼり詰めた彼女への批判が込められていることは間違いない。しかし私は一方で、彼女が男たちの威を借りつつ、自らもいわば精神的に男と化すことでしか権力を得ることができなかったということに、どこか淋しさも感じずにはいられない。その意味では小池百合子もまた、「淋しき女王」なのではないだろうか。
関連記事
-
-
シティポップだけではこぼれ落ちる80年代前夜のリアルを、スージー鈴木が小説『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』で語り直した理由
スージー鈴木『弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる』(ブックマン社):PR -
政治家に学ぶ“絶対に謝りたくない”ときの言い回し。奇妙な「政界語」が生まれるワケとは?
イアン・アーシー『ニッポン政界語読本』(太郎次郎社エディタス):PR -


















































